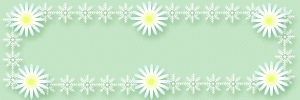
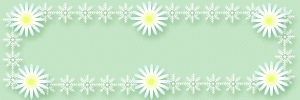
~Fanfan La Rose~
「アンドレ、これは突然、取れた休暇だと思えばいい。二人揃って休暇が取れたので旅行に来た。どうだ?」
アンドレを連れ、薄明るい夜道を歩きながら話すオスカルの声はどこか弾んでいた。
「まあ、そうだな。確かに旅行のようなものだ。それで?」
襟元と上着の裾にほどこされた金糸の刺繍よりもあざやかなブロンドの髪を眺めながら、アンドレは次の台詞を予想した。
「旅行に来て、夕食にジュースを飲む大人はまずいない」
案の定の台詞にアンドレは思わず、口元を緩めたが、まずはそ知らぬ声音で答えた。
「たしかに」
『やっぱり』という言葉を置き換えてみた。
オスカルも、アンドレを振り向くことなく足を進めていた。
まだアンドレから合意を得ていないことを心得ているからだった。
できるなら、「制限」などという野暮な言葉を気にすることなく、好きな飲み物を好きなだけ飲んでみたかった。
人を解放的な気分にさせるという意味では、時間の隔たりも一種の旅行かもしれなかった。
「そうだ!」
いきなり、振り向いたオスカルの顔には妙案が浮かんだと書いてあった。
「賭けをしよう」
ここで早く切り返さないと、オスカルの思う壺にはまってしまう。
「よし!では、賭けは俺が考える。おまえが勝てばおまえの好きな飲み物を好きなだけ飲め。俺が勝ったら、オレンジジュースで乾杯だ」
オスカルが渋い顔をしている間にアンドレは話を続けた。
「店に着くまでに流れ星を見ることができたら、おまえの勝ちだ」
「アンドレ、まだ空は明るい。たとえ、星が流れたとしても確認することは不可能だ」
溜め息交じりにアンドレの提案を却下すると、オスカルはにやりと笑った。
「店に着くまでに薔薇を見つけられたなら、私の勝ちだ」
たしかに、道の両脇の民家には小さな花壇を家の前に作っているところが何軒かあった。
「では、白薔薇限定だ」
アンドレはすかさず、確立を低下させる案を出し、オスカルもしぶしぶ承知した。
これで、確立は半々かそれ以下というところだろうか。
二人は花壇を見渡しながら進んだが、他の色の薔薇は植えてあっても白薔薇はなかなか見つけることができなかった。
薔薇といっても、ジャルジェ家の薔薇園にあるような大輪の花ではなく、野薔薇がほとんどだった。
「あのオレンジ色のレンガの建物が教えてもらった店のようだ」
アンドレの言葉に小さな溜め息を漏らしたちょうどその時、小路から出てきた娘とぶつかった。
娘は手にぶらさげていた花かごを落としてしまい、急いでそれを拾おうと身をかがめた。
「大丈夫ですか?お嬢さん」
オスカルも散らばった花を一緒になって拾った。
「ええ、どうせ売れ残りの花なんです」
「売れ残りの花・・・か」
オスカルは白薔薇を一輪、手にしたままアンドレを振り返った。
勝者の笑顔ほど光り輝いているものはない。
アンドレは両手を持ち上げ、負けを認めた。
「差し上げます」と言われた、その白薔薇を手にオスカルは意気揚々と店の扉を開けた。
人目を引く二人に、店の女主人はすぐさま駆け寄り、一番大きなテーブルへと案内した。
「旅のお方ですか?」
「いや、最近、入隊したばかりの者だ」
「そうですか。では、何をお持ちいたしましょう?」
女主人は胸の前で両手を合わせ、上客と思われる二人からの注文を待った。
「この店の自慢の料理と酒をどんどん、持ってきてくれ」
オスカルの言葉を遮るようにアンドレが口をはさんだ。
「いや、少しずつ頼む」
アンドレの言葉に、女主人はにっこりと頷いて店の奥に引っ込んでいった。
「今頃、アランは別の店で他の兵士達から情報収集中だろうな」
その様子を想像すると、思わず笑いがこぼれ、アンドレは口に拳を当てた。
「あいつはぶっきらぼうだが、なぜか人に好かれる」
話している二人の間に湯気を立てているポトフが運ばれてきた。
そして白ワインがなんの装飾もないグラスに注がれた。
装飾がないのはグラスだけではなかった。
店の内部はレンガがむき出し。
椅子もテーブルも安い角材を繋ぎ合わせた、粗い作りのものだった。
そこに、あたかもロカイユ様式の布張りの椅子に腰掛けるように、優雅な裾さばきで腰を下ろすのがオスカル。
オスカルの絹の洋服が、そのささくれた椅子で傷つかないか心配そうに見守るのがアンドレだった。
「扉をくぐる前の夜に、アントワネット様の婚礼の夢を見た」
「あの頃のおまえは、前途洋々、光り輝いていた」
「教えられたものがすべてだと、愚かにも信じ込んでいた。そして、王妃様を命がけで守ると誓いながらもそれが出来なかった」
オスカルはグラスをいったん置くと、額に手を当てた。
「オスカル、よい王妃にお育てするのはおまえの役目ではない」
「だが、私がお守りすると誓ったのは身体警護だけの意味ではない」
抑えた口調で言い切ると、オスカルは額に当てていた手をドンとテーブルに叩きつけた。
「オスカル・・・」
アンドレはオスカルが手をつけようとしないポトフを口に運んでみた。
「うん、うまい。オスカル、食べてみろ」
促されて、蕪を一口食べるとグラスを口に運んだ。
「若い頃のあの方の精神は、いつも興奮を求めていた。人の話に耳を傾けたり、ひとつのことを深く掘り下げて考えようとはなさらなかった」
「オスカル・・・」
「けっして、能力がない方ではないのだ」
アンドレは空になったグラスにワインを注いでやった。
「さあ、鴨のもも肉のコンフィでございますよ。よろしかったら、ボルドーの50年ものの赤ワインもございますが・・・値段がお高いものですから、なかなか注文してくださる方がなくって」
女主人は浮き立った顔を隠そうともせず、もみ手で返答を待った。
「ああ、もらおう」
やっと視線を上げたオスカルの表情が思ったほど暗くなかったので、アンドレはひとまず安堵した。
「オスカル、王もポンパドゥール夫人も戦地に来ているということは旦那様も来ているのではないか?」
「ああ、おそらく。おまえが引き取られてくる前の年まで父上は家を留守にしがちだった。戦地へ赴いたこともあったと聞いている。ポンパドゥール夫人に名前を名乗ってしまっているから、今頃、父上の耳に入っているかもしれん。出くわした時のためになにか考えておかねばな」
アンドレは骨付きで出てきた鴨のもも肉から、ナイフで器用に骨を取り外し、オスカルに差し出した。
そして、新しいグラスにボルドーの赤ワインを注いだ。
アンドレの所作をやや頬の筋肉を持ち上げ気味に眺めていたオスカルは目で礼を言うと、鴨肉を食べ、赤ワインを口に含んだ。
「うん、やはりうまい」
今度は、オスカルがアンドレのグラスにワインを注ぎ、店員を目で探した。
「もっと、料理を」
今度は店の奥から主人が飛んできた。
そして、アンドレに好みを聞いた。
「じゃあ、子羊の背肉のローストを頼む」
次にオスカルに視線を送った。
「私はなんでも、かまわん」
「では、とっておきのチーズを使わせていただきます」
そう言うと、いそいそと厨房へと引っ込んでいった。
「そういえば、おまえの父上の話を聞いたことがない」
「子供の頃、親父は外国に仕事に行っていると聞かされていた。だが、本当のところは戦争に行っていたらしい」
「最後に会ったのはいつだ?」
「俺が7歳のノエルの時だ。何年かぶりに帰ってきて、一緒に過ごした。その翌年に戦死したと通知がきた。友達を庇って、銃弾をあびたと・・・」
「そうか・・・」
「そして、一年と経たないうちにおふくろが亡くなった」
オスカルは無言になり、アンドレのグラスにワインを注いだ。
そして、何かに気づいたように瞳を上げた。
「そうだ!おまえの父上ももしかしたら、同じ連隊にいるかも知れん」
「オスカル、世界戦争だ。ヨーロッパ中で戦争をしていて、親父は一兵卒だ。万が一にもこんなところで出くわすはずがないさ」
「そうか・・・」
オスカルは深い溜め息をひとつ吐き、視線を下げた。
「もし、歴史を変えることができたなら。いや、せめて自分の愚かしさにもっと早く気づいていたなら・・・」
「オスカル」
アンドレはオスカルがまたしても自責の念の虜になる前に口を挟んだ。
「おまえは今まで、人や仕事に不誠実だったことがあるか」
オスカルは口元を引き結んで、アンドレを見返した。
「アンドレ、おまえは私の共をして宮殿に出入りしながら不条理を感じたことはなかったか?」
「それはあるさ。いやがうえにも身分の差は思い知らされた。だが、世の中とはそういうもんだと思っていた。俺だけじゃない。みんながそう思っていた」
香ばしい匂いをさせ、子羊のローストがアンドレの前に運ばれた。
そして、牛のほほ肉の赤ワイン煮とチーズの入ったオムレツがオスカルの前に並べられた。
「口に入れたら、すぐに溶けちまいそうなくらい柔らかいですよ」
自慢げに料理の説明をしかけた主人は客の顔つきを見て、早々に退散していった。
「オスカル、俺達が今、見つめるべきものは過去ではなく、未来とローストだ。そう思わないか?」
ふんっと、鼻で返事をすると、オスカルは牛ほほ肉にナイフを入れた。
「アンドレ、おまえは辛いと思ったことはなかったか?」
「俺にはおまえがいた」
晴天の日に突然、雷鳴が轟いたような、あるいは、いきなりドスンと心臓を短剣で突かれたような衝撃にオスカルはナイフを動かす手を止めた。
瞳をあげて、子羊のローストをほおばりながら事もなげにその言葉を言ったアンドレの顔を、まじまじと眺めていると胸の奥から熱いものが込み上げてきた。
―それは、こっちの台詞だ、アンドレ。
私にはおまえがいた。
「おまえがいたから、どんな辛いことでも乗り越えられた」
赤ワインで子羊を飲み込むと、アンドレはウィンクとともに次の台詞を投げた。
オスカルはアンドレを眺めながら、なにか言葉にしようとしたが何も言えなかった。
―それも私の台詞だ。
おまえがいたからこそ、私はどんな辛いことでも乗り越えてきた。
当たり前のように、私に寄り添ってくれていたおまえも私と同じように感じていたとうのか。
「どうした?オスカル」
ナイフとフォークを置いたオスカルを怪訝そうにアンドレは見つめた。
「・・・言葉を飲み込んでいたら、入らなくなった」
「どんな言葉だ?」
「ふっ、もったいなくて教えられん」
「そうか・・・」
アンドレは自分のグラスにワインを注いだ。
一口、口に含むと、再びその豊かな酸味と甘みが口の中に広がった。
静かな視線を自分に注ぐオスカルからは言葉を発する様子はなかった。
アンドレはごくんとワインを飲み込むとグラスを自分から少し離れた位置に置き、テーブルの上で組まれたオスカルの手をそっと取った。
ナイフがアンドレの手に触れ、カシャンと皿の上で音を立てた。
「オスカル、俺はおまえの影だ」
静かな店内にアンドレの声が低く響いた。
「おまえの信じる未来に俺を連れて行け」
その言葉の重大さとは対照的に、アンドレの声音にはなんの気負いも気取りも感じられなかった。
ただ、静かでしっかりとした口調と、まっすぐな眼差しが彼の固い決意と覚悟を示していた。
それが思いつきや抽象的な意味合いで発せられた言葉ではないと、アンドレの濡れてきらめく二つの黒曜石の瞳が語っていた。
オスカルはいっぱいになった胸で浅い呼吸を繰り返しながら、アンドレを無言で見つめ返していた。
―どうしてこの男は私の考えていることをすべて察知し、次々と言葉に代えていってしまうのだろう。
いつか、私はすべてを捨てる。
身分も地位も、貴族としての生活も・・・
そして、おまえだけを連れて家を出る。
そう告げるのはもう少し、先だと思っていたのに・・・
無言のオスカルの頬に一筋の涙がつたい、アンドレの手の甲に落ちた。
言葉のないまま、互いの思いを確かめ合うかのように見つめ合っている二人に静かに時間は流れた。
周りで聞こえる会話や食器を扱う音は30年近くも昔の音。
元の世界に帰れば、1788年、冬。
けっして、思い通りに進まぬ三部会開催が翌年五月に迫っていた。
衣擦れの音に気づき、アンドレはオスカルから手を離した。
「あのお、よろしかったらもう1本いかがです?」
女主人が若い娘にボトルを持たせて、二人の横に立っていた。
オスカルは急いで、涙を拭うと視線を上げた。
「実はこのマドレーヌがお客さんの膝に座りたいってきかないんですよ」
女主人はやや困り顔でオスカルの顔色をうかがった。
「あいにくだが、私は女性を膝の上に乗せたことはない」
娘に目を移すと、まだ12か13歳くらいの少女が物怖じもせず立っていた。
薄暗い蝋燭の灯りの元でも、娘の顔立ちはくっきりと浮かび上がっていた。
丸く整った眉、大きな茶色の目、小さめの形のよい鼻、薄い唇に三角の顎。
その器量が娘を実際の年よりも大人びて見せていた。
「よろしかったら、こちらへどうぞ、お嬢さん」
オスカルは微笑むと隣の椅子を勧めた。
娘はオスカルとアンドレのグラスに新しいワインを注ぐと、勧められた椅子にちょこんと腰掛けた。
「兵隊さん達は都会から来たんでしょ?」
「パリからだ」
「ああ、やっぱり!」
娘の声はひと際、高くなった。
「パリに行きたいのかい?」
アンドレも声をかけた。
「行きたいわ!だって、いろんなお店があるんでしょ?劇場もお城も!」
娘は二人の酌をしながら、声を弾ませた。
「パリに行って何をしたい?」
「まずは働くわ。そして、いつか女優になりたいの!」
オスカルはアンドレと顔を見合わせた。
いく皿もの料理に高級ワイン、それに若い娘の弾む声。
ただでさえ目立つ二人の席は、店の中でまったく異質な空間を作り出していた。
二人が娘の話し相手になっていると、突然、大きな手がオスカルの肩を掴んだ。
オスカルが振り返ると、そこにはアキテーヌ連隊の軍服を着た黒髪の長身の男が立っていた。
「おい、新米!えらく豪勢なテーブルだな」
無礼な言葉にオスカルは男を憮然とした表情で睨み返した。
「なんで歩兵なんかに配属されているのか知らないが、あんた貴族だな?」
オスカルは立ち上がると同時に男の手を振り払った。
座っていた椅子はガタンと音をたて倒れた。
マドレーヌは大急ぎで、テーブルの上のグラスを片付け始めた。
ガラス製品はたとえ簡素なつくりのものでも貴重品だった。
だから、滅多にテーブルに並ぶことはない。
喧嘩なんかで割られてしまっては店の大損害である。
「いかにも私は貴族だ。それがどうした?」
「オスカル!」
アンドレは止めようとしたが、どうも血の気の多い二人のようだった。
「あんた達貴族のために、俺達は何年もやりたくもねえ戦争に付き合わされている!」
「貴族のためではない。フランスの戦争だ」
「おんなじことだ。俺達には決定も選択もできねえ!」
男の足元はふらふらとふらついていた。
「呆れたな。悪いがこんなところで喧嘩の相手などせんぞ」
「ああ、貴族様だからな。なら、決闘だ!決闘を申し込む!」
「なにぃ?」
不用意に発せられた『決闘』の二文字がオスカルの逆鱗に触れた。
「よおし、受けてたとう!」
「やめろ!オスカル!」
アンドレが止めるのと同時に店の奥のテーブルから一人の男が駆け寄ってきた。
「いい加減にしろ!ジャン!」
その男も軍服のままだった。
見ると奥の薄暗いテーブルで軍服を着た男4~5人がしんみりと酒を飲んでいたらしい。
「すまない。この男は普段は気のいいやつなんだが、酒が過ぎると自分を見失う癖がある。許してやってくれ」
「貴族がいったん受けた決闘をなかったことにはできない」
オスカルもこんな喧嘩がもとの決闘など、さらさらやる気はなかった。
ただ、売り言葉に買い言葉、それだけだった。
「謝っているのに・・・なら、俺が代理だ。こいつは剣も銃も弱い」
「引っ込んでろ、シモン!」
「おまえこそ、引っ込んでろ、ジャン!」
シモンはジャンの胸を片手で押すと、ジャンはふらふらと後ずさりし、そのまま壁に頭をぶつけてその場にしゃがみこんだ。
「シモン、止めろ!」
奥で成り行きを見守っていた兵士達がテーブルに集まってきた。
「騒ぎを起こすな、シモン・グランディエ!」
その名にアンドレはぎょっとし、シモンという男をまじまじと眺めてみた。
父親と同じ名のその男に父親の面影を探そうにも、面影自体を覚えていないのでどうしても重ならない。
「代理だろうと私は構わんぞ」
「オスカル!待て!」
後に引こうとしないオスカルを、アンドレは前に立ちはだかって制した。
そして、今度はシモンの方を向き直った。
「シモン・グランディエ、家に帰ったら子供がいるんじゃないのか?」
「ああ、小さな息子が母親と待ってるよ」
「なんという名前だ?」
シモンは一瞬、きょとんとしたが、その問いに答えた。
「・・・アンドレだ」
アンドレはごくんと、唾を飲み込んだ。
その後でオスカルは目をまん丸くした。
「・・・そうか。偶然だが私の名もアンドレだ。残念だが、あんたはどんな武器を使おうとこの男には敵わない。そちらが代理なら、俺がこの男の代理を務める。いいな?」
アンドレはシモンとオスカルの両方に了解を迫った。
「俺は構わない」
シモンは了解した。
アンドレはオスカルを振り返った。
「す、好きにしろ、アンドレ」
いくらオスカルでも、いきなり降りかかったこの大ピンチを乗り切る妙案はそう急には思い浮かばなかった。
それにひきかえ、なにも知らないシモンの方は落ち着いていた。
「日時と場所はどうする?」
「今、ここでだ」
その言葉に店内にざわめきが起こった。
「武器は?」
その問いにアンドレは答えず、振り返って、目でマドレーヌを探した。
マドレーヌは店の隅で女主人に身体を寄せて、怯えていた。
「マドレーヌ!」
アンドレは、マドレーヌに向かって、サインを送った。
それを解したマドレーヌは厨房へと走りこんだ。
しばらくすると、盆にふたつの木製のグラスと安いワイン2本を載せマドレーヌが現れた。
アンドレに促されるまま、テーブルにグラスとワインを置くとマドレーヌはすっと店の奥に引っ込んだ。
「もし、銃や剣で決闘すれば、勝った方も王の兵士を傷つけた罪で罰を受ける。そして、ここに居合わせたすべての兵士にも罰が下るかもしれない。これなら、勝った方も負けた方も二日酔いが残るだけだ。どうだ?」
アンドレの言葉に、事の成り行きを見守っていた者達すべての顔から緊張が消えた。
「よし!」
そう言うと、シモンはテーブルに着いた。
アンドレもシモンと対面する位置に腰掛けた。
シモンはアンドレのグラスに、アンドレはシモンのグラスに一杯目のワインを注いだ。
そして、一気に飲み干した。
二杯目も同じように飲み干した。
そして、三杯目、四杯目、五杯目を飲み干そうとする頃にマドレーヌが次の二本を運んできた。
アンドレは目の前の父親にかける言葉を探しながらも見つからず、次々と杯を空けた。
シモンは律儀にも、大真面目にこの決闘の決着をつけるべく、これまた次々と杯を空けていった。
あっという間に、テーブルの上には空瓶が10本並んだ。
「あんた、帰ったら息子になにを話す?」
ようやく口を開いたアンドレは、やや呂律が回らなくなってきていた。
「なんでそんなことを聞く?」
シモンも同じく目つきが怪しくなってきていた。
「俺は子供の頃に親父を亡くした」
シモンはアンドレをちらりと見た。
「息子には友達を大事にしろと教えるさ」
「女房や子供ではなく、友達をか?」
「女房や子供が大事なのは当たり前のことだ。だが、男にとって友達っていうのは特別だ」
「そうか・・・」
空瓶は12本になっていた。
最初は応援していたシモンの連れもだんだん、心配になってきていた。
酒など付き合い程度にしか飲んだことのない男だった。
オスカルも後で気が気ではなかった。
アンドレの飲める量というのは、せいぜいフルボトルで2本から3本までだった。
「あんた、子供は?」
「俺は独身だ」
シモンはアンドレをちらりと見る気力さえ無くなってきていた。
「では、信頼できる一生の友達は?」
「いるさ!最高の友が・・・」
「そうか。友達が一人もいない男っていうのは、女房や子供がいない男よりも寂しいもんだ」
「そうか・・・」
アンドレも顔を上げていることができなくなってきていた。
「あんたは死んだ親父さんに何か言いたいことはないのか?」
薄れゆく意識の中でアンドレは懸命に考えてみた。
「言いたいことは山ほどあるさ。・・・だが、いざ口にしようとすると何も言えない」
「そうか・・・」
「ただ・・・」
「ただ、なんだ?」
「いや、なんでもない・・・」
「あんたの親父さんは、きっとあんたのことを誇りに思ってるよ。あんたは自分の友達と俺の友達の両方を同時に救った」
しどろもどろになりながらも、シモンはそう言った。
「・・・俺も親父が誇りだ・・・」
そこまで言うと、二人は同時にバタンとテーブルの上に倒れた。
「マドレーヌ!水だ!」
オスカルはアンドレに水を勧めたが、アンドレはテーブルにうつ伏せたまま、ぴくりとも動かなかった。
シモンの連れの兵士達はシモンとジャンを介抱していたが、二人とも泥酔したまま目覚めることはなかった。
しばらくすると、兵士達は二人を抱きかかえるようにして店を出て行った。
他の客達もぽつりぽつりと帰りだした。
やがて、店内にはオスカルとアンドレだけになった。
「アンドレ、大丈夫か?」
オスカルの言葉にアンドレはむにゃむにゃと口を動かした。
「なんだ?アンドレ?」
「・・・俺の言った賭けをしていれば・・・きっと、俺が勝ってた・・・」
「何を言っている、アンドレ」
こんなところに来て、こんなことになるとはまったくもって、予想外の展開だった。
だが、途方に暮れているわけにもいかなかった。
「マドレーヌ、すまないが、この男を背負わせてくれ」
オスカルはアンドレの椅子の前に身をかがめると、アンドレを背中に乗せた。
そして、アンドレの頭をぶつけないように店の扉をくぐると、外へ出た。
空には幾百万もの星が瞬き、その光が二人に降り注いでいた。
「アンドレ、星が綺麗だ。このまま、おまえを背負って兵舎まで歩くぞ」
オスカルの言葉が聞こえているのかいないのか、オスカルの肩ですやすやと寝息をたてていたアンドレの目から、一筋の涙がこぼれた。
ちょうどその時、夜空を大きく一筋の星が流れ、消えていった。
「アンドレ!流れ星だ!見えたか?」
アンドレからの返答はなかった。
「ふっ、やっぱりおまえの言った賭けをしていたとしても、結局、私の勝ちだ」
父親に背負われた記憶さえ不確かで、どんな顔だったかも覚えていない。
ただ、物静かで優しい父親だった。
そういえば、久しぶりに帰ってきた父親が枕辺で四人の英雄の話をしてくれたような・・・してくれなかったような・・・
朦朧とする意識の中でアンドレはそんなことを思い出していた。
1761年、平和ヶ原で勝ち戦をおさめる五日前の夜だった。
![]()
![]()
時に脅し、時ににんじんをぶら下げ、あの手この手でけし
かけた結果、このような素敵なお話ができあがりました(^o^)。
これはひとえに掲示板で叱咤激励くださった皆さまのおかげ
です。心からお礼申し上げますm(_ _)m。
グランディエ親子の飲み比べ…何とも素敵な設定ではありま
せんか♪
オンディーヌさま、本当にありがとうございました。
ガッツポーズのさわらびより(笑)
![]()
-番外編Ⅰ-

