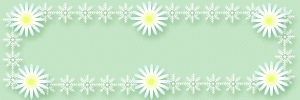
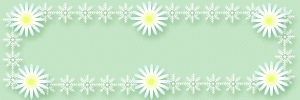
~Fanfan La Rose~
「こんなに早くお帰りなられるとは・・・」
オスカルを出迎えた侍女は、部屋の暖炉にまだ火が入れてないことをとても大きな失態のように感じ、身を小さくしていた。
「大丈夫だ。俺がすぐに他の部屋で燃えている火種を持っていってやるよ」
アンドレのフォローに少し気を楽にした様子の召使いにコートを渡すと、オスカルは一人、階段を昇っていった。
まだ日も暮れていないのに、室内でも水に薄氷が張るほどの冷え込みだった。
しばらくすると、侍女が手洗いの用意を持ってきた。
石鹸を泡立てた手に水差しの湯が注がれると、かじかんだ手がいくぶんか解きほぐされていくようだった。
着替えはアンドレが暖炉に火を入れてからにすることとして、ひとまず、長椅子にその疲れた身体を沈めることにした。
暴徒をうまく交わすタイミングでアンドレが教会の祈祷室の扉を開くと、4人は転がり込むように元の世界に戻ってきた。
そして、急いで辻馬車をひろうと、予定通りサントノレ通りのカフェへ向かった。
ディアンヌの胸で輝く薔薇のブローチが、あれが夢ではなかったと証明しているが、アランもどうしてあんなことが起こったのかということにはついては、あえて何も聞いてこなかった。
ただ、最後まで物問いたげな眼差しを向けていたのは、父に言った『真実のために戦う』という言葉についてだろうと理解した。
だが、それをアランに言うには時期が早すぎた。
来年早々にはフランス全土で三部会議員の選挙が行われる。
そして、開催後の警護は当然のことながら衛兵隊にも任せられる。
三部会開催で道が開けたのではなく、道を切り開いていくのはまさに、そこからだった。
オスカルは何気なく、暖炉の上の飾り時計に目をやった。
まだ5時にもなっていない。
いつもよりずっと早い時間の帰宅にも関わらず、こんなに疲れているのは別の世界から疲れを持ち帰ったせいだろう。
病気の治療結果を持ち帰れるのだから、疲れも当然、付いてくる。
オスカルは視線を元に戻したが、その直前に暖炉の中でなにかが光った。
しかし、これも疲れのせいだろう。
オスカルは内ポケットから例の嗅ぎ煙草入れを取り出すと、仕舞い場所を考えた。
父上に見つからなければ、それでいい。
なら、シリンダーデスクの一番奥の引き出しが最適に思えた。
そっと、その小箱を仕舞い込むと上に手紙の束を載せてみた。
これなら、誰も触るまい。
再び、暖炉の前を通りかかると、やはり中で何かがきらりと光っている。
アンドレが来るのを待てばいいのだが、なぜか気になって暖炉の前に身をかがめてみた。
そして、手を伸ばすとつるりとした冷たい手触りの何かが触れた。
指で挟んでみたが、そっと取り出さなければ燃え尽きた薪の間に落ちてしまう。
オスカルは慎重に取り出そうと前のめりになったせいで、身体のバランスを崩し、前へつんのめってしまった。
怪我をしないためにも、とっさに洗ったばかりの手を暖炉の奥の壁にドンとついて体重を受けることにした。
だが、受けることにしたつもりが、そこに壁はなく、オスカルはその勢いで自ら暖炉の中へ-正確には
暖炉の奥へ-身を投げるはめになってしまった。
またしても、あの感覚・・・浮いているのか沈んでいるのか分からないような感覚に捕らわれながら、時間と空間の狭間にある闇の中を漂い始めた。
しかも、今回はたった一人で。
一人という心細さが、この暗闇の中での不安をいっそう、増強させていた。
いったい、今度はどこへ行き着くのだろう。
無事に帰ってこられるのだろうか。
疲れを残す程度で帰ってこられればいいが。
もし、向こうの世界でなにかがあれば、もうアンドレと会うこともできないのだろうか。
あれやこれや考えているうちに前方にうっすらとした明かりが見えてきた。
オスカルは必死に手を伸ばし、何かを掴もうとした。
手に触れたのは木のぬくもりだった。
その小さな木のドアを押し開くと、そのまま地面へどすんと腹ばいで横たわる形で向こうの世界へ着地した。
地面には青々と草が茂り、自分を取り囲んでいるのは隙間だらけの小さな小屋の壁だった。
立つこともできなければ、足は入ってきたドアの外に出てしまっている。
犬小屋を少し大きくしたようなその小屋は、なんのための物かも見当もつかないが、鼻くうに漂うこの木々の匂いからすると、ここは間違いなく森の中だった。
外に人の気配があるわけでもない。
オスカルは目の前にあるもうひとつのドアをそっと押し開いてみた。
開けば、そこには静寂と、時折、聞こえる小鳥のさえずりと、そして胸いっぱいに吸い込みたくなるような森の木々が放つ自然の香りだけがあるはずだった。
だが、違った。
「うわーー!!うわーー!!」
ドアを開くと同時に、オスカルの耳をつんざくような子供の叫び声が響き渡った。
その亜麻色の髪をした子供はドアから顔だけだしたオスカルの姿を見て、まるで森の精霊にでも出くわしたかのように慌てふためいて走り去っていった。
今まで、『扉』をくぐる時はなんらかの意味を持っていた。
今回はいったい、なんだというのだろう。
出会ったのは、今のところ子供一人。
それに、まだ過去とも未来とも分からない。
オスカルは訝しがりながら、その小屋から這い出した。
あたりを見渡すと、間違いなく森の中で、耳を澄ましても往来の人のざわめきや教会の鐘の音など、まったく聞こえてきそうになかった。
入ってきた方のドアに回り込むと、まだドアは開いたままだった。
とりあえず、そのドアを閉め、もう一度、反対側に戻ってみた。
今、もう一度、この小屋に入り、入ってきたドアを開けば元の世界に帰れるかもしれない。
こんな、いつのどこかも分からない場所にいるよりも、その方がよっぽど安全に思えた。
オスカルは一呼吸つくと身をかがめて、その小屋のドアに手をかけた。
「ほんとだよ!僕達の秘密基地から金髪の女の人が出てきたんだったら!」
遠くでしゃべっているのか、近くの木の陰にでも隠れてこちらを見ているのか、さっきの子供の話し声が聞こえてきた。
そんなものは無視して、小屋に入り『扉』をくぐってしまえばいい。
「どんな?」
「どんなって、よく見てないから分かんないよ。ジョルジュ、見てきてよ!」
「僕、やだよ!アンドレ、見てきてよ!」
ジョルジュもアンドレもよくある名前だった。
もし、今、自分の姿が見える位置に彼らがいるのだとしたら、小屋に入っていった人間が次の瞬間には消えていたという事実を見せ付けられることになる。
だが、それがどうしたというのだろう。
まだ、7歳になるかならないかのような子供だった。
いつか大人になれば、昔、そんな不思議なことがあったと昔語りができるだけだ。
だが、なぜか気になった。
オスカルはそっと、後を振り返ってみた。
すると、一番太い木の幹に隠れながら、三人の子供がこちらをじっと見つめていた。
一人は、最初に会った亜麻色の髪の少年、そして茶色い髪にそばかすだらけの顔をした、似たような年の男の子。
そして、一番後ろから不思議そうにこちらを眺めているのは、木漏れ日を照り返す黒葡萄の巻き毛、くるりとした黒い目、ふっくらした頬に挟まれたもの言いたげな唇をした懐かしい面差しの少年。
その懐かしい面差しそのままに、その少年はこちらの様子を遠慮がちに眺めていた。
オスカルは思わず、息を飲んだ。
そして小屋のドアにかけた手を離すと、少年達の方に身体を向けた。
ごくりと唾を飲み込んだ後、子供達に声をかけてみた。
「やあ、この小屋は君達のものなのか?」
三人の少年たちはビクンと身体を固くした。
「女の人じゃないじゃないか、アルマン」
最初に会った亜麻色の髪の少年はアルマンというらしい。
「だって、最初は顔しか見えなかったんだもん」
「そうだよ。僕達が作った秘密の基地なんだ」
アンドレが口を開いた。
「そうか・・・」
こんな高い声をしていただろうか、子供の頃のアンドレは。
そして、自分と会う前はこうして男の子同士で遊んでいたのだ。
「ムッシュウは何をしてたの?」
少年達は木の陰から出てきた。
「森を散歩していたら疲れてしまってね。君達の基地で昼寝をさせてもらっていた」
三人は顔を見合わせた。
「ムッシュウはどこから来たの?」
「ベルサイユだ」
「あの、ムッシュウは貴族?」
「そうだが、なにか不都合か?」
三人はまた顔を見合わせた。
「貴族は僕達とそんな風にしゃべらないよ」
アルマンがおずおずとした口調でオスカルを見上げた。
「私は君達ともっと話がしてみたい。どうだ?」
オスカルはやわらかく微笑み、少年達の反応を待った。
「うん!」
一番うしろのアンドレが元気よく答えた。
こんなにも人懐っこい子供だっただろうか。
ジャルジェ家に引き取られてきた当初は表情も固く、どこか寂しげな表情をしていることが多かった。
三人の少年達はそろそろとオスカルに近づいてきた。
「ムッシュウはよく森を散歩するの?」
「いや、今日だけだ」
「いつもは何をしてるの?」
少年達の興味はつきることがなかった。
大人達は忙しく、自分達と遊んでくれる暇などなかった。
そして、今、目の前にいる大人は自分達が知っている大人とはずいぶん違っていた。
「宮殿の警護をしている」
「え?兵隊さん?」
子供達の目がとたんに輝きだした。
三人はそわそわとし、小声で何かを囁きあい出した。
「おい、ジョルジュ、あれ持ってこいよ!」
アルマンがジョルジュを肘でつついた。
ジョルジュは小屋に走って行くと三本の棒切れを持ち出してきた。
そして、一本ずつアルマンとアンドレに手渡した。
それを三人は右の小脇に抱えた。
どうやら、銃のつもりらしい。
たしかに、片方の先端は二股になっていて銃床のようにも見える。
オスカルは思わず、くすりと笑いをこぼした。
「ねえ、号令かけてよ」
アルマンがねだった。
その真剣なお願いが、いかにも子供らしく、オスカルは思わず口に手をあて笑ってしまった。
しかし、三人の子供達の必死な表情に負け、オスカルは姿勢を正した。
「よし!整列!」
オスカルの号令が静かな森の中に響き渡った。
とたん、三人は横一列に等間隔に並んだ。
慌てたアルマンは足を開いたままだったのを、オスカルに直された。
「捧げ、銃!」
子供達はどうやったらいいか分からずに、とりあえず銃を掲げてみた。
「両手を使って、こうだ」
「もっと、高く」
「まっすぐにだ」
オスカルはひとりひとり、丁寧に直してやった。
「そうだ」
褒められると三人の表情は一段と輝いた。
「では、この姿勢のまま一人ずつに質問をする」
三人は一瞬、きょとんとしたが姿勢を崩すことなく、質問に備えた。
「まず、アルマン。どうして秘密の基地を作った」
「基地は敵に秘密にしといた方がいいと思ったからです、隊長」
凛としたアルマンの声が響いた。
しかも、最後に隊長と付け加えて。
大真面目な兵隊ごっこにオスカルは噴出しそうになるのを必死でこらえ、次の質問をした。
「では、ジョルジュ。君達の敵は誰だ」
「プロイセンです、隊長」
「そうか、プロイセンか。では、アンドレ。プロイセンに勝つにはどうしたらいい?」
アンドレは必死で考えているようだったが、そのうちほっぺを膨らませ唇を尖らせた。
「僕の質問だけ難しいです」
そう、少年アンドレはぽつりとつぶやいた。
これはたまらない・・・と思ったが、笑いは胃袋の中に押し込んだ。
「じゃあ、アンドレは何歳だ」
オスカルは自分が一番、聞きたかった質問に変えてみた。
すると、アンドレが答える前にジョルジュが口を挟んだ。
「アンドレは今日が誕生日なんだよ!」
オスカルは微笑んで、視線をアンドレに戻した。
「で、何歳になった?」
「7歳」
アンドレ・グランディエ、7歳。
1761年8月26日。
そのアンドレの答えが、オスカルを現実に引き戻した。
この時から、約30年後、この子達はおもちゃの武器を本物の武器に持ち替えることになるのだろうか。
そして、敵は貴族・・・
飢えと貧困から、王室と貴族・僧侶に銃を向けるときがやがて、やってくるのだろうか?
その時、私とアンドレは・・・
いつか、この子達と対峙する日。
その時、私はこの子達に恥ずかしくない自分でいられるだろか。
オスカルはもう一度、子供達を見渡してみた。
子供達は何も言わなくなった隊長を、ただじっと見つめていた。
アルマンの眉頭を上げ、口を少し尖らせていた。
ジョルジュはアルマンとアンドレの顔を交互に覗き込んでいた。
そしてアンドレは、真ん丸い目でオスカルを上目遣いに見上げていた。
ああ、願わくば、彼らが武器を手にするのはけっして憎しみのためではないことを。
自分達の思想、フランスの将来、人類の未来のためたらんことを。
だが、この子達が自分で正しい道を選べるだけの知識を誰が授けるのだろう。
まともな教育さえも受ける機会が乏しいというのに。
オスカルは子供達から視線をはずすと、奥歯を噛み締めた。
「大丈夫?ムッシュウ」
子供達はもう木の銃を下ろしていた。
子供というのは大人の表情の変化に敏感だ。
「近くの池に白鳥が来てるんだ。見たい?」
アンドレが無邪気な顔で声をかけた。
もしかしたら、無邪気を装っているだけかもしれないが。
「ああ」
オスカルは震えるような声で返事をすると、笑顔で少年達を見つめなおした。
「じゃあ、こっちだよ!」
アルマンが先頭に立ち、ジョルジュとアンドレがオスカルの手を引っ張った。
いつか、この子達と同じ方角に向かって走って行ける日がくるのだろうか・・・
1761年8月26日。
アンドレ・グランディエ、7歳の誕生日。
パリの森には三人の子供達の笑い声が響いていた。
![]()
![]()
拙サイト開設記念日ということでオンディーヌさまが、
お贈りくださいました。
アンドレのお誕生日にこんなにピッタリのお話に感涙です。
そしてこの先の展開がどうなるのかワクワクドキドキしています。
オンディーヌさま、本当にありがとうございました。
胸いっぱいのさわらびより(笑)
![]()
-番外編Ⅱ-

