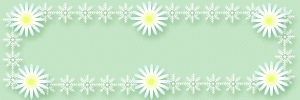
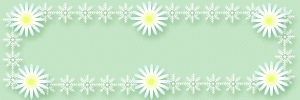
〜Fanfan La Rose〜
子供達に案内されるまま、木々によって日光も視野も遮断されがちな森の中を走っていくと、いきなり前方に明るく開けた空間が見えてきた。
先頭を走っていたアルマンは歩みを止めて、後を振り返った。
そして、唇に人差し指を当てると、後に続く三人に物音をさせないように無言の指示を出した。
当然、ジョルジュもアンドレも忍び足になり、オスカルもそれに習った。
途中、オスカルが落ちていた小枝を踏んでしまい小さな物音をたてると、三人は同時に振り返った。
アルマンは諌めるような顔つきで、ジョルジュは驚いて、そしてアンドレは心配そうな顔でオスカルを見上げていた。
しばらく前から、離してしまっていたオスカルの手をアンドレが再び握ると、今度は木の枝や小石の落ちていない場所を選んで案内した。
自分の手を包むアンドレの手は小さく柔らかく、そして、しっとりと汗ばんでいた。
今のアンドレの手は、自分の手も頬もすっぽりと押し包んでしまうほどだが、子供のアンドレの手は自分の指を握りしめているのがやっとの大きさだった。
「あ、ほら、いたよ」
先頭のアルマンが振り返って囁いた。
確かに、池の真ん中に葦の茂みがあり、そこから長い首とくちばしをのぞかせている。
「こっちの方がよく見えるよ」
「いつもは2羽いるんだ」
オスカルは合図されるまま、木陰に腰を下ろした。
しばらくすると、白鳥は茂みからその優雅な姿を現した。
日の光が水面を静かに照らし、小鳥もさえずりを止めていた。
「どうして白鳥はすべるように水の上を泳げるの?」
音のない空間にぽつりとアンドレの言葉が漏れた。
アンドレは前方を向いたままで、その問いは特定の人に向けられたものでもないようだった。
「水かきのついた足を水面下で動かしながら、前に進んでいる」
アンドレの小さな頭を見下ろしながら答えてやると、すかさずアンドレが振り返った。
「水面下ってなに?」
「水の中ってことだよ」
少し離れたところに座っていたアルマンが、覗き込むように声をかけた。
「アルマンは難しい言葉をいっぱい知ってるんだ」
ジョルジュは自分のことのように、得意げに友のことを語った。
「難しい言葉は父さんが教えてくれる。綴りも」
「そうか」
そう答えながら、父親が不在であろうアンドレが気になったが、アンドレは別段、寂しそうな表情をしている風でもなかった。
「君達、自分の名前は書けるか?」
「うん!」
そう言うと、三人は近くに落ちている小枝を探し出した。
そして、それぞれのファーストネームを地面に書き始めた。
それを眺めながら、オスカルはなぜかほっとした。
文盲のまま生涯を終える平民も多いのに、この子達はとりあえず自分の名前だけは書ける。
「では、苗字はどうだ?」
アルマンとジョルジュはオスカルを見上げると、得意げに微笑み、自分達の苗字を名前の後に書き足した。
だが、アンドレは二人が書いているのを、ただじっと見つめているだけだった。
水面では白鳥が片方の翼を持ち上げ、身づくろいを始めていた。
「アンドレの苗字は・・・」
オスカルはアンドレの持っていた小枝を取り上げて、思わずGの字を書き始めようとして、ハッとした。
「アンドレの苗字はなんという?」
「グランディエ」
「そうか。では、こうだ。G・R・A・N・D・I・E・R、アンドレ・グランディエ。いい名前だな」
アンドレは真っ直ぐにオスカルを見つめ返し、「うん!」と今までで一番大きな声で答えた。
そして、自分の名と苗字を地面に書き始めた。
「アンドレの父さんは仕事で外国へ行ってるんだって。でも、帰ってきたときは、いつも僕達とも遊んでくれるんだ」
アンドレの綴りを見ながら、アルマンの声が明るく響いた。
「そうか」
アンドレはその言葉を肯定するわけでもなく、ただうつむいて口もとをきゅっとひきむすんだ。
もしかしたら、この頃のアンドレはもう、父親が仕事ではなく戦争のために家を離れていることを悟っていたのかも知れない。
「今年もノエルには帰ってくるんだよね、アンドレ」
ジョルジュの言葉はいつも思いやりに溢れていた。
アンドレはもう一度、自分の名前を綴りながら、「うん」と小さく答えた。
次の言葉を発する者は誰もなく、アンドレが小枝で地面を削る音だけがリズミカルに響いた。
子供の頃はこんなにもゆっくりと時が流れただろうか。
ちょうどその時、池の方からバタバタという鳥の羽ばたきが聞こえてきた。
4人が目を向けると、いつのまにか現れたもう一羽の白鳥とともに、二羽の白鳥が池を飛び立とうとしているところだった。
「あ、2羽そろった」
「おそらく、つがいだな」
オスカルの言葉に子供達が不思議そうな顔で問うた。
「ふふっ、夫婦ということだ」
「へえ」
「また、この池に帰ってくるよね」
「おそらくな。それより、君達は子供だけでこんな森で遊んでいて怖くないのか?」
子供達は、今度は首をすくめた。
「ほんとは、森で遊んじゃいけないんだ」
「ばれたら、父さんに怒られる」
ジョルジュがおどけて舌を出した。
「では、送っていこう」
「ほんとに?ムッシュウが?」
「僕達の家はこっちだよ」
子供達はすっくと立ち上がると、アルマンとジョルジュがオスカルの手を引いた。
その後をアンドレがついてきた。
オスカルはアンドレの足音が自分から遠のくことのないことを確認しながら、森の出口へと向かった。
ただ、時折、ふと不安になり振り返るとアンドレはややうつむき加減に後をついてきていた。
「これ見て!」
アルマンが木の幹を指差した。
それはちょうど、子供の目線の高さに刃物で付けられた印だった。
隣の木にも、またその隣の木にも同じように印が付けられていた。
「ここから奥へは入っちゃいけないんだって。アンドレの父さんが付けたんだ」
「約束やぶっちゃってるけどね」
ジョルジュがおどけて、そう言った時、4人はちょうど森を抜け森と畑の間に沿って造られた馬車も悠々と通れるほどの幅の道に出た。
「僕とジョルジュの家はあっちなんだ」
アルマンが左を指して言った。
「では、私はアンドレを家の近くまで送っていこうか」
アンドレが満面の笑顔で答えると、ジョルジュがオスカルの手を引っ張った。
「ねえムッシュウ、また僕達と遊んでくれる?」
「ああ。だが、もう子供達だけで森で遊ぶのは止めた方がいい。入っていいのはアンドレの父さんが付けた目印のところまでだ」
オスカルに見つめられると子供達は笑顔で約束した。
「うん。分かった」
「次は大砲の使い方を教えてね」
そう言うと二人は何度か振り返って手を振りながら、走り去っていった。
二人が行ってしまうと、アンドレはオスカルの手を握った。
そして、二人とは反対方向へ歩きだした。
「父さんが帰ってきたら、あの秘密の基地を見せてやるんだ」
「そうしたら、森で遊んでいたことがバレてしまうではないか」
「うん。でも、いいんだ。怒られるだろうけど、きっとその後で褒めてくれる」
オスカルを見上げて話すアンドレの表情はすっかり、うちとけてしまっている様子だった。
「ねえ、ムッシュウは名前なんていうの?」
オスカルは一瞬、躊躇したが、自分の名前がそれほど珍しいものではないこと、また子供の一日一日というのは多彩過ぎて、今日の出来事がアンドレの幼少期の思い出として残っていくとは限らないことなどを考え合わせ、答えることにした。
「オスカルだ」
「僕達、友達だよね」
子供の会話というのは、単純だが、大人が想像するのとはまったく違う方向へ発展していってしまうものだと、オスカルは微笑んだ。
「ああ」
「じゃあ、名前で呼んでもいい?」
「いいとも」
二人が話していると道は緩やかに蛇行し始めた。
するとアンドレはぴたりと歩みを止めた。
「母さんだ。母さんが呼んでる」
その声はオスカルには聞こえなかったが、しばらくすると、道の向こうから若い女性が辺りを見回しながら、こちらに歩いてくるのが見えた。
アンドレが手を振ると、その女性は一瞬、きょとんとしたようだったが、息子の姿を確認するとこちらに向かって駆け出した。
若い身体は弾み、黒い巻き毛がその肩で跳ねていた。
「アンドレ、母さんの名前はなんという?」
「カトリーヌだよ」
オスカルは初対面のアンドレの母への挨拶の用意をしたが、彼女が近づいてくるにつれ、彼女の心がその足取りよりも急いていること、その若さ美しさが得体の知れない恐怖によってかき消されてしまっているのが分かった。
カトリーヌはやっとの思いでオスカルの前まで駆け寄ると、膝を折り、両手を膝の上で握り締めた。
「どうか、どうかお優しい旦那様、この子の父親は不在で母親の私ひとりで育てております。躾の行き届かない点はすべて私の責任でございます。この子の無礼はどうぞ、その慈悲深いお心でお許し下さいませ」
息絶え絶えにそう一気に言い切ったカトリーヌは、まだ顔を上げようとはしなかった。
母親の様子に驚いたアンドレはオスカルの手を離し、母親の横に歩み寄りそのスカートを握った。
それと同時にオスカルはカトリーヌの握り締めた両手をふわりと自分の手で包み込んだ。
「どうかマダム、あなたを驚かせてしまった私の愚かさをお許し下さい」
低く静かな声にカトリーヌはやっと顔を上げた。
「アンドレと、そしてジョルジュとアルマンに私は遊んでもらっていたのです。おかげでとても楽しい時間を過ごすことができました。どの子も優しく賢い。さぞかし、ご子息がご自慢でしょう」
青ざめていたカトリーヌにやっと安堵の表情が戻った。
それと同時に、緊張から解き放たれたカトリーヌの膝から力が抜け、その場に崩れ落ちそうになった。
オスカルはすかさず、カトリーヌの腰に手を回し抱きとめた。
「あなたをこんなにも驚かせてしまって、私はどうお詫びをしたらよいか・・・」
「お詫びなどと・・・」
カトリーヌは半分、オスカルの手に体重を預けたまま、あらためてオスカルの顔を間近で見た。
目の前に広がる金髪の髪、吸い込まれそうな深く青い瞳、何人の女神達が嫉妬するのだろうというほど整った顔立ち。
まるで、夢の中に迷い込んだような錯覚に捕らわれそうだった。
そんな彼女を、スカートを引っ張るアンドレが現実の世界に引き戻した。
アンドレを引き寄せると、カトリーヌは自分の足で立ち直した。
「アンドレを探していたのは、何か急用があったのでは?」
カトリーヌはやっと、なんで家事の手を止め、家を飛び出してアンドレを探していたのかを思い出した。
「ええ。この子の父親から手紙が届いたのです」
「それは、とんだお邪魔をしてしまいました。お会いできて光栄でした、マダム」
オスカルはそう言うと、カトリーヌの手を取りキスを送った。
「では、失礼」
そう言うと、戸惑っているカトリーヌときょとんとした表情のアンドレに背を向け、もと来た道を引き返した。
しばらくすると、母親の手を振り切ったアンドレが追いかけてきて、オスカルの前に回りこんだ。
そして、ズボンのポケットを探ると何かを探り出し、オスカルの手の上にのせた。
それは、つるりとしてひんやりとした記憶に新しい手触りの物だった。
こちらの世界に転がり込む前に、暖炉の中からつまみ上げた何か、それはこの水色の石だったのだ。
「父さんにあげようかと思ったけど、オスカルにあげる」
「私に?」
「うん。オスカルの瞳ほど青くないけど綺麗でしょ?」
「ああ」
「あのね、父さんがノエルに帰ってくるんだ。王様がいつもより長い休暇をくれたんだって」
「そうか」
嬉しそうに話すアンドレの頭をくしゃくしゃっと撫でてやると、アンドレは母親のもとへ走り去って言った。
途中、振り返り、何度も手を振っていたアンドレがなにかを叫んだ。
「オスカル、また会える?」
オスカルは軽く手を上げ答えて見せた。
「ああ、きっとな」
遠ざかる母子の姿を見届けるとオスカルは再び、森の中へと入っていった。
アンドレ、父さんは怪我も病気もしていないんですって。
今度のノエルには長い休暇がもらえるそうよ。
なんでも、4人の英雄のおかげで誰も怪我をせずに戦争に勝てたご褒美だって手紙に書いてあったわ。
ノエルの料理はなにを作ろうかしらね。
飾りつけもいつもより豪華にしましょうね。
アンドレも手伝ってくれる?
いままでで一番、素敵なノエルにしましょうね。
父さんとアンドレと母さんで。
−番外Ⅲ−

