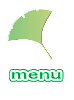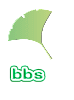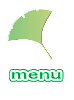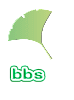突然ノルマンディーのどんぐり屋敷で暮らすことになったアンドレは、ここをオスカルが快適に暮らせる場所にするため、日夜、心身を酷使していた。
一方、絶対安静の身でありながら、セーヌ川をパリからノルマンディーまで船で下ってきたオスカルは、もはや息をする以外の動作を全て禁じられたかのごとき暮らしを余儀なくされて、かえって息が止まりそうなくらい腹立たしくも苛立たしい日々を送っていた。
それは、ただただ、やがて生まれ来る命のために…であり、これほどの大義名分はないのだが、オスカルにとっては、フランスのために、国王のために、国民のために…というのは何の抵抗もなく受け入れられたのに、この体内に宿っているらしい命のため、と言われても、今ひとつ合点がいかない。
というか、納得できない。
これはおそらく男として育てたジャルジェ将軍に起因するもので、決してオスカルのせいではないのだが、わかっていても、面と向かって、我が子が腹の中にいることに納得がいかない、と言われてしまうと、腹の子の父であるアンドレとしては、あまりに悲しい。
というか、情けない。
そういうちょっとイビツな形の夫婦を、使用人たちは不思議そうに見守っているが、まったく違和感なく受け入れているのが、オスカルの姪、ニコレットだった。
ニコレットは父、バルトリ侯爵からは容姿を、母クロティルドからは性格を、それぞれに受け継いだと思われ、従ってジャルジェ家の金髪碧眼は持ち合わせていない。
しかしながら、父は充分に美男子であったので、黒髪に黒い瞳のエキゾチックな非常に美しい少女に育っている。
育っているが、彼女自身はそのことに興味はなく、日々教会に通い、神父の慈善事業に協力することが生き甲斐という、一風変わった…オスカルに比べれば大したことはないのかもしれないが…令嬢である。
彼女は教会では、信者の子どもたちに読み書きを教えている。
もちろん子どもに限らず、字を読めるようになりたい、書けるようになりたいというものであれば大人でも分け隔て無く教えている。
かわいいお嬢さまが先生とあれば、教会の文字教室は大流行で、信者が頻繁に出入していた。
信者の出入の耐えない教会というのは、神父にとっても嬉しいことで、神父はこの若い令嬢に全幅の信頼を寄せている。
信者たちは、侯爵家の中だけにいれば決して触れることはない庶民の暮らしぶりをニコレットに教えてくれる。
彼女がまだ15歳というのに、いやに落ち着いた素振りを見せるのには、そういう理由がある。
人の暮らしは人の数だけ種類があるのだ。
貴族の暮らし、農民の暮らし、商人の暮らし、船乗りの暮らし…。
同じフランス語を話していても、みんな暮らしは違うのである。
ニコレットは、軍人の暮らしはあまり知らないが、それはそれで様々な事情があるのだろうと思っていた。
だから、元軍人の叔母が男の格好をしていることも、使用人のアンドレと夫婦だということも、それはそれで、そういうものなのだと受け止めていたのである。
「オスカル・フランソワ、ちょっとお聞きしたいことがあるんだけど、よろしいかしら?」
15歳のニコレットが33歳のオスカルに話しかけた(この呼び方については『出逢い』参照)。
寝台の上から、顔だけをニコレットに向けたオスカルは「あらたまってなんだ?」と聞いてやった。
8月の終わりとはいえ、まだ暑さが残っていて、窓は開け放たれている。
ニコレットは母からことづかった食糧と書籍を届けるためにどんぐり屋敷に来ていた。
さきほどコリンヌがお茶を出してくれたが、すぐに厨房に引き上げた。
アンドレは町へ買い物に出て留守だ。
「教会の文字教室に来ている方からのご相談なんだけれど…」
こんな小娘に相談するとは、大人ではないな、とオスカルは推察する。
「暇だからなんでも聞くぞ。どんな奴のどんな相談だ?」
「名前はアンヌ、歳は40歳と言ってるわ」
わたしより年上ではないか、それがこんな娘に相談するのか。
オスカルは素知らぬふりを続ける。
「それで?」
「とても大切にしていた聖書が無くなったので捜してほしいそうです」
無論、知恵を貸すということで本当に探しに行くわけではない。
「盗まれたのか?」
「わからないの」
「ではどこかに置き忘れたのではないか?」
「それがわからないそうなの。確かにあったと言えるのは先週のミサの時までで、そのあとわからなくなったって」
「では考えられるのは二つ。ひとつは教会で誰かに盗まれた。もうひとつは、アンナが教会に置き忘れた」
「もし忘れたのなら、誰かが気づいているはずでしょ。でも神父さまに届け出た人はいないそうなの」
「ならば答は出ているではないか」
「やっぱりそうなるわよね」
「当然だ」
「でも、教会で聖書を盗む人なんているのかしら。あまりに罰当たりだわ」
「置き忘れてあったので出来心で盗った、というのが一番有力な説だな。神父からそれらしい説教をしてもらって、盗んだ奴が自発的に返すようしむければよいのではないか。わざわざ狙って盗ったというより、たまたまあったものを盗ったと考える方が自然だ。ということは今度の日曜日も犯人が来る可能性は高い」
「なるほどね。ありがとう、オスカル・フランソワ。これからもう一度教会に行って神父さまにご相談してみるわ」
「健闘を祈る」
そういう会話をしたのが二日前である。
そして今、ニコレットは再びオスカルの寝台の横に腰掛けている。
「今日、神父さまに盗みはいけないというお説教をしていただいたの」
「で、聖書はでてきたか?」
「ええ」
オスカルは大変満足した。
「よかったな」
「それが…」
ニコレットが眉をひそめる。
「どうした?」
「出てきた聖書が違うとアンナが言うの」
「なんだと?」
「お説教が終わって、みんなが帰って、そしたら椅子の上に聖書が置いてあったの。だからてっきりアンナのだと思って、神父さまにアンナを呼び返していただいたの。でもアンナはこれは自分のものではないと言うの」
「では犯人は偽装工作をしてきたということか」
「まあ、オスカル・フランソワ、犯人だなんて…」
「窃盗行為は犯罪だ。アンナが紛失していただけなら違うものか出てくるわけがない。誰かが盗んだのだ。そしてその事実をなかったことにするために別のものでごまかそうとした。これは明らかに犯罪で、犯罪を犯したものは犯人だ」
「とてもシンプルね」
「複雑にする意味がわからん」
「いいわ。では犯人でいきましょう。とにかくアンナの聖書は行方不明のままなのよ」
「そうなってくるとアンナの聖書がどうしてもほしいものの仕業ということになる。なにか特別な聖書なのか?」
「亡くなったおばあさんから譲られた形見で、とても古いものだそうよ」
「古い聖書か…。盗んでまでほしがるとも思えないが…。違うという聖書は持ってきたか?」
「ええ、神父さまのご許可をいただいてここに…」
ニコレットはごそごそと袋から聖書を取り出した。
大きさも形もいたって普通のものである。
表紙は古びた羊の皮だがこれとて珍しいものでもない。
「アンナはどう違うと言ってるのだ?」
「よく似てはいるらしいの。けれど、自分のものは裏表紙にちょっとした落書きがあって、それが目印だったって」
オスカルは手にした聖書をひっくり返し最後の頁をめくってみた。
印刷された文字以外に書かれたものはない。
「どんな落書きか聞いてみたか?」
「右隅に小さく十字架の絵が描いてあったのですって」
再度手元の聖書を確認したがそういうものはない。
「やはりすり替えられたのだろう」
だが理由はわからない。
「アンナは、この聖書をかわりに使うということには納得していないのだな?」
「ええ。これは自分のものではないって。聖書ならどれでも良いというわけではないみたい」
「祖母の形見なら当然だな」
「そこで相談なんだけど…」
「本物を探せ…か」
身動き取れない自分が、頭だけで失われた聖書を探し出せるのか。
だが、ただ寝ているだけよりは面白そうだ。
良い暇つぶしになる。
「よし、わかった。では詳しい話を聞こう」
オスカルは久しぶりに瞳を輝かせた。