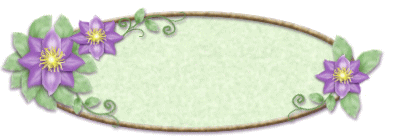
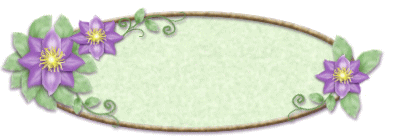
真夏の奇蹟

8

「今日は、いつになく隊長の怒鳴り声がよく響いていたなあ。」
のんびりとしたフランソワの声を背後に聞きながら、フェルゼンは疲れ切った体をひきずるようにして馬車に向かった。
いっそのこと真っ暗になってくれれば身を隠すこともできように、フランスの夏の太陽はいつまでも西に残り、うすぼんやりとあたりを浮かび上がらせる。
まともに食事にもありつけず、オスカルの言うままに右に左に走り回り、最後はあきらめきったオスカルの声で、本日の任務がいつもより早い終了となった。
「アンドレ、おまえ、本当にフェルゼンではないのか?恐ろしいほど無能な動きだぞ。ええい、もうやめだ、やめだ!今日は帰る!」
ここまで罵倒されると、さすがにみずからフェルゼンだと名乗り出ることはできなかった。
彼にも相応のプライドというものがある。
もうかなりズタズタになってはいたが…。
怒り狂ったオスカルの後ろをとぼとぼと歩き、ようやく馬車にたどりついた。
今日はじめてゆっくり座ることができそうな場面だが、目の前に険しい顔つきのオスカルがいるのだ。
とてもくつろげる空間とは言い難い。
オスカルの前に座るのは耐えがたい気もしたが、さりとて隣に座るわけにも行かず、仕方なく、オスカルに続いて馬車に乗り込むと、すぐに顔を窓の外に向けた。
夕景の中、次第に遠ざかる宮殿を見れば、王妃さまが思い出される。
御前に出られない自分の姿が切なくつらく、かといって視線を車内に戻せばオスカルの不機嫌な顔が痛い。
いったいこれは何の罰だろう。
ただただ善意で動いていたはずの自分がどうしてこんな目に遭うのだろう。
フェルゼンの瞳はうつろに空を見つめるほかなかった。
そんな呆けたようなアンドレを見つめるオスカルは、ようやく怒りを収め、アンドレの身に何か起きたのかと真剣に考え始めていた。
そういえば、最近、ためいきをつくことが多かった。
だが、祝賀会に忙殺されているせいだと思い、さして気にもとめなかった。
執事からもアンドレからも縁談の話を聞かされていないオスカルには、深い訳があるなどとは思いもよらなかったのだ。
そのうち元気になるだろうと高をくくっていたら、このありさまである。
ひどい一日だった。
本物のフェルゼンでももう少しましな動きをするのではないか。
何も知らないオスカルは、フェルゼンが聞けば卒倒しそうなことを、かなり真剣に考えている。
だが、昨年末の馬鹿げた入れ替わり以後、アンドレが細心の注意を払ってフェルゼンと遭遇しないようにしているのを知っていたオスカルは、まさか二人が再び入れ替わっているとは思わなかった。
アンドレはオスカルにばれていないつもりだったろうが、当直のシフトの不自然さに気づかないほど鈍感な司令官では、職責をまっとうできない。
恋愛関係ならいざ知らず、この手のことに関してのオスカルは極めて優秀なのだ。
だが、知っていながら、あえて黙認していた。
なぜなら、自分自身も、フェルゼンと顔を合わせたくなかったからである。
最初は、失恋の痛手による理由だったが、ノエルからこっちは、なまじフェルゼンと出くわして、またぞろアンドレと入れ替わられたりしては、仕事が回らないと痛感したからである。
陸軍連隊長としてのフェルゼンはともかく、衛兵隊の司令官補佐としての彼は、箸にも棒にもかからないお粗末さだった。
いない方がまし、とまでは言わないが、ほぼそれに近い状態だった。
それゆえ元の姿に戻ったアンドレが、金輪際フェルゼンには近寄らぬ決意を固めたようであることを、オスカルは是認した。
まさか二人が再び入れ替わっているということは、したがってオスカルにとって想定外だったのである。
双方黙りこくったまま、馬車はようやくジャルジェ邸に到着した。
フェルゼンは慣れぬ仕草で先に降り、オスカルが出てくるのを待った。
不信感の固まりのような一瞥をフェルゼンにくれると、オスカルはスタスタと廷内に入った。
フェルゼンは、うつむきがちにあとに続く。
出迎えのばあやに手袋を渡しながら、オスカルは一言も話さず階段をのぼり自室に引き上げていった。
ばあやと侍女がそのあとを追う。
忙しくて不機嫌なときのオスカルのいつものパターンである。
フェルゼンは、前回覚えたアンドレの部屋に向かってゆっくりと歩き出したが、すぐに執事に呼び止められた。
「アンドレ、大事な話がある。ついてきなさい。」
なにごとだろう、と恐る恐るフェルゼンは執事を見た。
「いいから、とにかくついてきなさい。オスカルさまに気づかれぬようにな。」
よほどの秘め事らしい。
執事がとある部屋の扉を静かに開けた。
執事の執務室のようだ。
フェルゼンが戦々恐々の体で室内に入ると、執事は急いで扉を閉めた。
「お待たせいたしました。フェルゼン伯爵。」
いきなり名前を呼ばれて、ぎょっとして顔を上げると、目の前に自分がいた。
「アンドレを連れて参りました。」
「ありがとう。オスカルには気づかれなかったかな?」
「はい、ご依頼通り、アンドレだけでございます。」
「無理を言って悪かった。何しろ、こちらの勘違いだからね。恥ずかしくてオスカルにあわせる顔がないのだよ。」
スラスラと話す自分の姿にフェルゼンは心底呆然としていた。
なぜ、ここにわたしがいるのか。
いや、これはわたしではない、アンドレ・グランディエだ。
元の姿にもどるためにわざわざやってきたのか。
それなら大歓迎だ。
にわかに表情が明るくなる。
「アンドレ、伯爵さまにご挨拶もしないとは失礼のきわみだぞ。」
執事が厳しい声で叱責した。
日頃から行儀作法において非の打ち所のないアンドレが、どうも今日は態度がおかしい。
無礼な使用人になりかわって執事が慇懃にとりなそうとするのを、アンドレはにっこり笑って受け入れた。
「アンドレ・グランディエ、驚くのも無理はない。実は、きみに紹介した縁談だが、なかったことにしてほしいのだ。どうもわたしが選んだ女は問題ありだったようで…。」
「えっ…?」
フェルゼンは激しく混乱した。
ジェヌビエーブに問題?
なかったことに…?
どういうことだ。
王妃さまのことで頭がいっぱいだったフェルゼンは、ようやくアンドレの縁談のことを思い出した。
「他に思う男がいるらしい。結婚する気はないと言うのだよ。こちらからもちかけておいて情けない話だが、破談にしてもらおうと思ってこうしてやってきた。」
執事が、恐縮きわまりない態度でお辞儀をする。
「伯爵おんみずからおいでになるとは、もったいない限り。アンドレ、よいか。このことは決してオスカルさまのお耳にいれてはならんぞ。おまえの結婚相手についてはわたしも気をつけておくから、今回のことは忘れるのだ。もともとおまえも乗り気ではなかったのだから、文句はあるまい。」
執事にたたみかけるように言われても、フェルゼンは目をぱちくりするしかない。
だが、次第に事の真相が見えてきた。
体が入れ替わったことを千載一遇の機会ととらえたのは自分だけではなかったのだ。
アンドレもまた同様だった。
そして、早速ジェヌビエーブに面会し、好みにあわなかったということか。
よい娘だと思ったのだが…。
それに他に好きな男などいるようには見えなかったが…。
長年の親友が自分を愛していることすら気づかなかったフェルゼンである。
一週間ほどお屋敷仕えをしただけの侍女の気持ちになど気づくはずもない。
徹頭徹尾、自分なりの解釈をしつつ、フェルゼンは、仕方がないとあきらめた。
というか、今はアンドレの縁談などもはやどうでもいいのである。
とにかく早くアンドレと二人きりになって、元に戻りたい。
でなければ、晴れの閲兵が…、王妃さまの護衛が…、とこれまた自分勝手な理由で、彼は勢いよく返答した。
「ありがとうございます。伯爵にそのようにお気遣い賜り、もったいないことと感激いたしております。すべて仰せのとおりにいたします。」
アンドレは、想像以上に聞き分けのいいフェルゼンに驚きつつ、深く安堵した。
これで縁談はつぶれた。
さあ、あとは元に戻るだけだ。
アンドレは執事に向かって礼を言うと、続いてフェルゼンに声をかけた。
「アンドレ、すまないが、オスカルに見つからないよう、厩舎まで案内してくれないか。」
執事は、すぐにフェルゼンに向かって、そうするよう指示を出した。
アンドレとフェルゼンは二人だけでそっと部屋を出た。
無論、厩舎に案内したのは方向音痴のフェルゼンではなく、廷内を知り尽くしたアンドレの方である。
二人は誰にも見つからないよう、そっと厩舎に向かった。