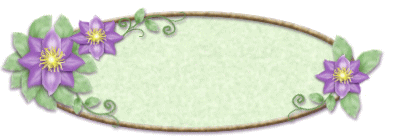
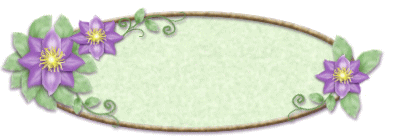
真夏の奇蹟

7

思惑通り、縁談の破棄を勝ち取ったアンドレは、その後、見事な誘導尋問で、爺から、フェルゼンがロザリー似の女性を見つけたいきさつを聞き出した。
どうやらジェヌビエーブというのは、パリのカフェの看板娘だったらしい。
両親が営む店で、引く手あまたの結婚の申し込みを巧みにかわして、いずれ玉の輿をねらっていた節がある、というのが爺の見立てだった。
そこへたまたま通りかかった伯爵が、金色の髪と、優しげな微笑みに、これこそロザリーだ!と勝手に思い込み、強引にフェルゼン家で働かないか、と声をかけた。
彼は営業用スマイルに気づかなかったのだ。
娘は、ずいぶん驚いていたが、しがないカフェで言い寄ってくる男に比べれば、大貴族のお屋敷で働く方が、どんなチャンスが訪れるとも限らない。
ほどなく、両親を説き伏せ、フェルゼン家の侍女として働き始めた。
ほんの一週間前のできごとだそうだ。
こんな風だったから、爺としても、彼女がこの縁談にもっと乗り気になると思ったのだが、とんだ思い違いだった。
大貴族の後継者がもっとも信頼する従僕、いずれは家政をとりしきる執事になるかもしれない男との縁談なら、ジェヌビエーブの育ちからすれば破格の出世のはずだ。
だが、ジェヌビエーブは、爺がもちかけた話に、心底困惑した顔をし、悲しそうに言ったという。
「それはだんなさまのご命令ですか。ご命令ならしたがうしかございませんが…。」
悲しげに目を伏せる女に、爺は、自分も人を見る目がなくなったものだとつくづく反省した。
「爺ももうろくいたしました。あれには下心などなく、やはりハンスさまが随分強引に引き抜かれたのでございましょう。いかにお親しいジャルジェさまゆかりの者のためとはいえ、あまり使用人の私的なことにまでお気を回されるのはいかがなものかと存じます。」
爺はしっかり説教して、退室した。
思えばこちらもかわいそうな話である。
もともとが、アンドレと結婚させるためだけに、両親から引き離し、慣れないお屋敷勤めをさせたのだ。
アンドレも大概伯爵の被害者だと思っているが、最大の被害者はジェヌビエーブかもしれない。
なんとかこのさき身の立つようにしてやらねばなるまい、と思ったアンドレは、さっそく翌日、ジャルジェ邸へ向かう前に、ジェヌビエーブを呼び出した。
彼女の気持ちを直接聞いた上で、親元に帰してやろうと思ったからである。
できればフェルゼンでいる間に、この件はすべて片をつけておきたかった。
爺に連れられて、主人の部屋に入ってきたジェヌビエーブは、中肉中背で、豊かな金髪の持ち主だった。
だが、ロザリーほど目が大きいわけではない。
むしろややきつい感じの瞳である。
似ている、といわれれば、どことなくそんな気もするが、そっくりとは到底言い難い。
伯爵の目は爺以上にあてにならないではないか、とアンドレは密かに思った。
というか、爺が感じた第一印象にかなり近いものを、アンドレも感じ取った。
だが、人は初対面で判断してはならない。
アンドレは椅子に座ったまま、ゆっくりとジェヌビエーブを迎えた。
「お召しにより参りました。」
ジェヌビエーブは、ドレスの両端を持ち、ぎこちなく頭をさげて挨拶をした。
不慣れな貴族の館でのしきたりに、まだとまどっているようだ。
やはりあわれさが募る。
まったく伯爵という人は…。
「やあ、ジェヌビエーブ。わざわざ呼び出したのは他でもない。おまえの縁談のことなのだが…。」
ジェヌビエーブが体をこわばらせたのが、傍目にもあきらかだった。
「そんなに堅くならなくて良い。無理強いする気はないのだ。あまり乗り気ではなかったようだが、それならば、なかったことにしてもかまわないか?実は先方もあまり結婚する気がないようなのだ。」
緊張感が一気にとけたようにジェヌビエーブがほほえんだ。
「はい、一向に…。すべてだんなさまのよろしいようになさってください。」
なかなか魅惑的な声である。
「そうか、それは助かった。まったくわたしの早とちりでずいぶん迷惑をかけてしまった。もし、実家に戻りたいというのなら、すぐにでもそう取りはからうが、どうだ?」
開いた花が急にしぼんだ。
「あ、あの、もう、ここにいてはいけないということでしょうか?」
意外な答えだった。
「おまえがいたいというなら、やめさせたりはしない。なんと言っても連れてきたのはわたしなのだからね。そうだろう、爺。」
アンドレはジェヌビエーブの反応に少々驚きながら爺の意見を求めた。
「もちろんでございます。」
「ありがとうございます。わたし、一生懸命働きます。ですから、ずっとずっとここに置いて下さい。わたし、だんなさまのおそばでいつまでも働きたいんです。」
驚くほど媚び含んだ視線がアンドレに投げかけられた。
強烈な流し目である。
これは、これは断じてロザリーなどではない。
この目は…、ジャンヌだ。
アンドレの背筋を冷たいものが流れた。
あわよくばだんなさまの愛人となってお屋敷のひとつでももらい、子供の一人か二人を産めば、この優しい性質の伯爵なら、一生食いっぱぐれはない。
カフェの常連たちのような金のないものと結婚するより、こちらのほうがよほど良い。
彼女はパリの口さがない連中のうわさ話で、王妃の恋人の名前がフェルゼンだと知っていた。
そのフェルゼンから勧誘されたのだ。
王妃の愛人で独身の貴族ならば、本妻と愛人の争いもなく、いじめられる心配もない。
願ったりかなったりだ。
ジェヌビエーブがあっさり両親の元を出てきた理由と、縁談を断った理由がようやくわかった。
思いもよらぬジェヌビエーブの反応に、アンドレは随分驚いたが、爺の方はさらに衝撃を受けたようで、腰をぬかしそうになっている。
なんという女だ。
こんな女を大切なハンスさまのおそばに置いておくわけにはいかない。
今までの使用人はすべて自分が選んできたのに、今回ばかりは主人が強引に連れてきたので、面接も何もせず雇い入れてしまった。
おまけにすぐに嫁入りさせるというものだから、使用人としての働きぶりも人間性もそこまで徹底して監視しなかったのだ。
言いたくはないが、爺は主人の人を見る目をあまり、というか全く信用していない。
自分の失態に歯ぎしりしそうだ。
やはり自分の第一印象は正しかった。
爺は早々に彼女を連れて退室した。
「とんだ女と結婚させられるところだった。」
一人になったアンドレは背もたれにドンと勢いよくもたれると、大きくためいきをついた。
本性を知らずに見合いさせられ、周囲の圧力に耐えきれず、結婚などに持ち込まれては、一生を台無しにするところだった。
無論、どんなことがあっても結婚する気などないのだが…。
それに、見合いをしても向こうから断ってきそうな気配ではあったのだが…。
これからジェヌビエーブをどうするか、それは執事職を兼任する爺の考えることだ。
気の毒だが主人の尻ぬぐいは使用人の仕事である。
と、考えて、アンドレは自分の主人を思い出した。
国王誕生祝賀会が目前に迫り、恐ろしいほどいらいらしていたオスカルの顔が浮かんだ。
懸案事項を片付けたアンドレは、あわてて本来の姿に戻るために行動を開始した。