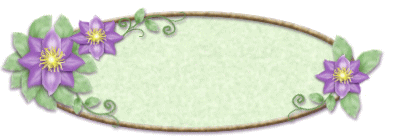
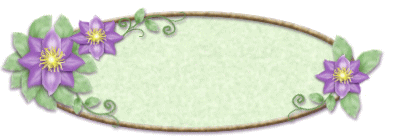
真夏の奇蹟

6

翌朝、出仕の規定時間より幾分早くオスカルが出勤してきた。
フェルゼンは意気揚々と彼女を出迎えた。
さあ、ここからががんばりどころだ。
善良なフェルゼンは、オスカルの顔色をうかがうなどという器用なことなどまるっきり忖度せず、おはようの挨拶もそこそこに本題に入ろうとした。
「オスカル。ちょっと話がある。」
ギロリと鋭い視線がフェルゼンに向けられた。
一瞬、フェルゼンはたじろいだ。
おそらく本物のアンドレならオスカルの機嫌を即座に察し、口を閉じるところである。
それほどオスカルの機嫌は悪かった。
当然オスカルは、アンドレが黙ると思った。
だが、このアンドレは、アンドレではない。
「あ…、え…と、実は昨夜、庭園で…」
と言いかけたとたん、オスカルはブチ切れた。
「この忙しいときに、フェルゼンごっこなんぞするな、馬鹿者!」
フェルゼンの思考が凍り付いた。
「え…?フェ、フェルゼンごっこ?」
なんだ?
そんな遊びがあったか?
脳内を疑問符がすきまなくとびかう。
だが、怒り心頭のオスカルは、フェルゼンの反応など完全無視である。
「いいか、国王陛下のお誕生日まで、あとわずかなんだぞ。悠長にごっこ遊びをしている場合か!二度とフェルゼンのまねなんぞするな、この大馬鹿者!!」
大きな石が頭上に落ちてきたようなショックだった。
馬鹿者、さらには大馬鹿者…。
フェルゼンのまねをするのは馬鹿者なのか…。
ようやく意味がわかりかけてきた。
あの入れ替わり以後、オスカルとアンドレは、空気が読めない態度のことを、フェルゼンごっこと呼んでいたのだ。
機嫌のいいときのオスカルは、アンドレがちょっとしたミスをすると、
「おい、おまえ、本当にアンドレか?実はフェルゼンではないのか。」
とからかった。
するとアンドレも調子に乗って、
「ばれたか。実は昨夜、庭園で…。」
と受け、そろって大笑いしていたのだ。
だが、もちろん気が立っているときのオスカルは、そんな冗談は言わない。
ましてアンドレから言うこともない。
何も知らないフェルゼンは、たまたま、このふたりのフェルゼンごっこの決まり文句を、最低最悪の状況で口にしてしまったというわけである。
「ぼやぼやしていないで、さっさと近衛に顔を出してこい。祝賀会当日の警備の配置は、いったいどうなってるのか、聞き出してくるんだ。まったく上が仕事をせんから、何の情報も降りてこない。結局、こっちが各方面に頭を下げて仕入れるしかないのだ。」
ブイエ将軍の嫌がらせだということはあきらかだった。
両陛下のお気に入りという憎たらしいジャルジェ准将に、わざと情報をおろさず、御前で恥をかかせようというのだろう。
だが、そのような内情は、今のフェルゼンにとってはどうでもいい。
彼は、仕事ができないことをフェルゼンごっこ、と言われていた事実にうちのめされていた。
これでも…、これでも陸軍連隊長だぞ、と思ってから、はっと気づいた。
国王陛下の誕生日祝賀会には、御前で閲兵式を執り行う、晴れの栄誉を与えられていたのだ。
もちろん王妃の意向である。
フェルゼンの貴族としての正装姿もさることながら、武官としての礼装もことのほか素晴らしい、と常々賞賛してくれる王妃が、数ある軍隊の中から、わざわざフェルゼン旗下の陸軍を選び、閲兵式を行うよう指示したのである。
人目もはばからず、ほれぼれと彼の姿を見つめる王妃を、周囲がどのような思いで受け止めているかには、いくつになっても無邪気な彼女は気づかない。
好きな人に親切にして何が悪いの?わたくしにはその力があるのに、とすら思っている。
政治的影響力を発揮しないフェルゼンはともかく、完全に王妃の寵愛で出世街道をばく進したポリニャック伯夫人の存在が、結局王妃の周囲から貴族を遠ざけていることには思い至らない。
諸々鈍感なフェルゼンも、愛する人に冷たい宮廷の空気はしっかり感じ取っていたから、この祝賀会では、必ずや王妃の盾となってお守りせねば、と思っていたのである。
どこまでも王妃一途のフェルゼンだった。
しかるに…。
今の自分の格好では、王妃の御前にでることなど、到底望むべくもない。
怒鳴り散らすオスカルのもとで下働きを強いられるのが関の山だ。
ああ、千載一遇のチャンスなどと、何を思っていたのだろう。
急いで戻らねばならない。
だが、触れれば全身の毛を逆立てる猫のようなオスカルに、今更、自分はフェルゼンで、早く戻りたいから屋敷に帰る、とは言い出せなかった。
「何をもたもたしている!さっさと行ってこい!」
ついに雷が落ちた。
フェルゼンは仕方なく司令官室を出た。
彼は、身から出たさび、という言葉を知らなかった。