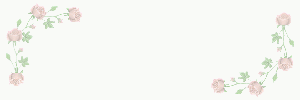オスカルは案内されるまま、カフェの窓際の席に座った。ひとつおいて隣の席には、待ち人のある様子の20歳前の娘が一人、冷めた紅茶を前に心もとなげに座っていた。髪や服の襟元をしきりに気にしている様子からみれば、待ち人はおそらく恋人なのだろう。華美ではないが、外出用のローブは着古した様子もなく、髪は小さくまとめ、化粧も口紅だけだが、それで充分、彼女は美しかった。おそらく恵まれた平民の家庭の娘なのだろう。身なりからだけでなく、男性に待たされるのを厭わない様子からすれば貴族ではないことは明らかだ。
オスカルは運ばれたカフェを一口飲むと、中庭に目を移した。今日は冷え込みが厳しく、いちいの木がその緑の枝を冬風に揺らせていた。明日からの仕事の調整のためにパリの留守部隊まで、出かけてきたのだが、その用が済むとアンドレがついでに金物屋で屋敷の用も済ませたいと言い、結局、カフェで待ち合わせることとなった。
オスカルが中庭をぼんやり眺めていると、人が慌てて入ってきた気配がした。
「またせたね。イヴォンヌ!」
男は待っていた娘よりも、ふたつみっつ年上で、これまた簡素だがきちんとした身なりをしていた。役人か弁護士か、あるいは貴族の屋敷に雇われている家庭教師か、おそらくそういった職業の人間だろう。
娘はその唇にのせた紅よりも、さらに頬を赤らめて青年の瞳を見返した。
「いいえ、ちっとも」
青年はテーブルの上に置かれた娘の手を握ると、自分も腰掛け、カフェを注文した。
オスカルは小さな溜め息をついた。
―ふっ・・・『いいえ、ちっとも』・・・か・・・
間違っても、私の口からは聞けぬ言葉だ。
オスカルが自嘲気味な笑みを浮かべていると、カフェの入り口にアンドレが姿を現した。
店内を見渡すとすぐにオスカルを見つけ、大きな体を軽快に切り返しながらテーブルの間をすり抜けて、オスカルの前に立った。
「すまない、オスカル。待たせたか?」
「ああ、小一時間ほどな」
思わず、口から出た自分の皮肉めいた言葉にオスカルはクスッと笑いを漏らした。
「この店のはす向かいにあった小間物屋が店じまいしたらしい」
アンドレはそう言いながら、席に着いた。
「ああ、不景気だからな」
そう言って、オスカルはまた中庭に目を移した。
「いちいの木か・・・こんなご時勢でもあの木だけは元気だな」
運ばれたカフェを口に運びながら、アンドレも中庭に目を移していた。
「モーツァルトはもう、ウィーンに着いただろうか?」
「まだ、うちの御者からは連絡がないが、そろそろ送り届けて、帰路についている頃だろう」
「パリからウィーンか・・・遠いな」
「昔、王妃様が御輿入れの時に通った道だ」
「私達もいつか行くときがあるのだろうか?ウィーンへ」
突拍子もないオスカルの言葉にアンドレは小さく笑った。
「当分の間はパリとベルサイユの外へは出られないことだけは確かだな」
無粋なアンドレの返答に少し不服そうな表情を見せると、オスカルはアンドレから視線を外した。
店の入り口にはちょうど、30後半から40代の男が二人、店員に壁際の席に案内してくれるよう指示していた。二人は席に着くが早いか、書類を広げ商談に入りだした。
「見ろ!今、一番、勢力のある階級だ」
オスカルの言葉にアンドレは後方を振り返った。
「ああ、ブルジョワの勢いは留まるところを知らないかのようだ」
「では、貴族は?」
「・・・貴族は相変わらず、華やかだ」
微笑んで答えるアンドレに対し、オスカルは視線を落とした。
「自分達の立場の危うさを感じ取っているものなど、皆無に等しい」
溜め息をつくオスカルに、アンドレは明るい声をかけた。
「さあ、そろそろ出よう」
「ああ」
二人は席を立つと、先ほどの若いカップルの席の前を横切った。
二人は将来について語り合っているのか、娘は相変わらずはにかんだ微笑を青年に向けていた。
歩調が遅くなったオスカルの肩をアンドレがポンポンと叩き、先を急がせた。
この美しい男友達同士にしか見えない二人が店を出ようとすると、少し、離れた場所から先ほどのブルジョワ二人の話し声が聞こえてきた。
商談が成立したらしく、二人は固い握手を交わしていた。
「あの立地を考えれば、ぜひとも今購入されておいて、ゆくゆくは店舗として活用されるのが最適ですよ」
「この不穏なご時勢に店舗を持つのはいささか、躊躇われるがね」
「どんな、ご時勢でも土地の価値には変わりはありません」
「それにしても、ドゥトゥール男爵からご息女に縁談の申込みがあったとか」
「まったく、困ったものです。あちらはすでに貴族同士で縁談がまとまっているにも関わらず・・・」
「どうやら、貴族には珍しく先の見えるお方らしいですな」
ここまで話して、二人はオスカルの視線に気づいた。
慌てて二人は口をつぐみ、不自然にカップに手をのばしカフェを口にした。
店を出たオスカルは、とたんに険しい表情になっていた。
「ドゥトゥール男爵というのは、たしか、ディアンヌ嬢の婚約者ではなかったか?」
「同じ名前だが、もしかしたら別人物かもしれん」
アンドレはそう答えたが、ディアンヌの幸せに満ちた笑顔が浮かぶと同時に、なにか不吉な予感が脳裏をかすめた。
翌朝、オスカルはいつもより早く起き、アンドレを伴って屋敷の庭を散策した。
アンドレは腕にかごをぶら下げ、片手にハサミを持ってオスカルの後についた。
「あれがいいな」
オスカルが命ずるままに、アンドレは花の茎にハサミを入れた。
「やはり、冬は咲いている花が少ないな」
「では、温室まで行ってみるか?」
今度はアンドレが先に立ち、オスカルがそれに続いた。
薔薇園の奥に作られた温室の中は外気から遮断され、色とりどりの薔薇や百合の香りで満ちていた。
「さすがにここだけは艶やかだな」
二人は冬には到底、嗅ぐことのできない甘く華やかな香りを胸いっぱいに吸い込んだ。
「あの百合はどうだ?」
オスカルは大輪の白百合を指差した。
「いいが、ブーケの出来上がりを考えて花を選んでくれよ」
「ふふっ、分かった。おまえもいいと思う花があったら選んでくれ。テーマは『私の春風』だ」
二人は笑みを交わしながら温室内を歩いた。
そして、アンドレは淡い色合いの花に次々とハサミを入れ、花かごを満たしていった。
アンドレの作った、まさに『春』を思わせるブーケを手にオスカルは出勤前にソワソン宅を訪ねた。
馬車で待つアンドレにすぐに戻ると言い置いて、オスカルは小路に入っていった。
以前に部下に教えてもらったソワソン宅のドアをノックすると、ほどなくディアンヌ嬢が顔を出した。
ディアンヌはドアの隙間から朝日に照らされて光り波打つ金髪に思わず、目を細めたが、それがオスカルのものだと分かると口に手を当てたまま「あっ!」と小さな驚きの声を上げた。
「ディアンヌ嬢、あなたの顔が無性に見たくなり、突然、訪ねてしまいました」
自分に向けられた穏やかな笑顔に、ディアンヌは顔を赤らめたまま、いまだ発する言葉を失っていた。
「これは、私が朝、あなたに似合いそうな花を屋敷の花壇から摘んだものです。それをアンドレがブーケにしてくれた」
そう言うと、オスカルは白からピンクの淡い色で絶妙なグラデーションを作るブーケをディアンヌに手渡した。
「朝から、あなたの笑顔が見られてよかった」
ブーケを手にしたまま、まだお礼の言葉さえ出てこないディアンヌの後ろから、アランの声が聞こえてきた。
「ディアンヌ!いったい、こんな朝っぱらから誰だ?借金取りなら追い返せよ!」
アランの声など聞こえない様子のオスカルはディアンヌを見つめ、さらに甘い微笑みを送った。
そしてオスカルが「では」と立ち去ろうとしたとき、初めてディアンヌが言葉を発した。
「あの、オスカルさま・・・」
オスカルは振り向いて、ゆっくりと歩みをディアンヌの方へ歩みを戻すと、壁に左肘と体重の一部を預け、ディアンヌを視線で包み込んだ。
「また、お訪ねしても構わないだろうか?」
オスカルの香りと視線に包み込まれ、ディアンヌは白い頬を紅潮させた。
「ええ、オスカルさま。綺麗なお花をありがとうございます」
「いったい誰なんだ?ディアンヌ」
アランが放心状態のディアンヌの後に立ったとき、オスカルの姿はもう見えなくなっていた。
そして、ブーケを胸に抱きしめたまま、振り向いたディアンヌの姿にアランは思わず息を飲んだ。
妹は手にしているブーケ以上に春の香りを漂わせ、人生で一番、光り輝く時を過ごしているとばかりに、その頬を紅潮させていた。
「男爵家の使いか?」
アランは寂しげに微笑んで尋ねた。
「いいえ。オスカルさまよ」
瞳を上げて答えた妹の言葉に、今度はアランの心臓が飛び出しそうになった。
「なっ、なにをバカなことを!こんなとこに隊長が来るわけねぇだろ!」
「ふふっ・・・オスカルさまがね、お屋敷の花を摘んで持ってきてくださったの」
満面の笑顔で答える妹を見て、アランは、妹は結婚式前で気分が高揚し、珍しく自分をからかっているのだと思い込んだ。
「また、来てくださるそうよ」
からかいの手を緩めない妹にアランは呆れた。
「だったらな、今度は花なんかじゃなくて食い物持ってくるように頼んどけ!」
兄の言葉が聞こえているのかいないのか、ディアンヌは無言で、家にひとつしかない花瓶に水を入れ、ブーケをテーブルに飾った。
次の朝、またソワソン家に来客があった。
玄関に出たのはディアンヌだった。
「どうも、あなたの顔を見たいという衝動は睡魔さえも打ち負かしてしまうらしい」
オスカルはそう言うと、持ってきた紙袋をディアンヌの手に載せた。
驚きと嬉しさを隠し切れないディアンヌの鼻に、甘く香ばしい香りが漂ってきた。
「それは、今朝、焼きたてのクロワッサンです。王妃様がウィーンからフランスに持ち込んだキプフェルンを当家流にアレンジしてあります」
ディアンヌは、恋人の突然の訪問を受けた娘のように、口元を引き上げたまま上目遣いでオスカルを見上げていた。
玄関から聞こえてくる聞き覚えのある声に、アランは慌ててシャツのボタンを留めると玄関の方へ走り出てきた。
途中、椅子につまずきながらもドアの外にオスカルの姿をみとめると、ピタリとその乱れた歩調を止めた。
オスカルはディアンヌの後で唖然としているアランに気づくと、ちらりと視線を送って声をかけた。
「これはディアンヌ嬢の兄上!今度、ディアンヌ嬢をお茶にお誘いしてもかまわないだろうか?」
「ディ、ディアンヌはけっ、結婚前だ!」
会話として成り立たないアランの返答振りにオスカルは小さく、首を傾げてみせた。
「結婚前の女性が、女友達とお茶に出かける。なんとも平和的な光景だ」
オスカルはそう言って微笑み、視線をディアンヌに戻した。
「では、来週の日曜の午後、お迎えに参ります」
ディアンヌは輝いた目で膝を折り、オスカルに答えた。
オスカルはディアンヌの手を取り、その甲にキスを送るとくるりと背を向け、去っていった。
「さあ、兄さん、朝食にしましょう!カフェを煎れるわね」
ディアンヌは嬉々として皿にクロワッサンを並べると、お湯を沸かし始めた。
ジャルジェ家のクロワッサンの底にはスライスアーモンドが敷き詰められ、砂糖で固めてあった。
甘く香ばしいクロワッサンをほおばり、ほろ苦いカフェを口にしてソワソン家の3人は顔を見合わせた。
「ふふふふっ」
最初に笑い出したのはディアンヌだった。
「なんだ、おまえ。こんな菓子くらいで嬉しそうにしやがって!」
アランはクロワッサンのかけらを口角につけたまま、次のクロワッサンに手を伸ばそうとしていた。
「あら、おにいさんだってとっても嬉しそうよ」
確かに、こんな甘い香りのものを家族で囲んでカフェを飲むなど遠い記憶にさえないことだった。
サクサクとした歯ごたえと、口の中で広がるバターの香り、そして昨日からテーブルに飾られているピンクのブーケ。
ディアンヌの微笑みだけが一家の灯だったソワソン家に、一瞬、春の風が吹き込んだような、そんな朝だった。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プチよしこさまの挿絵![]()