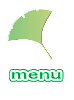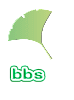祖父は近衛隊の将軍職を代々勤めたジャルジェ伯爵家の現当主であるが、ミカエルが4歳の時にイングランドに亡命した。
その一年前に一度ミカエルの住むノルマンディ−に来たのだが、その時は夫人のみ残して再びベルサイユに戻っていった。
曰く「ジャルジェ家は、何があっても王家に忠誠を尽くすため」だそうである。
しかし、1793年10月16日に王妃が処刑された。
ジャルジェ将軍がベルサイユにとどまり、命を賭して守るものがこの世から消え失せた。
ミカエルの両親は、残された王子と王女の救出のためパリに出て行ったが、将軍は同じ頃にノルマンディーに現れ、やがて傷心を癒すため夫人と共に長女と五女のいるイングランドに渡った。
したがってそれ以降、ミカエルは祖父に会っていない。
両親もパリが長かったのでミカエルは顔を忘れそうなくらいだったが、とりあえずこちらは無事帰ってきて、今は親子4人、どんぐり屋敷で暮らしている。
祖父は肖像画を描かれるのが嫌いだとかで、どんぐり屋敷にもバルトリ邸にも将軍の絵はない。
変わった人だったのだろう。
それは母を見ていても明らかだ。
母が、世間一般の母親と色んな意味で異なるのは、かかって祖父が原因である。
それに異を唱える人はいない。
確か母も肖像画を描かれるのが嫌いだったと父が言っていた。
とにかく母も祖父も変わっているのだ。
いつだったか、そう、確かだまどんぐりがたわわに実っていた頃、軍人がやってきて母と話していた。
立派な軍人が母の前で背筋を伸ばして固くなっていた。
父にはそんな風にはしていなかった。
しばらく遊んでくれたので、優しい人なのだと思ったが、それを口にすると、その人は真っ赤な顔をして帰って行った。
その姿を見て両親は笑っていた。
あんな立派な軍人でも母にはかなわないのだ。
やはり母は特異なのだ。
もちろん母だけが変わっているということはなく、当然その夫たる父も変わっているのだろうが、母の異様さが際だっているので、誰もそこにはあまり触れない。
ミカエルも、父を変わっているとはあまり思っていない。
どんぐり屋敷のどんぐりもすでにすべて落ち、母の誕生日であり、両親の結婚記念日でもあるノエルが先日終わった。
父が趣向を凝らした楽しいノエルだった。
そしてもうすぐ7回目の誕生日が来る。
ミカエルが生まれたのは1790年の公現祭の日。
妹とともに双子として生を受けた。
以来、何をするにも妹とセットである。
衣食住のすべてを共にしている。
ついでにいうなら、顔も共にしていると言って良いほどそっくりだ。
だが、当然中身はそうではない。
もとより男女の違いもある。
違って当たり前なのだ。
「おまえたちは本当に性格が違うな」
母はよくわかっているようで、また、それを楽しんでいるようでもある。
だが、ミカエルにしてみれば、そう思っているならノエルと同じ事をさせるのはやめてほしい。
ノエルが好きなことと、自分が好きなことは違うのだ。
ノエルは剣が大好きだが、自分はそうではない。
嫌いではないが、大好きではない。
そのことを母はわかってくれない。
週に3回くらいならいい。
だが毎日毎日練習するのは苦痛だ。
それも時に午前中いっぱいつぶされる。
母とノエルは嬉々として手合わせをしている。
暑い日も寒い日も…。
だから、言い出せない。
つくづく思うのだが、どこの家でも母というのは剣の稽古をするとき、こんなに厳しいのだろうか。
バルトリの叔母上やローランシーの叔母上がこんなに厳しいとはさすがに思えない。
きっともっと優しく教えてくれて、もっと回数も少ないのではないか、と思う。
実は、母が剣を使えること自体が尋常ではないので、一般的な母というのは子どもに剣の稽古をつけたりはしないのだが、ミカエルはまだそのことは、知らない。
なんとか母が世間並みの母になって剣の稽古の頻度を減らしてほしいと願うばかりだった。
「さぼってみようかな…」
今年一番の寒波がきた朝、ミカエルは寝台の中で考えた。
こんな日に剣の稽古はしたくない。
となりで寝ていたノエルは先に起きて、もう身支度をしている。
寒い日ほど嬉しそうだ。
まるで子犬だ。
「寒い日ってさ、どんなに稽古しても汗をかかないからね、暑い日よりずっといい」らしい。
だが、ミカエルはそうではない。
「ミカエル、そろそろ起きろよ」
案の定、ノエルが声をかけてきた。
「う…ん」
ちょっと苦しそうな声を出してみた。
「ミカエル?」
「う…ん」
もう一度うめく。
「どうしたの?」
ノエルが枕元に駆け寄ってきた。
心がちくりと痛む。
「今日は絶好の稽古日よりだよ」
耳元で言われて、ちくりとした痛みはどこかに飛んでいった。
「なん…か、ぼく、変なの…」
弱々しい声で訴える。
「どこが?どんな風に変なの?頭?おなか?それとも手とか足?」
怒濤の質問が降ってきた。
そんなのどこでもいいじゃない、とは言えないので、もう一度うめいてみた。
「う…ん」
「待ってろ、誰か呼んでくる!」
ノエルは駆け出して行った。
ミカエルはがばっと起きあがった。
なんだか空恐ろしいことをしてしまった気がする。
まもなく大人がやってくるだろう。
どうしよう。
今度はがばっとふとんをかぶった。
世界が狭く、そして暗くなった。
ああ、ここにこもっていたい。
狭くて暗いけど、ここは暖かく、居心地が良い。
ずっとここにいられたら…
「ミカエル!」
父の声だった。
ちょっとホッとした。
母だと心の痛みに負けそうだ。
ふとんがめくられ、急に世界が明るくなった。
「熱でも出たか?」
大きな手が額に当てられた。
「違うな」
次に目の下を引っ張られた。
「ふむ、特に変わった様子はないな」
続いて腹の上に手を置かれぐっと押さえられた。
「張っているわけではないな。ミカエル、口を開けろ」
大きく開けた口の中をのぞき込んだ父は、こちらにも異常を認めなかったらしい。
「父上、ミカエルはどこが悪いんですか?」
ノエルの質問は直球だ。
「ちょっとわからない。だが医師を呼ぶほどでもなさそうだ」
ミカエルは心底ホッとした。
具合が悪いと言えば医師が呼ばれるという当たり前のことを失念していた。
そんなことをすれば、どこも悪くないのは一目瞭然、えらいことになる。
「とりあえずノエルは食堂に行って母上にミカエルのことを報告してくるんだ」
ノエルは元気に走り出した。
「ミカエル、腹は減ってないか?」
優しく聞かれて困った。
具合が悪いのに食べたいとは言えない。
だが、実はちょっとお腹がすいている。
どうしよう…。
「よし、ミルクとパンだけ持ってきてやろう。軽く腹に入れとくほうがいいからな」
そういうと父も部屋を出ていった。
どこも悪くないのにどっと汗をかいていた。