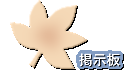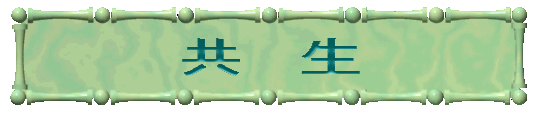バルトリ邸から帰宅したオスカルの顔は明るいとはいえないものだった。
どちらかというと、寂しそうな、哀しそうな、何か大切な物がなくなって、しばらく忘れていたが、ふと思い出したときのような、そんな表情だった。
書斎にいたアンドレに、帰ったことを告げに来ると、すぐにも引き上げようとする。
それを押しとどめて、物問いたげにするアンドレに、オスカルは軍務証書を差し出した。
「今日、わたしのもとに戻った。不思議なものだな。あんなに肌身離さず携帯していたのに、今の今まで、わたしはその存在を忘れていた。」
小さくため息をつく。
何か心にかかるのだろう。
だが、アンドレにすれば忘れていて当然だ。
すでに軍人でない以上、そんなものはなんの役にもたたない。
むしろ、そういう世界からできるだけ遠く離れた場所で生きたいと願っている。
そう、アンドレにとっては二度と行きたくない場所なのだ。
「こうして手元に帰ってくると、二度と戻れないのだと、一層思い知らされる。わたしがすべてを捧げたあの場所に…。」
伏し目がちに話すオスカルの声は低かった。
オスカルは戻りたいのだろうか。
このノルマンディーでの生活よりも、軍隊での生活のほうがよかったというのだろうか。
「帰りたいのか?」
逡巡したあげく、アンドレは回りくどい聞き方はやめた。
率直に尋ねる。
オスカルは少し驚いたように顔を上げた。
「え?」
思いがけない質問だったらしい。
その反応にアンドレも驚いた。
「ああ、いや…。あまりに寂しそうに言うから、戻りたいのかと思って…。」
アンドレが取り繕うと、オスカルは再び目を伏せた。
それから、首を振った。
「別に…。戻りたいと思っているわけではない。というか、思ったわけではない。ただ、この証書にわたしの半生がつまっているのか、と。たったこれだけのものなのか…と。」
オスカルの視線が窓から遠い空に移される。
そしてそのまま書斎から引き上げてしまった。
アンドレは、自分の軍務証書を探し始めた。
ノルマンディーに来る時、一応荷物の中に入れたはずだから、この書斎のどこかにあるはずだった。
案の定、余り使わない机の引き出しの奥にしまいこまれていた。
しみじみと久しぶりの対面をはたす。
氏名と生年月日の他は、ほとんど記載がない。
軍隊における履歴が、衛兵隊への入隊と除隊しかないのだから、無理からぬことである。
これは除隊のとき、ダグー大佐から返還されていた。
オスカルの華麗な履歴とは比べものにならない、貧相とさえ言える軍務証書だ。
彼は書斎を出てオスカルを探した。
そして、居間の肘掛け椅子に所在なげに座っているオスカルの前に自分の軍務証書を付きだした。
突然の思いがけないアンドレの行動にオスカルがびっくりしている。
「なんだ、これは?」
「おれの軍務証書だ。おれはちゃんとあのときダグー大佐から返還された。だからこうして自分で持っていた。」
「ほう…。」
オスカルの瞳に少し興味の色がわいた。
アンドレの軍務証書か。
オスカルは、アンドレから受け取ると、しばらくながめていた。
一応衛兵隊士だったのだから、持っていて当然だ。
だが、どうもアンドレには武官とか軍人とかいうイメージがないため、軍務証書との取り合わせに違和感がある。
「あっけないものだろ?おまえのと違って…。」
「確かに…。軍歴は二行だけか。」
「ああ。だんなさまのごり押しで放り込まれたからな。普通、あの歳での新兵はないだろう。」
アンドレは苦笑した。
そうだった。
オスカルの突然の転属に驚いたジャルジェ将軍が、とにかく護衛しろ、とアンドレを衛兵隊に送り込んだのだ。
着慣れない軍服、持ち慣れない銃。
そして訓練。
「そのたった二行におれの血と涙と汗が込められている。」
アンドレが真面目な顔をしてオスカルを見た。
オスカルは思わず笑った。
「大げさな…!」
「そう思うか?思うだろう?」
「え?」
「こんなものに自分の人生があるなんて、おれは思っていない。だけど、他人にははかりしれない思いがあるのも事実だ。たった二行におれの血と汗と涙があるようにな。」
オスカルはアンドレの正面に顔を向けてきた。
「何が言いたい?」
アンドレは、チラリとオスカルに目をやってから、二枚の軍務証書を机に並べた。
「ほら、最後の日付が同じだ。」
「うん?」
「おまえの休隊処分と、おれの除隊。どちらも1789年6月末日になっている。」
履歴の最後は確かにそうなっていた。
「おれたちの軍務はここで終わったんだ。休隊というのは王妃さまの方便だ。」
「わかっている。軍務は終了だ。ただ…、ただ…長い長い交流は…。」
休んでいるだけなのだ、と言おうとしたオスカルの言葉はアンドレに遮られた。
「このあとを書くとどうなると思う?」
「?」
「1789年7月からだ。」
「…。」
「二人でパリに行き、バスティーユ陥落を確認。そして二人でノルマンディーに来て、新生活開始。それから二人の子どもの誕生。おれとおまえの交流は少しもとぎれていない。いつも一緒にしてきた。休んでいたことなどない。」
「アンドレ…。」
オスカルは並べられた二枚の軍務証書を手に取った。
スタートは全然違うが、確かに最後は同じだった。
そしてそれからもずっとともに歩んできている…。
「お嬢さま!」
突然、居間の扉が開いてばあやが現れた。
「お帰りになってたんなら、お子様のお部屋をのぞいてくださいまし!おまちかねでございますよ。」
ばあやの言葉がおわらないうちに、トコトコと小さな足音が二人分近づいてきた。
「ほら、おいでにならないから、あちらからお越しになりましたよ。」
まずはノエルが、そしてその後ろからミカエルが、ばあやが開け放したままの扉から駆け込んできた。
二人してオスカルの足にとびつく。
オスカルは、すぐに膝を折り、二人の顔に自分の顔を寄せた。
「悪かった。さっき帰ったのだ。お利口に、元気にしていたか?」
双子のかわりにばあやが答える。
「まあ、お利口とは言い難いですが、お元気はお元気でございましたよ。」
オスカルは吹き出した。
「さすが、わたしの子どもだ。それでいい。」
オスカルはノエルを抱き上げた。
すぐにアンドレが横に来て、ミカエルを抱き上げた。
はからす゜も同時に子どもを抱いている。
オスカルはつぶやいた。
「確かに、何でも一緒にしているな。」
それから、オスカルはばあやが思わず見とれるほど、とても優しく笑った。