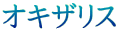マロン・グラッセが逝ってから、どんぐり屋敷は広くなった。
あんな小さな人だったのに、その存在感がこんなにも大きかったのかと、屋敷の中で思わないものはなかった。
彼女は、いつもシーツや燭台を持って、庭から屋敷へ、あるいは一階から二階へ、はたまたこちらの部屋からあちらの部屋へ、それはそれは忙しそうに走り回っていた。
それは大きなお屋敷であるジャルジェ家にいた時も、こぢんまりとしたどんぐり屋敷に来てからも、変わる事なきマロンの習性だった。
そうやって彼女はあちこちに目配りしていたのだ。
実際、マロンの目がなくなったとたんに、ノエルが失踪するという大事件が起きた。
そんなことは、マロンが生きていたらあり得ないことだった。
マロンの目配りは、よく言えば見守り、悪く言えば監視だったが、それによって保たれているものが、厳然と存在したのであるから、やはり代え難い見守りだったのである。
アンドレ、オスカル、そして双子に四人の使用人。
それぞれが、様々な瞬間に亡き人の残像をそこら中に見ていた。
かまどの前でスープの味見をする姿。
こども部屋でおもちゃを片付ける姿。
庭で季節の花を摘む姿。
そしてアンドレを怒鳴りつける姿。
「そろそろおばあちゃんの部屋を片付けないとな…」
アンドレは久しぶりに祖母の部屋に入り、窓を開けた。
同時に暖かい春風が入り込んだ。
「葬儀の時は冬だった。だが、不思議と暖かかったな」
アンドレの開けた窓の外を眺めてから、オスカルは部屋の真ん中に置かれた揺り椅子に座った。
マロンのお気に入りのこの揺り椅子は、ジャルジェ家に頼んでわざわざ届けさせたものだ。
アンドレは祖母のために新しい揺り椅子を用意していたのだが、長年愛用していたものでなければ落ち着かない、と言ってアゼルマにあげてしまい、ベルサイユのオルガに手紙を書いたのだ。
揺り椅子を送って欲しいと。
ばあやのたっての望みならば聞かねばならないということになったジャルジェ家では、この椅子一脚をご丁寧に荷馬車に積んで送ってきたのである。
「届いた日、ばあやはなんとも嬉しそうな顔をしていた。よほど気に入っていたのだろう」
「わざわざ送らせたんだから驚いたよ。せっかくこっちで買っておいたのに…」
「ばあやは、自分のことでは頼み事をしない人間だった。母上も長い間一緒にいて、めったに聞いたことがなかったそうだ。それがわざわざ手紙で依頼してきたのだから、よほどのことなのだろうと…」
「そんなに執着していた割に、俺はあまりこれに座っているおばあちゃんを見たことがない」
「そう言われればそうだな。ばあやといえば走り回っているイメージしかないな…」
「いつ座っていたんだろうな」
思い出話をしているときりがなかった。
結局片付けるどころではなくなるのだ。
これではいつまでたってもこのままだ。
アンドレは室内をぐるりと見渡した。
あまり家財道具のない部屋で、目を引くのはこの椅子と、それから小振りな書き物机と寝台、そしてロココスタイルそのものの柔らかな曲線を描いたチェスト。
どれもきちんと整頓されていて、磨き込まれている。
屋敷中ピカピカに磨き倒して、そのあと自分の部屋もしっかり掃除していたところがさすがマロンである。
あの歳で、これだけの労働をこなしていたのだ。
それが1ヶ月も放置したためすっかりホコリをかぶってしまっている。
この現状を当人が見たら、どんなに嘆くだろう。
いや、どんなに怒るだろう。
生きていたら絶対アンドレはヤキを入れられたはずだ。
「何を見ても思い出してつらかったからな。ここには入れなかった。わたしも、おまえも…。ホコリがたまっているのはやむを得まい。ばあやも許してくれるだろう…」
オスカルがギコギコと揺らす古い椅子の音が、主のいない部屋で響いている。
この音は、仕方ないね、というマロンの声なのだろうか。
アンドレがチェストの最上段の引き出しを開けた。
どうやら手紙の束だ。
アンドレの母の名前が書かれたものもあり、興味を引かれたが、そのまま戻した。
ここにあることがわかっていれば、それでいい。
読むのはまた今度にしようとアンドレは思った。
続いて2段目を開けてみる。
また手紙だった。
ただし束ではない。
ほんのわずかな数の封筒が、きれいにリボンでくくられていた。
ずいぶんと拙い字の宛名書きがある。
わざわざ引き出しにしまうほど大切なものだったのかと、取り出してみた。
「あっ…これは…」
思わず声が出た。
「どうかしたのか?」
「おれが書いたものだ…」
「おまえが?ばあやに?」
「ああ。懐かしいな。取ってあったんだ…」
「同じ屋敷にいたのに手紙を書いてたのか?」
「ああ…」
いぶかしがるオスカルには答えず、アンドレは封筒から中身を取り出した。
記憶に間違いがなければ、これには手紙とともに押し花をいれたはずだった。
と言っても、何の花かも知らず、ただ庭の隅に咲いていた雑草のような花を摘んできたものだ。
黄色く小さいこの花は、手入れを怠った花壇の縁や、植え込みの周囲でよく見かけた。
まだ幼かったアンドレには、可憐な花に見えたのだが、大人たち、特に庭師たちは雑草だと言って嫌っていた。
両親が死に、ジャルジェ家に引き取られ、環境の激変の中で頼るべき唯一の血縁者は、めいっぱい屋敷中を走り回っていて声をかける暇すらなかった。
たまに向こうから声がかかれば、お小言か用事かのいずれかだった。
庭師達がふーふー言いながら引っこ抜いていった黄色い花が、どうにも哀れに見えて、つい一番綺麗に咲いていたものを持ち帰ってしまった。
だがそのあとどうしていいかわからなかった。
このままでは枯れてしまうと思った時、我ながら名案が浮かんだ。
押し花にすれば長持ちする!
そこでオスカルから借りた本を堆く積んで黄色い花の押し花を作った。
そしてそれをおばあちゃんに持っていった。
たぶん、気を引きたかったのだ。
まだ慣れない暮らしのなかで、少し肉親の暖かさが欲しかったのかもしれない。
だが、祖母に持っていったは良かったが、こんなに長い間大事にしてくれそうな受取方はされなかったと記憶している。
この忙しい時に何の用だい!と怒鳴りつけられ、おずおずと差し出した封筒はひったくられるように奪われたはずだった。
「その日のうちに処分されたとばかり思っていたのに…」
「なんなのだ、そのひからびたものは?」
「押し花さ」
オスカルが揺り椅子から立ち上がり、チェストの脇へ歩いてきた。
アンドレの手元をのぞきこむ。
「オキザリスか…」
「ああ、そういう名前だったな」
「知らなかったのか?」
「もちろん今は知ってるさ。だけどあの頃はベルサイユに越してきたばかりで、何も知らなかった」
「なかなかかわいいではないか、手紙のほうはなんと書いたのだ?」
「なんだったかな、覚えていない。というか手紙を書いたことさえ忘れていた」
「貸してみろ」
オスカルは横から手紙を奪い取り、声を上げて読み始めた。
「親愛なるおばあちゃんへ…なかなか正当な書き方だ」
「きっとお屋敷でならったばかりだったんだろう」
「どうか、死なないで下さい…!アンドレ、これは…?」
オスカルは手紙をアンドレに渡した。
アンドレも驚いて、手紙を見た。
「この花のようにいつまでも生きて下さい…。俺…、こんなこと書いたのか…」
オキザリスは繁殖力が強く、一度根付くと根絶するのがなかなか困難で、それゆえ庭師達を困らせていたが、要するにそれだけ生命力があるということだ。
父を亡くし、母を亡くしたアンドレが、続いて祖母まで逝ってしまうことのないよう、オキザリスに思いを託したのだとしたら…。
その悲痛な願いを感じたからこそ、マロンはずっと大切に取っておいたのだろう。
そして、何があっても長生きしようと思ったのだろう。
「ばあやはおまえの頼みを聞いてくれたのだな」
「ああ、そうだな。本当に頑張って生きてくれたと思うよ」
「こんな押し花をずっと持ち続けるくらいに、おまえを…」
オスカルは言葉に詰まった。
嗚咽が言葉を言わせてくれなかった。
「もっと、と思うのはわがままなんだろうな…」
アンドレの瞳も潤んでいた。
「もう少し、この部屋はこのままにしておこう。かまわないか、オスカル?」
オスカルは答える代わりに何度もうなずいた。
まだまだ片付けてしまうことはできない。
亡き人の姿はなくても、思いはずっと残っている。
亡き人の思いも、亡き人への思いも…。
無理に忘れる必要はない。
オキザリスのようにばあやの子孫は続いている。
あのにぎやかでたくましい双子は、紛れもなくマロン・グラッセのひ孫なのだから。
血も思いも続いているならば、たとえ目の前にいなくても、マロンはここにいるのだ。
※こちらはは第三部の「はじめての冒険」の次のお話しです。
扉 目次 はじめての冒険 掲示板