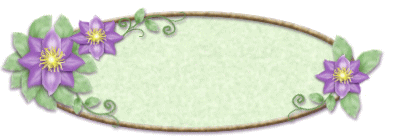
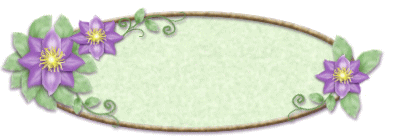
真夏の奇蹟

3

「君から呼んでくれるとはね」
フェルゼン伯爵はいかにもうれしそうだ。
「この縁談によほど乗り気と見える」
伯爵は右手の親指と人差し指で美しい顎をはさんだ。
どういう脳内構造なら、事態をこんなに都合良く解釈できるのか、アンドレには不思議でならない。
アンドレ自身、真面目なオスカルのそばにあって、彼女の研ぎ澄まされた神経をほぐすため、随分明朗快活に生きてきたつもりである。
ものごとを深刻にとらえるよりも、笑い飛ばすくらいの気持ちでオスカルを支えてきた。
おまえはよく言えば大らかだが、悪く言えばいい加減だ、とオスカルに指摘されても、あえて意識的にそのように努めてきた。
だが、フェルゼン伯爵のご都合主義的態度というのは、もはや異次元、別世界であるとしか言いようがない。
彼が行動したときに述べる理由は、どう考えても客観的正当性を持っているとは思えないからである。
こんな相手に理路整然など、絶対通用しない。
単刀直入に懐に飛び込むのみだ。
深夜のベルサイユ宮殿の庭園で、アンドレはフェルゼン伯爵の前に意を決して対峙した。
「フェルゼン伯爵、この縁談は破談にしてください。わたくしは結婚するつもりなどまったくないのです。」
一気に言った。
このアンドレの断言を聞いたフェルゼン伯爵は、ちょっと愕いたように眉をひそめると、まるで年長者が若者を諭すように言った。
「アンドレ、こんな話はね、誰でも最初はそう言うのだよ。何と言っても照れくさいことだからね。」
フェルゼン伯爵はアンドレより一歳年少であることにも、自分が独身であることにも全く頓着せず、優しく微笑んだ。
ここで引き下がるようなら、わざわざ疫病神のような伯爵を呼び出したりはしない。
アンドレは大きく息を吸った。
「伯爵は大きな誤解をしておられます。わたしとロザリーとその夫との間には、伯爵がご想像なさっているようなことはなにひとつありません。ですから、わたしがロザリーに似た女性と結婚する必要はどこにもないのです。」
黒いたった一つの瞳は真実を語る強さに満ちあふれていた。
誰だって、この真摯な瞳を見れば、嘘偽りのないアンドレの本心が察せられるはずである。
だが、見ようとする気のないフェルゼンには、黒曜石の瞳はないのと同じだった。
「アンドレ、人を愛して、堂々と決闘までして敗れたことは、決して恥ずべきことではない。女性の心とはなかなか不可解なものだ。ロザリー嬢の選んだ男性がどれほどのものかは知らないが、君を捨ててまでというのなら、よほどの傑物だったのだろう。そういう男と剣を交え、傷を負ったことは、まったく隠す必要のないことなのだよ。」
愛情には満ちているのだろうが、まったくありがたくない、しかも事実とかけ離れた物語がフェルゼンの頭の中で勝手に構築されているようだ。
他国の王妃と恋愛関係を持続させるには、これほどまでに頑なな思い込みが必要なのだろうか。
絶望的な気分になるのをアンドレは必死でこらえた。
「どんなお話をご想像なさっても、それは伯爵の自由ですが、事実に基づかないことであれこれ動かれては大変迷惑です。」
一介の平民の衛兵が、陸軍連隊長である伯爵に言うにしてはなかなか大胆不敵な言葉をアンドレはやむなく口にした。
フェルゼンは厳しい返答にややたじろいだ、ように見えた。
だが、すぐに深い思いやりを発揮して、アンドレの固持する背景を思いやることにした。
「アンドレ、何か結婚に踏み切れないわけでもあるのか?」
ストレートな問いかけに、今度はアンドレがたじろいだ。
「え?」
その通りなので、言葉が出てこない。
オスカルの顔が脳裏をかすめる。
「オスカルか?」
心臓に銃弾をくらったような衝撃が走る。
その様子にフェルゼンは自分の推測の正しさを確信した。
「やはりオスカルなのだな?」
「…。」
報われない思いだと骨身に沁みて悟っていても、忘れきれない自分の恋情。
だが、この思いある限り、他の女性など考えられることではないのだ。
アンドレの瞳に何とも言えない悲しい色が浮かんだ。
先ほど、真摯な瞳には気づかなかったフェルゼンだが、今度は敏感にアンドレの悲しみを読み取った。
すっとアンドレに近づくと、フェルゼンはポンとアンドレの肩を叩いた。
それから、ポンポンと再び肩をたたき、それから、あろうことか、腕を回してきた。
傍目には肩を組んだ二人の男に見える。
「オスカルはわたしにとって唯一無二の尊敬すべき友人だが、君ほど近くから見ると、確かに人にはわからぬ彼女の本質が透けて見えてくる。」
フェルゼンはアンドレの耳元で小さくつぶやいた。
アンドレははじかれたように目を見開いた。
友人としてならばわからないが、近づけばわかるオスカルの本質…。
「これは、君の姿になって初めて気づいたことなのだがね。以前にはわからなかった。いや、決してわたしが鈍感というわけではなく、世の全ての人がわからないに違いない。」
なんだかものすごく言い訳がましいところもあるが、いったい何を言おうとしているのだろう、と、さっき銃弾を食らったばかりのアンドレの心臓が早鐘のように鳴る。
オスカルの女性らしさだろうか。
凛々しく見えて実は優美な仕草だろうか。
アンドレの姿になってわかることと言われれば、外見だけではないオスカルの持つ内面的な美しさしか、思い浮かばない。
アンドレは真横にあるフェルゼンの唇をじっと見つめた。
「あいつは…、人使いが、荒い。」
アンドレは思いもよらない言葉に息をのんだ。
「というか、君に関してのみ、恐ろしく荒い。君は本当によく耐えている。わたしはほとほと感心した。」
「それ…は、どうも…。」
何を言っているのだろう、この人は…。
たった今まで話していた自分の縁談と、オスカルの人使いと、どんな関係があるのだろう。
「わたしも使用人を使う身だが、わたしの場合は、もっと相手の立場にたっている。」
フェルゼンの目に若干の優越感が浮かんでいた。
使用人に対しては知らないが、少なくともアンドレにとって、フェルゼンが相手の立場に立っているとは到底思えない。
「しかしオスカルは違う。他の人にはそうでもないのだろうが、こと君に関しては、おそらく自分の手足のごとく本気で思っている節がある。だから配慮というものがかけらもない。」
こんなに見当外れなのに、どうしてこんなに核心を突いているのか。
フェルゼンは得々と話を続けていく。
「彼女にとって、君は自分の体の一部だから、離れて存在することはあり得ない。いつも、君がそばにいること、いやそばにあることといった方が良いかもしれないが。とにかく君の存在を要求している。もはや過酷なまでに…だ。」
フェルゼンは、初めてアンドレとなった夜のオスカルの態度を思い出していた。
いつも通り起こせ、から始まって、朝はいつものを煎れろ、馬に乗る、出かける、などなど、わずかな指示だけですべてが整えられると思い込んでいるオスカルは、それらことごとくに対処できないフェルゼンを容赦なく罵倒したのだった。
こんなことは絶対他の人間ではつとまらない。
アンドレ・グランディエなればこそ、水が流れるように流暢にやってのけるのだ。
「もし、君が結婚すれば、オスカルは体の一部をそがれると感じるはずだ。」
フェルゼンはアンドレに向き直った。
「君の結婚の最大の障害は、このオスカルの存在だったのだろう。」
登山口がはるかにかけ離れていても、到着した山頂は唯一つしかないように、フェルゼンの言い分は、前提で大きく外しているにもかかわらず、結論において大正解だった。
アンドレが結婚しない理由はオスカルの存在以外の何ものでもない。
それならば、解きようのない誤解は誤解のままで置いておき、とにかく結論だけ正しいその理由で結婚できないことにしておこう、とアンドレは開き直った。
「はい、そうです。わたしはオスカルゆえに、決して結婚しないのです。」
アンドレは心底偽りのない本心を告げた。
「やはり…。」
フェルゼンは同情のこもったまなざしをアンドレに向けた。
こんなに良い男なのに…。
そして自分が見つけてきた女は本当に彼に似合いなのに…。
オスカルのせいで…。
「わかった。」
フェルゼンの口から了承の言葉を聞いたアンドレは涙ぐみかけた。
が、次の瞬間、彼は奈落の底に突き落とされた。
「わたしがオスカルを説得してやろう。」