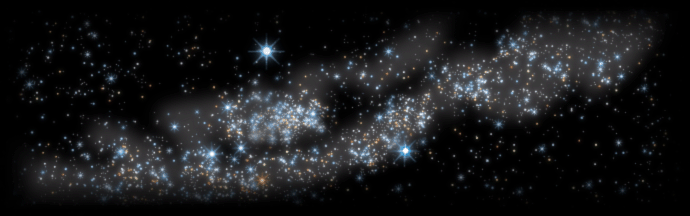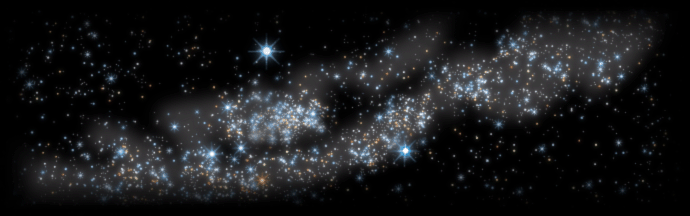
「よくもまあ、あなたおひとりでこんな危険なところへ…。」
バルトリ侯爵は、妻の言葉をもじって歌うように言った。
「あなた…。」
クロティルドは、一瞬、幽霊でも見ているような顔をしたが、すぐに表情を戻した。
さすがジャルジェ夫人の娘だ。
「どうしてここへ?」
たぶん、充分すぎるほど驚いているのだろうが、それを見事に消し去って、まるで夫が隣の部屋からふらりとのぞいたかのような調子で尋ねた。
「どうしてといって、馬を飛ばしてきたのですよ。船はあなたが乗って行ってしまいましたからね。ご丁寧にアラン・ルヴェや水夫まで連れて…。」
バルトリ侯はあえて質問の意味をはずし、ちらりとアラン・ルヴェを見た。
アランは突然の候の出現に驚きを隠せず、呆然と主人を見ていたが、この皮肉に気づくや、ばつの悪そうな顔で頭をかいた。
彼にとって、侯と夫人の指示が異なるものであるときほど困惑することはないのだ。
無論、バルトリ侯は、それをよく知っているから、直接にはひとこともアランを責めない。
「ロンドンではなかったのですか?」
「例年買い付けの季節ですからね。ちゃんと戻ってきましたよ。ちょうど三日前のことですが…。」
「あら、まあ…。」
「まさかあなたがわたしの代理で行かれるとはね。しかもこんな時期に…。」
非常に丁寧な口調である。
彼は結婚以来、ずっと妻に対してこういう風らしい。
夫婦歴も20年を超えると、互いの言葉や表情ではないところから、本心を読み取ることができるようだ。
まだ結婚半年あまりのオスカルとアンドレには到底理解できない境地である。
いや、二人で過ごした歴史は決して姉夫婦に引けを取らないほど長いのだが、こんな駆け引きとは無縁の歳月だった。
バルトリ侯は、無事ロンドンでの商談を終えて領地にもどり、思いもよらぬ夫人の不在を聞くや、単身馬を飛ばして妻のあとを追った。
懐には妻が書き置いていった手紙がしっかり入っていた。
世間体もあって使用人には言えないオスカルの結婚と妊娠が書かれていた。
好奇心に満ちあふれた妻が単身でベルサイユまで行くには充分すぎる理由だった。
宿場ごとに馬を乗り換えながら走り次いで、ようやく今朝方ベルサイユのジャルジェ邸に到着したところ、今度は、船はノルマンディーではなくパリに向かったと、マリー・アンヌたちから聞かされたのだ。
申し訳なさそうに、少し休んで行かれよ、という岳父の申し出を丁重に断り、疲れ果てた自分の馬の代わりにジャルジェ家から一頭拝借して、とりあえずこの桟橋まで駆けてくれば、我が船が、折良く停船し、ご丁寧になわばしこまで降りてきたというわけである。
簡潔、かつもっともな説明である。
時勢を見る目があるものならば、クロティルドのしたことがどんなに危険かは論を待たない。
「なんだってこんな危険なことをしでかしたのですか?」
妻を見つめる黒い瞳は、非常に複雑なものが入り交じっていた。
かたわらで見守るアンドレにはそれが痛いほど理解できた。
まずは、無事の姿に安心し、続いて勝手な行動に腹が立ち、だが水夫の手前、威厳は崩せず、どうして自分がこんな目にあっているのかを考えれば、狂おしいほどの愛情ゆえなわけで、それはそれで男として情けなくもあり…。
「バルトリ侯爵、いや、義兄上、ご無沙汰していてます。こんなところでではありますが、お会いできて大変嬉しい。」
オスカルがつかつかと候に歩み寄って片手を差し出した。
こんなところって、ここは候の所持船だ、言葉に気をつけろ、とアンドレは気が気ではない。
まして夫婦のこの微妙なやりとりの間に割って入るなどデリカシーがないにもほどがある。
だが、侯は紳士だった。
義妹でありかつての部下でもあるオスカル・フランソワに対し、まったく自然に応対した。
「やあ、オスカル・フランソワ。しばらくだったね。」
旧交を温める固い握手が交わされた。
どう見たって、誰が見たって、元軍人の上司と部下の挨拶だ。
だれが兄と義妹の握手だと思うか、とアラン・ルヴェが心中毒づいていることなど、誰も気づかない。
「随分慌ただしい日々だったようだが…?」
「ええ。なかなか刺激的な時間を過ごしましたよ。」
「君の体を流れる血の賜かね?」
遠回しではあるが、妻への皮肉がこもっている。
「血?」
オスカルは不思議そうに首をかしげた。
「私の血がたりないことまで、姉上からお聞きになったのですか?」
クリスに貧血を指摘されたことだと思っているらしい。
「別に血のせいで、忙しいわけではないのですが…。」
だめだ、完全に会話がずれている。
アンドレは意を決して話に加わることにした。
「バルトリ侯爵、ご無沙汰いたしております。またこのたびは色々とご迷惑をおかけしましたようで、心からお詫び申し上げます。」
「どうしてあなたが謝るの?」
クロティルドが言った。
「どうしておまえが謝るのだ?」
オスカルも同時に言った。
そして、二人は顔を互いにそむけた。
その問いには答えず、アンドレはバルトリ候に対し深々と頭を下げた。
「やあ、アンドレ・グランディェ。懐かしいね。」
バルトリ侯は目を細めた。
「わたしたちの結婚式でかわいいドレスを着て介添人をしてくれた君が、こんなに立派になったのだから、感無量だ。」
こいつも女だったのかあ!!
アランが目をむいた。
彼の今までの価値観が根底から音を立てて崩壊していっているようだ。
「侯爵、そのお話はどうぞご勘弁くださいませ。まだほんの子どもの頃の、何もわからぬままに着せられた衣装でございますから…。」
アンドレはあわてて訂正する。
「ハハハ、これは失敬。参列したうちの親族の間で語りぐさになっているものでね。あのかわいい少女が男だったなんて…。」
アランの頭は混乱をきわめ、ついにはめまいすら感じ始めていた。
「なごやかな思い出話の最中に申し訳ありませんけれど、わたくしがしていたことの続きをさせていただきとうございますわ。」
クロティルドは男二人に背を向け、妹の真正面に立った。
「オスカル。万一のことがあったら、取り返しがつかないところでしたのよ。わたくしの許可なく小船で脱走だなんて…。」
貫禄充分である。
「マダム。万一のことがあったら、取り返しがつかないところだったんですよ。わたしの許可なく馬車や船をだすなんて…。」
侯爵が小さく復唱した。
クロティルドは完全に無視して続けた。
「少しは振り回されるアンドレのことも考えなさいな。」
ぴしゃりと言いはなった。
「少しは振り回されるわたしのことも考えて下さいよ。」
またもや侯が小声で復唱した。
様子を見守っていた水夫たちがこらえきれずに笑い出した。
アンドレもついつられて吹き出した。
神経が限界まで引っ張られていたアランは、急にゆるんだのか、声を出して笑った。
周囲の笑い声の中で、丁々発止の様相で対峙していた姉妹は、やがてつり上げていた目を戻した。
「まったく、あなたにはかないませんわ。」
クロティルドが夫に笑顔を向けた。
「こちらこそ、あなたにはかないませんよ。」
侯爵は、情けなさそうに妻を見た。
二人の間を優しい風が吹き抜けた。
「オスカル、これぞまさしく助け船だ。侯爵に心から感謝申し上げろ。」
アンドレがオスカルに諭した。
「その助け船は乗っても怒られないのか?船にもよると姉上はおっしゃっていたぞ。」
「オスカル、仮にもバルトリ侯爵を、小船と同じ扱いだなんて…、とんでもないことです。大船に乗ったつもりで結構よ!」
オスカルのユーモアたっぷりの言葉と、クロティルドの機知に富んだ答えに、船は大きな笑いの渦に包まれた。
「アラン・ルヴェ、出航だ。」
バルトリ侯爵が打って変わった凛とした声で命じた。
「こんなところでぐずくずしている時間はない。皆、急げ!」
「おお!」
水夫たちが一斉に返答した。
一際大きなかけ声はアランだった。
船はようやく下流に向かって進み始めた。
※もう少し続きます。
back next menu top bbs
天の川 地の河
ー3ー