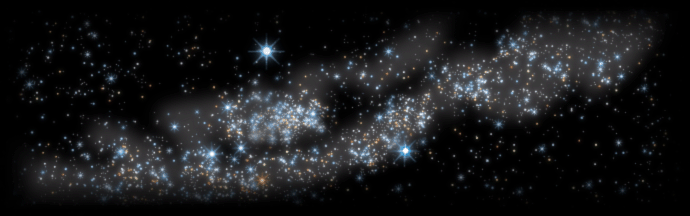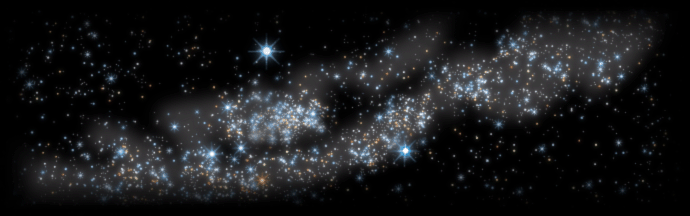
7月15日の夜、バルトリ侯爵とアンドレは、甲板にいた。
すでにベルサイユから西へかなり進み、豊かな緑におおわれた農村の間をセーヌはやはり蛇行を繰り返しながら流れている。
日が落ちる前に船はあえて船着き場ではない、村のはずれの川岸に停泊した。
夜間の航行は危険が多く水夫への負担が大きいためであり、桟橋のないところを選んだのは、万一にも襲われることのないように、というバルトリ侯の配慮だった。
パリから随分離れたとはいえ、混乱はあっという間に伝播する。
用心するに越したことはなかった。
バルトリ侯は、今夜は自分が見張りをするから、と水夫全員に休養を言い渡した。
思わぬ珍事が続き、いつになく疲れているアラン・ルヴェを休ませるための配慮だった。
だが侯自身、三日間ノルマンディーから駆け通しだったのだから、その疲労たるや並大抵ではないはずである。
到底一人に任せることはできない、としてアンドレも見張りを買って出たのである。
「もう少し行くと、蛇行は収まり、西へまっすぐ進み始める。」
バルトリ侯は夜空にまたたく星ををながめながら、スッと西を指さした。
「無数の星の中からでも目指すべき方角の星を見つけられるものですか?」
何気なくアンドレは尋ねた。
侯は静かに微笑んだ。
「目をこらし心をこらす。繰り返しそうしていると、自然に他の星と間違うことはなくなる。」
目指す星を探す方法は、思い人を探す方法と似ているのだ。
アンドレも空を見上げた。
「あのとりわけ星の多いところ、あれが天の川ですね?」
「ああ、そうだ。ベルサイユの空にも同じように輝いているはずなのに、そこで暮らす人々は、それに気づかない。」
「星ではなく、シャンデリアの輝きに目を奪われてしまいますからね。」
アンドレは、不思議な居心地の良さを感じ、なれなれしいのでは、と思いつつ素直に自分の思いを口にした。
「その通りだよ。暗い夜は暗いままがいいのだ。なぜあのようにたくさんの灯をともし、夜な夜な舞踏会にさんざめくのだろうね。」
侯爵もまた心のありさまをそのまま語ってくれている。
信じられないくらい穏やかなひとときだった。
「わたしはあの世界にどうしてもなじめなかった。妻には本当に申し訳なかったが…。」
アンドレは驚いて視線を天空から隣に立つ侯に移した。
ルイ15世陛下の覚えもめでたく、出仕するや、近衛隊に取り立てられ、直属の上司のジャルジェ将軍には婚姻関係を求められるほどのバルトリ侯が…。
「田舎ものだったのでね。いつも気後れしていた。そしてそれを押し隠し克服するために人一倍努力した。その結果…。」
侯は一旦息を止め、それから一息に話した。
「あの人がわたしの妻になったのだよ。遠い星だと思っていたあの人が…。」
ジャルジェ将軍は、若い近衛士官を、よく自邸に招き面倒を見ていた。
ノルマンディーから出てきたバルトリ侯も、何度か招待され、そこで令嬢たちに会った。
すでにマリー・アンヌは結婚が決まっていたから、席に呼ばれるのはたいがいクロティルドとオルタンスで、どちらも華やかなのに清楚で、士官たちの憧憬のまとだった。
ことにまだ幼さの残るオルタンスに比べ、少女から女性へと変わる境目にいたクロティルドは、手折れぬ花、届かぬ星と言われ、この人を妻にする果報者はどんな男だろうと噂されていた。
そして将軍は、バルトリ侯を選んだ。
侯とクロティルドの結婚式は、アンドレがジャルジェ家に引き取られてまもなくだった。
アンドレはオスカルとともに介添えの少年と少女の役を申しつかり、その豪華な式典を目の当たりにしていたから、よく覚えていた。
美男美女のこれ以上ない似合いの新郎新婦だった。
「この人が、わたしゆえに貶められるようなことだけはすまい、と思った。地方貴族の男と、親の言いなりに結婚したあの人が、自分のせいで傷つけられるようなことなどあってはならないと…。」
あのとき飛ぶ鳥を落とす勢いだと言われ、少年の目からは威風堂々の貴公子にしか見えなかった侯爵が、そのように考えていたとは…。
アンドレには大きな驚きだった。
「わたくしは、あのとき、お屋敷に引き取られたばかりで、豪華な式典にはからずも参列させていただきました。この世にこんなに美しい方々がおられるのかと、子供心に本当に感激いたしました。」
アンドレの偽らざる感想だった。
「わたしもね、この世にこんなかわいい少年と少女がいるのかと思ったよ。」
侯はクスっと笑った。
また思い出したのだろう。
「侯爵…。」
アンドレが赤くなった。
「だがあの人は、聡明でね。わたしが無理をしているとすぐに察した。そしてわたしが居心地よく暮らせるように、それはそれは配慮してくれた。だからわたしは余計にがんばったのだ。アントワネットさまのお輿入れに合わせて、ジャルジェ家のオスカル・フランソワが近衛に特別入隊し、彼女が働きやすいようにとのことで、義兄のわたしが連隊長に抜擢された。考えられないほどの破格の出世だった。」
走馬燈のように当時のことがよみがえる。
キラキラと輝く目をして、未来の王妃をお守りするのだと誓ったオスカル。
自分の妹が女でありながら、そのような大役を命ぜられたことを、クロティルドがどんなに案じ、その後見として夫がついたことをどんなに心強く思ったか…。
今になって明かされた真実にアンドレは当時のクロティルドの心情がようやく慮られた。
「おかしな話だね。がんばればがんばるだけ評価されるのだ。こんなありがたい話はない。それのに、自分の心は闇夜にいるかのように落ち込んでいくのだ。ここはわたしのいるべき場所ではない、わたしの暮らす場所はここではない、と。」
ほんの少しではあるけれど、アンドレにもその気持ちが理解できる気がした。
アンドレも平民でありながら宮廷への出入りを許され、オスカル付きとして王太子夫妻からも声をかけられるような待遇に感謝しつつ、ことあるごとに場違いであることが思い起こされ、そのだびに葛藤していた。
オスカルへの思慕を自覚してからは、その葛藤は一層募り、そのことに真っ正面から向かい合えば、息苦しいほどだった。
「罰当たり、かつ恩知らずなことだが、ルイ15世陛下の崩御でわたしは呪縛から解き放たれたのだ。わたしを任命下さった方が、もうこの世におられない。葬送の行列警護を最後にわたしは退任を決意した。もちろん誰もが止めた。だがあの人は、あの人だけは何も言わなかった。」
オスカルをことのほか寵愛しているアントワネットが王妃になる。
オスカルの後見としてとどまる必要はもうないだろう。
クロティルド自身が、実は実家と夫との板挟みの暮らしをしていたのだ。
決して誰にも言わなかったけれど…。
「あの人は、一緒に海を見に行きましょう、と、そう言って笑ってくれた。」
10数年前、セーヌを行く船の甲板からにこやかに手を振っていたクロティルドの姿が、鮮明に思い出された。
涙にくれる母や姉妹に、あんなに晴れやかに笑って挨拶をしたクロティルドの本心が、今わかった。
「大切な人を、その人が大切にしているところから連れ出すのは、本当に心苦しい。わたしの場合、ただただ自分のためだけにそうしたのだ。届かぬ星だった人を連れてわたしはセーヌを下った。だからわたしは一生あの人に頭が上がらないのだよ。」
今日の夫婦の会話の謎解きをしてくれていたのだと、アンドレはようやく理解した。
そして、同時に自分を激励してくれていたのだということも…。
大切な人を、その人が大切にしているところから連れ出したのは、アンドレとて同じことだ。
妊娠さえしていなければ、オスカルはきっと軍に留まった。
たとえベルナールとの約束があって一旦除隊したとしても、市民側に寝返った衛兵隊に合流することはできたはずだ。
それならベルナールにとがめられることもない。
だが、彼女があえて小船から見守ることに留めたのは、ひとえに懐妊していたからだ。
他ならぬアンドレの子を…。
無茶苦茶な行動に終始しているように見えて、オスカルはいつもギリギリのところで母体を優先していた。
それが彼女なりの愛の証であったのだ。
昔、クロティルドが笑ってセーヌを下ったように…。
「今朝お目にかかったジャルジェ将軍は、オスカル・フランソワが無事ノルマンディーに行けることを心から願っておられた。君はわたしとちがって、彼女を無理に連れ出したのではない。ご家族全員が、彼女が出発することを願っておられたのだ。いいね、アンドレ。そこのところをよく理解しておきたまえ。決して卑屈になってはいけないよ。それは君たちを送り出して下さった方々への冒涜なのだからね。」
バルトリ侯は静かに話し終えた。
暖かいものが、候から自分に流れ込んでくる。
「侯爵…。」
アンドレはそう言ったきり、返すべき言葉を持たなかった。
ロンドンから戻るや、三昼夜、馬を飛ばしてベルサイユに駆けつけ、そして今、大切な人の眠る船の見張りとして静かに甲板に立つ侯爵。
頭が上がらないと笑いながら、彼は、大きな愛で妻を包んでいる。
届かぬ星を手にして、セーヌを下る。
アンドレもまた、今、オスカルという天上の星を胸に抱いて、ノルマンディーへとセーヌを下っている。
天を流れる星々の川を見上げ、そして大地を流れるセーヌを見下ろした。
大切な人を、大切な場所から連れ出した責任を、一生負って生きることを、アンドレは天の川と地の河に誓った。
back next menu top bbs
天の川 地の河
ー4ー