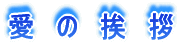
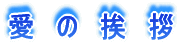
三部会議員の行列見学を終えたローランシー一家が領地に戻る日が近づいていた。
一度帰れば、次はいつになるかわからない。
一月ほどのベルサイユ滞在で旧交をあたためた人々との別れに際し、一家での挨拶回りが始まった。
その最初の訪問先としてローランシー夫妻が選んだのが、マリー・アンヌ宅だった。
ロザリーが、かつてジャルジェ家をベルサイユ宮殿と間違えたほど、貴族の邸宅というものは壮麗だ。
そのジャルジェ家が母の実家であり、なおかつ王太子殿下のご命令でムードンの宮殿に伺候したこともあるル・ルーにとっては、豪華な邸宅は見慣れたもののはずだった。
それでも、母の長姉の嫁ぎ先の公爵家はあまりに豪華で、ル・ルーはお得意の口をあんぐり開けるポーズを自然に披露してしまい、母にたしなめられた。
公爵家の女当主は、中肉中背で、ジャルジェ家伝統の金髪を豊かに結い上げ、仕立ては第一級ながら華美に走らぬドレスを着こなし、艶然と肘掛け椅子に腰掛けていた。
向かい合って座るローランシー伯爵は、義姉のその威厳にいつもながら圧倒され、ただ黙ってお茶を頂くのみであるが、夫人の方は姉妹の間柄ゆえ、遠慮なく饒舌に会話を楽しんでいた。
そしてル・ルーは…。
上下左右あらゆる方向に視線を巡らし、いたるところに興味の対象を発見し、それらをもっと近くで見るために、ムズムズとおしりが椅子から離れそうになるのを、懸命に耐えていた。
実は一度耐えかねておしりを浮かせたのだが、即座に母の手がドレスをひっぱり、すさまじい瞳でにらみつけてきたのだ。
この世で母ほどこわいものはない。
「前回お会いしたのが12月の聖誕祭。そして今回が5月の議員行列。次はいつになりますかしらね。」
ゆったりと羽根飾りのついた扇をゆらしながらマリー・アンヌがほほえんだ。
「その割合でいくと、11月頃ということでしょうか。」
オルタンスが単純計算で答える。
もう少し気の利いた返事ができないのかしら、とル・ルーは隣で菓子をほおばりながら思う。
「遠い領地からベルサイユに出てくるのもなかなか大変でしょう?」
マリー・アンヌが優しく尋ねる。
「それはもう…!ノエルのときのようにわたくし一人ならまだしも、今回のように一家でとなりますと、荷造りも3倍ですし…。」
オルタンスは勢い込んで答える。
「あら、わたしとお父さまのものを足しても到底お母さまおひとり分にたりなかったわよ。」
ついにこらえきれずル・ルーが突っ込んだ。
「まあ…!」
オルタンスは顔を赤らめて娘をにらんだ。
「貴婦人の支度とはそういうものなのですよ、ル・ルー。いずれ四、五年もたてばあなたにもわかります。」
マリー・アンヌがおっとりと妹に助け船を出した。
全体を見渡し、調和に破綻の兆しが見えればさりげなく軌道修正して、場の雰囲気をなごやかに保つ手練手管の見事さは、マリー・アンヌの天性の持ち味だったが、年とともに一層の磨きがかかって、間近で見ている伯爵などは圧倒されてしまう。
到底、田舎では醸成できかねる代物だ。
ところが、ひとり予定調和など全く関知せず、独自の世界を持つものがこの場にいた。
クルクル巻き毛の少女は伯母の顔をじっと見つめた。
「わたしよりはるかに歳をとっているオスカルお姉ちゃまは、以前うちにいらしたとき、それはそれは少ないお荷物だったけど…。」
「…!」
マリー・アンヌの扇を揺らす手が止まった。
少女の父は息がとまるかと思った。
かねがね怖いもの知らずの娘だとは思っていたが…。
なればこそ王太子殿下への拝謁も難なくこなしてきたとは思うが…。
ある意味、自分たちのような田舎貴族にとって、ご縁のない王室より、なまじ縁戚の公爵家のほうがよほど気遣いか必要なのだ。
それをこの娘は…、と伯爵はまじまじと我が子を見つめた。
「そうなの?」
公爵夫人が誰ともなく尋ねた。
「ええ、そうでしたわ。だってあのときのお姉ちゃまはずーっと軍服だったもの。着替えなんてあったのかしら。それにアンドレだって毎日同じ格好だったし…。そうそう、ロザリーお姉ちゃまは少しばかり持ってきてらしたけど、それだってお母さまほどじゃなかったわ。」
ル・ルーが流れるように解説した。
「オスカルは例外です。」
マリー・アンヌが憮然として言った。
予定調和を呼び戻すには、声の調子がいまひとつ険しいが、たかが小娘ひとり、威厳のある声で一気に沈黙させてしまうつもりだった。
ところが、小娘はひるまない。
「でも間違いなく女性でしょう?貴族の。だったら貴婦人のはずよ。」
ル・ルーは怖いもの知らずの典型で、公爵夫人に立ち向かっていった。
彼女にしてみれば、別段反抗しているつもりはさらさらなく、同じ姉妹で、母とオスカルとのあまりの違いを、純粋に疑問に思い、そのまま指摘しているに過ぎない。
「もちろんですとも。オスカルだってドレスを着れば、誰より素晴らしい貴婦人です。なんといってもわたくしたちの妹なんですから…!」
珍しく沈着冷静なマリー・アンヌの声に熱がこもった。
末妹は、ひいき目なしに、極上の美人だと長姉は思っている。
家のため、父のため、本来の性と異なる格好をしているが、正真正銘女性だ。
だからこそ、無理筋の恋愛もなんとかかなえてやろうと骨を折ったのだ。
花嫁衣装こそ着せてやれなかったが、誰にもいえないことではあるが、一応人妻である。
オルタンスがマリー・アンヌとル・ルーの間をとりなすように言った。
「まあまあ、オスカルが軍人だろうと貴婦人だろうと、この際どっちでもよろしいじゃございませんか。ねえ、あなた。」
オルタンスはこの際誰でもいい、とばかりに隣の夫に話を振った。
あくまで場つなぎで、答などはなから期待していない。
ところが、ル・ルーの勢いに感化されたのか、今まで黙っていた伯爵がぼそりと言った。
「ジャルジェ准将は生粋の軍人だよ。貴婦人だなんて…。准将に失礼だ。」
三人の女性がいっせいに目を見開いた。
マリー・アンヌなど、この義弟の声を聞いたのはいつ以来かと真剣に考えてしまったほどだ。
それくらい公爵夫人の前では寡黙な人だということだが。
「男のあなたからご覧になっても、オスカルは軍人ですか?」
この際、とくとお声を聞かせていただきましょう、とばかりにマリー・アンヌが尋ねた。
言ってしまってから、自分でも驚いていた伯爵は、正面切って公爵夫人に問いかけられ、完全に動転してしまった。
「私たちから見れば、間違いなくあの子は妹、つまり女性だけれど、殿方からは違って見えると言うことですか?」
オルタンスも不思議そうに尋ねてきた。
「い、いや、その…。」
口ごもりながら、なんとかごまかそうと試みるが、妻はともかく公爵夫人にいい加減な返答も許されず、ついに伯爵は重い口を開いた。
「あの人は、生き様が軍人だと言いたかったのです。誰かの庇護を必要としないで、むしろ庇護する側に立っている。並の男など及びもつかない覚悟が腹の底にある。そんな貴婦人はいませんよ。」
そこまで言うと伯爵は手をのばしてカップを取り、ごくりとお茶を飲み干した。
「男という存在のいらない人である以上、あの人自身が男なのです。」
オルタンスはまじまじと夫を見つめた。
「では、あの子には男はいらないと?」
「当然でしょう。大体男から見ても、守るべき対象には見えないですよ。はるかに強いんだから。近衛を指揮されているときは、絵画のような美しさがあって、それが男性の目をひきましたが、衛兵隊に移籍してからは…。あんなところです。おとなしく指揮に従わせるのに必要なのは美貌でもなければ王妃さまのご寵愛でもないはずですよ。」
マリー・アンヌとオルタンスは顔を見合わせた。
そして黙って伯爵に続きを促した。
「兵士達を圧倒する何か、この場合は腕力というか胆力というか、そういうものを持って彼らを統括しているのでしょう。こんなこと貴婦人にできるわけがない。いや並の男にもできません。だからあの人は生粋の軍人なんですよ。」
マリー・アンヌが小さく言った。
「以前、あの子に結婚を申し込む人を募ったとき、結構な数の方が応募なさいましたが…。これはなぜです?」
ローランシー伯爵は即答した。
「あれだけの美貌です。もしもあの強さを完全にご本人が否定して、夫に尽くす貴婦人になってくれるなら、こんな美味い話はないでしょう。求婚者を募集するからには、そのつもりだと男達は期待したのですよ。まあ、すっかり裏切られたようですが…。」
伯爵は当然だと言わんばかりに口元をゆるめた。
そうだったのか。
姉妹は深くうなずいた。
末の妹は、いでたちこそ男だが、自分たちにとってはまごう事なき妹で、いつだって女と思って接してきた。
だが、世の男どもにはそうは見えないらしい。
妹は男だったのだ。
でも…。
「オルタンス、ちょっと一緒にお庭へ出ましょう。ローランシーさまに当家秘蔵のワインをお出しして。」
マリー・アンヌは侍女に言い置き、立ち上がった。
「はい、お姉さま。」
いそいそとオルタンスは姉に付き従った。
伯爵とル・ルーは緊張感から解放される歓喜を押し隠すのに難儀しつつ、二人を見送った。
「どう思いましたか?今のローランシー伯爵の言葉…。」
マリー・アンヌは庭に出るなり、小声でオルタンスに尋ねた。
「驚きましたわ。殿方がオスカルのことをそのように見ていたなんて…。」
オルタンスも一層小声で答えた。
「本当に、わたくしも驚きました。でもよくよく考えれば無理もありません。お父さまが男としてお育てになったのですから、世間的にはあの子は男なのです。」
花壇を彩る様々な花に囲まれて、貴婦人二人が密談している。
「そうなんですわね。それも普通の男よりよほど男らしい男だと思われている。」
二人は見知らぬ世界の扉を開けた少女のように興奮していた。
それからふとあることに思い当たった。
「じゃあアンドレは…。」
同時につぶやいた。
そして目を見合わせ、そろって扇で口元を隠した。
妹が姉に発言を譲った。
「あの子が男でもかまわないと思ってくれたのかしら?」
「強さをこれっぽっちも捨てていないあの子でもかまわないと…。」
妹は大きく首を立てに振った。
「結婚させてしまったのですものね、わたくしたち。」
マリー・アンヌは今さらのようにつぷやいた。
「オスカルの希望と、お母さまの願望で、一気にことを運んでしまいましたものね。」
オルタンスが回想する。
本当に奇特なことだ。
人生の大半をオスカルのもとで費やし、心身に生傷の絶えない日々だったろうに、結局彼女の一生を引き受けてくれた。
もしかして生涯日陰の身かも知れないのに…。
ローランシー伯爵の言葉によれば、男の手助けなど全く不要の軍人の彼女のために…。
「いたわってやらないといけませんね。」
マリー・アンヌは自身に言い聞かせるように言った。
「まったくですわ。」
オルタンスも大きくうなずいた。
「あなた、明日はカトリーヌとジョゼフィーヌの所に行くと言ってましたね?」
「はい、その予定です。」
「このこと、二人にもしっかり伝えてちょうだい。そしてアンドレをよくねぎらうようにと。」
「承知いたしました。必ず伝えます。」
「それから、最後にジャルジェ家に寄ったら、くれぐれもアンドレによろしく言ってちょうだい。安易に押しつけて悪かったけれど、どうも替えはないようだから、見捨てず頼む、と。」
「わかりました。替えはないのですものね。」
オルタンスは重要事項を復唱して確認した。
それから二人は仲良く室内に戻り、何事もなかったかのようにお茶の続きを楽しんだ。
珍しく多くを語った伯爵は、昼間というのに公爵家秘蔵のワインに目尻を下げて、楽しんでいた。
そして、ドレスを引っ張る人がいなくなったル・ルーは、すでに姿を消していた。
ローランシー家の挨拶j廻りの初日は、おだやかな日溜まりの中、ようやく予定調和を取り戻していた。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1