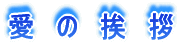
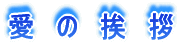
マリー・アンヌ宅を訪問した翌日、ローランシー一家はカトリーヌの住む瀟洒な屋敷を訪問した。
マリー・アンヌの絢爛たる邸宅に比べれば、やや小振りに見えるが、あちらが特異なのであって、一般的な貴族の屋敷としては充分な構えであり、ことにカトリーヌが丹精こめた庭園は、ベルサイユでも評判の美麗さを誇っていた。
折しも春たけなわ、様々な色の花が競って咲き誇る中、東屋に用意された昼食は、ほどよい量で彩りよく盛りつけられ、女主人の目が細部まで行き届いていることをさりげなく示していた。
あえてカトリーヌがこのような設定にしたのは、ル・ルーのために他ならない。
昼食を終えれば好きなだけ庭園を散策してよい、と言ってやると、ル・ルーの瞳はこれ以上ないほどに輝いた。
母の数ある姉妹の中で、この叔母の雰囲気は、ル・ルーにとって最も肌触りのよいものだった。
他のおばさま方が悪い人だというのではなく、あえて表現すれば、皆、大変個性的なのに対し、カトリーヌはいい意味で没個性的あり、対する人が自然な姿のままで存在できるのだ。
従って、おばさま方に負けず劣らず超個性的なル・ルーも、カトリーヌの前では素のままをさらけ出すことが可能であり、また、受け入れてもらえるという安心感もあった。
「お庭の中央の日時計が3時をさしたら、もどっていらっしゃい。おいしいお菓子を用意していてよ。」
なごやかな昼食が終わると、カトリーヌはツボを心得た言葉で、ル・ルーを野に解き放った。
この妹の配慮はオルタンスにとって願ったりかなったりだった。
昨日の公爵家では、さあ帰ろうと言うときになってもル・ルーの姿が見えず、家中の使用人を総動員して大捜索が行われた結果、あろうことか、隅々まで探索を終えて満足したル・ルーは、乗ってきた馬車に一足先に乗り込み、そのままぐっすり眠っていたのだった。
マリー・アンヌの予定調和がここまで打ち砕かれたのは珍しく、公爵家の執事のヴェリや息子のジェラール、その新妻のエヴリーヌら使用人たちは、驚きを通り越して感心していたほどだった。
一方、ローランシー伯爵の方も、昨日に比べれば数倍くつろいでいるようだった。
家格の面でも、また年齢の面でも、カトリーヌ宅ではさほどの引け目を感じずにすむ。
さらに会食の場が屋外であるということで、一層開放的な気分を味わえる。
食事中から、カトリーヌの夫君とは、趣味の葉巻に話がはずみ、わずかですがコレクションをお見せしましょう、という誘いに乗って、食後は喜んで男二人、廷内に戻っていった。
実は、カトリーヌの夫君は、密かに義兄の趣味を調べておき、接待に粗相のないよう万端の準備を整えていたのだが、もちろん、そのようなことはおくびにも出さない紳士である。
とはいえ、カトリーヌがその配慮に気づかぬわけはなく、席を立った夫に対し客には気づかれぬよう、軽く頭を下げて微笑んだ。
夫君はそれだけで妻からの感謝を充分に受け取って、いたって満足し、午後からの接待を機嫌良くこなしてくれるだろう。
春風の心地よい東屋にはオルタンスとカトリーヌの姉妹だけが残った。
小鳥のさえずりが絶え間なく聞こえ、昨今の不穏な世の中の空気を、ひととき忘れさせてくれる庭園である。
「お母さまのお庭いじりの趣味は、あなたが一番色濃く継いだのね。本当に見事なお庭だわ。」
オルタンスが感嘆した。
「いいえ、お母さまにはまだまだ及びませんわ。」
カトリーヌは嬉しそうに微笑んだ。
実は、母から受け継いだものは庭造りだけではなく、夫操縦法という庭いじりより数倍役立つものもあるのだが、こちらは姉妹全員が継承しているので、互いには気づいていない。
「マリー・アンヌお姉さまはお元気でしたか?先日お会いしたときは、時局のことでオスカルのことを随分心配しておいででしたが。」
「ええ、お元気…、あっ!!」
オルタンスはにっこりと返事をしかけて、それから素っ頓狂な声を発した。
「そうそう、大事な伝言があったのよ!」
カトリーヌは姉の奇声に驚いて、思わず手にしたカップをテーブルに戻した。
「マリーお姉さまがね、アンドレをねぎらうように、と。」
「アンドレをですか?」
「ええ、そう。」
「また、急にどうなすったのでしょう?」
「それがね、実はうちの主人が…。」
オルタンスはかいつまんで昨日のやりとりを紹介した。
だが、オルタンス流のかいつまみかただったので、理路整然とものごとを考えるカトリーヌには、理解不能な状況しか思い浮かばず、姉妹は意志の疎通に大変労力を費やす羽目になった。
だが父の短気は末娘だけが似て、姉たちはそろって母親似ののんびりだったから、互いに少しも苛立たず、会話は進んだ。
入れ立てのお茶がすっかり冷え切った頃、ようやくカトリーヌが言った。
「では、男のようなオスカルと結婚してくれたアンドレはとても奇特な存在だから、疲れて逃げ出されないよう、しっかり労うように、ということですのね?」
オルタンスは小首をかしげながら
「まあ、そんなところかしらね。」
と頷いた。
カトリーヌはほーっと肩で息をして、それからにわかに笑い出した。
「お姉さまからの伝言とおっしゃるから何かと思えば…ホホホ、そんなことでしたのね?」
「ええ、そうよ。そんなにおかしい?」
オルタンスが怪訝そうに妹を見つめた。
威厳にあふれたマリー姉に対し、カトリーヌは実に清楚な外見を持っている。
瞳は柔らかく、声も涼やかで、一見ひとりでは何も出来ない貴婦人の典型のようである。
だが、芯はずば抜けて強いものがあり、マリー・アンヌと互角に政治論を戦わせ、また、姉妹たちに領地支配についての助言もしているほどである。
その知的な妹が、面相を崩して笑う様子が、きわめて珍しく、オルタンスはしばらく黙って不思議そうにその様をながめていた。
やがてひとしきり笑ってからカトリーヌが言った。
「大変失礼いたしました。オスカルが誰より優れた軍人であることは、お姉さま達もすでにご承知のことと思っておりました。ローランシーさまは軍人であるから女ではない、とおっしゃったようですが、それは違いましょう。軍人であることは男であることと同義ではございません。男のすべてが軍人ではないように、女の軍人も存在するのです。他ならぬオスカルがそれを身を張って証明いたしております。ですからオスカルは軍人であっても充分立派な女であると申し上げますわ。」
カトリーヌは、アンドレが大変な覚悟でオスカルと結婚したのだろうと察している。
単に美貌に惹かれたとか、ましてや財産めあてのわけがない。
そのような枝葉のことが、彼の決断を左右するはずはないのである。。
なぜなら、自分たち姉妹以上に彼は妹の側に居り、心身の危険を厭わず妹の生き様を見守り続け、その上で、神の前で生涯の愛を誓ってくれたのだから…。
だがこのような抽象的、形而上的説明がオルタンスに通じる訳はなく、カトリーヌは、キョトンとしている姉に、彼女にわかる言葉で、言い直した。
「オスカルが軍人だということを一番知っているのはアンドレなのですから、彼が今さらそのことでオスカルとどうこうするはずはない、ということですわ。」
オルタンスはなるほど、と扇をパチリと閉じた。
「それもそうね。」
「そうですとも。」
カトリーヌはやっと納得した感の姉に微笑んだ。
基本的におっとりとしていて、誰に対しても素直に正直に自分をさらけ出して接するオルタンスとの会話は、カトリーヌにとって憩い以外の何物でもない。
まして末妹のこととなると真剣に心を砕いて、自分ができることをしよう、としている姉である。
善意の固まりのような方だわ、またしばらく会えなくなるのが本当に寂しいと、カトリーヌは思った。
そして姉への深い愛を込めて、カトリーヌは言った。
「ですからご心配はご無用ですわ。でも、もちろんマリー・アンヌお姉さまのお言いつけですから、わたくしからも充分にアンドレをねぎらってやることにいたします。ご安心下さいませね。」
「ありがとう。よろしくね。」
オルタンスはほっとしたように笑い、それから付け足した。
「そうそう、アンドレへの伝言もあったのよ。これも忘れないようにしなくてはね。」
「まあ、どのような?」
「簡単なのよ。『どうも替えはないようだから見捨てずよろしく頼む』って。」
今度こそカトリーヌは何年来したことのないほど笑い崩れた。
そしてそんな妹をキョトンとしてながめていた姉もつられてコロコロと笑いだした。
三時を前に、ル・ルーが東屋に戻り、男性二人もお気に入りの葉巻をくゆらしながら、再び庭に姿を見せたとき、貴婦人二人は目に涙を浮かべて笑い転げていた。
花と鳥と春風とが、貴婦人二人と紳士二人、そしてひとりの少女を暖かく見守っていた。
2