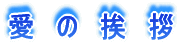
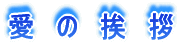
レイモン・エドゥアール・ド・ブラマンクは、フランス西部の海岸に領地を持つ伯爵家の継嗣として生まれ、青年時代をベルサイユ宮殿で美貌の貴公子として華麗に過ごし、いくつかの浮き名を流したのち、さる舞踏会で出会ったジャルジェ家の五女、ジョゼフィーヌに一目惚れして、連日連夜彼女の家を訪問し三ヶ月かけて口説き落とした。
六女が男性として育っていることは周知のことだったから、ジョゼフィーヌは美形で有名な姉妹の、最後の一人というわけで、それを射止めたことが人生最大の自慢であった。
当然ながら、このようないきさつの結果として、日々の暮らしは絶対的に妻のいいなりだが、そんな毎日をいたって幸せに過ごしている。
このたび、三部会の開会にともなってベルサイユに来ていたオルタンスの一家がいよいよ帰郷するというので、内々ではあるが晩餐会を催して、別れを惜しむ場とすることになった、と妻から告げられたのは、昨日のことだった。
当初、ジョゼフィーヌは、オスカル以外の姉妹及びその家族全部に加えて両親まで招待しそれなりに盛大な晩餐会を挙行するつもりでいたようだが、派手なことが苦手なローランシー伯爵が尻込みしたので、オルタンスは日程調整の難しさを理由に丁重に遠慮し、一軒ずつ挨拶回りをすることにしたらしい。
このローランシー伯爵の気持ちが痛いほどわかるブラマンク伯爵は、さりげなく妻に、ささやかだけれども一番心のこもった晩餐にしようと提案して、密かに義兄の援護射撃をおこなってやった。
一方、カトリーヌ宅でなごやかな午後のひとときを過ごしたロンランシー一家は、そのまま夕闇の中、馬車をブラマンク邸に廻した。
さんざん庭をかけずり回ったル・ルーもさすがに疲れておとなしくしている。
前回、ひとりで訪問して、ジョゼフィーヌや従兄弟達に立派な淑女だと褒めそやされた手前、ル・ルーとしても、ここでだけは精一杯いい子でいなければならなかったから、適度な運動で有り余る体力と好奇心を消耗してきたことは、カトリーヌおばさまに深く感謝せねばならないと思っていた。
ブラマンク邸に到着すると、屋敷の主一家はそろってホールまで出迎えに出てくれていた。
そしてブラマンク伯爵、ジョゼフィーヌ、アンリ、シャルルの四人と、ローランシー伯爵、オルタンス、ル・ルーの三人は、談笑しながらそろって広間に向かった。
執事が広間の扉を開けると、心地よい音楽が流れてきた。
モーツァルトのセレナーデだ。
七人は、しばらく立ち止まり、美しい音に耳を傾けた。
短い曲はすぐに終わり、指揮者が立ち上がって、一同に向かい深々と頭を下げた。
「とてもきれいな音色だったわ。ありがとう。」
ジョゼフィーヌが楽団のメンバーに声をかけた。
全員が起立してパトロンであるブラマンク夫人に一礼した。
ブラマンク一家とローランシー一家がそれぞれの席につき、腰を下ろした。
と、同時に、二曲目が始まった。
今度はモーツァルトのコンチェルトだった。
ブラマンク伯爵がグラスをとった。
「ローランシーご一家の長旅のご無事を祈って、乾杯。」
一同はグラスを交わした。
まだ小さいシャルルとル・ルーには、果物の絞り汁が用意されていた。
自分が外遊びで喉がかわいていたことに今頃気づいたル・ルーは、豪快に飲み干し、
「おいしい!」
と叫んだ。
ジョゼフィーヌが嬉しそうにル・ルーを見た。
「あら、このおいしさがわかるの?さすがだわ。」
「え?」
ル・ルーは意外な叔母の台詞に素っ頓狂な声で聞き返した。
隣の席のシャルルは、グラスを持ったままで、一口も飲んでいない。
「飲まないの?」
とル・ルー。
「飲めるの?」
とシャルル。
「飲めないの?」
とまたル・ルー。
そこにアンリが口を挟んだ。
彼のグラスにはおとなと同じワインが入っている。
「そのジュースはおかあさま特製で、身体にいいそうなんだけど、僕たちにはどうにもすっぱくてね。ぼくもこの間までとても苦労したんだ。」
ようやく大人と同じワインを許可されるようになった幸福をかみしめるようにアンリが言った。
「すっぱい?」
ル・ルーが聞き返した。
「きみ、これがおいしいなんて、すごいよ。」
シャルルが本当に目をまるくしている。
「よかったら、僕のも飲んでくれない?」
口調は軽いが目は哀願している。
乾いた喉への有り難い申し出に、ル・ルーは喜んでシャルルのグラスを受け取り、もう一杯をぐーっと飲んだ。
確かに口に酸味が残るが、冷たく冷やしてあって、変に甘くなくて、ル・ルーには美味としか思えない。
「うわ〜!ほんとに飲んでくれた!ありがとう!!」
シャルルが泣かんばかりにル・ルーの手を取った。
「アンリ、シャルル。」
ジョゼフィーヌのやや怒りを含んだ声がした。
しまった、という表情が露骨に出た二人は、あわててうつむいた。
「このジュースはわたくしの特製で、それはそれは身体によいのです。しっかり飲まなくては丈夫な身体になりませんよ。」
男にしておくのはもったいないほど美貌の少年達は、小さくハイとつぶやいた。
「あなた、わざわざご自分でジュースを作っているの?」
少年たちの窮地を救ってくれたのはオルタンスだった。
もちろん、本人にそんな気はさらさらないのだが。
「ええ、そうですわ。」
「ふ〜ん…!」
オルタンスが感心している。
「オーストリアの亡きマリア・テレジア陛下は特製スープを考え出されて、お子様方に、必ず飲ませておられたのですって。もちろん、ご自身も、ご夫君も…。それがご丈夫な身体をつくり、ハプスブルグ家の繁栄のもととなったのですわ。」
「へぇ〜…。」
オルタンスの感心はさらに増した。
「当家の息子たちは残念ながらあまり丈夫ではありません。ですからわたくしがマリア・テレジア陛下にならって特製ジュースを考え、毎日飲むようにさせたのです。」
ジャルジェ家の子女は、ことほどさように個性的かつ能動的である。
案外どの娘が男として育っていてもそれなりに活躍していたのではないか、と思え、ローランシー伯爵とブラマンク伯爵は、そうならなかったことを心から神に感謝した。
「せめてもう少し甘かったらなあ…。」
ポツリとシャルルがつぶやいた。
「いけません。幾度もの試行錯誤の結果、これが一番あなたたちの身体によいのだとわたくしが判断したのですから。いいですか、中身はイチゴ、サクランボ、フランボワーズ、フレーズ・デ・ボワ、グロゼイユ、オオグロゼイユ、カシス、ミュール、ミルティーユ。この中からおのおのの季節に取れるものを集めて絞ったのです。赤い実ばかりでどれも栄養が豊富なのよ。」
ジョゼフィーヌがピシャリと言い切った。
母の言葉に少年達がシュンとしおれたとき、
「わかったァ!!」
と、ル・ルーが叫んだ。
「かわいいマドモアゼル、何がわかったのかね?」
静かに神に感謝を捧げていたブラマンク伯爵が優しく聞いてくれた。
「このジュースの味よ。これ、わたしがいつもつんで食べる果実の味がそのままなのよ。」
ローランシー夫妻は真っ赤になった。
いかに田舎暮らしとはいえ、れっきとした貴族の令嬢が、庭の果実をもいで食べていたとは…。
おそらく落ちていたものではなく、木によじ登って取ったであろうことまで、親ならば容易に想像できて、さらに恥ずかしさが募る。
「すばらしい!」
次に大声を出したのはジョゼフィーヌだった。
「ル・ルー、なんて素晴らしいの!果実をそのままおいしいと思えるあなたの味覚。それこそが健全な人間の基本です。」
オスカルとジョゼフィーヌが天敵であるのと正反対に、ル・ルーとジョゼフィーヌは同好の志であるように神様に生み出されたらしい。
オスカルのすることはことごとくジョゼフィーヌの癇に障るのに対し、ル・ルーのすることはおしなべてお気に召すようだ。
ル・ルーは今回、労せずしてジョゼフィーヌの信用を勝ち取り、二人の絆は一層強固なものとなった。
あっけにとられて二人を見つめていたローランシー夫妻は、どうやらここではこの個性あふれる娘が大変好意的に受け止められていることに気づき、ほっと胸をなで下ろして、心づくしの晩餐を楽しんだ。
少年たちは代わる代わるル・ルーにダンスを申し込んでくれて、彼女は生まれて初めて貴婦人気分を味わい、これもまたなかなかいいものだわ、と顔をほころばせた。
無論、いつものように、それに付随するさまざまな制約は一切無視しているのだが…。
娘の楽しげな様子を微笑ましく見つめながら、オルタンスは夫にそっとつぶやいた。
「自然なままが一番すばらしい、とジョゼフィーヌは言うけれど、昔から庭の果実をもいだりするのは、いっつもオスカルで、あの子は眉をひそめて見ていたのよ。人って不思議なものね。」
ローランシー伯爵は、いやいや、なかなか、と首を振り、
「わたしからすればあなたたち姉妹全員が不思議このうえないけれどね。」
と言って、向かいに座るブラマンク伯爵にそっとウインクをした。
ブラマンク伯爵も隣の妻に視線をやると、深く頷き、かつて大勢の貴婦人をしびれさせたウインクでローランシー伯爵に答えた。
昼のカトリーヌ邸でのさわやかな風を受けた午餐会と、今宵のジョゼフィーヌ邸での心地よい調べに包まれた晩餐会は、まもなくベルサイユを離れるローランシー一家にとって何よりのはなむけとなって、いつまでもいつまでも心に残るはずである。
3