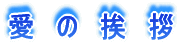
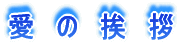
「お二人ともあまりにお忙しそうで、申し上げるのが今日になってしまいましたが…。」
と、ジャルジェ家の朝食の席で、夫人が当主と後継者につつましく話し始めた。
「オルタンス一家が今日帰郷いたします。」
ホォ〜と聞き手の二人は顔を上げた。
「滞在一ヶ月、潮時だな。」
将軍がもっともらしく言うのにかぶせて、夫人は続けた。
「ですのでお暇乞いのご挨拶にまもなくこちらに参ります。あなたもオスカルも休暇が取れたなんて、まさに天の恵みでございますわ。」
ガチャン!とマナー違反の大きな音が部屋に響いた。
「聞いておらんぞ!」
と将軍が声を荒げ、
「聞いておりませんぞ!」
と准将も朝に似合わぬとがった声を出した。
「ですから、最初にお断りいたしましたでしょう。お二人ともあまりにお忙しそうで、申し上げるのが今日になってしまいました、と。」
夫人だけは二人とは別世界に住んでいるかのように大層落ち着いている。
「…。」
言葉を失った父と子はめずらしく目を見合わせた。
やがて将軍がボソリと言った。
「今日帰ると言うのならば、一目会ってやらねばならんな。」
どんな孫でも孫はかわいい。
まして娘はなおさらだ。
遠くに住む一家とは、今日別れてしまえば、次にいつ会えるかわからないのだ。
もとより基本的には家族愛にあふれた当主である。
夫人はにっこり微笑み
「オルタンスも、あなたのお顔を見たくて参るのですわ。ベルサイユを出る最後の最後にこちらに寄るそうですから。」
と、父性愛にとどめをさした。
「そうか…。急なことで何も餞別を用意しておらんが、おまえ、何か?」
「もちろんですわ。お父さまからということで、様々に取りそろえました。ご安心くださいませ。」
「うむ。それならよい。」
将軍は寡黙に、満足げに食事を続けた。
まったく満足していないのは夫婦のやりとりを黙って見ていたオスカルである。
冗談ではない!と声を大にして言いたかった。
今日は、ダグー大佐の身に染みる好意によって、隊員たちに先駆けて久しぶりに取れた休暇である。
しかも、アンドレも勤務をはずし、同日に取れるよう工面したのだ。
今さらローランシー一家を避けて急遽出仕するわけにも行かない。
せめて昨日の朝に聞いておれば、休暇を一日延期したものを…!
ギリギリと歯を噛みしめながら、母によって完全に籠絡されていく父の様子をただ見つめていた。
「オスカル、朝からそんな怖い顔をして…。給仕のものが恐れて近寄ってこれないではありませんか。」
母は、誰よりもその理由を知っているはずなのに、見事にそしらぬ振りをして、オスカルを諭した。
は〜は〜う〜え〜!!
オスカルの内心の声は含みうる限りの怒りに震え、身体まで共振しそうだ。
だが、冷静であるべき軍人としての日頃の鍛錬が、かろうじて声帯を通ることを防御し、オスカルは黙々と食事を続けた。
「おまえは知っていたか?」
食後、自室に戻る途中でそっと近づいてきたアンドレにオスカルは振り向きもせず尋ねた。
「いや、ついさっき、厨房でオルガから聞いたところだ。」
当然だ。
彼は四六時中自分と行動を供にしていたのだから、自分の知らないことを知っているわけがない。
それでも…。
それでも、時々おまえは、魔法のようにわたしの知らない情報を入手して手を打ってくれるではないか、今回は魔法が使えなかったのか?
と、かなり真面目に問いただしたい心境のオスカルであった。
「とりあえず、予定していた遠乗りは中止だな。」
アンドレはオスカルの部屋の扉を開けながら言った。
「やむを得ん。断腸の決断だが…。」
ずかずかと大股で窓辺の長椅子に近づき、どさっと座った。
「なんてこった!」
両手を頭の後ろで組んだ。
誰もいない宙をにらみつける。
アンドレは扉を確実に閉めてから、ゆっくりと近づいてきて、静かにオスカルの隣に腰を下ろした。
「オルタンスさまがわざわざお別れのご挨拶に来られるのだ。そう嫌がるな。」
アンドレがオスカルの後ろに手を回した。
抱き寄せられるかと思ったが、彼は背もたれに手を沿わせただけで、肩には触れてこなかった。
少し上方にある彼の顔を見やる。、
「わかっている。」
オスカルは短く答えた。
そうだな、とアンドレは思った。
オスカルにはわかっているのだ。
一ヶ月あまり滞在なさったとはいえ、直接お目にかかったのは、2,3回である。
しかもどれも短時間だった。
こまっしゃくれのル・ルーはムードンに連れて行ったりして、結構関わったが、姉上ご本人とは、なにほどの会話も交わしていない。
陽気で暢気で人の良いオルタンス姉上…。
以前、御領地のお住まいに伺ったときも、想像を絶する恐ろしい事件に巻き込まれたにもかかわらず、泰然自若となさっていて、肝の太さに恐れ入ったものだった。
普通、娘と妹が同行した遠縁の令嬢が惨殺されたら、震え上がって寝込んでしまうと思うが、この方は、率先して大勢の犠牲者の追悼ミサを企画し、また被害者の遺族に物心両面の援助を行うなど、精力的に事件の後始末に取り組んでおられた。
ローランシー伯爵も、決して表立ってではなかったが、妻のすることに一切口をはさまず、やりたいようにさせることで、協力の意志を表明していた。
全く肩肘はらずに接することができるこの人の性格は、アンドレにとってもありがたいもので、ローランシー家滞在中は、完全に客人としてもてなしていただいた。
扉がノックされ、侍女が廊下からローランシー一家の来宅を告げた。
オスカルは、すっと立ち上がった。
アンドレも続いて立ち上がった。
オスカルはやはり少し上方にある彼の顔を見た。
部屋を出るまで、アンドレは無言のままオスカルの肩を抱いて歩いた。
そして扉をあけると、手を離しさっと一歩下がった。
ここからは使用人だ。
玄関ホールの上まで来ると、階下からにぎやかな笑い声が聞こえてきた。
階段の手すり越しに下をのぞくと、将軍夫妻が三女一家を出迎えに出ていた。
「姉上!」
と、声をかけ、オスカルもすぐに一族の輪に合流した。
「まあ、オスカル。今日は勤務ではなかったの?」
オルタンスが嬉しそうに言った。
「たまたま、休暇ななったのです。ご挨拶できて幸運でした。」
穏やかに答えるオスカルを、ジャルジェ夫人は優しく見つめた。
「アンドレ!」
ル・ルーは目ざとく階上のアンドレを見つけ、階段を駆け上がっていった。
踊り場で、降りてくる途中のアンドレに飛びつくと、そのまま抱き上げてもらい、ニコニコと一同に加わった。
「アンドレ、アンドレも休暇なの?お姉ちゃまと同じ日に?」
ル・ルーがアンドレの首にしがみつきながら聞いた。
「めったにないことだけど、そうなんだ。」
アンドレも笑って答えた。
「ふーん…。めったにねえ。」
意味深につぶやくル・ルーに内心ドキリとしながら、アンドレはテラスに用意されたお茶の席に向かう一行の最後尾に続いた。
テラスでのお茶会に使用人が同席できるはずもなく、当然ながらアンドレの席は用意されていない。
が、ローランシー家では、いつもアンドレの席があったので、ル・ルーは椅子が足りないと察するや、アンドレを自席に誘導し、彼の膝にちょこんと座った。
そこはわたしの指定席だろうが、とは、さすがにオスカルもル・ルー相手には思わない。
むしろさりげなくアンドレを同席させるル・ルーの機転に感嘆していた。
「アンドレ、あそこのお菓子を取ってちょうだい。」
ル・ルーは手の長いアンドレを最大限に活用し、テーブルの上に散りばめられた菓子類を片端から味見していく。
「ここのコックはとてもいい腕ね。」
おませな口調でル・ルーが批評する。
「おや、おわかりですか?」
アンドレが笑い出しそうになるのをこらえながら丁重に聞いてやる。
「もちろん。ムードンのお菓子もおいしかったけれど、マリー伯母さまのところは、いまひとつだったわ。悪くないんだけどなんか食べてて疲れるの。」
「ホォ…。」
「カトリーヌ叔母さまのところの焼き菓子はとてもおいしかったわ。どれもふんほりしてて、ちょっとたよりなかったけれど。」
「フ…ム。」
なかなか鋭い味覚である。
「ではジョゼフィーヌさまのところは?」
今度はアンドレから聞いてみた。
「自然のまんまでわたしは好きだけど、アンリとシャルルは喜んでなかったわね。お菓子は固いし、ジュースは酸っぱいんですって。」
アンドレはなるほど、と感心した。
この小さな女の子の各家のお菓子批評は、そのまま家の雰囲気、つまり女当主の雰囲気を彷彿とさせていて、非常に納得できる。
「見事な舌だな。で、ここのコックは腕がいいって?」
ついジャルジェ家の印象を知りたくて、アンドレは質問した。
「ええ、とても。だっていろんな味があるのだもの。どんな人が来ても、必ず口に合うものがあるはずよ。そこがすごいと思うの。」
「その通りだ、ル・ルー!素晴らしいよ。」
アンドレの手放しのの賞賛にル・ルーは得意満面である。
「ま、大したことじゃないわ。誰でも食べてみればわかることよ。」
ツン、と大人びた顔で答えながらも、かなり嬉しそうだ。
「ご機嫌だな、ル・ルー。」
横からオスカルが会話に入ってきた。
「いや、大したものだよ、ル・ルーは。」
アンドレが二人のやりとりをオスカルに説明した。
「ほ…う。各家のお菓子判定か?」
また、妙なことを…と思いつつ、オスカルもル・ルーの解説には少なからず感心した。
特に、このジャルジェ家評は、誰でも暖かくおおらかに受け入れる母の性格そのもののようで、オスカルも賛成せざるを得なかった。
また姉上方の印象も、自分のそれとさほど差がなく、小娘のくせになかなか人を見る目があるではないか、とル・ルーを見直したりもしていた。
「ところでおまえの母上、というか、おまえの家の菓子はどうなのだ?」
オスカルはもののついでに尋ねてやった。
すると、今までスラスラと答えていたル・ルーが言葉に詰まった。
ん?わが母親となると難しいか?、とニヤリとする。
「とても一口では言えないわ。」
「?」
「強烈に甘かったり、恐ろしく辛かったり、かめないほど固かったり、つかめないくらい柔らかかったり…。まあ、そうね、何でもありだけれど、決してここのようにおいしいってわけじゃないわね。」
ものすごい評価である。
さすがにオスカルとアンドレは開いた口がふさがらなかった。
「でも、不思議とわたしの舌にはなじんでるみたい。毎日違っていてスリリングなんだけど、不思議と害はないのよ。」
恐れ入りました、と聞いていた二人は舌を巻いた。
まさにオルタンスの人となりそのものではないか。
コックと女夫人というものはかくも深いつながりをもっていたのか。
オスカルは、実の娘からかくも鋭い評価を受けているとはおそらく気づいていないであろう姉をそっと見やった。
オルタンスは父と母の間に席を取り、代わる代わる二人に顔を向けながら、それはそれは楽しげに話していた。
「本当に、まさかお父さまとオスカルのお二人に今日お目にかかれるとは思いも致しませんでした。」
オルタンスはすでに何度も言った言葉を再び繰り返した。
「お父さま、どうぞご無理をなさいませんように。いつまでもお若いと思っていらしてはダメよ。マリーお姉さまのところではまもなくひ孫も生まれるそうですからね。」
きつい台詞も、暢気なオルタンスの口調だと、将軍の怒りを買うこともないらしく、軽く受け流されている。
スリリングだけど害がない、との言葉通りである。
「それからオスカルも…。」
と、オルタンスはしげしげと自分を見つめている妹に言った。
「色々と女性の身体がつらくなってくる歳頃なんですから、充分気をつけるのですよ。」
こちらも、ジョゼフィーヌあたりが言うと血を見ることになりかねないが、オスカルは苦笑いですませた。
嫌味がまったくかんじられなかったからだ。
さらには、
「お母さま、こんな頑固なお二人に囲まれてさぞ気苦労が絶えないこととお察しいたしますけれど、どうかお母さまは我関せずでお過ごし下さいませね。」
とまでのべるにいたって、さすがにローランシー伯爵が妻の袖をひいた。
が、オルタンスは、あら?という顔をして、
「もう、お暇の時間?あらあら、楽しいと時のたつのが早いわね。」
と、あわてて立ち上がった。
確かに頃合いの時間だった。
皆、それぞれにゆっくりと席を立った。
あいかわらずル・ルーはアンドレに抱かれている。
おまえは歩き方を忘れたのか?とオスカルがからかうが、
「この方が楽なのよ。お姉ちゃまも知ってるでしょう?」
と返され、頬を赤く染めて、二人から離れた。
アンドレの方は腕の中の少女の発言が、どこまで本気なのか、とまどうばかりで、こちらも顔を赤くするしかなかった。
テラスから居間に戻ると、テーブルにたくさんの進物が置かれていた。
うわあ〜!と奇声を発して、ル・ルーがアンドレの手から飛び降りた。
「おじいさまからですよ。」
夫人がその中からかわいい帽子を取り、ル・ルーの頭にかぶせた。
「まあ…!なんてかわいらしい!」
オルタンスが歓声を上げた。
「馬子にも衣装だな。」
オスカルが小声でつぶやいた。
ささやかにしっぺ返しのつもりだが、ささやかすぎて通じなかった。
「どう?似合うかしら、アンドレ。」
ル・ルーがオスカルを無視して、アンドレの前でポーズを取った。
「ああ、とてもかわいいよ。」
アンドレはかがんでル・ルーに背を合わせて言った。
「貴婦人に見える?」
真面目に聞くル・ルーに周囲の大人がどっと笑った。
「貴婦人というには、まだちょっと早いかな。」
アンドレが優しく言うと、ル・ルーは
「確かに。まだちょっと若すぎるわね、わたし。」
と口を尖らせて言った。
侍女たちが一箱ずつ抱えて、餞別の品々を車寄せの馬車まで運んでいる間に、一同は最後の別れを惜しんだ。
オルタンスは、父、母、妹と丁寧に言葉を交わし、最後にアンドレの所にもやってきた。
ル・ルーの貴婦人発言で思い出したのだ。
肝心なことを言い忘れていたことに。
オルタンスはアンドレがびっくりするほど顔を寄せ、小声でささやいた。
「あやうく忘れるところだったわ。マリー・アンヌお姉さまからの伝言よ。」
「?」
「どうも替えはないようだからよろしく頼みます。」
「??」
アンドレの目が点になった。
「な、何のことでございましょう?」
呆然としているアンドレから離れると、オルタンスは皆に言った。
「さあ、馬車に乗りましょう。」
オルタンスは夫と腕を組み、反対の手を娘とつなぎ玄関を出た。
ローランシー伯爵が最初に馬車に乗り込み、続いてル・ルーが父に手を引かれてステップを上がった。
最後にオルタンスが車中に消えた。
やがて窓が開いた。
「みなさま、ごきげんよう。さようなら。」
三人が口々に挨拶し、残された者も、同様に返した。
馬車がガラガラと走り出した。
ジャルジェ夫人はうっすらと涙を浮かべ、それをそっとぬぐい、手を振った。
将軍は口を真一文字に結び、遠ざかる馬車を黙って見つめていた。
オスカルとアンドレは大きく手を振った。
馬車が門を出るとオスカルは隣のアンドレに言った。
「さっき姉上に何を言われた?」
「え?」
「鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしていたぞ。」
おかしそうにオスカルが言った。
「それが、よくわからないんだ。」
「ふん。まあいい、言われたとおりに言ってみろ。」
アンドレは仕方なく、言われたまんま繰り返した
「どうも替えはないようだからよろしく頼む。」
「なんだ、それは?」。
「わからんだろう。マリー・アンヌさまからの伝言らしい。」
「ますますわからんな。大体なんの替えがないんだ?」
「それがわかれば苦労はしない。」
二人がぶつぶつ言っている後ろを通りながらジャルジェ夫人がひとりごとのように言った。
「せっかくのマリー・アンヌの伝言も、仲介者が悪いとまったく役に立たないようね。オルタンスはとてもいい子だけれど、今度ばかりはマリー・アンヌの人選ミスだわ。」
背中に寂しげな香りを漂わせながら引き上げる夫に続いて、夫人もまた屋敷に戻っていった。
「え?何ですか?母上…?」
オスカルとアンドレはあわてて夫人のあとを追いかけた。
「何の替えがないんです?」
オスカルの言葉が、閉められた扉の音にかき消された。
祭りの後の静寂が、ジャルジェ家の庭を包んでいた。
4