
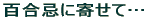
−2−
ディアンヌは思いがけず、窓の外に兄の顔を見て、大きな目を一層大きく見開いた。
が、すぐに視線を手元の幼子に戻し、にっこり微笑むと、頭を撫で、はだけた衣服を戻してやった。
子どもを抱いた母親が頭を下げながら部屋を出て行くと、消毒綿などを手早く片付け、それから医師に、兄の来訪を告げた。
目を細めて微笑む医師の許可を得て、ディアンヌは外に出た。
アランが楡の木の下で立っていた。
彼は妹に三日間の休暇が取れたこと、それでおまえの様子を見に来たことを伝えた。
「お母さまにはお会いになった?」
ディアンヌが尋ねた。
「ああ、先に家に寄った」
「お元気そうだった?わたしも最近忙しくてなかなか帰れないから…」
「びっくりするほど元気だった。今晩、飯を作るからおまえも帰ってこいって言ってたぞ。雨でも降るんじゃないか?」
「そう、よかった!急患がなければ帰るわ。三人でお食事なんて何日ぶりかしら…?」
ディアンヌの声は明るくはずんでいた。
妹は仕事中だ。
元気にしていることもわかった。
いつものアランなら、そそくさと帰るところだった。
だが、なぜかアランはぐずぐずしている。
ディアンヌは、怪訝そうに兄を見た。
「どうかなさったの?」
アランは顔をあさっての方向に向けると、小さな声で聞いた。
「ここの先生、うちの隊長のこと、なんか言ってなかったか?」
「え…?なあに?聞こえないわ、お兄さま」
「ここの先生は、隊長のことなんか言ってなかったかって聞いてんだ!」
兄の突然の大声にびっくりして、ディアンヌは後ずさりした。
「あっ、すまない。いや、この間、診察に行ったんだろ?何か言ってなかったか?その、ひどい、とかなんとか…」
兄の顔が心なしか赤いことに気づき、ディアンヌはクスクスと笑った。
「まあ、わたしよりそちらが心配で、わざわざいらしたのね?残念ながら何も聞いてません。先生はそういうことを誰彼なくお話になる方ではありませんもの」
「そうか」
小さいため息をついた。
シュンとした兄に憐れを催し、デイアンヌは言った。
「お身体の調子がどうかは知らないけれど、今朝アンドレが来たわ」
「えっ?」
「これは単なる事実だからお兄さまに言っても叱られないでしょう」
「奴はなんて?」
「そんなこと知りません。先生とのお話の間は席をはずしてましたもの」
兄への優しさとイタズラ心がないまぜになっているディアンヌは、楽しくておかしくて仕方がない。
だが、アランの方は、アンドレが来たという情報に動揺していた。
おそらくアンドレも自分と同じ意図でここに来たのだろう。
違うのは、アンドレなら、医師に会い直接疑問を聞けるが、自分には何の権利も立場もないことだ。
「チェッ!」
思わず舌打ちした。
再びディアンヌに仏心が起きた。
「では情報をもう一つ。明日、クリスがジャルジェさまのお屋敷に伺うそうよ。もちろん何のためかは知りませんけれど」
「あの女が?」
アランは再び大きな声を出した。
「あいつ、医者か?」
「先生について随分勉強しているから、そのあたりのお医者さまよりずっと信頼できるとわたしは思ってます」
ディアンヌのクリスへの評価は高い。
母も今朝ほど同じように言っていたことを思い出した。
「わたしから教えて差し上げられるのはここまでよ」
ディアンヌは今度こそ本当に声を上げて笑い、患者が来たようだと言って、そそくさと戻っていった。
アランは、足下の石ころを蹴り上げた。
なにをやってるんだ、俺は?と自問する。
馬鹿なことをして、何がどうなるっていうんだ?
再び、自問。
そして、どうにもならない…と、自答。
そうだ、わかっていたことだ。
隊長の様態が本当のところどうか、ということは、心配はできても、聞き出すことはできない。
単なる部下なのだから。
隊長自身が、もう大丈夫だ、と言えば、それを信じるよりほか、なすすべはない。
だが、アンドレは違う。
医師に会い、話をし、クリスが屋敷を訪れる段取りをつけたという。
あいつだって、衛兵隊では、俺らと同じ部下じゃないか。
しかも、屋敷でだって、単なる使用人じゃないか。
なぜ医師はあいつには言うんだ?
あたりまえのように…。
小さいときから一緒に育ったのだ、と、以前隊長の口から直接聞いた。
兄妹のようなものだ、とも。
俺とディアンヌのようなものか?
だから互いに心配するのは当然か?
いや、少なくともアンドレの奴は違う。
隊長を妹だなんて思っていやしない。
見ればわかる。
では隊長は?
あいつを兄だと思っているのか?
再び小石を蹴り上げた。
それが楡の木に当たって自分の方に跳ね返ってきて、足下に落ちた。
大きなため息が知らず知らず口をついた。
やがてとぼとぼと来た道を引き返し始めた。
両手をポケットに突っ込み、唇をややとがらせ、少し前屈みで、大股に歩く。
さて、これからどうする?
夕飯にはまだ早い。
なじみの居酒屋も真っ昼間から開いてはいまい。
突然、行く手を人だかりに阻まれた。
高い身長を利用して、人垣の頭越しにのぞき込むと、老人が倒れていた。
どうやら行き倒れらしい。
もはやこのパリではめずらしいことではないが、かといって誰もが無視して通り過ぎるほどの日常茶飯事でもない。
アランは、どうせ暇なのだから、と、人垣を割って入り、老人を抱え起こした。
「おい、大丈夫か?家はあるのか?」
地方から出てきた無宿者の行き倒れだと、始末が悪い。
収容施設がどこもいっぱいだからだ。
だが、老人は首を振った。
よく見ると、着ているものも、なかなか仕立がよさそうだ。
「そうか、家はどこだ?」
と聞くと、ささやくようなしわがれ声で、
「ラソンヌという医者を訪ねてきた。もうすぐそこだ、と言われて、辻馬車をおりたとたんにめまいがしての…」
と言う。
アランは、奇遇だな、と思いながら、老人を担ぎ、今来たばかりの道を引き返した。
老人を囲んでいた人垣は、すでに崩れ、皆、自分が生きるために、それぞれに散っていった。
四月初旬、日はまだまだ高かった。



