
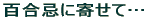
−3−
扉をやや乱暴に叩き、中から開けてもらうのを待ちきれず、自分で押し開け、
「お客さんだぜ!」
と、アランは大声で叫んだ。
そして、肩に担いだ老人に
「ついたぜ」
と一言告げた。
兄の声だ、と気づいたディアンヌが、小走りで出てきた。
続いて、クリスが何事か、という顔でやって来た。
「どうなさったの、お兄さま」
と、ディアンヌが言うのと同時に、クリスが叫んだ。
「お父さま!」
アランとディアンヌは驚いて顔を見合わせた。
「先生!先生!来てください、父が…!」
クリスの大きな声に、医師があわてて出てきた。
そして、玄関先でアランに肩を借りてようやく立っている老人を見ると
「兄さん…!」
と言ったきり絶句した。
応接室の長椅子にゆっくりと腰掛け、ようやく落ち着いた老人は、ディアンヌが持ってきた水をゴクリと飲み干すと、口を開いた。
「驚かせてすまなかった。おまえの手紙を見て、いてもたってもいられなくなってな。直接気持ちを聞こうと思ったんじゃよ」
老人は医師とクリスを代わる代わる見つめた。
「もう、うちへ帰るつもりはない、というのは本当なのか?」
弱々しい声だった。
この老人が、ラソンヌ医師の兄で、クリスの父だということが、話の流れで、アランにもディアンヌにも理解できた。
クリスと医師が叔父と姪の関係だということは以前から聞いていた。
そして、貴族の専属医師兼町医者としてそれなりの地位を得た叔父のもとに、田舎から家事手伝いのために出てきて住み込みはじめたということも、クリスの口から聞いて知っていた。
それが、次第に能力を発揮して、今ではなくてはならない助手となり、ゆくゆくは後継者とすら医師に決心させる存在となっていっていることは、共に暮らしていれば一目瞭然だった。
だが、田舎の両親にしてみれば、ほんの行儀見習いのつもりでパリに出したのだ。
パリ帰りの箔をつけて、できれば地元の資産家にでも嫁がせたいとの思惑もあった。
そして、このたびめでたく領主の縁戚に連なる家から縁談が舞い込んだ。
欣喜雀躍してさっそく帰郷を促す手紙を送ったところ、娘からは、思いがけず、否、との返事が来たというわけだ。
青天の霹靂だったに違いない。
バリ暮らしはそんなに楽しいものなのか。
田舎の老親を見捨ててしまえるほどに、魅力的なのか。
しっかりもので、けれど人一倍心の優しい娘が、本気でそんなことを考えているとはにわかに信じがたかった。
そこで、はるばる老父がパリまで確認しにきたという事の次第が、その朴訥とした語り口からアランとディアンヌにも推察された。
込み入った親族の会話を聞くべきではない、と二人は判断し、外に出ようとした。
だか゜クリスが止めた。
「いいのよ、ここにいてちょうだい」
それから、父に向かって淡々と言った。
「お父さま、ごめんなさい。わたしは帰りません。ええ、たぶん一生、懐かしいふるさとに帰ることはありません」
老父は呆然と娘を見つめた。
「ここに、わたしがすべきことがあるのです。わたしは医者になります。だから、わたしを連れて帰ろうとか、どこかへ嫁にやろうとかいうお話は、一切なさらないで。それさえお約束していただければ、わたしは、折々にお顔を見に帰ることはいたします」
とりつく島もない決然とした言い方だった。
「もう少し言い方があるんじゃねえか?」
アランは思わず口を挟んだ。
「あんたの決心は立派だけどよ、遠路はるばるやって来て、往来でぶっ倒れてた親父さんにむかって、もうちょっと思いやりのある言い方ができねえのか?」
ディアンヌが袖を引いているのがわかったが、こういう風に口走ってしまった以上、引くに引けないアランである。
だいたい、自分自身が日頃母に優しい言い方などしたことがないのだ。
もしディアンヌにそこをつっこまれたら申し開きのしようもない。
当然、あなたの口出しすべきことではない、と言われる覚悟はできていた。
だが、クリスはそうは言わなかった。
アランの言葉に対し、真っ正面から返答した。
「いずれわかること、どうしても言わねばならないことは、先送りすればするほど、言う方にも言われる方にも負担になるのよ」
なるほど、とアランは思った。
そのとおりだ。
言いたいことを腹に溜めて、ウジウジしているのは、自分も性に合わない。
はっきり言った方が、結局話は早いのだ。
アランは、今度こそおのれの立場をわきまえて、一歩踏み出していた足を引っ込めた。
ディアンヌがほーっとため息をついた。
結局、娘の気性を誰よりも理解していた老父は、はっきり聞けて良かったよ、と力なく微笑みながら了承した。
おそらく万に一つの望みを持って出てきたものの、結果は予想していたのだろう。
けれども、このような理由でもなければ、わざわざパリに出てきて娘の顔を見ることはかなわない。
あっさり承諾した父の態度に、その本心をかいま見て、クリスの瞳がわずかに潤んだ。
それまで沈黙していた医師が言った。
「兄さん、随分、身体が弱っているようだ。とてもこのまま田舎に帰すわけにはいきませんよ。わたしがいいというまで、しばらくここで養生してもらいます。義姉さんにはわたしから知らせておきます。ぜひそうしてください」
老人は、こちらもまた目尻に光るものを見せながら、弟の言葉にうなずいた。
気の毒だが、遠回しに言われるよりは、これでよかったんだろう、とアランは思った。
いつか言わなければならないことは早く言った方がいい、というクリスの言い分はまったくの正論だ。
くやしいがこの女の言うことは大抵あたっている。
今朝方、母も言っていた。
ディアンヌもいつも言っている。
あの人こそ先生だ、と。
アランは素直に認めた。
やがて医師の指示で、クリスとディアンヌに両脇を抱えられた老人は、二階の客間に上がっていった。
応接室には医師とアランの二人が残された。
「やれやれ、思わぬ所を見られてしまったな。だが、たまたま君が通りがかってくれて助かったよ。単なる過労だが、路上で放置されればあの歳だ。どうなったかわからん。よく助けてくれた。ありがとう」
医師は律儀に頭を下げた。
その白い頭を見て、アランは、どうしても聞きたいことを、今なら聞けそうな気がした。
クリスの先ほどの言葉が背中を押す。
言わなければいけないことは早く言ったほうがいい。
それなら、聞かなければならないことも早く聞いた方がいい。
そうだ、今しかない。
意を決して、アランは言った。
「あの、単なる過労でも放っておくと危ないんですか?」
「もちろんだ。過重労働が身体をむしばみ、自然に備わっている回復力を奪っていく状態が続けば、ふとしたことがきっかけで身体は悲鳴をあげ、一巻の終わり、ということは間々あることだ」
「では、ではうちの隊長はどうなんですか?」
大きな声に医師はびっくりしてアランを見つめた。
アランは両手をきつく握り、必死で問いただした。
「先生!」
ついに聞いてしまった。
こうなったら答えを聞くまで動かないぞ、と腹に力を入れた。
「オスカルさまは、衛兵隊では人気がおありなのだな」
医師はアランの問いには答えず小さな声で言った。
そして
「将軍閣下は、近衛隊ならともかく、衛兵隊など務まるか、と大層お怒りだったが、この分では心配なさそうだ」
と、さも安心した風に続けた。
気合いを入れて質問したアランは出鼻をくじかれた格好でワナワナと震えている。
「あんたが心配なくても俺は心配なんだよ!ええ?どうなんだよ?」
最初の神妙な口調はどこへやら、すっかりいつもの調子で怒鳴ってしまった。
こうなったら破れかぶれだ。
「先生!」
だが医師は一向気にせず、鷹揚に笑った。
「きみはそんなにオスカルさまが、隊長が心配なのかね?衛兵隊というのはみんな君のように、隊長の健康状態を気遣っているのか?」
皺に埋もれた細い目がいたずらっぽく問いかけてきた。
「それとも、君だけ何か特別な感情でもあるのかな?」
「ば、ばかやろうっ!な…何を…」
「ハッハッハ!いやいや君をいじめたりからかったりするつもりはないのだ。気を悪くしないでくれ」
無礼な言葉をかけられたにも関わらず、医師は寛大に笑った。
「オスカルさまのことはオスカルさまにきちんと説明している。また対処も相応に行っている。すまんが君にはこれ以上言うわけにはいかん。わかるな?」
話はこれで打ち止め、という宣言のつもりで医師は言った。
だが、アランは引かなかった。
というより、引くことなど頭になく、ただ頭に浮かんだことをそのままストレートに口にしてしまっていた。
「アンドレには言ったんだろう?あいつには…」
と続けかけて、それからアランははじかれたように黙った。
医師も驚きつつ、黙った。
馬鹿なことを言っている、と自分でわかった。
こんなみじめな姿を人前でさらすなんて…。
ああ、馬鹿なことをした。
畜生、なんてザマだ。
このアランさまが…畜生!
「今の話は忘れてくれ!」
そう叫ぶとアランは脱兎のごとく走り去った。
医師は、開け放たれたままの扉をしばし見つめていたが、やがて眼がねをはずし、ハンケチでキュッキュッとふいた。
そしてしみじみと思った。
朝、アンドレに昔話をしたのは間違いだった。
相手を間違えていた。
わたしと同じ匂いを持つのはアンドレではない。
今、逃げるように去っていったあの男こそがわたしとおなじなのだ。
むくわれぬ愛に長い時の営みをじっと耐えるのは、アンドレではなく、あの男だ。
これからもずっと、ずっと。
運命のひとに出会ったときに、まさにその瞬間に、すでにその人の傍らに分かちがたい魂の持ち主がいることを同時に知ってしまう、なんともいえない宿命…。
そして決して忘れられず、あきらめきれず、かといって離れられず、二人を見守り続けるしかないさだめに、ただ耐えるのだ。
オスカルさまは結婚しないと、将軍に宣言されたそうだ。
それは他ならぬ将軍の口から聞いた。
あの馬鹿が、と考えれば考えるほど血圧があがり、たまらないから薬を持ってくるよう言いつかったのだ。
非婚を貫くオスカルさまの真意はわからない。
アンドレのことをどう思っておられるかなど、侍医である自分の知るべきことではない。
だが、生まれたときからお見守りしてきたのだ。
アンドレの負傷時のオスカルさまの姿も、もっとも間近で見つめた。
左眼のときも、馬車襲撃のときも…。
それが恋愛や結婚という形を取れないとしても、だからといって別の人間をあのように信頼されおそばに置かれることはないだろう。
二人がどのような道を選ぶにしろ、二人で歩いていくのだろうということは、断言できた。
そろそろ診察室に戻ろうと部屋を出たところで、二階から降りてきたディアンヌに出くわした。
「あら、兄は帰ったんでしょうか?」
キョロキョロとあたりを見回しながら尋ねてきた。
「つい先ほど帰ったよ」
「そうですか。あの、先生、とても勝手なお願いなのですけれど、今夜は実家に帰ってもよろしいでしょうか。せっかく兄が休暇で戻ってきているので…」
おずおずと聞く少女のような瞳に、、慈愛をこめて許可を与え、それから、今度は医師が尋ねた。
「ディアンヌ、きみの兄上はなんという名前だったかな?」
「アランです。、アラン・ド・ソワソンといいます、先生」
「そうか、アランか。いや、ありがとう。なかなかいいお兄さんだね。帰ったらよろしく伝えておくれ」
「はい、ありがとうございます」
ディアンヌはにっこり笑ってその場を去った。
ラソンヌ医師は、口の中で繰り返し「アラン・ド・ソワソン」とつぶやきながら診察室に向かった。



