
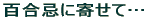
−4−
ディアンヌが、息を切らして自宅の扉を開けると、いつもは母が座っている揺り椅子に、アランが腰掛けていた。
眼を閉じて、静かに揺られるに任せている。
テーブルには、決して豪華とはいえないが、手間暇かけたことがすぐにわかる食事が並べられていた。
アランを起こさないよう、そっと横を通り抜け、厨房に入った。
母がスープを注いでいるところだった。
「ただいま」
と、声をかけると、最後までこぼさず入れたのを確認してから、母はふりかえり、おかえり、と言った。
「お兄さま、眠っちゃっているわ」
「そう?さっきまでは起きてたみたいだったけど」
「とてもかわいい顔をしてらっしやるわ」
「まあ、随分怒った様子で帰ってきたのに…」
「あらそうだったの?どうしてかしら?」
「知りませんよ。何を聞いても黙ったままで答えてくれないんですもの。まさかとは思うけれど、あなたと喧嘩したのかしら、と思ったくらいよ」
「いいえ、全然。ちょっとしたアクシデントがあったんだけれど、お兄さまには直接関係ないことだったし、それに、先生もクリスもお兄さまにはとても感謝してたんだし…。変ね」
ディアンヌが首をかしげた。
「さあ、できましたよ。あちらに運んでちょうだい」
ディアンヌはトレーにスープを三人分乗せて、隣室に行き、兄に声をかけた。
「お兄さま、お食事ですよ。起きてくださいな」
アランは、ハッと眼を開けた。
そしてあたりを見渡し、そこが実家であり、自分がうたた寝していたことに気づき、ピョンと揺り椅子から降りた。
「帰ってたのか?」
大きく伸びをしながら聞いた。
「ええ、ついさっき。クリスがくれぐれも御礼を言っておいてって」
「ふん、別に大したことじゃねえ」
アランなら当然そう答える、と予想したとおりの返事だった。
ディアンヌはそういう兄が好きだ。
「先生もね、お兄さまによろしくっておっしゃってたわ」
アランの眉がピクリと動いた。
そして少し視線を泳がせながら妹に聞いた。
「先生は何か言ってなかったか?その…俺のこと、とか隊長のこと…とか…」
「別に」
「そうか」
ほっとしたようにな、残念そうな微妙なニュアンスの声の響きだった。
勘の良いディアンヌはピンと来た。
「もしかしてお兄さま、先生に直接オスカルさまのことをお聞きしたの?」
「えっ?」
ディアンヌがまじまじと兄を見つめた。
アランはプイと顔を背け、押し黙った。
「お兄さまったら…。オスカルさまのことがそんなにご心配だったの?」
デイアンヌが真顔で問うてくる。
「あ…あたりまえだろう。軍人が馬の上でぶっ倒れたんだ。何か悪い病気かと思うじゃないか…」
歯切れ悪い答えが自分でも情けない。
「先生は何もおっしゃってなかったわ。安心してちょうだい。あっ、そういえばお兄さまの名前を聞かれたわ。そしていいお兄さんだねっておっしゃってた。よかったわね。差し出たことを聞いたのに、お気に障らなくて…」
ディアンヌは姉が弟を諭すような口調で、たたみかけるように尋ねた。
「で、先生はなんておっしゃったの?教えてくださったの?」
だがアランは答えない。
「ほら、やっぱり何も聞けなかったのでしょう?」
ディアンヌはにっこり微笑んだ。
「うるさい、この話は終わりだ!」
アランは強引に話題を打ち切った。
ディアンヌが、あきれた!という風に口をとがらせていると、母がどこから手に入れたのか、ワインを持って入って来た。
「久しぶりにそろったのだから、乾杯しましょう。いつもらったかもわからない古いものだけど…」
そういうと嬉しそうにグラスに注ぎ始めた。
アランとディアンヌは顔を見合わせ、それから、黙ってグラスを取った。
「何に乾杯するの?」
ディアンヌが聞いた。
それぞれ首をかしげて考えている。
どうも適当な題目が見つからない。
やがて母が言った。
「ありふれているけれど、こうして家族がそろってお食事できることに…」
兄妹はうなずいた。
「乾杯!」
三人は声をそろえて言い、グラスに口をつけそれぞれに飲み干した。
この際、味は問題ではなかった。
いみじくも母が言ったように、家族がそろって食事ができるありがたさをアランは感じていた。
元気になった母、元気になった妹…。
それで充分だった。
一度は完全に自分の手からこぼれ落ちたと思った平凡な家族の営みが、こうして再び戻り、むしろ前よりも一層絆を深めて確かにここにあった。
アランが感無量の思いでいると、グラスを置きながらディアンヌが屈託なく言った。
「あのね、お兄さま。先生はアンドレにはおっしゃったと思うのよ。だから、休暇が明けたら、彼に聞いてみればいいんじゃないかしら?」
「ゲホっ!」
アランは危うくワインを吹き出しかけた。
「まあ、大丈夫?やっぱりまずかったかしら?」
母があわててナプキンを差し出した。
アランはむせながらそれを受け取り口に当てた。
わかってんだよ、そんなことは…!
とっくに聞いたさ。
だけどあいつは教えてくれなかった。
隊長に直接聞けばいい、って言いやがったんだ!
聞けるか、そんなこと…。
「なんでそんなことを聞く?」と返されたら、なんて言えばいいんだ。
聞けないことを知ってて奴は言いやがったんだ。
だから、だから今日、思い切って帰ってきたのに…。
ああ、畜生!
言わなければならないことを思い切って言っても、思い通りの返事が返ってくるとは限らない。
クリスの言うことを真に受けた自分が浅はかだったのだ。
言えない言葉を胃に流し込むように、アランはワインを飲み続けた。
家族そろって元気でいれば充分、と、たった今悟ったはずの境地は、はるかかなたに飛んでいった。
そして母と妹が止めるのを歯牙にもかけず、一人で古い安ワイン一本明けると、ふらつく足で二階へ上がり、久しぶりに自分の寝台に転がり込んだ。
幸せだか不幸せだかわからないアラン・ド・ソワソンの一日がようやく終わろうとしていた。
終わり



