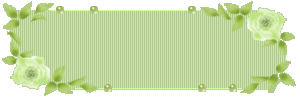
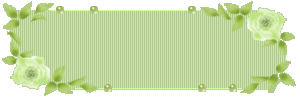
ラソンヌ医師の見立ては、過労、というものだった。
「無論、歳が歳ですからな、何が命取りになるやら、いつ心臓がとまるやら、確たることは申せませんが、それをのぞけば別段どこが悪いというわけでもなさそうです」
マロンがすでにそういう高齢なのだと思い知らされつつも、オスカルとアンドレは悪い病気ではないとわかり安心した。
医師はとにかくゆっくり休ませればそのうち快復するでしょう、栄養のあるものを食べていれば、特に薬もいらない、と言い置いて、帰っていった。
おばあちゃんの抜けた穴を埋めてやらないと、と厨房へ向かうアンドレと別れてオスカルはひとりでマロンの寝ている客間に戻った。
ちょうど侍女のひとりが水差しを取り替えに来ていて、オスカルに黙礼して部屋を出た。
話し相手が欲しいもの、というアンドレの言葉を思い出し、寝台の横に椅子を引き寄せて
「どうだ?」
と声をかけながら座った。
「働きすぎだそうだよ。しばらくゆっくり休むといい。ばあやに何かあったらアンドレが男泣きするからな」
と言うと
「何が男泣きですか。情けない。あたしの心配の種はあの馬鹿のことだけですよ」
とマロンは吐き捨てた。
「これは、なかなか厳しいな。ばあやはアンドレのなにが気に入らないんだ?」
「全部です」
「……」
かわいそうに、まるで立つ瀬がないな、とオスカルは深くアンドレに同情した。
自分にできるせめてものこと、と思い、この際とことんばあやの愚痴を聞いてやろう、と覚悟を決めた。
「では、順番に言ってごらん。今日は夕食まで時間があるから、たっぷり聞いてあげるよ」
との、最近めったにないサービスぶりにマロンはここぞとばかりに話し出した。
「あの子はね、もう34歳なんでございますよ。恐れ多くも国王陛下と同じ歳なんでございます」
意外なところに話がいくな…。そうだ、アンドレは陛下と、そしてわたしは王妃さまと同い年だった。
「比べるのももったいないことですが、ご夫妻にはすでに三人もお子様がいらっしゃっいます。それなのに…」
話はそういくのか…。
なんとなくオスカルは嫌な予感がした。
「アンドレは嫁のあてすらございません」
いや、すでに嫁はいるのだ。ばあやの目の前に…。王妃さまと同い年で…。
と、オスカルは心の中でつぶやく。
「身びいきかもしれませんが、あの子は人並みの見てくれですし、馬鹿ですが気だても悪くありません」
見た目も気だても充分だぞ、ばあや。
とは言わずフムフムとうなずいてやる。
「今までだんなさまにお願いして、何人もの娘を世話して頂きました」
「そうだったのか?」
今度は声が出てしまった。
「聞いていないが…」
憮然とした顔でつぶやいた。
「オスカルさまのお耳に入るところまで話が進まないんでございますよ。あの馬鹿が断るもんですから…」
当然だ、と笑顔が戻った。
「アンドレにその気がないなら仕方ないだろう」
「でもね、オスカルさま、あたしももう歳です。いつどうなるかも知れません。あの子が一人前に嫁をもらって、お屋敷の片隅にでも家を頂いて…」
だから、嫁はいるし、屋敷の片隅でなくまん中で暮らしているんだよ、まあ二人で片隅で暮らすというのもなかなか面白そうだが、などと馬鹿なことを考えてみる。
「このまえ、お嬢様方がいらしたとき、チラリと聞いてしまったんですがね、ジョゼフィーヌさまのところのシャルルぼっちゃまがこちらに養子にお入りになるとか…」
「そうなのか?あの話はジョゼ姉が断固拒否していたが」
「アンドレに子供でもいれば、またシャルルぼっちゃまの遊び相手としてお屋敷にも置いて頂けます。でもね、今から結婚して子供が生まれてもぼっちゃまとは歳が離れすぎて相手になりゃしませんよ」
もしもアンドレに子供がいるとしたら、その子の母親はわたしだから、シャルルとは従兄弟だ。心配しなくても遊び相手くらいはするだろう、などとぼんやりオスカルは考える。
「ところが、でございます。あの子が怪我で寝ていたときジョゼフィーヌさまがわざわざお見舞いにいらして下さって…」
確かそうだった。
しかも自分の出勤中をねらってあの姉はやってきたんだ。
いろいろ世話になったとはいえ、どうしてもジョゼフィーヌには厳しい反応をしてしまう。
「そのときお連れになっていた侍女が器量よしでございましてねえ。ジョゼフィーヌさまも随分お気に入りのご様子で、ノエルのときもお連れでございました。もしあの娘がアンドレのところに来てくれたら、シャルルさまがこっちに来られたとき、お世話もしやすいと思うんでございますよ」
ばあや、なんと狭い世界で遠大な計画を練っているのだ。
オスカルは相づちを打つのも忘れて、ばあやの話に聞き入ってしまった。
「なかなかの計画だと思うが、その中の登場人物の何人くらいがそれを知っているんだ?」
「まだ、誰も知りやしません」
「…!」
「あたしが言ったってどうせ話はうまくいかないんです」
「ばあや…」
「だあれもあたしの話をまともに聞いちゃくれないんです。年寄りの戯言だと思って…」
と言うとマロンはさめざめと泣き出した。
「ばあや。誰もばあやのことをそんなふうに思ってなんかないよ」
「では、オスカルさま、オスカルさまの口からあの馬鹿に言ってやって下さい。そしてジョゼフィーヌさまにお話しなさってみてください」
「えっ?わたしが?」
「はい」
マロンはきっぱりうなずいた。
……。
わたしが、このわたしがアンドレに嫁をもらえと説得するのか?
ジョゼ姉に、姉上の侍女をアンドレの嫁に下さい、と交渉するのか?
馬鹿な…。
どこをどう押せばそんな馬鹿げた考えがでてくるのだ。
だが、真実をばあやに告げることはできない。
まだ父上すらご存知ないのだ。
オスカルは返答を待つマロンに何か言葉を、と思いながら、どうしても何も言えなかった。
運良くというか運悪くというか、扉がノックされ、
「晩餐の用意が調いました」
と、侍女が告げた。
オスカルはマロンの上懸けをなおしてやりながら、
「愛しているよ、ばあや」
と、いつもどおりの挨拶をして複雑な表情で部屋を出た。
Menu