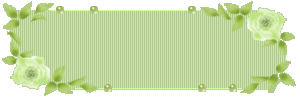
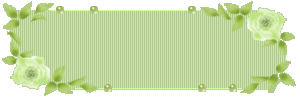
「ばあやがアンドレの嫁の世話をしてほしい、と言っています」
晩餐後、めずらしく自分から母の部屋を訪ねたオスカルは、刺繍をしている夫人に顔を背けて言った。
結婚式のあとも、別段これといって、その話題は出さず、今まで通りの生活をしている。
何と言っても当主に内緒のことである。
変わった動きを取るわけにはいかなかった。
それに加えて、恥ずかしさもあった。
どうも、こういう話題を母娘でするのは慣れない。
だから今も顔を背けているわけで、母親だけあってそのあたりは完全に理解して夫人も接してくれていた。
が、さすがに、この話には驚いたようで、夫人はオスカルの顔をじっと見つめた。
頬にやや赤みがさしているのがわかり、めずらしく夫人はこの男装の娘をかわいい、と感じた。
「それで…。なんと答えたのです?」
「答える前に晩餐の時間になりました」
「そうですか。ばあやの気持ちもわからないではありませんね。アンドレの歳ならもう子供のひとりやふたり、いてもおかしくありませんもの」
「確かに、そうなのですが…」
「で、誰を世話して欲しい、というあてはあるのですか?それとも探して欲しいと?」
「ジョゼ姉のところの侍女がいいと言っておりました。なんでもアンドレの見舞いの時に連れてきていたとかで…。どこで聞いたのか、シャルルが養子にくるなら、顔見知りの侍女がこちらにいるのは好都合だとか…」
「まあまあ、シャルルがうちへ?」
夫人は思わず口を押さえた。
確かにノエルの晩餐会でその話は出た。
だが、それはあの場から将軍とオスカルを追い出すための策で、二人の退出後、ゆっくり話がしたいからと、人払いをして計画を詰めたのだ。
その人払いの前に大広間で給仕をしていた使用人が小耳に挟み、噂が広まってしまったのだろう。
とすれば
「わたくしたちにも少しばかり責任のありそうな話ですね」
と夫人は刺繍をテーブルに置いた。
「ジョゼフィーヌに相談しますか?」
「とんでもありません!だいたい何でわたしがアンドレの結婚を世話しないといけないのです?」
確かに、妻が夫の嫁を世話するというのは不合理だ。
「わかりました。わたくしからばあやに話してみましょう」
母があっさり言ってくれたのでオスカルは少し気が楽になり、先程来気になっていたことを思い切って聞いてみることにした。
「父上が何度かアンドレに嫁の世話をした、というのは本当ですか?」
人にものを聞くときは決して目をそらさないオスカルが、今度も母から視線をそらして、テーブルの上の刺繍を見ながら尋ねた。
それに素知らぬフリをしながら夫人は答えた。
「まだ、あなたが近衛にいたころですよ。宮廷でアンドレを見た方が何度かそういう話を持ち込まれて…。なかなかいい条件のものもあったのですけれど、アンドレは皆断っていました。衛兵隊に移ってからは、忙しくてそんな暇はありませんでしたよ。うちの侍女の誰かと、という話は出たことがありますが、それはおとうさまからではなく、ラケルやオルガが仲立ちを買って出ていたようですね。あなた、知りませんでした?」
「いえ、わたしは一向に…」
長く一緒にいても気づかないこともあるのだな、と思うと情けなくもあり、寂しくもあり…。
複雑な表情を浮かべている娘に、夫人はさらりと言った。
「あなたはたった一回の縁談でも大騒動でしたものね。それを思えばアンドレは断り方もスマートでした。誰にも知られないよう、誰も傷つかないよう、そしておとうさまの面目をつぶさないよう、細心の配慮をしてくれていましたからね」
きつい一撃だった。
あの舞踏会を根に持っていたのは父上だけではなかったのか、とオスカルはいかにも優しげな母を空恐ろしい思いで見つめた。
確かに自分の縁談は衆目の知るところとなり、ジェローデル以下招待された客から両親までも傷つけ、父の面目をまるつぶれにしてしまった。
夫人は、どうしましたか、という顔でオスカルを見ると、にっこりと微笑み、
「ばあやの願いももっともではあるのですよね。生きている間にひ孫の顔が見たいのでしょう。それはわたくしにもよくわかります」
と小さな声でつぶやいた。
ノエルの夜、神の思し召し、と静かに娘たちを諭していた夫人の本音がポロリとこぼれ落ちた。
「では、よろしくお願いします」
オスカルは丁重に頭を下げた。
Menu