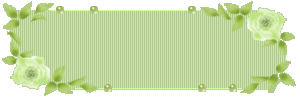
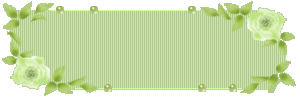
ばあやのためにも早く帰ってやりたいと思っていたが、たまった仕事が片づかず結局夕食も司令官室で簡単に済ませる羽目になり、オスカルとアンドレがようやく屋敷についたときには、日付が変わろうとしていた。
こんなに遅くに帰れば、屋敷の皆にも申し訳なく、本部に泊まることも考えたが、やはりばあやのことが気がかりで帰ってきた二人である。
ことに、オスカルはばあやの容態とともに、アンドレの結婚話の方も気になるところで、明朝、出勤前に母上に事態の推移を確認しておきたかった。
できるだけ音を立てないようにしたつもりだったが、車寄せで馬車を降りると中から扉が開いた。
誰が起きていてくれたのだろう、と暗がりで目をこらすと、燭台を持って、お帰りなさいませ、と言ったのは、マロンだった。
「ばあや!!」
オスカルの大声に、馬小屋へ轡を引いていたアンドレも驚いて戻ってきた。
「おばあちゃん!」
アンドレも負けずに大声を出した。
「しーっ!こんな夜更けに大きな声を出して…!」
と言いながら、マロンはオスカルに入るよう促し、
「おまえはさっさと馬を連れてお行き!」
とアンドレに言い捨てて扉をしめた。
「大丈夫なのか…?起きあがって…」
オスカルは恐る恐る尋ねた。
暗闇でわずかばかりの燭台の灯りに照らされたばあやは、この世の物とは思えない不思議な生き物のようだ。
「丸二日横になってましたらね、どうにも寝付けなくて、ためしに起きあがってみたら、どっこもなんともないんでございますよ。それでみんなに今晩はあたしが起きているからって…。オスカルさま、お部屋に何かお持ちしましょうか?」
達者な足取りで階段を上がるマロンに続きながら、
「無理せず寝ていてよかったのに…。明日に響くぞ」
と、言いながら、とりあえず元気そうでよかった、と安心した。
慣れた手つきでオスカルの着替えを手伝い、寝台を用意し、と、いつも通りのきびきびした動きに、肉体的というよりは内面的な理由があるように感じられ、
「何かいいことでもあったのか?」
と聞いてみた。
オスカルの脱ぎ捨てた軍服を手際よくたたみながら
「ええ。ございました。おわかりになりますか?」
と、答える声にも張りがある。
「さて、何だろう。じらさないで教えておくれ」
時間が時間であることを思い出し、早くこの疲れたお嬢様を休ませてさしあげねば、と、マロンは、常になくあっさりと正解を教えた。
「奥さまが、アンドレによい嫁を世話してやると、お約束くださったんですよ」
「母上が…?あの姉上のところの侍女か?」
軍服から勲章や階級章をはずすことに集中しているマロンはオスカルの驚きには気づかず、
「いえ、あの娘はもう決まった人がいてダメだったんですけどね、どうも奥さまにはいい心当たりがおありになるようで…。オスカルさまのお仕事が一段落したら、きっと紹介してあげようって、おっしゃってくださったんでございます」
と、嬉しそうに続けた。
「あたしの条件まで聞いて下さって…」
「ほう、ばあやは条件を出すのか。アンドレの嫁も大変だな」
ここまでくると当事者であることは忘れ、人ごとのように返していた。
そのとき遠慮がちに扉をたたく音がした。
「オスカル、俺だ。おばあちゃんはまだいるかい?」
アンドレの声だった。
「ああ、ここにいる。かまわん。入れ」
との返事に、私服に着替えたアンドレがいかにも困った顔で部屋に入ってきた。
「おばあちゃん。今、オルガに聞いた。みんな心配している。無理は禁物だ。さあ、部屋に帰ろう」
と、マロンのそばに来て言った。
「オルガがなんと言ったか知らないが、あたしはこの通り元気だよ。おまえこそ、こんな時間にお嬢さまの部屋へ来るなんて非常識だろう。とっととお帰り」
「もちろん、俺も帰るさ。だけどおばあちゃんだって戻らないと、オスカルが休めないだろう?明日も早いんだ。とりあえず今夜は奥さまのお心遣いを無にしないためにも客間の寝台へ戻ろう。俺も一緒に行くから」
オスカルが休めないのだ、と一番の弱みをつかれたマロンは渋々孫に従った。
小さな肩に手を回してマロンを誘導しながら、アンドレはそっと振り返り、
「おやすみ」
とオスカルに言い、それから声を出さずに
「愛しているよ」
と、口を動かした。
寝台にひとりで横たわりながら、オスカルは考える。
きっと今夜はもうアンドレは来ない。
ばあやを見張っておかなければならないからな。
アンドレのあの口ぶりでは、どうやら空元気らしい。
きっとオルガたちを困らせて無理を言って起きていたんだろう。
まったく無茶をする。
おかげでアンドレは…。
フェルゼンといい、ばあやといい、どうして皆、わたしからアンドレを遠ざけるのだろう。
しかもまったく悪意なく…。
それに油断ならないのが母上だ。
何もかもご存知の上で、アンドレに嫁を世話するおつもりなのだろうか。
馬鹿な…!
重婚罪だぞ。
と、毒づいてみたところで相手がいなければ空しいばかり。
明日はパリの警護にあたる部隊に同行し選挙の現状を自分の目で確かめる予定だった。
私的なことにとらわれている暇はない。
少しでも心身を休ませておく必要があるのだ。
上懸けを頭まですっぽりと被り無理に目を閉じた。
Menu