![]()
「だんなさまのお帰りでございます」
と、叫ぶ声がして、屋敷のあちこちから、手の放せるものが出迎えに出た。
ジャルジェ夫人も、何人かの侍女を引き連れ、優雅に腰を折り、
「お帰りなさいませ」
と、夫に声をかけた。
その様をチロリと見やり、将軍は
「あれは帰っておるか?」
と、ぶっきらぼうに尋ねた。
「はい、たった今帰って参りましたところです。自室で着替えておりますわ」
夫人はスタスタと廊下を歩く夫の後ろをついて行きながら、
「なにかございましたか?御前会議で…」
と、尋ねた。
今し方戻ってきた娘の様子に、いつもと違ったところは見受けられなかったが、それは、彼女が
鈍感なだけで、実は結構大胆な行動を起こしていた、と後で知るという経験は一度や二度では
ない。
夫がこういう言い方をするときには、まず何かあったと判断して間違いはない。
今度は何を…と、親心が答をせかすが、夫の方は、そうか、と一言言ったきり、事情を説明する
気配はなかった。
しかも、彼は娘を大声で呼びつけるでもなく、淡々と着替えを済ませて書斎に入っていった。
ならば、大したことはないのだろう、と夫妻の居間から書斎へ続く扉が閉められたのを見届ける
と、夫人は大きなため息をついた。
「ほぉ…。まったく次々と何がしかおこるものだわ。晩餐が無事にすめばいいけれど」
長椅子に腰を下ろし、思わずこめかみに手をやった。
昨日、ジョゼフィーヌの所に急遽出かけ、侍女の縁談を進めてきた。
それを受けて、今日はマリー・アンヌの屋敷に、エヴリーヌ が見合いに出かけたはずだ。
結果は吉と出たのだろうか。
夫人が将軍の帰館の際に、すぐに出迎えに出られたのは、実は、マリー・アンヌからの使者を待
って、玄関に一番近い客間にいたからなのだが、待ち人はなかなか現れず、こう言うと
きに限って、日頃帰りの遅い娘や夫が次々と帰ってきたのである。
すでに日が暮れてからかなりの時間がたった。
マリー・アンヌの報告は明日になるのだろう。
気がかりではあるが、致し方ない。
侍女が晩餐の支度が調ったことを告げに来て、夫人は長椅子がら立ち上がった。
親子三人で食卓を囲むのは久しぶりである。
「御前会議はいかがでしたか?オスカルは宮廷にあがったのは久しぶりだったでしょう?」
と、母が話を向けると、オスカルは顔を上げ、
「そう言われれば、久しぶりでした。年末に王太子殿下のお見舞いにムードンには伺ったのです
が」
と、答えた。
「会議は滞りなく進みましたか?」
さりげなく夫人は探りを入れてみた。
「はい。もとより形式的なものでございますから、とりたてて問題の起ころうはずもありません」
やはり、娘にとっては何事もなかったのだ、と思い、ちらっと夫の方を見た。
「ブイエの奴は相変わらずだな。昔から権威ぶった男だったが、ちっとも変わっておらん」
将軍は肉にナイフを入れながら、独り言のように言った。
「父上とブイエ将軍のおつきあいは長いのですか?」
と、オスカルはあらためて聞いた。
王妃から、転属の際に、二人の不仲は聞いていた。
実際、ブイエ将軍の方は、何かにつけて、父の話を持ち出して嫌味を言ってくるが、詳細を父に
確認したことはない。
「士官学校の同期だ」
父が簡潔に答えた。
「ほお…。ではまた随分長いのですね」
「だからこそ、遠慮なく互いの不十分な所は指摘しあえるはずなのだが、あいつは聞く耳を持た
ん」
「何か個人的に恨みを買っておられる気もします。何かあったのですか?」
「いや、心あたりはない」
「さようでございますか。まあ、父上とブイエ将軍に限って恋のさやあてなと゜があったとは到底
思えませんし。あちらの勝手な思い込みなのでしょう」
と、オスカルがいかにも軽い調子で冗談を言ったつもりが、突然、両親の動きが止まった。
そして気まずい沈黙…。
「え…?」
と言ったきり、オスカルは両親をまじまじと眺めた。
まさか…。
「母上…?」
と、さすがに父には振らず、母に声をかけてみた。
だが、母も沈黙したままである。
我が母ながら、若い頃はさぞ美しかっただろうと思う。
あのブイエ将軍が想いを寄せたとしても、不思議はない。
だが、この堅物の父が、とオスカルとしてはそちらが信じられない。
代わる代わる二人を見つめているオスカルを尻目に、将軍はさっさと食事を終え、席を立った。
その後ろ姿を見送りながら、夫人は静かに娘に言った。
「おとうさまは正しいことを言い過ぎるのです。それがかのお方には目障り、耳障りなのでしょう。昔からそうでした。別にブイエ将軍とわたくしがなにかあったというわけではないのです。ただ、
舞踏会でのわたくしへのお振る舞いに少々行きすぎたものがあって、お父さまはそれに見ぬふりができなかったのですよ。そのとき、わたくしははじめてお父さまにお逢いしました」
傍若無人な若い将校にからかわれる令嬢を放っておけず、同期の友を公衆の面前で叱責する
父の姿がありありと浮かんだ。
なにか特別詳しい話をされたわけではないが、それは、とても納得のいく説明だった。
オスカル自身、同じ理由でブイエ将軍に嫌われているのだから。
そして、父が心当たりはないと断言し、かつ、巷でささやかれる同輩との不和説を全く意に介して
いないことも、オスカルにはすんなりと理解できた。
自分になんら間違ったこと、引け目に思うことがない以上、堂々としていればいい。
それは、女ながらに士官学校や軍隊で優秀な成績を修めてきた自分へのいわれのない嫌がら
せに対して、常に自分が保持してきた信念だった。
「わたくしはそういう父上を心からご尊敬申し上げております」
オスカルは心からそう思い、嬉しそうに母に言った。
そのとき、急ぎ足で侍女が夫人に近寄り、一通の手紙を差し出した。
マリー・アンヌからだった。
夫人はおもむろにそれを受け取ると、続いて侍女が差し出したペーパーナイフで封を切り、さっ
と中身に目を通した。
それからにこやかに微笑み、
「ジョゼフィーヌのところの侍女とマリー・アンヌのところの執事の息子との結婚が決まりました」
と言った。
突然の話に目を丸くするオスカルに、
「もとはといえばあなたが原因なのですから、何かお祝いをしてあげねばなりませんよ」
と、言い渡した。
「結婚というからにはめでたいことだと思いますが、わざわざ面識もないわたくしが祝いの品を届
ける理由がわかりませんが…。ましてわたくしが原因とは、まったくお話が見えません」
と、異議を唱えるオスカルに
「いいえ、どうでもこうでも、あなたは心をこめた品物を届けねばなりません。そして若い二人の
幸福を誰よりも祈らねばなりません。いいですね」
と、珍しく穏やかな母が命令調で言った。
「ばあやにアンドレの縁談をどう断ったか、ゆっくり思い出してご覧なさい」
最後の言葉を置きみやげに、夫人は席を立った。
きょとんとしたオスカルが残された。
母の言葉を反すうしてみる。
アンドレの縁談…姉上の侍女…決まった人がいるからだめだった、と残念そうに言ったばあや
………!!
そういうことか。
決まった人はいなかったのだ。
だから母は決まった人を作った。
誰だ?
今、母はなんと言った?
「ジョゼフィーヌのところの侍女とマリー・アンヌのところの執事の息子との結婚が決まりました」
すべてを理解したオスカルはあわてて立ち上がると大声でアンドレを呼んだ。
「アンドレ、アンドレ!いるか、アンドレ!」
落ち着いた声で
「何か…?」
と、言いながらアンドレが近づいてきた。
その腕を強引につかんで
「今度の休暇はいつだ?急ぎの買い物がある」
と言いながら、大勢の使用人がびっくりして見守る中を自室にひきあげていった。
おわり
![]()
![]()
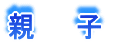
back
next
menu
home