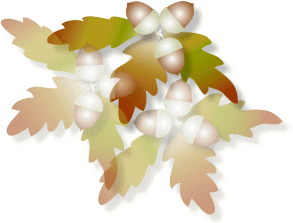
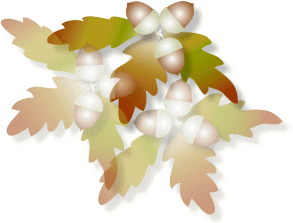
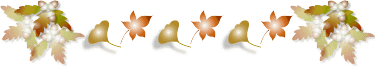
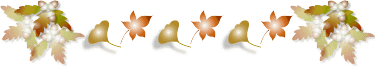
どんぐりころころ
どんぐりは長らく人類の主食だった。
樫、ブナ、ナラなど、およそどんぐりを産する地帯は、文明の先進地域と見事に重なる。
決して美味ではない。
味うんぬんではなく生きるために必要な存在、それがどんぐりだ。
であるならば、「おばあちゃんそのものだな。」とアンドレは思った。
親を亡くして以来、マロンはアンドレが生きていくために必要不可欠な存在だった。
優しいとは決して言えないが、いてくれなければ生きてこれなかった。
それにすがって成長し成人した。
どんぐり以外の食物を得ても、その人類に対する輝かしい恩恵が決して消えないように、おばあちゃんの存在も、大人になった自分の心の中では決して存在意義を失わない。
常ならば考えられないほどたびたび手紙をよこす妹を案じたジョゼフィーヌが動いてくれた。
姉たちと相談し、両親と共にアラスに同行させるつもりだったばあやを、急遽ノルマンディーに派遣したのだ。
道中の危険を案じなかったわけではないが、背に腹は代えられない。
マロンもまたオスカルのためならどんな状態でも、どこへでも行くと言った。
そして10月半ばにベルサイユを出発した。
ジャンやジュールが護衛を兼ねてついて行こうと言うのを、これ以上お屋敷を手薄にはできないとことわり、襲われないよう辻馬車を乗り継いでの強行軍だった。
そのため、ジョゼフィーヌはオスカルへの手紙の中では、ばあやについて一切触れなかった。
別便でクロティルドにだけ連絡しておいた。
そしてクロティルドからアンドレの耳に入った。
ジョゼフィーヌ同様、世情不安な折りから、到着の正確な日がわからない以上、対面までマロンのことは伏せておくべきだとアンドレも判断した。
高齢のマロンが、安全でない街道を来るのだ。
何が起こるか分からない。
皆が道中の安全を祈る中、いたって元気な顔で、マロンは何事もなかったかのようにやってきた。
そしてこの対面となった。
オスカルは、駆け寄ったマロンの胸に顔をうずめ、そのぬくもりに我が身を包んだ。
「あったかいね。ばあやの胸は…。あったかくて、やわらかくて…。昔のまんまだ…。」
にじむ涙がマロンの服を濡らし、マロンの涙がオスカルの金色の髪を濡らした。
時計が止まったようだった。
いやずっとずっと昔、幼い頃に戻ったというべきか。
アンドレだけでなく、オスカルにとっても、マロンは、間違いなくどんぐりだったのだ。
アンドレは黙って二人の様子をながめていた。
ストンと憑きものが落ちたのだろう。
オスカルは、もう焦らなくなった。
ばあやが来て以来、ベルサイユへ書く手紙の数は格段に減った。
そのことが、ジョゼフィーヌの判断の正しさを彼女に知らしめた。
ばあやに会えたのならば、もう安心だ。
オスカルは落ち着いた。
ジョゼフィーヌの関心は、ノルマンディーからベルサイユとパリに戻った。
もはや逐一妹に報告はしない。
している余裕もない。
マリー・アンヌもカトリーヌも、そして両親も自分も、亡命すべきかどうかで、恐ろしいほどの葛藤の中にいた。
皆、自分だけなら、貴族の義務として当然のように留まるつもりだが、子どもや使用人たちの安全を考えると、早急にベルサイユを離れるべきでは、とも思うのだ。
そういう苦悩を、懐妊中の妹に知らせる理由はどこにもなかった。
「随分大きくなられましたね。」
ばあやがオスカルの掛布をととのえながらほほえむ。
「ぼこぼこと動いて、全然落ち着かない。赤子というのは、こんなに腹の中で動くものなのか?」
「お元気なんでございましょう。もう一人前に起きる時間と寝る時間があるはずでございますよ。それにあわせてオスカルさまもお休みになるとよいのです。」
「だが、わたしの場合、四六時中動いていて、寝ている時間があるとは思えんのだ。」
それは赤子が思いっきり母親に似ているんだろう、とアンドレはおかしかった。
オスカルは、子どもの時、読書以外、じっとしていたことがなかった。
腹の中には書物などないのだから、そうなると子どもだって動くしかないはずだ。
時々、痛い!と叫んで腹部をにらみつけている姿に、少し同情するものの、おかげでオスカルの無茶な動きが封じられていることを思うと、アンドレは密かに我が子に声援を送っている。
もっともっと暴れろ。
さんざん我慢させられたんだ。
それくらい構わんぞ。
アンドレはオスカルが聞いたら烈火のごとく怒りそうなことを、にこにこしながら考えていた。
「ばあやが来て、アンドレ、おまえも嬉しそうだな。」
アンドレは時間があれば、オスカルの寝台の傍らで、領地関連の書類に目を通している。
別におばあちゃんが来たから嬉しい、というのではなく、そのおかげでオスカルが落ち着いたのが嬉しい、と言う方が近いのだが、そんなひねくれたことは言わない。
「そうか?」
目は書類に落としたままだ。
「険しい目つきをすることがなくなった。自分では気づいていないだろうが…。」
びっくりした。
それはオスカルの方だったはずだ。
ジョゼフィーヌからの手紙を見ては、眉間にしわを寄せていた。
では、そんなオスカルのそばで、自分も怖い顔をしていたのだろうか。
「そんなに…?」
「ああ。ため息もしょっちゅうついていた。」
「そう…か。悪かったな。」
「いや…。お互い様だ。気にするな。」
優しい響きだった。
「おばあちゃんには感謝している。」
「わたしもだ。」
「もうすっかりこっちの暮らしに慣れたようだしな。」
「たいしたものだ。」
「今は、モーリスのところに味付けの注文に行ってる。」
二人は顔を見合わせて笑った。
こんな風に笑うのもばあやが来てからだ。
万事オスカルさまのため、という大義名分で、マロンは雑用担当のベッケル夫婦にも料理人のダルモン夫婦にも遠慮会釈ない。
だが、ここまで高齢で、ここまで率先して動かれては、二組の夫婦も逆らいようがないらしい。
「ばあやさんから見たら、わしらはまだ小僧っ子らしいですよ。」
農作業が身体にこたえるから、という理由で屋敷勤めを選んだベッケル夫婦も次第に刺激を受けて、廷内の雑用だけでなく、最近では荒れていた庭の手入れも始めてくれている。
「そうか。マヴーフとアゼルマだけでなく、モーリスとコリンヌもやられてるのか。」
オスカルは、ベッケル夫妻とダルモン夫妻の名前をあげて笑った。
だが一瞬でこちらの暮らしに慣れたばあやに刺激を受けたのは、この四人だけではない。
実はオスカル自身が一番影響を受けたのだ。
「オスカルさま、どんぐりは落ちたところで芽を出します。どんなところでも、そこで生きていくんでございますよ。人間だって、どんぐりとなんにも変わりはいたしません。」
ばあやの言葉が耳に痛かった。
ベルサイユやパリが気にならないと言えば嘘になる。
だが、とにかく、人間は今いるところで生きていかねばならないのだ。
「ばあやにどんぐりを見習えと言われたが、まったくその通りだな。」
オスカルの言葉に、アンドレはぎょっとした。
なんでどんぐりみたいだって思ったことがばれたんだろう。
気づかぬままつぶやいたことがあったのだろうか。
これだから年寄りの耳はあなどれない。
アンドレは、今後独り言は決して言うまいと固く決心した。
そんなアンドレをオスカルが不思議そうに見ていた。
back next menu top bbs
![]()
![]()
![]()
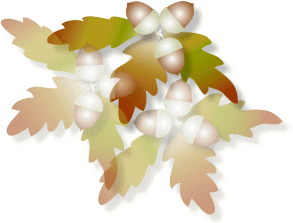
2