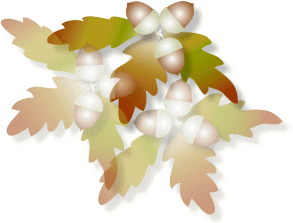
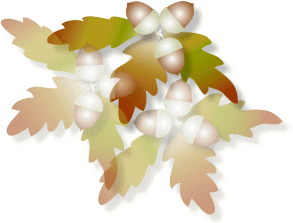
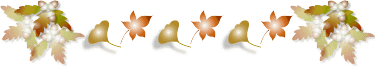
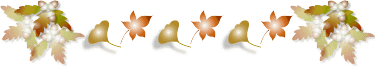
どんぐりころころ
ばあやが随分忙しそうだ。
ベッケルたちを配下に、厨房と広間を行きつ戻りつしている。
ジャルジェ邸のように広大ではないが、高齢のばあやにとって、この屋敷のなかをこれだけ動くのはなかなか大儀であろうに…。
「何か始まるのか?」
ばあやと対照的に、オスカルは寝台で座ったままである。
大きなお腹で動くのは想像以上におっくうなのだ。
あんなに動きたかった自分が、こんな風に思うようになるなんて…。
オスカルは恨めしげに腹部に視線を落とした。
「バルトリ侯爵のご一家がいらっしゃるんだ。」
アンドレの言葉にオスカルは目をむいた。
「聞いてない!」
「ついさっき書状が来た。めずらしく四人の都合がついたので、昼から行く、と。」
「なんてことだ!四人揃ってか?わたしは会わんぞ!!」
オスカルは乱暴に掛布に潜り込んでしまった。
自分の今の肢体を誰かに見られるのはまっびらだ。
アンドレ、ばあや、ベッゲル夫婦とダルモン夫婦。
この6人は仕方がない。
だが、それ以外は絶対に嫌だ。
「おまえに会いに来られるのに…。」
「知るか!」
こうなると手に負えない。
聞き分けの点でいうなら、あの過酷な環境に耐え抜いた赤子の方がはるかに良い、とアンドレは思う。
オスカルは、幼い頃から、ごく親しい人に対しては、果てしなく強情かつわがままなのだ。
アンドレは仕方なくマロンのもとへ相談に行った。
客間の中を小走りに行ったり来たりしている祖母の後ろから声をかける。
だが振り向いてももらえない。
短い歩幅の祖母に、長い歩幅のアンドレがなかなか追いつけない。
スカートに隠れて見えこそしないが、実は足が四本あるのではないだろうか。
ようやく、オスカルが、という言葉に反応して、マロンは立ち止まった。
そしてほぼ直角に首をあげて孫を見上げる。
「オスカルさまが何だって?」
「一日誰とも会わないそうだよ。」
「侯爵さまご一家がいらっしゃるのにかい?」
「だから嫌なんだって…。」
フン…と言ったきり、しばらく黙ったマロンは、くるりと向きを変えるとまたもや小走りでオスカルの部屋に向かった。
あわててアンドレが後ろに続く。
「おまえはわたしの代わりに客間のしたくをしておいで!」
一喝されてアンドレはすごすごと引き返した。
その様子をベッケルとダルモン夫婦が不思議そうに眺めていた。
バルトリ侯爵夫人の妹ぎみとそのご主人、そしてあの最近来たばかりのばあやさんの関係は、彼らにとって、最初、ちょっと理解しがたいものだった。
なんといっても妹ぎみは、失礼ながら女性には見えないし、ご夫君のはずのだんなさまには常に命令口調だし、ばあやさんは、妹ぎみには馬鹿丁寧な言葉遣いなのに、だんなさまのことは呼び捨ての上、いつも怒鳴り散らしている。
しかも、その老女を、妹ぎみは「ばあや」と呼ぶのに、だんなさまは「おばあちゃん」と呼ぶ。
ということは、だんなさまはばあやの孫、妹ぎみとは乳兄弟ということになる。
でも、二人が結婚していて夫婦だということは、あの大きなお腹を見れば一目瞭然だ。
そうか。
そういうことか。
身分違いの恋の果てに、二人はベルサイユからこんな田舎にやってきたのだ。
きっとあのお優しいバルトリの奥さまが、悲恋の妹に同情して、ベルサイユから遠く離れたこちらを世話したのだろう。
勝手にそう思った二組の夫婦は、別段の詮索をすることもなく、うわさ話をすることもなく、不思議な主人一家のためにせっせと働いた。
ご一家のなかで奥方に頭が上がらないように見えるだんなさまは、毎月はじめにきちんきちんと決まった額を支払った上、何かと心遣いをしてくれる。
ねぎらいの言葉も暖かい。
60代のベッケル夫婦も、30代のダルモン夫婦も、だからだんなさまが大好きだった。
「オスカルさま、今日はとてもお天気がよろしゅうございます。お庭に出てみられてはいかがですか?」
マロンはつかつかと寝台に近づき、掛布をまくった。
「いやだ。動くと腹が重くてつらい。」
「そろそろ動かれた方がよい時期です。もう心配はいりませんから、どんどんお散歩いたしましょう。」
「どんどん、と言われたって…。」
「運動不足は難産のもと、さあまいりましょう。」
「そうなのか?」
「そうですよ。お産は体力勝負です。よく動いて身体をきたえておきませんとね。」
「さんざん動くなと言われてきたぞ…。」
「それは安定期に入るまでのこと。もう産み月も近いのですから、どんなに動かれてもかまいません。久しぶりに外に行かれたら、きっとご気分も良くなられます。」
確信的なばあやの提言に、あえて逆らうのもおっくうで、オスカルは渋々寝台をおりた。
久しぶりの外の世界だった。
色づいた木々、地面を埋め尽くす落ち葉。
頬を撫でる風。
窓越しではない日の光。
どれもが新鮮だった。
オスカルは大きく息を吸った。
それからゆっくりとはき出す。
「なかなか気持ちのよいものでございましょう?」
マロンが目を細める。
「ああ。体中の血液が入れ替わるような感じがする。」
「これからは毎日こうしてお散歩いたしましょう。たとえいつ産気づかれても、ばあやがついておりますからね。なんにも心配ございませんよ。」
胸を張るばあやを見ていると、本当にそんな気になってくる。
もしばあやが来てくれていなかったら、初めての出産がどんなに心細いものになったことだろう。
「だんなさまも、六人のお嬢さまも、みなさまあたしが取り上げたんですから。」
これはばあやの口癖だ。
将軍が生まれた時の姿など、どんなにがんばっても想像できないが、ばあやにはかわいい赤子の将軍がすぐに思い浮かぶらしく、それが将軍の弱みでもあった。
「道中、随分危険だったのではないか?高齢のばあやに随分無茶をさせてしまったね。」
対面したときはただ嬉しくて思い及ばなかったが、冷静に考えれば、クロティルドが単身ベルサイユに出てきた以上に、ばあやの一人旅は危険だったはずだ。
「ここまで歳を取りますとね、かえって安全なんですよ。」
ばあやはしたり顔で言い切った。
「そういうものか?」
「そういうものです。」
物騒になったパリに恐れをなして、生まれ故郷に帰りたい老婆。
働きづめに働いてようやくわずかばかり蓄えた金で辻馬車を乗り継いで、ひたすら故郷に向かっている。
金目のものも持ってなければ、魅惑的な美女でもない。
襲われようがないのだ。
クロティルドの方がよほど危険だったはずだとマロンは思っている。
だが危険を冒してクロティルドが来てくれたおかげで、オスカルとアンドレはこうしてノルマンディーでの生活を始めることができた。
感謝してもしきれない思いがマロンの胸にはある。
「オスカルさま。まがりなりにもここでこのように落ち着いた暮らしができておりますのは、すべてバルトリ侯爵さまご夫妻のお力によるものです。ご想像どおり、パリも道中も殺気だっておりました。騒ぎがいつ飛び火してくるかわからない状況で、わざわざご一家でお見舞い下さる皆さまに、このようにお元気なお姿を見ていただくのが、今のオスカルさまのつとめでございますよ。」
痛いところをつかれた。
ジョゼフィーヌの手紙でも、パリの暴動は、すでに暴動の域を超え、革命として認識されてきていると書いてあった。
であるならば、フランス全土にその余波が及ぶのは当然のことだ。
このノルマンディーも例外ではない。
色づいた木々、地面を埋め尽くす落ち葉。
頬を撫でる風。
窓越しではない日の光。
これらの恩恵に預かる幸運は、すべてバルトリ侯爵夫妻によってもたらされているのだ。
「そのとおりだ。ばあやにはかなわない。姉上にも義兄上にもきちんとお会いするよ。」
オスカルは、そう言うと空を見上げた。
樫の木の隙間からこぼれる光が、まぶしい。
今はこの恵みをありがたく甘受しよう。
と、ざーっと風が吹き、バラバラと大きな音をたててどんぐりが降ってきた。
「うわあ…!これはかなわん!」
ばあやとオスカルは手を頭上にかざしてどんぐりの来襲を防いだ。
だが、どんぐりは容赦なく落ちてきて、次々と身体にあたっていく。
「恵みとはなかなか痛いものだな。」
オスカルがつぶやいたとき、昼食ができたとアンドレが知らせにきた。
すると嘘のように風がやみ、どんぐりも止まった。
落ち葉とどんぐりを踏みながら、三人は並んで屋敷に戻った。
back next menu top bbs
![]()
![]()
![]()
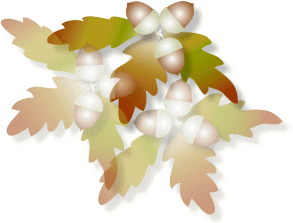
3