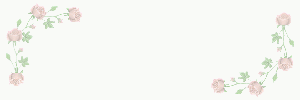この暗闇の中の通過時間は短いようにも思えるが、永遠のようにさえ感じる。
いったい、いつのどこへ行き着くのかという不安とともに、今握っている手を離してはどうなってしまうのだろうという恐怖感が時間の経過への感覚を麻痺させてしまうのかもしれない。
必死でアンドレとディアンヌの手を握り締めながら、オスカルにはなぜか今朝、見た夢の映像が浮かんでいた。
それはルイ14世寺院で行われた、若き王太子と王太子妃の結婚式の場面だった。
6千人の貴族、僧侶に取り囲まれ厳かに式典は進行していた。結婚証書にインクのしみが付いたとしても、だれがこの王太子夫妻の悲惨な運命など予測できただろうか。みな、式典に続く晩餐会のこと、異国から嫁いできた王皇子妃の噂話くらいしか頭になかった。
ただ、自分だけは14歳の自分ではなく、王家に立ちこめる暗雲に気づき、遠くから若い夫妻を重苦しい気持ちで見守っていた。
そして、次に王妃となったアントワネットが自分の前に現れた。王妃は取り巻きを一人も連れず、泣いていた。
「もし、私がハプスブルク家の皇女にさえ生まれなければ、好きな男性と結婚できていたのでしょうか?」
そう言って、王妃は顔を覆い泣き崩れてしまった。
オスカルは慰める言葉も見つからず、王妃としての立場を第一にと、諌める言葉も発することもできず、ただ自分の胸で震えるように泣く王妃の背に手を添えていることしかできなかった。
訳の分からないアランは、ただ妹の手を放したら取り返しの付かないことになると本能で感じていた。
そして、アランも今朝、見た夢をなぜか急に思い出していた。
あんなに結婚に恋焦がれていたディアンヌが、嫁ぎ先の男爵家で泣き暮らしているのだった。
時折、訪ねて、どうしてそんなに泣くのか尋ねるがディアンヌはなにも答えなかった。
男爵は結婚前とあまり変わった様子もない。
そして、自分が帰るときには、いつもディアンヌは涙も枯れ果て、憔悴しきった顔で見送ってくれた。
結婚を決めたのは間違いだったのだろうかと、アランは帰途で頭を抱えてしまっていた。
物を考えたり、思い出したりしている時間というのは長いようで、実は一瞬なのかもしれない。
「アンドレ、何か見えるか?」
暗闇の中でオスカルが聞いた。
「ああ、わずかな光が・・・」
アンドレはそう言うと、目の前に見えてきた扉の取っ手に手をかけた。
とたん、四人は暗闇から光の中に躍り出た。
そして、そのまま真っ逆さまに落っこちた。
ドスンという音ともに、4人が我に返るとそれぞれが、干草の中から顔を出した。
「どこだ!?ここは?」
アランが最初に叫んだ。
「あそこから落ちたんだ。納屋の二階に着いて、勢い余って柵を破って落ちたらしい」
アンドレが納屋の二階を見上げながら答えた。
「そうじゃなくて、どうして教会から暗闇通って農家の納屋に出てくるんだ!?」
アランは髪に絡まった干草を首を振って落としながら、声を荒げた。
オスカルはディアンヌの髪から干草を抜き取りながら、事態への対策を考えていた。
「まずは、ここがいつでどこかを怪しまれないように誰かに聞き出さねばな」
「隊長!!いつで、どこかってどういうことだ!?」
ますます興奮してくるアランの肩をアンドレが叩いた。
「とにかく、外へでよう」
4人はあたりを見渡しながら、納屋の扉を開き外へ出た。
周囲にはこれといった建物もなく、見渡す限り田園風景が広がっているだけだった。
この納屋の裏手に農家があったが、いきなり訪ねて怪しまれるよりも外で人を探すことになった。
少し離れたところに、道らしきものが見えてきたのでそこに向かって4人は歩きはじめた。
「こんな田舎に、いきなりよそ者が4人揃って歩いていたらよけいに怪しまれる」
「アラン、おまえはディアンヌとここで待て」
上官からの命令と妹を守る使命のため、アランはディアンヌと道の手前の木陰で待つことになった。
オスカルはアンドレとともに、小道までたどり着くと、通行人を待った。
季節はまだ、夏の終わりか秋くらいらしく、オスカルは思わず襟元を緩めた。
「ここは、過去か未来か?」
「さあ、俺にはただのフランスの田舎にしか見えないが」
二人が話していると、道の左右から篭を背負った娘が一人ずつ、歩いてきた。
「アンドレ、おまえはあっちから歩いてくる娘にそれとなく聞きだせ。私は反対側へ行く」
こうして、二人はそれぞれ目的の娘に向かって歩き出した。
「ああ、美しい髪のお嬢さん、実は・・・」
オスカルが話しかけた赤毛の娘は最初、驚いたような顔をしたが、次に表情が凍った。
オスカルはそれに気づいたが、話を続けてみた。
「私はパリから来たのだが、実は道に迷ってしまってね」
娘は両目を見開き、両手を握り締めていた。
『しまった、言語が分からないのか!?』
またしても、異国に迷い込んだかと思ったが、とりあえず、話を続けた。
「その荷物はあなたの細い肩には重過ぎるようだ。私に手伝わせていただけるなら光栄なのだが」
オスカルは笑顔で娘の背負っている篭に手を伸ばそうとした。
すると、とたん娘は緊張した面持ちのまま、退いた。
それと同時に、鋤を手にした大男が娘の前に立ちはだかった。
アンドレはこちらもまた、農作業を終えたばかりのブルーネットの娘に笑顔で声をかけた。
「こんにちは、お嬢さん。今日はとてもいい天気だ」
娘は眉根を寄せた。
アンドレは相手が警戒している様子は理解したが、とりあえず、話を続けた。
「実は、教えてもらいたいことがあるのだが・・・」
娘は光沢のあるアンドレの黒髪を上目遣いに眺めていたが、今度はアンドレの口元に視線を移し、真っ赤になった。
「あの、荷物が重いのでは?お手伝いさせてもらえれば嬉しいのだが」
アンドレはそっと、手を差し伸べたが、こちらの娘も飛びのいた。
すると、娘の後にその両親と思われる夫婦が走り寄ってきた。
「おまえ!うちの娘になにする気だ!?」
「おまえ!うちの娘になにする気だ!?」
両方の親が同時に叫んだ。
「ムッシュウ、私は、娘さんに道を尋ねただけだ」
オスカルは、軽くお辞儀をしてから、説明した。
「じゃあ、なんで娘が泣いている?」
オスカルは大男の後に隠れてしまった娘を覗き込んだ。
確かに、顔を赤くし目を潤ませ、なぜか日に焼けた胸元をしきりに気にしている。
その様子を見た父親はよけいに誤解をした。
「いったい、娘になにをした!?」
同じ台詞がアンドレの方からも聞こえてきた。
「とんでもない誤解です、ムッシュウ・・・」
オスカルが言いかけると、大男は持っていた鋤を振り上げた。
オスカルは、飛びのくとアンドレを振り返った。どうも、アンドレも同じような展開の中にいるらしい。娘の両親に詰め寄られて、後ずさりしていた。
「アンドレ!走るぞ!」
口で説明しても、理解してもらえそうもない農夫達を後に二人は走り出した。
「いったい、どうなっているんだ?」
「えらく戒律の厳しい村なのかもしれん」
「結婚前に男性と話してはいけないとか・・・」
二人は後を振り返った。
すると、農夫達とその娘二人が自分達を追いかけてきていた。
「父さん、あたし、あの人と結婚したい!!」
二人の娘が走りながら、親に懇願していた。
「やっぱり、何かされたんだな!任しておけ!絶対、責任をとらせてやる!!」
オスカルとアンドレは顔を見合わせた。
「とにかく、こんなところで面倒はごめんだ」
「ああ!」
二人は全速力で走った。しばらくすると、木陰でアランとディアンヌが待っているのが見えた。
「アラン!ディアンヌ!一緒に走れ!けっして、はぐれるな!」
隊長の声にアランはディアンヌの手を握り、同じ方向へ走り出した。
「いったい、何があったんだ?」
「なにもないが、娘になにかしたと誤解され逃げてるだけだ」
4人は後方を振り返ったが、自分達を追いかける農夫の数が増えていた。
「男として、今まで生きてきたが、こんなことは初めてだ」
オスカルの言葉にアンドレがつまずいた。
「大丈夫か、アンドレ!」
「・・・あ、ああ」
気を取り直して、アンドレも走り続けた。
しばらくすると、教会や集落が見えてきた。
「村だ!」
「あそこまで行けば、なんとかなるかもしれん」
4人は村に飛び込んだが、当然のことながら農夫達も自分達の村に入り、追いかけながら、事の顛末を村人達に説明していた。
外の騒がしさに台所から飛び出してきたおかみさんが、買い物途中の老婆に聞いた話を伝える。
「イレーネがよそ者にたぶらかされて、逃げられたんだってよ」
鍛冶屋のジョゼフはその話をお客のジョリに身振り手振りで説明する。
「畑から帰るマリーズがよそ者に手をだされて、そいつが逃げてるってことらしい!」
こうして、4人を追いかける人の数はますます増えてゆき、その群集の後に野良犬までが加わった。
「このまま、あのよそ者を教会へ連れて行き、娘と結婚させる!」
そして、親達はどんどん興奮し、やっきになってオスカルたちを追いかけた。
「おい、このままだと本当に結婚させられてしまうぞ!」
アランが群集を振り返りながら、心配した。
「オスカル、おまえが女だと証明したらどうだ?」
「どうやってだ?」
オスカルはアンドレを睨んだ。
「・・・止めよう!!」
アンドレとアランは顔を見合わせ、同時に叫んだ。
4人は市場にさしかかった。
果物の入った桶をひっくり返し、鶏を飛び上がらせて市場をつっきろうとしたが、オスカル達に続いて、群集も市場になだれ込んだ。
砂埃の舞う中、ディアンヌの息もきれ、走る速度も落ちてきた。
すると、遠くから聞き覚えのある太鼓の音が聞こえてきた。
軍に籍をおく3人は顔を見合わせた。
「軍隊だ!」
「とにかく、あそこまでたどり着こう!」
自分達が一番、馴染みの深い軍隊、果たしてどこの軍隊かも分からないのだが、とにかくそこを目指して、最後の力を振り絞り4人は走った。