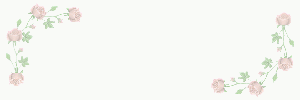三人は城門に到着した。
「マダムにお取次ぎを」
警護の兵はオスカルの胸元に輝く薔薇のブローチをみとめると、すぐさま上官の元に走った。
女官長により、オスカル達はスムースにそして丁寧な対応をもって、ポンパドゥール夫人の部屋へと案内された。
オスカルが来たことは侍従長によりルイ15世にも伝えられた。
部屋の扉が開くとポンパドゥール夫人は立ち上がって出迎えた。
「よく来てくれました」
「再び、ご尊顔を拝し・・・」
「社交辞令はよろしい。早くそばへ」
夫人は言葉を遮って、オスカルを近くへ呼んだ。
跪いたオスカルに夫人は、手袋を取って手を見せるように促した。
夫人は椅子に座りなおし、オスカルが差し出した手を自分の両手で受けた。
白く長い指を見ながら、夫人は溜め息をついた。
そして、今度は掌を上に向けさせた。
「美しい手、そして鍛錬を怠っていない手・・・」
オスカルは夫人が何を言おうとしているのか測りかねた。
「マダム、私の手は楽器を奏でることもあれば、銃や剣で・・・」
「この美しい手で男以上の働きをするとは」
夫人はひとつ溜め息をつき、オスカルの顔を覗き込んだ。
「マダム・・・」
「そなたは私以上に数奇な運命の元に生まれたようじゃ」
夫人はオスカルの手を放すと、再び手袋をつけるよう命じた。
「そなた、ここに参ったのは褒美を得るためではなかろう?」
オスカルは一歩退き、跪くと静かに話しはじめた。
「長引く戦争は国を疲弊させると存じます」
側近でもないものが、このようなことを話すのは無礼極まりないことであったが、夫人はそれを許した。
「それは、私も常々、考えていることです。早く戦争を終わらせ、オーストリアとの関係をもっと強固なものにしなければ」
「はい」
「オスカル・フランソワ、いいですか。マリア・テレジアの末娘を我が国の王太子妃として迎えようと思うのです」
「それは・・・」
とたんに曇ったオスカルの表情を見て、夫人は訝しがった。
「そなたまで、ザクセンの姫君の方がよいと言うのですか?」
「いえ。そうではありません。ただ、オーストリアの末の皇女は一国の王妃としての資質に欠いております」
夫人の表情はますます、険しいものとなった。
「何を言うのです。まだ、ほんの子供ではありませんか。それにあの女帝マリア・テレジアの末娘ですよ」
「末娘だからこそ、マリア・テレジア殿は甘やかして育ててしまわれることでしょう」
そう言うとオスカルは夫人を見上げた。
もし、あの方がこの国に嫁いでさえこなければ、きっとまた別の幸せな人生を送られるに違いない。
不可能なことかもしれないが、もしそれができるなら・・・。
オスカルは扉に迷い込む前の日にみた王太子夫妻の結婚式の夢を思い出していた。
一方、婦人は冷静だと思っていた人間から発せられた、必死な訴えに首を傾げた。
見つめ合う二人の後に控えていたアンドレはオスカルに歩み寄り、そっと肩に手をかけた。
「オスカル、どんなにあがいても歴史は変えられない」
アンドレの静かな声に促されるようにオスカルは立ち上がった。
「マダム、失礼をお許し下さい」
夫人には理解できなかった。
権威ある者の傍に呼ばれたにも関わらず、その寵愛を得ようとするのではなく、政策に反論するなど、せっかくのチャンスを自ら捨てるも同然であった。
「オスカル・フランソワ、いったい何が望みです?」
「フランスの平和と栄光だけでございます」
その言葉がいっそう、夫人を不安にさせた。
自分の見込みどおりであれば、今、自分の目の前にいる人間は類希なる軍人としての資質に恵まれ、必ずや我が軍を勝利に導いてくれる存在だった。
それが、自分に反論し、フランスの平和と栄光だけを望むと言う。
それではまるで、この先、フランスの平和とブルボン王朝の栄光が脅かされる時がくるとでも暗示しているようではないか。
夫人はしばし、寡黙になった。
その時、ノックの音もなく続き部屋の扉が開いた。
夫人は扉の方に向き直ると、すぐさま膝を折った。
入ってきたのは若き日のルイ15世であった。
「そなたがオスカル・フランソワか?」
「お目にかかれて光栄でございます」
オスカルは再び、跪いた。
「ジャルジェを名乗っているようだが、レニエ・ド・ジャルジェの親戚の者か?」
「はい。遠縁の者にございます」
「そうか。レニエはついに六女を跡取りと決め、男として育て始めたと申しておる。そなたのような跡取りに恵まれたなら、どんなに喜んだことであろう」
オスカルは無言で目を伏せた。
国王は寵妃をちらりと見て、言葉を続けた。
「そうであった。そなたに褒美を取らせよう。なんなりと申してみよ」
「馬を三頭、頂戴いたしたく存じます。そして、きらびやかな軍服を私にしつらえて下さいませ」
突拍子もない申し出に王は微笑んだ。
「そして、どうする?」
「戦闘の朝、敵陣を一騎駆けいたします」
「なんのためにだ?」
王は明らかに嘲笑していた。
「敵は数において勝っております。勝算を踏んで、油断しているところを驚かせてやりたいのです」
王は声をあげて、笑い始めた。
「よかろう。好きな馬を三頭、厩舎より選ぶがよい。そして、仕立て屋を兵舎に遣わそう」
夫人もオスカルの真意を測りかねていたが、ノックの音で我に返った。
入ってきたのは、若き日のブイエ将軍だった。
ブイエは王に耳打ちした。
「敵の伝令が参りましてございます」
王はオスカル達をちらりと見たが、ここで内容を話すよう命じた。
「戦闘は三日後、平和ヶ原でと申しております」
「して、勝算は?」
「もちろんございます。ですが、2万の兵を失うこととなりましょう」
「ふむ、いたしかたあるまい。承知したと伝えよ!」
ブイエ将軍が出て行くと王は、オスカルを振り返った。
「聞いたとおりだ。レニエだけが、戦闘を先延ばしにして野営の続く敵軍の疲弊を待てと言っているが、あまり得策とも思えん。仕立て屋には急ぐよう伝えよう」
王は、飾り時計に目をやると、夫人の腰に手を添え晩餐へと退室していった。
オスカル達は王の厩舎で、選りすぐりの馬を三頭貰い受けると、それに跨って兵舎へと急いだ。
そして、その夜から丸二日をかけて、オスカルの軍服が仕立て上げられた。
採寸の必要はなく、サイズもオスカルの好みのスタイルもすべてアンドレが把握していた。
そして、ディアンヌが人手不足の仕立て屋を手伝い、将軍顔負けの遠目にも目立つ、きらびやかな軍服が仕上がった。