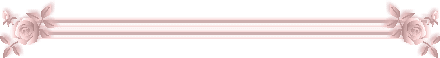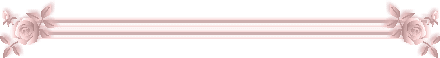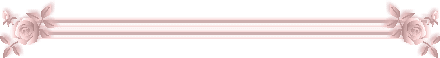
ジョゼフィーヌが卓上の呼び鈴を振ると、すぐに扉が開き、控えの間から侍女のエヴリー
ヌが華奢な姿を現した。
「何かご用でございますか?」
という声は、今鳴らした鈴にも負けない愛らしさだ。
それを見ると、ばあやの眼力も大したものだ、とジョゼフィーヌは感嘆せざるを得ない。
今日は、貴族の暮らしでは珍しく、実家の母が突然午前中から訪ねてきたため、応対に
大わらわだった。
しかも、用件が用件だった。
エヴリーヌをすぐ婚約させてほしい、とは…。
尋常なことではなかったのだが、おっとりとした母がおっとりと理由を語ってくれるので、
事態の異常さの割りに、自分もおっとりと受け答えしていたと思う。
だが、冷静に考えれば、どうもおっとりしている場合ではない。
当然のことだが、婚約というのは一人ではできないから、相手が要る。
「どうするのですか?」
と聞くと、母は
「とりあえずマリー・アンヌとカトリーヌに手紙を書きました。適当な相手を探すように、
と。まもなく返事がこちらに届きます。その中から、あなたが、あの侍女に、エヴリーヌ
でしたか。そのエヴリーヌに一番ふさわしいと思う人を選んでやってちょうだい」
と、おっとりとした口調とは対照的なすばやい行動を披露した。
「わたくしがエヴリーヌの結婚相手を決めるのですか?」
突然の話にジョゼフィーヌの声も高くなった。
だが、母の声は冷静だ。
「ええ。何も不思議はないでしょう。わたくしもうちの侍女たちの相手をみんな選んでき
ましたよ。オルガのように手放せない子は、ちゃんと使用人の中から選んで、屋敷内に住
まわせて…」
それはそうだが、まさかオルガだって、こんなとばっちりのような理由で結婚したわけで
はないだろう、とジョゼフィーヌは思う。
だが、母には通じない気がして、反論しなかった。
午後には二人の姉から手紙が届いた。
エヴリーヌの相手として、マリー・アンヌからは、執事の息子、カトリーヌからは出入りの宝石商の息子、というものだった。
母とも相談の上、ジョゼフィーヌはマリー・アンヌ宅の執事の息子を選んだ。
この執事は母も自分も面識があって、実直で信頼できる人物だと知っていたし、その息子
なら当然父の跡を継いでいずれは執事になるはずだから、エヴリーヌにとっても悪い話で
はない、と思ったからである。
宝石商のほうは、きらびやかな商売がエヴリーヌの気性にあわない、と判断したためでもある。
こうして、エヴリーヌの縁談は本人のまったくあずかり知らぬところで話が進み、ジャル
ジェ夫人はすぐにマリー・アンヌとカトリーヌに決定を知らせる二通目の手紙を書いた。
そして、午後のお茶を堪能し、煎れてくれたエヴリーヌに
「大変美味しかったわ。いつでもお嫁に行けるわね」
とにっこり微笑むと、ジョゼフィーヌにむかって
「あとは、マリー・アンヌと相談して、適当にやってちょうだい。わかっているとは思う
けれど、この件が片づくまで、我が家へ来てはだめよ。ばあやに会うわけにはいかないの
ですからね」
と、言い渡して、帰っていった。
一陣の風のような訪問だった。
そして、今し方、マリー・アンヌからの返事が届けられた。
−諸般の事情に鑑みて、迅速にことを運ぶ必要があるため、何でもいいから理由をつくって、明日、エヴリーヌを当家に使いによこすように。あとはこちらでなんとかする。−
と、さすがに日頃は美しい姉の字も少し急いだ風が感じられた。
理由ねえ、とため息が出た。
ほんの今朝まで、エヴリーヌを手放すことなど考えもしなかったのだ。
半年前に奉公に来たエヴリーヌの、愛くるしい笑顔と素直な性質が気に入り、自分付きの
侍女にしてからというもの、何くれとなく目をかけてかわいがった。
当然実家を訪れるときも供をさせた。
それが仇になって、むざむざやめさせるようにこのわたくしが計らうなんて…。
ジョゼフイーヌは、あまりに突然のことで怒ることすら忘れていた自分にようやく気づい
た。
おかあさまのお話はわかる。
ばあやがエヴリーヌをアンドレの嫁にと言い出したので、あきらめさせるために、あの娘
には決まった人がいる、と告げた。
嘘とばれないようにするためには、エヴリーヌに本当に婚約してもらうしかない。
母がばあやのために、というから了承した。
だが、よくよく考えれば、実はオスカルのためではないか。
自分も一枚かんだオスカルの結婚、これを公にできないがために、ひきおこされた事態だ。
今朝からのもやもやとした気分をはらす怒りの持って行きどころがやっと決まった。
やはりオスカルなのだ。
まったくあの子と来たら、わたくしの大切なものをよくも簡単に奪っていってくれて…!
オスカル、この借りは大きいことよ、覚えてらっしゃいと、ジョゼフィーヌは久しぶりに
オスカルに敵意をむき出しにした。
目の前のエヴリーヌがそんな女主人の様子に少しおびえた顔を見せた。
「ああ、ごめんなさい。ちょっと考え事をしていたの。実はね、突然だけれど、明日、あ
なたに使いにいってほしいのよ。マリー・アンヌお姉さまのところまで」
と、用件を切り出した。
お使いにいくことは、たびたびあることではないが、なかったことでもないので、エヴリ
ーヌはなんの疑いもなく、ジョゼフィーヌの言うことを聞いている。
「かしこまりました」
と無垢な顔で言われて、なんでわたくしが罪悪感を感じないといけないのよ、とさらに怒
りが増長した。
が、自分の役目はこれで終わった。
あとはマリー姉がなんとかなさるだろう。
これ以上オスカルのために動くのはごめんだわ。
被害はわたくしが一番被ったのだから…。
と思いつつ、エヴリーヌに
「頼みましたよ。お姉さまのところに伺うのだからそれなりの格好をしていかないとね。
一緒に衣装を選びましょう」
と、言った。
そして他の侍女も呼び集め、恐縮するエヴリーヌにあれこれと美しいドレスを着せてみた。
一番の被害者はわたくしではなく、エヴリーヌだったわ、と思い至ったためである。
マリー姉のことだから、決して悪い相手を紹介したりはしないはず、と信じつつ、ジョゼフィーヌは、何も知らずに見合いに出かけるエヴリーヌの魅力を最大限に引き立てるドレスを真剣に選んた。
つづく