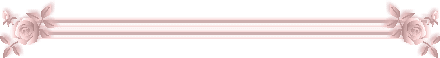
ジャルジェ家の長女マリー・アンヌは名門の公爵家に15歳で嫁ぎ、以来43歳の今日まで、一点の隙もない堂々たる公爵夫人としてのふるまいに努めてきた。
結婚当時は夫の両親が健在だったから、夫は子爵であり、彼女も子爵夫人だったわけだが、母と違って、すぐに男子に恵まれたことと、実家が有力な伯爵家であったことで、婚家での地位は程なく盤石のものとなり、義父母亡き後は、揺るぎなき公爵夫人としてベルサイユでも名を馳せた。
寵臣のジャルジェ准将の実姉として、また先祖が王家とわかれた名門家の夫人として、国王夫妻の覚えもめでたく、かといって、人を見下げるふるまいがなかったため、貴族の中でひがみを受けることもなく、いわば、順風満帆の来し方だった。
そんな彼女の唯一の気がかりが、実家ジャルジェ伯爵家のことだった。
自分が産まれたときは、まさかこのあと5人も女子が続くとは想像だにしなかった父と祖父が、ベルサイユ一の婿を見つけて嫁がせてやろうと、まだゆりかごにいる間に、相手選びをはじめて、早々に婚約者を決めてくれた。
したがって、受けた教育は当然ベルサイユの宮廷社会で権門の夫人として身につけておくべき、ダンスや音楽、立ち居振る舞いであったし、続いて産まれた妹たちも、同じような境遇だったと記憶している。
堅物の父と違い、先代当主の祖父はなかなかの洒落もので、政治的にも有能な男であり、ヨーロッパにおけるハプスブルグ家のごとく、ベルサイユにおいて、婚姻によって地位を固めていくことに長けていた。
彼は次々に産まれる孫娘を喜び、嬉々として嫁ぎ先を決めた。
そして四女の結婚相手を決めた後、孫息子に会えぬまま死ぬことは返す返す残念だと言いながら、亡くなった。
その後、五女が生まれ、六女の誕生にいたって、日頃堅物な人ほど切れると想像外、常識外の行動を起こすという世の常の典型のように、父が末妹を男として育てることを決めた。
女であることを隠して男として育てるのではなく、女であることを公表しつつ男として育てる、という前代未聞の決心を、おそらく父は勢いだけで決めたのだ。
10歳だったマリー・アンヌは祖父似の政治的才能を持ち、早熟であったため、充分にことの異常性を理解できた。
しかし、いかに聡明でも父に進言できるほどの年齢ではなかった。
祖父母も亡く、母が男子を産まなかった負い目から父に異議を申し立てられない以上、この父の暴走を誰も止められるものではなかった。
そこで彼女は幼いながら、決意したのだ。
それは、祖父の決めてくれた権門に嫁ぎ、自身の地位を高め、いずれ女ながらに軍隊で生きねばならない末妹を、背後から全面的に守る、という実にけなげなものだった。
そして彼女はその通りにした。
母が、そういう自分にどれほど感謝し、またそういう自分をどれほど頼りにしているかは、痛いほど伝わってきた。
父が勝手にオスカルの縁談を進めたときも、やはり異常な手法だと嘆息しつつ、結婚させることを考え始めただけ進歩だ、と、陰ながら協力もしたのだ。
だが、婚約者公募舞踏会はあの結果だった。
そして馬車襲撃事件が起きた。
人の心の機微を熟知しているマリー・アンヌは、末妹の本心を本人より先に察した。
母からの手紙を受け取ったのは同時期だった。
母も同じことを察し、家のために自身を犠牲にしたきた末娘の恋をかなえてやりたい、との同じ願いが綴られていた。
結果が、自分たち姉妹で密かに『ノエルのはかりごと』と名付けた一連のできごとだった。
いずれ、時が来たら公に、と思いつつ『ノエルのはかりごと』は、門外不出の秘密として厳に隠し通してきたわけだが、このたび、ばあやによって足下からすくわれかかるとは、思いも寄らなかった。
とにかく、誰も傷つかないようにうまく収めなければならない。
ジョゼフイーヌは、随分あの侍女をかわいがっていたから、つらいものがあるだろうが、
そんなことは取るに足りない。
何と言っても尊重しなければならないのは、当の侍女の幸福である。
母の手紙を前に思案にくれるマリー・アンヌの前に、執事のヴェリが息子のジェラールを伴って現れた。
すでに25歳になった息子をそろそろ一般の使用人から執事見習いに、という依頼のためだった。
神様、ありがとうございます!とマリー・アンヌは心の中で十字を切った。
マリー・アンヌは、鷹揚に微笑むと、
「もうこんなに立派に成長したのですものね。ヴェリの願いはもっともです。ジェラール、しっかり見習いにつとめなさい」
と告げた。
ヴェリとジェラールは目を見合わせて顔をほころばせ、声をそろえて、
「ありがとうございます」
と頭を下げた。
「ところで、ジェラール。ちょうどよい機会です。結婚する気はありませんか?もう心に決めた女性はいますか?」
と、尋ねた。
突然の話にヴェリは驚いて息子の顔を見つめ、
「私はなにも聞いていないが、おまえ、そんな相手がいるのか?」
と詰問した。
ヴェリ以上に驚いていたジェラールは
「と、とんでもない。父さんも知っているとおり、僕は屋敷の仕事に忙しくて、とてもそんな時間は…」
と、どもりどもり、答えた。
「実はね、妹のジョゼフィーヌのもとにとてもきれいな侍女がいてね…」
と、マリー・アンヌははやる心をおさえて、あくまで優雅な貴婦人を装いながら、狙った獲物は逃すまい、という狩猟者の心持ちで、ヴェリとジェラールに縁談を進めた。
執事と息子は、せっかくすんなりと執事見習いへの昇格を認めたくれた女主人の機嫌をそこなうまい、と二つ返事でくだんの侍女と会ってみることを了承した。
執事自身、妻との結婚は先代夫人の紹介だったから、よほど相性が悪くなければ、異論はない。
まして女主人の妹の侍女ならば、万事心得ていて、話も早い。
わざわざ断る理由はなかった。
マリー・アンヌとジョゼフイーヌの屋敷はそれほど離れてはいないので、すぐに妹に手紙を出し、翌日その侍女をつかいに寄越すよう指示し、委細承知との返事が妹から届いた。
そして、今日、いくつかの宝飾品を自分に届けに来たジョゼフィーヌの侍女は、好感の持てる恥じらいと、役目をきちんと果たそうとする誠意を兼ね備え、ジョゼフィーヌが親心を発揮したのであろう仕立ての良いドレスを着て、すらすらと口上を述べた。
「エヴリーヌと申します。主人より、こちらの品々を公爵夫人に直接お渡しするよう申し使ってまいりました。中身に間違いがございませんことをご確認頂きますよう、お願い申し上げます」
「承知しました。高価なものなので、信頼できる人にことづけてほしいとお願いしたのよ。あなたはジョゼフィーヌに随分気に入られているようね」
と、座ったまま、渡された箱のリボンを解き、ふたを開けると、マリー・アンヌは、
「確かに、お願いしていたものです。どうもありがとう。あちらの部屋にお茶を用意させました。少し休んで、それからお帰りなさい」
と言った。
思わぬ厚遇に恐縮しつつ、エヴリーヌは謝礼を述べ、執事に連れられて別室へ退いた。
別室ではジェラールが待っており、お茶のあとには庭など案内するよう段取りをしていた。
しばらくして、エヴリーヌを乗せた馬車が出て行く音がした。
マリー・アンヌは窓に近づき、車寄せを見下ろした。
車寄せのひさしの下から、少し小走りに馬車のあとをかけていく若い男と、窓越しにかわいい顔を出して、一生懸命手を振る車内の娘の姿を確認し、マリー・アンヌは呼び鈴を振って、執事を呼んだ。
未来の息子の嫁に大層満足げな彼の表情にマリー・アンヌは安心し、
「ヴェリ、ジェラールはこれから忙しくなりますね」
と、声をかけた。
「まったくもって」
と慇懃にこたえる執事に
「けれどもとても幸せな忙しさよ。若い二人が気持ちを確かめ合うには、少し時間もいるでしょうけれど、あたたかく見守ってやりましょう」
と、話す女主人が、わがことのように、息子の縁談を世話し、その良好な進展を喜んでくれたことを、執事は心から感謝した。
まあ、時には、気持ちを確かめ合うのに、20年以上かかる人もいるのですけれどね、とマリー・アンヌがつぶやいた声は、執事には当然聞こえなかった。
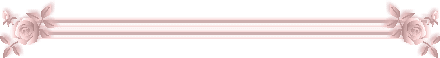
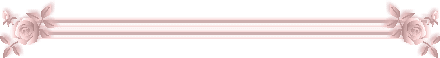
−おわり−