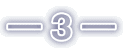アンドレ渾身の台本を熟読すること1週間、フランソワ・アルマンはディアンヌとともにタンプル塔に入った。
ディアンヌと二人きりの仕事をするにあたっての彼の精神は、アンドレの想像通り、悲喜混在するものだった。
与えられた台本を頭にたたきこみ、疲れて顔を上げるとディアンヌがいる。
そしてにっこりと笑ってくれる。
ほかの誰でもない、自分にだけ向けられた笑顔。
天国である。
また二人して会話の練習も再々おこなった。
夫婦なのだから、遠慮せずにものを言わなければならない。
ちょっとえらそうに言うぐらいがいいのでは?とディアンヌが提案してくれたりすると、もう心は躍り上がって、鼓動がバクバクと音を立てる。
けれど当たり前だが、抱擁はおろか手を重ねることすらできない。
ましてアランが練習の進み具合を見に来たりすると、そのにらみつけるかのような視線に震え上がり、せっかく築いてきたディアンヌとの関係が凍り付くような感じすらした。
だが、フランソワは、オスカルからのこの依頼を断ろうなどとは夢にも思わなかった。
恩人であるオスカルの頼みなのだ。
しかも自分を指名しての、かなり難しい任務だ。
誇らしいとこそ思え、拒否するなど考えられなかった。
タンプル塔は王家を幽閉している場所だと聞いて、以前に放り込まれたアベイ牢獄を想像し、ディアンヌが暮らせるのだろうかと案じていたのだが、こちらはさすがに元は王族の館として使われたというだけあって、極悪な環境ということはなかった。
むしろ国王の処刑までは王室一家がかなり優遇された暮らしをしていたことも、監視委員から聞いた。
ヴァレンヌから戻った王家を収容するため、わざわざ壁紙を貼り替え、食器を差し替え、入浴設備さえ整えられたとのことだった。
実際、王妃は処刑された国王のために喪服を調達するよう国民公会に要求し、パリの仕立屋に注文が出されたほどである。
フランソワとディアンヌは国民公会の委員に先導されて塔内の階段をおそるおそる上がっていった。
ルイ・シャルルはタンプル塔の三階の一室で、ぼんやりと座っていた。
もう母や姉とは会えないことがようやく理解できて、でも納得できなくて、そういう複雑な感情をもてあましている様子だった。
監視委員は囚われの少年に機械的に世話役になった二人を紹介するとすぐに部屋を出て行った。
監視委員の足音が遠ざかるのを確認し、ディアンヌはすぐにルイ・シャルルに駆け寄った。
そして小さな声でささやいた。
「シャルルさま、私たちはルイ・ジョゼフさまのお友達です。ルイ・ジョゼフさまのこと、わかりますか?ブリエ男爵です」
ルイ・シャルルは少し考えて、それからこっくりとうなずいた。
ディアンヌはホッとして、優しくほほえんだ。
「お手紙を預かっています。いつもやりとりなさってたんですよね?」
小さい子どもとの会話を途切れさせないためには、小刻みに質問を入れて、回答できるようにしてやる必要がある。
そうやって会話に引き込み、理解度を確認して次に話を進めるのだ。
ルイ・シャルルはまた小さくうなずいた。
「読んでみますか?」
白い封筒を荷物の中から取りだして、ルイ・シャルルに見せた。
小さい手がそっと差し出された。
封はされてない。
すぐに便せんを出して読み始めた。
「この二人はぼくの友達だ。だから言うことをよく聞いて。そうすれば会えるようになるから」
短く簡単な文面は、ルイ・ジョゼフがさんざん考えて中身をしぼったものだ。
ルイ・シャルルは、塔内で家族と暮らしていたとき、ずいぶん父母から読書を進められていたので、この年齢にしてはかなり読解力があるのだが、ルイ・ジョゼフにはまだその情報が届いていない。
だからとりあえず簡潔に要件だけをまとめておいた。
「また会えるようになるの?」
ルイ・シャルルのつぶらな瞳がほんの少し光を宿した。
「ええ、きっと。だからわたしの言うことをしっかり聞いてくださいね」
少年は今までより少し力をこめてうなずいた。
「ジョゼフは今どこにいるの?」
いつのまにかルイ・シャルルが質問する側に回った。
少し心を開いてくれたのかもしれない。
ディアンヌはさらに声を落としてささやいた。
「オスカルさまのところです。オスカル・フランソワ。知っていますか?お母さまのおそばにいた軍人です」
もう何年も会っていないオスカルのことをルイ・シャルルが覚えているかどうか。
やはり首をかしげている。
「お姉さまなら知っているんだろうけど…」
「いいんですよ。覚えていなくて…。でもみんなルイ・ジョゼフさまのお友達です。だから心配しないで」
ディアンヌは明るくふるまう。
「いつルイ・ジョゼフに会える?」
「そうですね。あなたの努力次第です」
本当は目処などたっていない。
けれど、希望がなければ人は前に進めない。
まして8歳の子どもだ。
この努力のさきにこんな素敵なことがあると示してやらなければ,今の状況につぶされてしまう。
ディアンヌはアンドレが特に強調して書いていた「常に明るく前向きに」という心構えをしっかりと実践した。
フランソワとディアンヌの仕事はきっちりと分担が決まっていた。
外遊びはフランソワ、室内での学習はディアンヌ。
監禁状態であまり体を動かせなかった今までと違い、フランソワがついているという条件で、タンプル塔の庭に出ることが許可された。
フランソワは毎日シャルルを外に連れ出した。
そこでシャルルは塔内で働く多くの人と接触することになった。
もちろん平民ばかりだ。
彼らは、ルイ・シャルルを見ても全然遠慮しないし、恭しくお辞儀をしたりもしてくれない。
フランソワに話しかけるのと同じように話してくる。
天気のこと、家族のこと、食べたもの、着ている服。
何でも話題になる。
そして、その会話はルイ・シャルルが今まで両親や親族、あるいは臣下たちと交わしていたものとはずいぶん違うものだった。
だがそれが新鮮だったのだろう。
ルイ・シャルルはすぐにそういう言葉を習得し、自分からできるようになった。
さらにフランソワはよく歌を歌った。
「ラ・マルセイエーズ」である。
このあまりにも有名な革命歌は、子どもが歌うにはずいぶん過激な歌詞であり、まして王太子であるはずの、というか父亡き後亡命貴族からは国王ルイ17世と認知されているルイ・シャルルが歌うには、あまりに不似合いな内容ではあるが、これを歌うことで、フランソワの世話係としての役割が間違いなく遂行されていることを革命政府に正しく伝える手段なのであった。
だからフランソワは特に熱心にこの歌をルイ・シャルルに教え込んだ。
かわいいこの歌声が、おそらく四階で暮らすルイ・シャルルの母や姉の耳に届いていることは想像できた。
だが意味も知らず歌っているものとして、元気でいることのみ感じ取ってもらえれば、と願うしかなかった。
だが気の毒な母は、まもなく裁判のためコンシェルジュリー牢獄に移送され、息子の歌声を聞くこともできなくなった。
タンプル塔には、四階にマリー・テレーズとルイ16世の妹エリザベート、そして三階にルイ・シャルルとシモン夫妻が残された。
1793年8月のことである。
HOME MENU NEXT BACK BBS