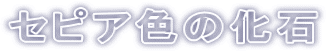ルイ・ジョゼフがタンプル塔に入った翌日、アントワーヌ・シモン、すなわちフランソワ・アルマンが、革命委員会に対し、ルイ・シャルルの体調不良を報告した。
食欲不振で寝台から起き上がれない状態だが丁重な看護をするべきか否か、との問い合わせに、委員会は「放置」を指示してきた。
そしてそれから3日後、食欲が落ちているようであれば、朝昼晩と三食与える必要はない、ただ生存確認だはするように、との文書が届いた。
非情なものである。
国王夫妻がいた頃と違い、マリー・テレーズとルイ・シャルルという子どもだけとなったタンプル塔に配属される衛兵の数は減員され、監視の目もかなり緩やかになっていた。
シモンの妻が、アラン・ド・ソワソンという革命軍の将校であることも、監視体制の弱体化を後押しして、それがオスカルが今回のルイ・ジョゼフの計画にゴーサインを出す理由にもなった。
フランソワ・アルマンは委細承知した旨を返信しつつ、実際には今までルイ・シャルルに接していたのと同じように心をこめてルイ・ジョゼフに接した。
無論、病気という触れ込みだから、ルイ・ジョゼフは終日寝台で過ごしている。
万一にも、革命委員会から直接ルイ・シャルルの様子を見に来る場合に備える必要があった。
いかに監視体制が緩んだとはいえ、誰も来ないとは言い切れない。
委員が来た時、眠っているといえば、起こしてこいとは言われないだろうし、わざわざ室内に立ち入ったとしても、シーツをめくることはあるまい。
身長も体重もすべてはシーツの下に隠すのだ。
寝顔だけならごまかせる。
実際、フランソワは、このとき初めてルイ・ジョゼフ・ド・ブリエに会ったのだが、面立ちや様子がルイ・シャルルとよく似ているため、違和感なく接することができた。
むしろ何もわからない幼子のようなルイ・シャルルと違い、実際には7歳も年長のルイ・ジョゼフは、物事をよくわきまえており、非常に接しやすかった。
なにしろこの「フランソワがシモン親方」という計画自体が、オスカルとルイ・ジョゼフの発案であるから、もはやフランソワが全責任を負っていたルイ・シャルルの教育係という役職ををようやく解任されたわけで、フランソワの態度からは大きな安堵が感じ取れた。
「病人ですからね、ただただ寝ていますよ」
自分の脚本にようやく登場できた役者のように、ルイ・ジョゼフ・ド・ブリエの演技は完璧だった。
また彼は非常に心優しくて、ディアンヌに対しても、そのスマートさに、フランソワがヤキモチをやくほど完全な淑女として応対した。
「無理難題をお願いしたのに、こんなに見事にやりとげてくれて、本当にありがとう。感謝してもしきれません」
高貴な生まれだということは、一目瞭然にもかかわらず、物腰はいたって丁寧で、靴屋夫婦を見下す素振りはみじんもなかった。
ディアンヌは世話係というよりは、話し相手として側にいるだけでよくなり、こちらも大任を果たし、肩の荷が下りる思いでいた。
こうしてルイ・ジョゼフ・ド・ブリエは、まんまとルイ・シャルルになりかわった。
ただし、明らかに外見が違うのであるから、そこは慎重に振る舞い、これまでのようにフランソワが庭に連れて出ることはなく、また大きな声で歌を歌わせることもなかった。
病気であるのだから、当然と言えば当然のことで、誰も怪しんだりはしない。
監視衛兵は、革命委員会の指示通り、毎日一回確認に来るだけだ。
寝台に横たわっているのを扉から入りもせず、遠目に見て、すぐに引き上げていく。
無駄な仕事をさせられているという不満感がありありとしていて、好都合だ。
露見する可能性は極めて低い。
革命委員会の指導者であるロベスピエールは1794年3月にエベール一派を粛清して、共和制樹立に邁進しており、ルイ・シャルルに対して、もはやなんの興味も持ってはいなかった。
年端のいかぬ元王子の存在など取るに足りず、恐れる必要もなかった。
有り体に言えば、生きていようが死んでいようがどちらでも良かったのである。
ひどい扱いであることは、かえって幸いで、徹底的な隔離も願ったりかなったりだった。
そのうち、ルイ・シャルルの状態はいよいよ悪いとの報告が委員会に上げられた。
1794年の春先のことである。
これは、ル監視を弛めさせるためのイ・ジョゼフの計画だった。
報告を受けてなされた革命委員会の決定は、ルイ・ジョゼフの予想をこえたさらに非情なものだった。
つまり、ルイ・シャルルの完全隔離である。
独房のような部屋に移し、1日1回食事を届ける折りに生存確認のみ、小さな窓越しに名前を呼んで行い、もし死んでいたらすぐに知らせよ。
人間の尊厳を謳った革命の精神は、ここでは完璧に忘れ去られていた。
それを幸いとオスカルたちが感じ取れたのは、しかし、ここまでだった。
誤算が生じた。
シモン夫妻が解任されたのだ。
もう世話係としてそばに使えることができなくなった。
あのようなところに、ルイ・ジョゼフをひとりで置いておくのか。
本当に病気になってしまう。
ただでさえ、虚弱体質なのだ。
オスカルは度を失った。
「こんちくしょう!!」
蹴り上げた椅子が床に転がった。
「自由、平等、博愛はどこに行ったのだ?!」
そんな日々がロベスピエールの失脚まで続いた。