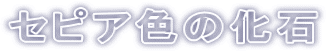マリー・テレーズはひとりだった。
タンプル塔に来た当初は家族が皆一緒で、狭い場所に移された分、人間同士の距離が近く寂しさはなかった。
だが、やがて父がいなくなり、弟が連れて行かれ、母と叔母も消えた。
ベルサイユ宮殿が豪華だった記憶は十分にあり、テュイルリー宮殿を汚いところと感じたことも覚えている。
けれど、彼女にとってそれらはもう二度と戻ることのない場所だ。
今は、革命前まで従兄弟であるアングレーム公の持ち物だった修道院が住まいである。
顔を覚えた頃に交替する世話係たちは、何も教えてはくれない。
もちろん父が処刑されたことは知っている。
母や弟たちと泣きながら別れの挨拶をしたのだから。
けれど母や叔母はどこでどうしているのか。
生きているのか死んでいるのか。
弟は時々歌っているのが聞こえた。
生きているのだと、それで確認できた。
だが唯一楽しみにしていたそれも、最近聞こえなくなった。
ラ・マルセイエーズだなんて、王太子の、いや、もう国王だった…
そう、国王の歌うものではないが、元気な声が聞こえるなら、たとえ貴族を縛り首に…という歌詞でも、彼女は耐えようと思っていた。
聞くたびに愛憎いりまじった涙がとめどなく流れるとしても…。
弟の声が聞こえなくなって一週間がたった。
病気だろうか。
それともどこかに連れて行かれたのだろうか。
彼女は、意を決して食事を持って来たものに尋ねた。
そして予想通り「知らない」との答しか得られなかった。
いつもの彼女ならここで引き下がる。
というか、彼女自身が革命側のものと会話をすることを拒否していた。
たとえ尋問の場にあっても必要最小限の言葉しか与えないか、もしくは全く答えなかった。
しかしこの日は違った。
「誰かわかる人を寄越してほしい」
彼女は強く要求した。
かつてないことだ。
監視員兼世話係は驚いて引き下がった。
そして、いつもなら「かわりなし」と報告するところを、「質問あり。回答できるものを派遣するよう求められる」と書いて上層部にあげた。
その翌日、国民公会から面接官がやってきた。
数ある委員会のうちのいずれかの委員らしいが、今までに見た顔ではなかった。
母の裁判をするからといって、何度か国民公会から議員が来たが、そのうちの誰でもないようだった。
黒髪の40歳前後の男は、「ベルナール・シャトレ」と名のった。
「弟になにかあったのですか?」
単刀直入に尋ねた。
「なぜそんなことを聞くのです?」
「いつも歌声が聞こえていました。しかし最近はまったくありません」
「さすが姉弟ですな」
「病気か移送されたか、いずれかだと思います。どうですか?」
「病気です」
「…!」
「相当重病のようです」
「医師は?見立てはどうなのです?」
元王女というのはなかなか大したものだ。
ベルナールは感心した。
人にものを尋ねて答えを促すのに、努力というものをしない。
相手は答えて当然だと思っているらしい。
これが王女か。
「個人的には、すぐにも医者を派遣すべきだと思っています。事実その手続きをしています。だが、どんな医師でもいいというわけにはいかんのです。なんといってもただの少年ではありませんから」
「なるほど、そういうことですか」
マリー・テレーズはなかなか聡明らしい。
ベルナールの意図するところをすぐに察した。
「では、わたしが見舞いに行ってやることはできませんか?」
外部から呼んだ医師が裏切って、逃亡を幇助する可能性を国民公会が懸念しているのなら、同じ内部に幽閉されているまだ年若い姉が見舞いに行くことに心配はあるまい。
マリー・テレーズがこの幽閉生活の中で、誰とも連絡を取っていないことは、国民公会も知っているはずだ。
「一度会議で検討しましょう」
「ぜひに!」
マリー・テレーズはベルナールが退室したあと、ホーッと大きく息をはいた。
それから窓際に歩き、外をながめた。
やはり病気だった。
かわいそうに…。
まだわずか9歳。
代われるものなら代わってやりたかった。
愛くるしい小さな弟。
マリー・テレーズは脇机に置いていた聖書を取った。
この際どこでもいい。
開いたところを一心に読み始めた。
これは叔母のエリザベート王女がくれたものだ。
もう暗記するほど読んでしまっているが、それでも読んでいると心が落ち着いた。
何も考えないよう、聖書に没頭して、気づくとあたりが真っ暗になっていた。
昨日の監視員が灯りを届けに来た。
わずかな光だが、ないよりはずっとましだった。
これがあればまだ聖書を読み続けられる。
黙って下がった監視員が、再び食事を持って部屋に来た。
いつものように黙って卓上に置いて、そのまま出て行くかと思ったが、何か言いたそうにしている。
めずらしいこともあるものだ。
マリー・テレーズは顔をあげた。
「今日来た国民公会のお役人が、弟さんに手紙を書かせるよう命令して…。さっきそれを受け取ってきた。渡しておいてくれと言われたんで…」
彼はごそごそと上着の内ポケットを探り、くしゃくしゃになった封筒を差し出した。
マリー・テレーズは目を見張り、口を一文字に閉じるとすっと手を伸ばして封筒を受け取った。
監視員が出て行くのが待ちきれないように封筒を開け、中から紙を取り出した。
灯りのそばに駆け寄る。
「なつかしいマリー・テレーズへ ぼくたちは同じ所、タンプルにいる。どうかあなたもぼくを感じてほしい。 あなたと血を分けたものルイより」
手が震えた。
これはルイ・シャルルの筆跡ではない。
一目でわかる。
こんな署名をするのはルイ・シャルルではない。
そうだ。
この世でこんな署名をするのは彼だけだ。
まだテュイルリー宮殿にいるとき何度も手紙のやりとりをした。
彼はいつ頃からか「血を分けたルイ」とサインするようになっていた。
だから自分も「血を分けたマリー」と書くようにした。
ルイ・ジョゼフ・ド・ブリエ!!
なんということだろう?!
下にいるのはルイ・ジョゼフなのだ。
ルイ・シャルルではないのだ。
いったいいつ入れ替わったのか?
そしてなぜ?
一週間前まで聞こえていた声は確かに弟のものだった。
ではそのあとに…?
声が聞こえなくなったのはそのせいか。
だが、今日来た役人はルイ・シャルルは病気だと言っていた。
頭が混乱する。
再び手紙に目を落とす。
ぼくを感じてほしい…
マリー・テレーズか駆けだした。
そして窓を開け放った。
「ルーイ!!」
大声で呼んだ。
きっと聞こえているはずだ。
自分にラ・マルセイエーズが聞こえたように。
どこにどんな監視があるかわからない。
だが、長年閉じ込められた姉が、弟の病気を聞かされて、その名を叫んでいる。
そういう情景だ。
誰も何も疑ったりはすまい。
マリー・テレーズは再び監視員がやってきて静かにするよう厳しく言われるまで「ルイ」と呼び続けた。
彼女の声は確かにルイ・ジョゼフ・ド・ブリエに届いていた。
そして報告はベルナールからロザリーを通じてオスカルに届いていた。
ルイ・ジョゼフに生きる張り合いができたはずだった。
そのことがオスカルにも一筋の光明を与えた。