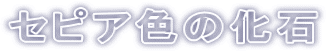「もしもおれがルイ・ジョゼフ・ド・ブリエだったとしたら…」
突然アンドレが話し始めたので、オスカルは少し驚いて、書き物をしていた手をとめアンドレの方へ顔を向けた。
「いや、とんでもないたとえだとは重々承知しているが、つい考えずにはいられないんだ…」
アンドレはオスカルの反応が想像以上に真面目なものだったので、やや気後れして話し続けることをためっらった。
決して気持ちよい話ではない。
オスカルが気分を著しく害する可能性もある。
自分で言い出しておきながら、できれば軽く冗談で流してほしかった。
だが、オスカルはアンドレを凝視したままである。
ペンはまだ右手に握られたままだったが、アンドレが黙っていると、ポンと書類の上に放り投げてしまった。
要するに先を続けるよううながしているのだ。
どうだ、聞く体制は万全だ、言い出しておいて黙るのは卑怯だろう、と。
まっすぐ向けられた蒼い瞳がオスカルの意思を明確に代弁している。
アンドレは意を決した。
「本望だと思うんだ」
あえて短く断定した。
そう、本望だ。
間違いない。
きっぱりと言い切って、それから恐る恐るオスカルを見た。
だが、オスカルは無言でいる。
その顔は、訳がわからないときのものだ。
アンドレは驚いた。
この一言では理解できないのか。
そうか。
所詮男の気持ちは…とため息でもつきたくなったところで気づいた。
オスカルの眉がほんの少しつり上がっていることに。
やはり怒った?
いや違う。
話の中身に怒ったのではない。
意味がわからないことに怒っているのだ。
「いや…その…ね。こういう展開もある意味、想定内だったろうし…。それならそれで受け入れるだろう、というかそれしかないし…」
しどろもどろに言いながら、われながら不十分な説明と思った。
案の定オスカルのまなじりは今度はキリリと傍目にもはっきりとつり上がっている。
「だから…、その…。おれなら鼻歌の一つでも歌うんではないかな、と思うんだ。そのときには…」
「アンドレ!!」
ついに雷が落ちた。
「さっぱりわからんぞ!わかるように説明しろ!」
ごもっとも…、いくらなんでもこの説明はひどすぎる。
アンドレは一度大きく深呼吸して、一気に、けれども丁寧に話し始めた。
「ここに、手の届かないひとを長いこと孤独に思い続けていた男がいる。本当に長いこと、存在すら心にとめてもらえなかった。それがあるとき突然思いが通じたとしたら…。通じないまでも、愛情と感謝を感じてもらえたとしたら…。きっと男は幸福で満たされるに違いない。そしてその人のために自分の命をかけられる場面が来たときは…。おれなら…きっと迷わず自分の命を捨ててその人を守るだろう。そして、命が尽きるその瞬間は案外満足そうに歌でも歌っていそうな気がするんだ。だから、ルイ・ジョゼフもそうではないかと…」
ルイ・ジョゼフは、もしかしたらはじめから命を捨ててかかっていたのではないかと思えるのだ。
この計画を熟考し決行するにあたって、覚悟を決めていたのだ。
ルイ・シャルルを救う為に、というよりマリー・テレーズを救う為に…。
ルイ・ジョゼフがマリー・テレーズに捧げていたのは一途で純粋で、怖いほどの愛だ。
それはフェルゼン伯爵が王妃に捧げた純愛にも決して劣らないし、そして、自分がオスカルに捧げた狂おしいまでの熱愛にも等しい。
であるならば、今頃彼はタンプル塔の汚れた部屋の寝台の上で、きっと微笑んでいる。
真の願いを達成できたことに満足して…。
その静かなほほえみが見えるようだ。
「この馬鹿野郎!!」
思いも寄らない罵声を浴びせられて、アンドレは我に返った。
オスカルがいつの間にか立ち上がって自分の目の前に来ていた。
しかもまさにこれから殴りかかろうとばかりに、右手を振り上げている。
アンドレは思わず後ずさった。
ああ、やはり怒った。
なぜか少し安心する。
ちょっと時間差はあったけれど、理解して、そして怒ってくれた。
胸が熱くなる。
「残された方はどうなる?!ひとりになるではないか!!」
アンドレは怒り心頭のオスカルの手首をすばやく握り、抱き寄せた。
そしてじたばた騒ぐ耳元に口を寄せた。
「すまなかった。荒唐無稽なたとえ話だ。気にするな」
「冗談ではないぞ!」
「ああ、わかっている。悪かった」
繰り返し謝罪しながら、アンドレはオスカルを長椅子に誘い並んで腰掛けた。
オスカルはためらうことなくアンドレの胸に顔をうずめてきた。
本当に愛しいと思う。
永遠にこうして寄り添っていたいと思う。
けれど、どうしてもそれがかなえられない状況が来たら、やはりおれはおまえのために命を捨てるだろう。
たとえおまえがどんなに悲しんだとしても、おれより先におまえを逝かせるわけにはいかないのだから。
アンドレはもう決して口にはすまいと思いつつ、この想像が間違っていないことを確信していた。