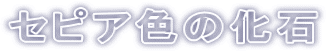しばしアンドレの胸に顔をうずめていたオスカルは、ふいに身体を離すと口を開いた。
「ぐずぐずしているわけにはいかない。思い立ったら即行動だ」
有言実行のオスカルは、言い終わる時にはもう立ち上がり歩き始めていた。
「どこへ?」
「ロザリーのところだ。ベルナールにあわねばならん」
「この暗闇を?」
だが、その返事の声は廊下からで全く聞こえなかったから、アンドレはあわててあとを追った。
階段を下りるオスカルに並ぶと辛辣な言葉が投げつけられた。
「つまらん男の感傷につきあっている暇はない。まったく…!」
少しく自尊心を傷つけられながら、それでもアンドレはオスカルに外套を羽織らせた。
春先のパリはまだまだ寒い。
そして荒れている。
まして夜だ。
一層すさんでいる。
王と王妃の命を奪った後も、おびただしい数の人間が断頭台の露と消えた。
大貴族でありながら王を裏切って革命側についたオルレアン公。
平民でありながら貴族と結婚し、そして革命のためにサロンを開いたロラン夫人。
三部会の立役者でありパリ市長だったバイイ。
反革命の立場の人間ではなく、革命側にいたものが処刑されているのだ。
昨日の敵は今日の友ならぬ、昨日の友は今日の敵というわけだ。
その抗争の激化の中で、風前の灯火になっているのが、ルイ・シャルルの身代わりであるルイ・ジョゼフ・ド・ブリエの命だった。
「このわたしがおめおめと弟子の最期を指をくわえて見ていると思うのか?馬鹿にするな!」
どうやら虎の尾を踏んでしまったらしい。
こうなったらアンドレは黙ってついていくしかなかった。
医師のラソンヌ家とシャトレ家は徒歩圏だ。
大柄の二人が大股の急ぎ足で歩けば15分で到着する。
ベルナールが帰宅している保証はないが、帰るまで待つ気でいることは聞くまでもなかった。
いつものようにロザリーは大歓迎してくれた。
アンドレは、かねがねロザリーのことを、オスカルの腹心の部下としてこれほど献身的かつ有能な人材はちょっとないと思っている。
きっとオスカルも同感だろう。
今までも困難な用件を散々依頼してきた。
その最たるものが、処刑前の王妃の世話係だった。
ロザリーは真心こめて仕え、王妃の心を癒し、それによって自責の念で絶望の淵にいたオスカルを救ってくれた。
だが、今夜はまた何を頼もうというのだろうか。
ロザリーが二階に向かって大声を出し、ベルナールを呼んだ。
「この頃は帰宅が早いんです。というか、あんまり行きたくないみたいで…」
「ベルナールにとってもきつい状況というわけか…」
オスカルは外套をアンドレに預けた。
自然な二人の動きにロザリーは心が和む。
本当にこの頃はきついことばかりだから。
普段ならいるはずのないベルナールがしばらく自宅にこもってしまうほどに…。
「タンプル塔にもう一回行けというならごめんだぞ」
少し赤い顔をしてベルナールが下りてきた。
そうだ。
つい先日も無理を頼んだばかりだった。
マリー・テレーズが弟の様子を質問してきたとき、返答に行く役を買って出てもらい、ついでに弟から手紙を受け取ってマリー・テレーズに渡すよう手配もしてもらったのだ。
おかげで、おそらく二人は塔内の別々の部屋に幽閉されながら、互いの存在を認識できているはずだった。
「おれはああいう種類の人間がどうも好かん。気位が高すぎるんだな」
「まあ、ベルナール、マリー・テレーズさまはまだとてもお若いのよ。それなのにあんな所に閉じ込められて…。お気の毒だとは思わないの?」
「ふん!もっとお気の毒な子どもはそこら中に五万といるぞ。おまえだってそうだっただろう?」
ロザリーが育ての母を失い、世の中に一人で放り出された時、あのときの年齢は確かにマリー・テレーズよりもまだ幼かった。
「犬も食わないものをわたしに出すな」
オスカルが止めに入った。
「なんだと…!」
「そうだろう?仲が良い証拠だ。結構なことだ」
ロザリーは顔を赤らめて厨房にひっこんだ。
「せめて、ご姉弟を同室にすることはできないのか?」
オスカルは本題に入った。
いつもながら率直である。
「難しいな」
にべもない。
「なぜだめなのか、わたしにはわからない。」
「ただの子どもとして生きていかせるためだ。姉といるとそれができない」
ベルナールの見たところ、マリー・テレーズは聡明な少女だった。
ということは、自分の置かれた立場を理解しているということだ。
おそらく、弟の立場も…。
「姉は弟に教えるだろう。おまえは国王だ。大きくなって革命をつぶせ、と」
たったひとりで幽閉されながら、少女は精神を正常に保っていた。
誇りも持っていた。
その証拠に「ここから出して」と一言も言わなかった。
恐ろしいまでの矜恃だ。
「だからだめなのだ」
オスカルはしばし沈黙した。
それからフッと笑みを漏らした。
「さすが、アントワネットさまのお子さまだ。そういうところ、そっくりだ」
「くだらん。おのが努力の結果を誇るならともかく、出自など誇ってどうなる?」
ベルナールが切り返した。
そのとおりだ。
人は皆、生まれながらに平等だ。
だが、それならば、父が国王であったというだけで罪に問われるのもおかしいはずだ。
オスカルの指摘に今度はベルナールが言葉に詰まった。
「表だってできないのなら、内々でもいい。ずっとが無理なら時々でもいい。姉弟を会わせてやってほしい」
ベルナールは黙したままだ。
「では、医者をつけてほしい。フランソワ・アルマンが王子の容体はかなり悪いと言っていた。それくらいならできるだろう?」
「それ、ラソンヌ先生のことか?」
「話が早くて助かる。もしかなり悪いと言うことなら、治療すべきだろう。それとも政府は王子を病気のまま見殺しにするつもりか?」
ベルナールはあさっての方角を向いてしまった。
見殺し…。
「王子どころか、最近はもう誰が誰を見殺しにしているかわからなくなっている」
「ベルナール…」
つらそうな夫のカップにロザリーがお茶のおかわりを注いだ。
「知ってるだろう?エベール一派も一掃された。おれはあいつが心底嫌いだったが、それでも同業者だ。ペンで戦ってきた仲間だったんだ」
エベールの新聞創刊は1790年。
ベルナールより遅い。
だが、彼の発行した新聞「デュシェーヌ親父」は貧困層から絶大な支持を受け、すでに300号を超えていた。
彼は処刑のわずか10日ほど前に385号を発刊していた。
まさか最終刊になるとは思わなかっただろう。
「エベールを切ったのはロベスピエールだ。そしてその後ろにはサン・ジュスト。やってられないな、まったく…」
ベルナールの深いため息につられて、オスカルもフーッと息を吐き出した。
サン・ジュストがこの家に居候していたのはいつだっただろう。
女と間違えてしまったほどの美貌と、鋭すぎる感性、そして秀でた頭脳。
「わたしを銃で狙ったとき、あいつの手は震えていた。人一人撃つことすら怖くてできないひ弱な奴が…」
もう何人を死に追いやったのだろう。
国王処刑が決議されたきっかけも彼の演説だった。
「死の大天使」などという呼称を献上されて、また例によって皮肉な笑みでも浮かべているか。
「かあさま…」
目をこすりながら小さなフランソワが部屋に入ってきた。
「あらまあ!起きてしまったの?」
ロザリーはすぐにフランソワを抱きかかえた。
「うるさかったか?悪かったな」
それまで黙っていたアンドレが初めてしゃべった。
オスカルが難しい話をしているときは、絶対に口を出さないが、子煩悩な彼は子どもを見るとあやさずにはいられないらしい。
ましてこのフランソワはノルマンディーでしばらく同居した仲だ。
にっこり微笑んでいる姿を見れば、たいがいの人は子どもの父親はこっちだと思うだろう。
「ちょっと寝かせてきますね。オスカルさま、ごゆっくりなさっててください」
ロザリーが部屋を出ようとすると、オスカルも立ち上がった。
「いや、これで失礼する。邪魔をしたな。明日もラソンヌのところに来るのだろう?返事はそのとき聞かせてくれ」
「その必要はない」
少し大きなベルナールの声に、フランソワがびっくりしている。
「医師の件、できるだけのことはやってみる。おれの子どもだということでフランソワがひどい目に遭うのはたまらんからな」
オスカルは強引にベルナールの手を両手で握りしめた。
「感謝する!」
ベルナールは仏頂面を崩しはしなかったが、オスカルの手をふりほどきもしなかった。
ただ握られるままになって、じっとフランソワを見ていた。