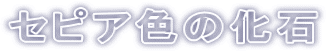どこか遠くで水の落ちる音がかすかに聞こえた。
1回だけかと思ったが2回、3回と続く。
何の音だろう。
どこから聞こえるのだろう。
確かめようとして、ルイ・ジョゼフは自分が闇の中にいて、しかも手足が自由にならない状態であることに気づいた。
目をこらしても何も見えない。
一気に不安が押し寄せてきた。
その間にもしずくの音は絶え間なく聞こえている。
これはもしかしてマリー・テレーズの涙だろうか。
彼女の美しい瞳からしずくがこぼれ落ちる様を想像する。
キュッと胸が締め付けられた。
泣かないで、愛しい人。
あなたが微笑む為ならばぼくは何でもするから…。
そう、なんでも…。
ああ、そうだった。
ようやくルイ・ジョゼフは自分の置かれている状況を思い出した。
秘薬をのんだのだった。
ニコーラが、クリスから渡された水薬を食事のときにそっとトレイに置いた。
ついにできたのだ。
ニコーラがオスカルの伝言を伝えた。
「覚悟ができたらのむように。のんだら42時間意識はない」
それはちょっと聞き取りにくいほど小さな声だった。
用心深いことだ。
この部屋にはニコーラとルイ・ジョゼフの2人しかいないのに。
靴屋のシモン夫妻が解雇されてから、元王子はずっと放置されてきたのだ。
それがベルナールの尽力で待遇が改善された。
ラソンヌ医師が診察に来てくれ、ついには旧知のニコーラが世話係として来てくれた。
そして自分の救出計画が着々と進んでいることを知らされた。
同時に、マリー・テレーズの元にはクリスが診察に行くようになり、まがりなりにも連絡がつくようになった。
もちろん完全に極秘であるから、口裏合わせは完璧に行われている。
出入りする人間が革命委員会に上げる報告はどれも悲惨な状況を綴り、ルイ・シャルルの病状は悪化の一途をたどっていることになっていた。
極悪な環境の中で虐げられた元王子。
まもなく命も尽きるだろう。
そうなれば好都合だと、委員会の大半は考えている。
なぜならば、こういう混乱の時には、幼い王子を担いで権力の座を狙うものが必ず出現するからだ。
だが、だからといって10歳に満たない子どもを断頭台に送ることはさすがにできない。
裁判にかけることもあり得ない。
自然に健康を悪化させ短い命を終えたというストーリーが最も望ましいのだ。
オスカルはそれを利用した。
死んで欲しいというなら、死んでやればいい。
突然シェークスピア談義を始めたオスカルは、文豪の虚構から現実を作り出した。
王子はタンプル塔内ではかない最期を遂げるのだ。
医師の診察や検死はラソンヌ医師がとりしきる。
どうせ報告をあげても委員会はすぐには発表しないだろう。
善後策の対応に2,3日はかかるはず。
その間に近くの共同墓地に埋葬してしまう。
そして掘り出すのだ。
無謀きわまりない作戦だが、膨大な時間をかけて綿密に準備を整え、あとはルイ・ジョゼフの覚悟だけだとなった。
ルイ・ジョゼフはオスカルを全面的に信頼していた。
だからその計画も信頼した。
彼は迷わず薬を服用した。
それから42時間がだったということか。
ではこの暗闇は棺の中ゆえ、というわけだ。
まだ完全に薬が切れておらず、だから身体が起こせないのだ。
計画では意識が回復するまでに棺が掘り出されるはずだったが、どうやら何か手違いがあったらしい。
掘り出すはずの人間が間に合っていない。
もしかしたらもう来られないのだろうか。
とすると、自分はこのままここで朽ち果てる。
現実の暗闇以上の闇が襲いかかってきた。
さっきまで聞こえていたしずくの音はいつの間にか止まっていた。
静寂と闇。
はじめてルイ・ジョゼフに恐怖心がわいた。
恐ろしい。
怖い。
金縛りにあったままの身体に心も同調し、思考が凍結していく。
先生…助けて…!
オスカルの顔が浮かんだ。
先生…!
優しい言葉を期待したが、甘かった。
険しい瞳でにらみつけられた。
ああ、怒っている。
先生が怒っている。
ついに怒声が聞こえてきた。
「馬鹿者!自分の頭で考えろ!!そして身体を動かせ!」
オスカルの口癖だ。
ルイ・ジョゼフはゆっくりと視線を移動させた。
呼吸ができているということは棺のどこかに空気孔があるということだ。
だが少なくとも正面には見えない。
恐らくは万一のことを考慮して見えにくいところにあるはずだ。
とすると足元か。
まだ首を起こすことができない為、確認しようがない。
フー…とため息をついてみた。
それからドキッとした。
もしも今外に人がいたら、そしてこのため息に気づかれたたら…。
仲間ならいいが、そうでなかったら…。
やはり音をたててはいけない。
とにかく静かに呼吸して、救助が来るのを待たなくては…。
ルイ・ジョゼフはオスカルの策が失敗してこのまま放置されるということは考えなかった。
先生は必ず来てくれる。
なぜなら先生はオスカル・フランソワ・ド・ジャルジェだから。
出会ってからこのかた、先生が言ったのにできなかったことはない。
というかできることしか言わない人だった。
もしそれが未完で終わるとすれば、よほどの天変地異が起きたのだ。
であるとすれば運命を受容するほかない。
薬を飲む時点でそれだけの覚悟を持ったのだから。
ルイ・ジョゼフはただオスカルの顔だけを心に浮かべることにした。
それだけで勇気がわくような気がした。
いつも夢想していたマリー・テレーズの姿は棺の外に追い出した。
マリー・テレーズはこのようなむさ苦しいところで想うべき人ではない。
「わたしならいいのか?むさ苦しいところでも…!」
オスカルの叱責が聞こえてきそうだ。
ルイ・ジョゼフは声を殺して笑った。
ガッ!と大きな音がしたのはまさにその瞬間だった。
それから小さな棺にゴンと何かが当たった。
続いてザーッザッと土をシャベルですくい上げるような音が数回した。
ガタガタと棺が揺れ、ルイ・ジョゼフの瞳はかすかな灯りをとらえた。
それから金色に輝くものが灯りを反射しているのに気づいた。
その金色が細い髪だと気づくまもなく、頬にぬくもりを感じた。
「ほう!心配懸けまいとしたか。すでに目が明いている」
懐かしい声が今度は本当に耳という五感を通して聞こえてきた。
大きな手が伸びてきて背中と膝の下に差し込まれすぐに身体が宙に浮いた。
ニコーラの手だ。
「薬の切れるのが少し早かったのだな。まだ身体のほうは戻っていないようだ」
「クリスが体重を考慮して薬の量を若干調整したと言っていました。それで多少時間のズレができたのでしょう、まだ意識も充分には覚醒していないみたいです」
オスカルとニコーラの会話は確かに聞こえるが、自分がものを言うことはできなかった。
「いつ頃から目が明いた開いたんでしょうね」
「まあ、そう長い時間ではあるまい」
「そうでしょうか?だと良いんですが…」
自分なら地下で埋められて意識があるなんて耐えられない。
ニコーラはルイ・ジョゼフのためにもその時間ができる限り少ないよう願った。
「見てみろ。この顔つきを…。少しも恐怖感がない。つまりは恐怖を感じる前に我々が来たということだ」
「なるほど。まあ、そういう風に解釈することもできますね」
ここでオスカルに逆らう必要は無い。
ニコーラは一刻も早くルイ・ジョゼフを連れて帰ることだけを考えていた。
驚くほど軽くなってしまっている少年のやせ衰えた体を、できるだけ優しく抱きかかえると、オスカルが持って来た布で完全にくるんだ。
誰にも見られないように、もし見られても何を運んでいるかわからないように、ルイ・ジョゼフは薄汚れた帆布で包み込まれた。
タンプル塔にほど近い共同墓地はすでに薄暗く、わざわざ灯りを灯す場所ではないため、人目につくことはまずないはずだが、用心に用心をするに越したことはない。
表通りは当然避けて、裏通りに面した側の出入口にアンドレが馬車を止めて待っている。
周囲を警戒しつつニコーラは全力疾走した。
まだ元王子の死は発表されいないから、怪しい動きさえしなければこんな共同墓地に注目するものはいない。
自然体が一番と思いながら、全力で走ってしまうところにニコーラの思いが溢れていた。
だからオスカルはあえてとがめなかった。
オスカルもニコーラの後ろを全力で走った。
背後からもしも追っ手が来たら遠慮無く剣を使うつもりだった。
馬車に近づくと待っていたかのように扉が開いた。
アンドレだ。
彼は黒い衣装で闇に隠れるようにして馬車の脇に立っていて、早く乗り込むよう目配せした。
ニコーラはルイ・ジョゼフを腕に抱いたまま馬車に滑り込んだ。
続いてオスカルも飛び乗った。
アンドレは静かに、しかし大急ぎで扉を閉めると御者台に戻りすぐに馬を走らせた。
ニコーラが帆布をほどきルイ・ジョゼフの顔を外に出した。
ほんの少しだが色が戻ってきている。
オスカルは少年の顔の間近に自分の耳を寄せた。
「よし、呼吸は平常だ」
だが平常なのはそれだけで、あとは惨憺たるものだった。
肌は荒れてガサガサに乾き、首筋はもはや骨だけで肉づきがまったくない。
美しかった透けるような金髪は汚れたひものようにねっとりとしている。
フランソワとディアンヌがついているときはここまでひどくはなかった。
やはりそのあとニコーラが来るまでずっと放置されたことが響いているのだ。
オスカルは己の無力を悔いた。
「しずくが止んでいる…」
消えるような声がした。
オスカルとニコーラは驚いて少年に目をやった。
ほんの少し唇が動いている。
「しず…く。マリー・テレーズの涙…」
ようやく聞き取れた言葉にオスカルは思わず苦笑いした。
「この状況で王女さまか…。まったく…」
一番の愛弟子だと想うからかわいがっているのだ。
「わたしの名前を呼べ!それが筋というものだ」
オスカルはコンと拳で弟子の額をこづいた。
「棺の中ではずっと先生を呼んでいました…」
正直に言うともっと怒られそうでルイ・ジョゼフは口をつぐみ、まだ意識が戻りきらないふりを続けた。
「昨夜からずっと雨だった。それで墓地の植栽の枝からしずくがしたたり落ちていた。
おまえは水たまりに落ちるその音を聞いていたのだろう」
ああ、そうだったのか。
ルイ・ジョゼフはフッと微笑んだ。
「こいつ、本当に意識が混濁してるのか?」
その問いかけにルイ・ジョゼフはあわてて目を閉じた。