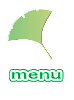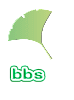船は次女の婿であるバルトリ侯爵のもので、そのまま侯爵に用意させた馬車に乗り込んで侯爵邸に入り、明けて今朝、自ら馬を御してどんぐり屋敷に到着した。
老いたりと言えど軍人である。
これくらいの強行軍で音を上げる根性も体力もは持ち合わせていない。
余裕で船旅も馬車旅も突破してきた。
だが、ホトホトまいったのは、行く先々、会う人ごとに驚かれ、問いただされたことだった。
まずは屋敷出発の際に妻から咎められた。
糟糠の妻は日頃しとやかでおとなしいが、一皮むけば恐ろしいほどの策士で、娘たちを味方に引き入れた時の力は計り知れないものがある。
「今頃、いったい何をしにノルマンディーに行かれるのですか」
正面切ってではなく、刺繍をしながら、目線もあわさずの静かな問いかけだった。
もともと妻には内緒で行くつもりだったので、露見していたことに度肝を抜かれたが、ここは胆力で乗り切るほか無しと腹を決めた。
「フランスに残してきた諸々の問題を解決してくる」
「問題とおっしゃいますと?」
「領地や屋敷や財産、使用人のこともある」
「随分急なご決心でございますね」
「何を言うか。ずっと考え抜いた結果だ」
「これは失礼致しました。で、お供は?」
「要らん!バルトリ侯の船で行くのだ。充分であろう」
「なるほど。承知致しました。どうぞお気をつけて…」
第一関門突破である。
続いてバルトリ侯所有の船に乗る際である。
侯の船で行く、というのは勝手に決めていただけで、侯に了解を取っていたわけではない。したがって、ポーツマスに行き、侯の船を探し、意気揚々と乗り込もうとして、当然だが、船員たちに咎められた。
強面の船員は、船主である侯爵の夫人の実父であり、かつてフランスに名を馳せた将軍の強行乗船に驚き、船長であるアラン・ルヴェに慌てて注進した。
そしてアランが誠実かつ丁重に忠告してきた。
「どんなにひいき目に見ても、今はフランスよりイングランドのほうが安全ですよ」
「無礼者!そんなことがわからんわしと思うか!」
わかってるならなんで?とアランが首をかしげる。
「無礼者!そんなことを恐れるわしと思うか!」
はた迷惑な爺さんだな、とアランが思っていることが見て取れたが、そこは威厳で押し通す。
逆らいきれないと思ったようで、船長はバルトリ侯爵用の部屋を空けてくれた。
そしてノルマンディーに着岸後は、積み荷の確認に来ていたバルトリ侯爵が、船から悠々と降りてきた義父の姿を見るや、恐懼の表情を隠しながら近づいてきた。
「将軍閣下、今回のご帰国の目的はなんですか?」
ここでも妻にしたのと同じ返答で煙に巻こうと試みた。
「フランスに残してきた諸々の問題を解決するためだ」
「とおっしゃいますと?」
「領地や屋敷や財産、使用人のこともある」
「ではベルサイユに向かわれるのですか?」
うっ、と詰まった。
実はベルサイユにはもう用はない。
「まあ、とりあえずは貴公のところだ」
ここも相当強引に押し通した。
侯爵はそれから大至急馬車を用意し、義父を自邸に送り届ける手配をしてくれた。
そしてようやく侯爵邸に着くと、次女のクロティルドが待ち受けていた。
馬車が着く前に侯爵が早馬を出して知らせたようだ。
「お父さま、正気ですか?」
クロティルドが、単刀直入に失礼なことを言ってきた。
「わしがおかしくなっていると言うのか?」
「失礼いたしました。でも御用向きがとんとわかりませんもの」
「ふん!わしにはわしの事情がある」
「もちろん、それはそうでございましょうが…。で、いつまでご逗留ですの?」
「用がすめばすぐ帰る」
「ですからどれくらいかかるご用ですかとお聞きしています」
「知らん!」
「?」
クロティルドがあからさまに驚いた顔をしている。
この父は頑固者だがいい加減ではない。
ものごとを勢いでする嫌いは多分にあるし、それゆえ、六女は男として育ったわけだが、基本的には几帳面で、計画的な人間だ。
それが、はるばる亡命先から帰国するのに、滞在日数の目算もたたないというのは、驚愕に値することであった。
そのようにクロティルドが考えていることが、将軍には手に取るように察せられた。
その考えは正しい。
だが、今回ばかりは、将軍自身、勢いだけで来ているので、目的が達成されるまでにどれくらいの日数がかかるのかは皆目見当が付かないである。
もしうまくいけば2〜3日で終わるが、こじれると延々と続く可能性もあった。
そこで仕方なく強行突破を繰り返している次第である。
とにかく馬を駆ってどんぐり屋敷に到着した。
門番もいないので、馬のくつわを引いたまま、敷地に入る。
ベルサイユの屋敷に比べれば取るに足りないほど小さい屋敷である。
その小さな庭でオスカルが子どもと剣の稽古をしていた。
茂みをかき分けて姿をあらわすと、案の定オスカルはこれ以上ないほど驚き、その一瞬の隙に子どもからのど元に剣を突きつけられていた。
「見事だ!」
将軍は子どもながら隙を見逃さない腕前を即座に賞賛した。
そして「隙有りだ、オスカル、なまったな」と娘を叱責した。
「父上、どうなさったのです?」
何故来たか、ではなく、どうしたかと聞かれ、こいつは父が呆けたと思ったかと、異様に腹が立った。
「用があったから来たまでだ」
「では何用ですか?」
それを無視して子どもに対峙した。
「ミカエルか?」
「ノエルです」
言下に否定された。
「そうか…」
残念だった。
今の手合わせを見る限り、この子どもは相当に筋がよい。
これがミカエルならば、ジャルジェ家は安泰だと思ったのだ。
「ミカエルはどうした?」
「本日は具合が悪く伏せっております」
驚いた。
大事な跡取りが病弱なのか。
「どこいる?」
「屋敷です。ノエル、すぐに戻ってアンドレにおじいさまが来たと伝えてこい」
子どもが走り出した。
「父上、とりあえず馬をこちらへ」
オスカルが馬のくつわを取りに来たので素直に渡した。
さすがに馬を引いたまま屋敷内には入れない。
オスカルのあとを着いていくと庭の隅にこれまた小さな馬小屋があった。
一頭だけつながれている。
その横に、将軍の乗ってきた馬もおとなしくつながれた。
そこにアンドレが息せき切って駆けつけてきた。
「だんなさま!」
それきり言葉を無くして立ちつくしている。
「アンドレ、父上を中にご案内してくれ。わたしはコリンヌたちに支度を命じてくる」
「接待は要らん!ミカエルの所に行く!」
そういうとつかつかと玄関に向かって歩き出した。
さほど大きくもない屋敷だ。
案内を請うまでもない。
「父上!」
「だんなさま!」
「父上、ミカエルは今朝から体調が優れぬのです…!」
であればなおのこと会わねばならんではないか。
将軍はオスカルやアンドレと行きつ戻りつしながら子ども部屋にたどり着いた
いつのまにか使用人も着いてきている。
室内には、顔かたちがそっくりの二人の子どもがいて、一人は寝台に座っており、一人はそれをかばうかのように両手を広げていた。