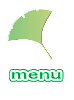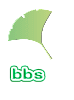つぶらな瞳が4つ、にらみつける2つと、ただ驚いている2つと。
そして吸い込まれるように蒼い切れ長の瞳が2つと、黒曜石の濡れてきらめく瞳が1つ。
それらがただ一点に集中していた。
一点とは、白髪の老将軍である。
「どこが悪いのだ?」
寝台の上に座り直した子どもに尋ねる。
だが、答えるのは両手を広げて立っているほうだった。
「咳がとまらなかったんだ」
仕方なく声の主に聞く。
「風邪か?」
すると今度はオスカルが答えた。
「まだなんとも。しばらく様子を見るつもりです」
またしても質問相手に無視された将軍は、ムッとした顔をオスカルに向けた。
「いつからだ?」
「今朝、ちょっと具合が悪いと言うので、念のため休養させています。たいしたことはないと思います」
流ちょうに説明するのはアンドレである。
この家は質問された相手は答えてはいけないという決まりでもあるのか。
肝心の本人の声は聞かれない。
「ミカエル」
たまりかねて名前を呼んだ。
「は、はいっ!」
ビクンとしながらミカエルが返事をした。
ノエルと同じ声だった。
つくづく双子というのはよく似ている。
「ゆっくり休め、明日また来る」
将軍は踵を返して部屋を出た。
「父上、何かご用でしょう、とりあえずこちらへ」
オスカルが後を追ってきて、隣室に父を引きずり込んだ。
コリンヌたちが全力で準備してくれたのだろう。
お茶のセットがテーブルに並べられていた。
すかさずアンドレが椅子を引き、将軍を座らせる。
無理矢理座らされた形だったが、フーッと大きく息が出た。
思えばバルトリ侯の屋敷から馬を駆けてきて、ようやく腰を下ろしたのだ。
身体が悲鳴をあげていたこにと今さらながら気づいた。
くやしいが、それが老いの現実だ。
紅茶の香が鼻をくすぐる。
アンドレがポットから見事な手つきでカップに注いでいる。
「どうぞ」
目の前に湯気の立つカップが置かれた。
黙って手に取り、口元に運ぶ。
顔を上げると、対面にオスカルが座り、同じようにアンドレからカップを受取っていた。
アンドレは立ったままである。
夫婦になって子どももいるのに、この二人の立ち位置はかわらないようだ。
「さて、父上。ご用向きは?」
一口すすり、皿とカップを持ったままオスカルが尋ねた。
もういいだろう。
機は熟したし、聴衆もいる。
将軍はようやく語り始めた。
水を得た魚のように、とくとくと…。
長い話だった。
とてつもなく…。
なんといっても将軍の70年の人生が滔々と語られたのだから。
父親の生まれた時からの物語に、始めは興味を示していたオスカルも、ここまで延々と続くと、さすがに辟易という言葉の意味をかみしめるしかない事態で、立ち尽くして聞いているアンドレに、黙って隣の椅子をすすめた。
最初は律儀に断っていたアンドレだが、やがて、20分後に将軍が腕を振り上げ、天井を見て語る隙をつくようにして、そっと腰を下ろした。
よくよく聞けば面白い話であったのかもしれない。
だが、将軍は、どこまでいっても将軍で、要するに自慢話しかないのである。
赤裸々な実体験ではなく、嘘か真実か判然としない手柄話だけを聞かされても、興味の持ちようがない。
カップの紅茶はとっくにカラになり、おかわりもし尽くして、ポットすらもはや一滴も残っていない。
それでもオスカルもアンドレも、異論は唱えなかった。
やめさせようともしなかった。
そして、ついに本題に入った。
一時間近く経過していた。
もう、老い先短い。
自分は爵位も財産もジャルジェ家のすべてをミカエルに相続させることにした。
本来ならオスカルが相続すべき所だが、この際、ここはとばして、ミカエルを自分の養子とする。
異論はないな?
しばしの沈黙の後、オスカルは静かに聞いた。
「この際、というのはどの際ですか?」
ぐっと押し黙った将軍はやがて絞り出した。
「今だ。今の今。いまわの際(きわ)だ」
いまわの際とは縁起でもない。
死に際ということである。
「父上はどこかお悪いのですか?」
そんなはずはない。
不調の人間に、海峡を越えて、馬をとばしてここまで来るなどできるわけがないのだから。
まして1時間演説をするなどありえない。
「なにを焦っておられるのですか?」
娘からの単刀直入な問いかけに父は押し黙った。
「お話しを伺ったところ…」
実は大半は聞き飛ばして聞いてないが、それは今は捨て置く。
「随分とご武運に恵まれご活躍なされたご様子。今もなお矍鑠(かくしゃく)としておられる。跡目のことをそんなに急がれる必要があるのでしょうか?」
もっともな話だ。
まして、時代は革命に翻弄され、もはや貴族制度は廃されたのだ。
爵位を授ける王もいない。
領土もない。
正確には、領民は、貴族の領主に対して土地代を支払う義務がなくなったのだ。
これはロベスピエールが断行したことだ。
耕す者が土地を所有する。
いたって単純明快な制度だ。
だが、そのために貴族は収入の道が断たれた。
自分で耕していた貴族はいないのだから。
ジャルジェ家もご多分に漏れず、現在領土から上がる収入はまったくない。
むしろ貿易にいそしんでいたバルトリ侯爵などは、厳然と収入を確保していて、それゆえ、オスカルたちも比較的安泰にこのノルマンディーで暮らせていた。
であるならば、ミカエルが祖父から何を相続できるというのか。
オスカルの問いかけは実に鋭いものであった。
一時間に渡って語られた将軍の業績は完全否定されたのだ。
継ぐ者がいないのではなく、継ぐ物がないのだ。
将軍は言葉を失った。
先祖から代々受け継いだもの、大切に守ってきたもの。
それがなにひとつないというのか。
革命によって奪われたというのか。
膝の上で握る拳が震えた。
「だんなさま」
沈黙を破ったのはアンドレだった。
「もったいないお言葉、ありがとうございます」
アンドレは椅子から立ち上がり深く頭を下げた。
「わたくしの息子にすべてを、とのお話、ただただ感じ入っております」
「おまえの息子は、まちがいなくわしの孫だ」
「そうお認めいただけただけで、わたくしには望外のことです」
「では承諾するな?」
「いえ、だんなさま。ただいまオスカルの申したとおり、だんなさまはまだまだお元気でおられます。ですので、大変失礼ですが、何かの時にはミカエルに譲ると、一筆お書き留めくだされば、だんなさまのご心配も払拭されるのではございませんか?」
アンドレは一気に話した。
「それがよろしかろう!アンドレ、良い提案だ」
オスカルが加勢した。
「アンドレ、紙とペンを用意しろ」
行動に移ると決めたらオスカルは早い。
その意を汲んでアンドレはすぐに紙と羽根ペンを取ってきて将軍の前に置いた。
こういうものは勢いだ。
将軍はオスカルにペンを持たされ、耳元でささやかれる言葉をそのまま一言一句したためる羽目になった。
いわく…我がすべてのものを、死後、ミカエル・グランディエ・ド・ジャルジェに譲る。
1797年1月5日
フランソワ・オーギュスタン・オーギュスト・レニエ・シュバリエ・ド・ジャルジェ
こうしてジャルジェ将軍の遺言状が本人の意思と裏腹に、しかし本人の希望通りの内容でできあがってしまった