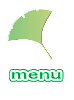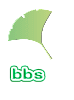アランが遠くから2列目の馬がいがんでいると指摘してきた。
視界がかすむので、ついそういう単純なミスを犯してしまう。
アンドレは小さくため息をついた。
気をつけなければ…。
もし指摘してくれなければ、事故につながったかもしれない。
しっかりとひもを結び直していると、アランが近づいてきた。
正確に言うと、オスカルに近づきたいためにアンドレに近づいてきたのだ。
案の定、パリへの相伴を交替してやろうと、お為ごかしに言う。
下心が見え見えで笑ってしまう。
からかうと、図星と見えて、顔を真っ赤にして叫びだした。
「死んでこい くそったれ」ときた。
貴族の端くれとも思えぬ言葉遣いを笑い飛ばしてやる。
アランの言葉はだいたい正反対に受け止めれば良いと気づいたのはいつごろだっただろう。
もうずっと前からだったような気もするし、つい最近だったような気もする。
不思議な男だ。
魅力的でもある。
無茶苦茶言っているようなのに、仲間がついてきているのがその証拠だ。
そして鋭い。
アンドレの右目が見えていないことに気づいた唯一の男でもあるのだ。
今も遠目から馬の綱がゆるいことを見て取った。
おそらく人間としての芯の部分が純粋なのだろう。
感情を隠せない若さが払拭されたらきっと有能な指揮官になる、とオスカルが言っていたことがうなずける。
馬車の準備を整えて衛兵隊本部の玄関でオスカルを待つ。
今日は公務による出張ということで、衛兵隊の中でも高級将校用の馬車を出すよう指示が出ていた。
パリの情勢を考えれば頑丈な車体の方が良いのだろう。
御者台にはすでに専属の御者が座り、いつでも出発できる態勢だ。
オスカルが颯爽と出てきた。
アンドレは馬車の扉を開け、オスカルのあとに続いて乗車した。
進行方向を向いてオスカルが座り、アンドレはその反対に着座する。
もう何年もの間、何度も何度もこうやって座ってきた。
ベルサイユからパリへの道も何度も往来した。
ふとオスカルがつぶやいた。
「ベルサイユからパリにつうじるこの道を…」
心の中を指摘されたようでビクンとする。
「なんどアントワネットさまのおともをしてかよったことだろう」
ああ、そうだ。
オスカルにとって、この道はまぎれもなく仕事で通った道だ。
思い出すのは王妃のことなのだ。
その時アンドレがおともをしていたことは、記憶にとどめて反芻するようなことではない。
アンドレは黙ってオスカルの話しに耳を傾けた。
オスカルは王妃が国民の暮らしに思いをいたさなかったと嘆いた。
自分が治める国の人々に心を寄せなかったと…。
もし王妃がそういうものに気づけていたら、今の世はもっと違った物になっていたかも知れないのに…。
そんなふうに、人の思いはいつも一方通行だ。
同じ馬車に座っていても、思い出すことは全然違う。
たとえ、どんなにオスカルが近しく王妃のおともをしたとしても2人の心は別々のことを思う。
アンドレとオスカルが全く別のことを考えているように、王妃がオスカルと異なる見解を持つのは、ある意味、当然のことなのだ。
オスカルは「残念だ…」と目を閉じた。
今のアンドレはそれを受け入れるしかない。
残念だな、と本当に心の底から思うけれど…。
ガタンと大きく馬車が揺れた。
慌てて窓から外を見る。
手に手になにがしかの道具を持った人々が押し寄せていた。
見えにくい目のアンドレにはそれが棒きれで武器なのだと気づくまでに時間がかかった。
市民だ。
市民がなぜ?
思うまもなく馬車の揺れがひどくなる。
頑丈な馬車のはずなのに、車体が傾いていく。
しまった!頑丈があだになったのだ。
豪華な馬車と思われてしまった。
高級将校用なのだ。
ぜいたくな人間が乗るものだ。
市民が思ったとしても無理はない。
「アンドレ、中にいろ!」
叫ぶやオスカルは飛び出していった。
「オスカル、おまえこそ出るな!
アンドレはオスカルの腕を掴もうとしたが振り切られた。
「出てきたぞ~!」
誰かの声が聞こえた。
「貴族だ!」
口々に叫んでいる。
剣で応戦するが多勢に無勢。
まるで湧いてきたかのような数の民衆が棒きれで殴ってくる。
アンドレは元々片眼が見えていないところにもってきて、残った目も最近は霞がかかったようになり、ひどい時には真っ暗になってしまう。
そのため四方八方からかかってこられるとまったく対応できない。
オスカルのほうは、生来の闘争心と武闘能力で暴徒を蹴散らしているが、剣は諸刃であるため、刀のように峰打ちができない。
振り下ろしたり突いたりすれば相手は深い傷を負ってしまう。
市民を傷つけたくないという心理が邪魔をして、通常よりは甘い応戦となっている。
しかも、貴族の馬車が襲われていると聞きつけて暴徒の数は増える一方だ。
助けてやろうとか、そうではなくとも、せめて近くの警察や軍の詰め所に連絡を入れてやろうと動くものすら皆無だった。
始めは近くにお互いの気配を感じていたが、次第に離ればなれになり、オスカルもアンドレも個別に襲われている形になった。
オスカルの姿が見えず、感じ取ることもできない。
それがアンドレを絶望させた。
守りきれない。
自分の命よりずっとずっと大切なのに、守ってやれない。
こんなことならアランをおともにするべきだった。
あの時替わっていれば…。
少なくとも自分よりはオスカルを守れただろう。
フェルゼン伯爵のように地位や名誉もなく、アランのように武力もない。
本当になにもない。
あるのはあふれるような愛だけだ。
そんな自分が、自分の恋情だけでオスカルのそばにいて、こうしてオスカルが襲われている。
オスカルが傷ついていっている。
市民に襲われたということは、身体的な傷だけではなく心情的にも深い傷になる。
いや、それどころではない。
このままでは命さえ危ない。
護衛が聞いてあきれる。
オスカル、逃げろ
頼むから逃げてくれ
アンドレは遠のく意識の中で、ただただ自分を呪っていた。