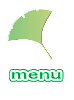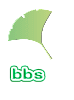意識が遠くなっていくアンドレの耳にオスカルの叫び声が聞こえてきた。
「アンドレは貴族ではない!」
オスカルかそればかり繰り返している。
その通りだ。
自分は貴族ではない。
だからオスカルに求婚する資格を持たなかったし、守ることもできなかった。
オスカルが暴徒に向かってアンドレが貴族でないことをあえて何度も叫んだのは、おそらく彼らの狙いが貴族であって、アンドレは対象外だから攻撃するな、という意味だったのだろう。
そんなことはわかっている。
オスカルはいつだって正々堂々としていて、正論を言う。
たとえ相手が自分を襲ってきている暴徒であってすら、襲う相手を間違えるなと説いてしまう。
オスカルらしいといえばオスカルらしい。
そう思いつつ、それでもアンドレにとって、この言葉は、二人の住む世界の違いを思い知らされるには充分だった。
「彼は貴族ではない、わたしだけだ!」
オスカルはこうも言っていた。
これもまた、襲うなら貴族の自分だけを襲え、という意味であったのだろうが、アンドレには相当にきつい言葉であった。
オスカルだけが貴族で、アンドレは貴族ではない。
なんという残酷な、けれども端的に真実をついた言葉だろう。
それがすべてだったのだ。
そして事実こそが真実なのだ。
オスカルが愛したのはフェルゼン伯爵であり、父の将軍が許婚者と認めたのはジェローデル少佐だった。
すべてが貴族だ。
どうして自分はその壁を越えてオスカルを愛してしまったのだろう。
しかも、愛するだけではなく、愛を告げてしまったのだろう。
さらには命さえ奪おうとした。
体中の痛みよりはるかに心の痛みのほうが強かった。
意識が遠のくことがむしろありがたかった。
愛してはいけない人を愛し、愛を告げ、その命をも奪おうとした。
そして暴徒からその人を守ることすらできない。
生きる意味がどこにあるのだろう。
今ここで襲われているのは天罰だ。
冷たい石畳に崩れ落ちた。
死んだと思ったのか、暴徒たちが離れていく。
このまま死んだふりをしていれば、助かるのだろうか。
だが、ハッと気づいた。
自分を放置した暴徒が向かう先はオスカルだ。
だめだ。
それだけは絶対にさせられない。
アンドレは最後の気力を振り絞り、立ち上がりかけ、そして倒れた。
次に意識が戻った時、アンドレは自分の部屋の自分の寝台の上であったため、普通に起き上がろうとした。
喫緊の記憶はとんでいて、寝台にいるのだから朝が来て目覚めたと思ったのだ。
だが、起き上がれなかった。
身体全体が痛かったのだ。
頭も足も背中も腕も…。
どうして…と考えた。
そして思い出した。
馬車を襲われたのだ。
オスカルは?
思わず声が出た。
だがそれはうめき声にしかならなかった。
「気がついたか?」
落ち着いた男性の声が近づいてきた。
この声は…。
視力が落ちてきてからは耳を研ぎ澄まし、声の主を聞き分けられるように鍛錬してきた。
だから顔を見なくてもわかった。
ラソンヌ医師だ。
「先生、オスカルは?」
「心配ない。少し手傷は負われたが、たいしたことはない」
アンドレはホーッと息をはいた。
よかった。
「先程までここにいらしたのだが、ばあやさんからお部屋に戻るよう言われて渋々戻られた」
実は戻ったというのは正確ではない。
引きずり戻されたのだ。
オスカルはここにいると最後まで抵抗していた。
医師は手元の呼び鈴を振った。
すぐに侍女頭のオルガがやってきた。
「アンドレの意識が戻ったよ」
医師の言葉に、オルガは顔を覆い、それからすぐに部屋を飛び出して行った。
「きみは一昼夜眠っていた。あまりに打撲がひどくてね」
医師は淡々とアンドレの症状を説明した。
全身打撲と擦過傷で相当なダメージを受けていた。
傷口が炎症をおこさないよう消毒し、内出血の箇所は冷たいタオルを当てた。
一番心配だったのが頭部の傷で、こちらも打撲があり、その上に出血もしていた。
もし意識が戻らなければ頭部損傷に寄るものだと思われ、その場合は命の危険もあるとジャルジェ家の人々には告げていた。
落ち着いた医師の声を聞いているうちに少しずつアンドレの記憶が戻ってきた。
襲われて倒れた。
そのあとは痛みで動けなかった。
もがいていると誰かが自分を支えてくれた。
「しっかりしてくれ」という声はオスカルのようだったが、それは自分の願望のなせる業で現実のこととは思われなかった。
馬車に押し込まれたような気もしたが、全身に激痛が走るので、あたりを確認する余裕はなかった。
あとはほとんどわからない。
この部屋にいるということは、誰かに連れてきてもらったのだうが、確たることは思い出せない。
だが、そんなことはもうどうでもよかった。
オスカルが無事だったのだ。
ならば自分は死んでも良かったのだ。
あのままみじめに冷たい石畳の上で朽ち果てていくことがおのれにふさわしい最期に思えた。
バーン!ととてつもなく大きな音がした。
びっくりして身体が飛び上がり、お陰であちこちに痛みが走った。
鍛錬した良いはずの耳でも何の音かわからなかった。
が、次の大声で、それが扉の開く音だったとわかった。
「アンドレ、このばか野郎!どうして馬車から出たんだ!!」
オスカルが全力疾走で入って来たのだった。
アンドレの脈をとっていたラソンヌ医師が目をパチクリさせて、あわててもう一度懐中時計を見直した。
「おまえはそのまま馬車に残っていればよかったんだ!」
ずきずきする頭に響くオスカルの大声にアンドレは顔をしかめた。
お言葉だが…、馬車自体が引きずり倒されたのだ。
たとえ残っていたとしても引っ張り出されて結果は同じだ。
そんなことがわからないオスカルでもないだろう。
と、言おうとするが、痛みで声が出なかった。
だから、オスカルに言われっぱなしになるしかなかった。
「本当に、おまえはわたしの言うことを聞かない奴だな。だからこんなことになるんだ!いいか、これからは絶対わたしに逆らうなよ。二度とこんな目にあうのはごめんだからな」
延々と続くオスカルの説教を止めてくれたのはラソンヌ医師だった。
いかにご主人とは言え、また、お怒りであると言え、この従者は重症で、やっと意識が戻ったばかり、少し安静にさせてやってはいかがか、と説得力満点の見解を披露してくれた。
だいたい、彼の回復を誰よりも祈っていたのはこのご主人のはずで、それならば喜びこそすれ怒り爆発というのはどういうことか、というのが医師の本音であった。
もちろん医師は決して口にはしなかったけれど。
オスカルは急におとなしくなり、この頃になってようやく部屋に入ってきたばあやに枕元の席を譲った。
すると、今度は医師の制止などまったく効果のないばあやの激烈な説教が始まった。
医師はつくづく気の毒な環境にいる不幸な患者に同情を禁じ得なかった。