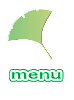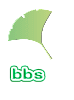フランソワ・オーギュスタン・オーギュスト・レニエ・シュバリエ・ド・ジャルジェは、貴族としての爵位は伯爵、軍隊における階級は将軍である。
したがって社会的には、ジャルジェ伯爵またはジャルジェ将軍と呼ばれている。
ただ本人は武骨な人柄ゆえ、将軍と呼ばれる方を好んでおり、家柄だけでこの地位を得たように言われることに相当腹立たしいものを感じているらしく、できる限り戦功をあげて実力で得た地位であることを周知させようと努めてきた。
そのためには、自身の剣の腕前や戦略的知識も必要だが、なによりも部下である将官や現場の兵士の掌握が欠かせない。
戦いは人と人との間に起こるものなのだから、人を動かせなければ決して勝てない。
ということで、ジャルジェ将軍は、常々人を見るということに注進してきた、つまり人を見る目があると自負してきたわけである。
そして、その目配りは、軍隊だけではなく、家にも向けられるべきだと彼は思っている。
家族のみならず、執事をはじめとする多くの使用人に対しても同様の態度で接しなければならない。
ましてそのうちの一人が大けがをしたというならば、直にこの目で状況を確認する必要がある。
このように長々と自分に大義名分を与えてから、将軍はアンドレの部屋に向かった。
時間は午後2時。
オスカルはまだ帰宅しない。
妻は部屋で刺繍に余念がないようだった。
自分は午前の会議をすませて宮殿を下がり、このあとは用がなかった。
使用人たちはウロウロしているが、主が自分の家のどこをどう歩こうが誰にも何も言わせる筋合いはない。
アンドレは自室で療養中だから、使用人棟に向かう。
この時点でかなり異常な状態だということに、本人は気づいていない。
ただ、使用人たちは各々の持ち場で忙しく働いているので、使用人棟はもぬけの殻だったのが幸いした。
つまり誰にも見とがめられずにアンドレの部屋の前まで来ることができたのである。
部屋の扉は開いていた。
まだ容態のすぐれないアンドレの異変に気づきやすいよう、オルガがそう指示したのだ。
なかなかよい判断だ。
マロン・グラッセやジャルジェ夫人相手に、侍女を束ねて勤め上げるにふさわしい人物だ。
密かに将軍は侍女頭に最大級の讃辞を送った。
そして静かに扉に歩み寄り、中をのぞき込んだ。
もし誰かがいるとバツが悪いので…。
当然だが、使用人の部屋は狭く、入口からのぞけば至近距離に寝台があり、アンドレが横たわっていた。
しかも顔を扉側に向けて…。
廊下と寝台との位置関係で、しっかり目があってしまったのである。
予想外のことで、かけるべきことばがとっさに浮かばず、将軍は立ち尽くした。
アンドレを驚かせてしまった、と思い、咳払いしてごまかそうとした時、意外な言葉が投げかけられた。
「誰…?誰かいるのかい?」
「…」
将軍は今度こそ言葉を失った。
こいつ…。
将軍は、即座に踵を返し、最新の注意を払って足音を立てずにその場を離れた。
そういうことは習得していた。
えらくなったので、あえていつも存在感を出すようにしているだけで、若い頃は、斥候の役割を担うために日常的に気配を消すことを相当訓練したものだ。
だから絶対にアンドレに将軍が来たことは気づかれていない。
だが、それはつまり、彼の目が見えていないという厳然たる事実を将軍に示していた。
あれほどはっきりと目があったのに…。
自室に戻った将軍は、すぐに妻を呼んだ。
そして、たった今知った事実を伝えた。
妻は絶句し、やがて目に涙を浮かべた。
「いつからだったのでございましょう…」
そうだ。
そこだ。
アンドレが左目の視力を失ったのは、オスカルがまだ近衛にいる時だった。
黒い騎士を捕らえるときに傷を負ったのだ。
それから1年以上の歳月が流れている。
「誰かが立っているのは見えたのだろう。だが誰かはわからなかった」
「いつもはきっと声や、足音や、姿、形、そしてその場の状況で誰か見当をつけることができたのでございましょうね」
「うむ」
「けれどまさかだんなさまがお越しになるとは思ってもいなかった。だから当て推量できなかった。かわいそうに…」
「わしは完全に気配を消して引き上げた。だから奴はわしが来たことには気づいておらん。自分の勘違いだと思っておるだろう」
「どうなさるおつもりですか?」
「まずはラソンヌに診せねばなるまい」
使用人であれ、家のものである。
こういうときの将軍は迷いなく判断する。
夫人はそんな夫を心から尊敬している。
「ではすぐに先生をお呼びしましょう」
夫人は呼び鈴を振った。
「馬車が襲われた時、アンドレの方が重傷だった理由は、これだったのですね」
「考えるだに恐ろしいことだ。あの視力であのオスカルの護衛が務まるわけがない」
「でも、言えなかったのですね」
夫人は再び涙ぐんだ。
「言わん奴も馬鹿だが、気づかん奴はさらに大馬鹿だ!だいたいがだな…」
激烈な言葉で娘への批判が始まりかけた時、オルガが呼び鈴に答えてやってきた。
「オルガ、ラソンヌ先生をお呼びしてちょうだい。至急こちらに来るように」
「かしこまりました」
怒濤の憤懣の出鼻をくじかれた将軍は「大至急だぞ!」と叫び、その形相に新入り侍女なら泣き出すところ、オルガはすっと一礼だけして、静かに部屋を出ていった。
やはり大したものだ。
あれは得難い侍女だ。
将軍は再び心中で讃辞を送りつつ、妻に目をやった。
「手遅れでなければ良いが…」
妻もまた、深くうなずいて、それから十字を切った。