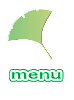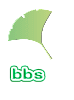大至急ジャルジェ家に来るように、との知らせが届いた時、実はラソンヌ医師は往診から戻ってきたばかりだった。
それも、あろうことか、ジャルジェ家への往診だった。
なので、彼は驚いて聞き返した。
「本当にジャルジェ家のお使いか?」
使者はブンブンと首を縦に振り、「とにかく先生を急いで連れてくるよう仰せつかっています」と言う。
確かに見たことのある顔だ。
「誰か急患か?」
「さあ…。私どもは何も知らされてはおりませんので…」
申し訳なさそうに使者は口ごもった。
「やれやれ…」
使者に罪はないとわかっていながら、ため息が出てしまった。
使者はさらにすまなさそうに頭を下げた。
たった今戻ったばかりだということは使者も知っているようだ。
さもあらん、先程診察してきたのは使者の同僚でもあるアンドレ・グランディエだったのだから。
暴徒に襲撃された彼のため、隔日でジャルジェ家に通っている。
随分快復して、今日は、口から自分で食事を取れるようになっていた。
若いというのはうらやましい。
自分の内に治癒力を秘めている。
それを引き出すようにすれば、あのような大けがでも、思ったより早い快復が見込める。
彼はその典型だ。
医師は気分良く帰宅したところだった。
再び診察室の椅子から立ち上がり、往診の仕度を始めた。
そして呼び鈴を振り、姪で助手のクリスを呼んだ。
後事を託し、時間が来たら医院を閉めて施錠しておくよう伝えた。
そして、戻れば呼び鈴を押すから、自分の顔を確認してから扉を開けるように、と細やかな指示を出した。
最近のパリは治安が悪い。
アンドレのけがもその証拠だ。
ちょっと裕福だと思われると狙われる。
ラソンヌはけして豊かではない。
小金を貯め込んでいるということもない。
ただ医師として患者を診るために必要な設備を整え、建物の広さを確保していることが、見ようによっては富裕層と受け止められることはある。
まして、ジャルジェ家のような貴族の主治医という立場は、パリにあってはかえって危険を誘う可能性が充分にあった。
たとえ、それが貧しい人々を低料金で診察するための仕事だとしても、そのことを看板に書いて張っているわけではない以上、周囲に理解されるものではなかった。
クリスに再びジャルジェ家に往診するというと、彼女は驚きつつ、万事心得ていると返事し、叔父の鞄を持って見送りに出てきた。
叔父馬鹿かもしれないが、聡明な娘である。
小柄な見かけに似合わぬ胆力もある。
医師という職業に適しているため、指導にも力が入っていた。
留守宅の懸念が払拭されたので、医師は安心して迎えの馬車に乗りこんだ。
そして再びベルサイユを目指した。
本日二回目の「やれやれ…」が思わず出た。
だが、その疲れも、ジャルジェ家の表門を入り、玄関の前で立つジャルジェ夫人の姿を見るとすっと消えていく心地がした。
歳を重ねても、立ち姿の美しい女性だ。
が、夫人みずから出迎えに出ているなどということは、日頃、まずないことだ。
ひょっとして将軍に何か…と思い立ち、慌てて馬車を降りた。
「奥さま」と医師が叫ぶのと、夫人が「先生」と叫ぶのが同時だった。
医師は慌てて口をつぐんだ。
「お待ちしていました。すぐにこちらへ」と夫人が案内してくれたのは、将軍の応接室であった。
やはり当主に何かあったのか。
それなら一大事だ。
恐る恐る部屋に入ると、大変血色の良い将軍が待ち構えていた。
満を持してという感さえ漂っている。
「おお、来たか」
「なにごとでございましょう…?」
挨拶もそこそこに尋ねると、「おまえは気づかなかったのか?」との言葉が頭上に降ってきた。
「は…?」
「アンドレの眼のことだ」
「アンドレの眼…でございますか?打撲の方ではなく?」
「若いのだから傷はそのうち治る」
経験則だろうが、的確だ。
医師は感心する。
「オスカルがあたふたしすぎているのだ。情けない奴だ」
このあたりも厳しいが当たっている。
「だがそれはこの際どうでもいい。わしが言っているのは失明していない方の眼がちゃんと見えておるのか、ということだ」
「そ、それは…」
言葉に詰まった。
刀傷により眼球を激しく損傷した左目は完全につぶれている。
だが、反対の眼については問題ないはずだ。
「見えておらん時があるのではないか」
将軍は続けた。
口から出任せを言うような人間ではない。
ものを言うからには、なにがしかの確証を持ってのことだ。
とすれば…。
「先生、もう一度、しっかりと眼の方を診察していただけませんか?もし残された眼も見えないとしたら、不憫すぎます…」
夫人は声を震わせた。
「もちろんです」
思い当たることがないわけではなかった。
言われてみれば、けがの治療の間、アンドレは目を閉じていることが多かった。
痛みのせいだと気にも留めなかったが、開けても見えないから閉じていたとも言える。
苦痛で顔をしかめると、目が閉じる。
だから見えなくてもおかしくない。
まして元より隻眼であるなら、視界は狭いのだから、首を回さなければ見えないのは当たり前で、けがで顔を動かせない彼が、枕辺に誰が来たかわかりにくくても怪しむものはない。
だが、もしアンドレが、わざとそうしていたとしたら…。
わざと目を閉じ、見えない理由にしていたら…。
「すぐにアンドレを診てきます」
医師は鞄を手に部屋を出た。
勝手知ったる屋敷だ。
案内は不要。
一度も迷わず使用人棟に行き、アンドレの部屋の前に立った。