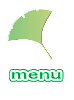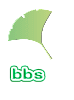なんといっても、先程診察を終えて帰宅したばかりである。
もう一度来たというには理由がいる。
どういう作戦でいくべきか。
もしアンドレの眼が見えていないとしたら、そして彼がそれを隠そうとしているなら、容易にばれることはすまい。
だいたい、今までばれていないことが奇跡なのだ。
よほど入念に対応してきたのだろうし、おそらく、まったく見えていない、ということではないのだろう。
輪郭が見えているのか、色彩が感じられているのか。
また、いつも見えていないのか、それとも見える時と見えない時があるのか。
一口に視力の異常といっても様々な形があり、それによって対応方法も変わってくる。
またその違いによって原因も推測できる。
そして、何より、治るのか、治らないのか。
将軍夫妻の最大の関心事はそこだ。
左目は眼球の損傷が原因となり、回復は見込めなかった。
聞くところによると、ムチが当たったのだという。
つくづく不運であり不幸なことだ。
だが、右目は異常なかったはずである。
もし右目に異常が認められるとすれば、左目を失った事による負荷が過度に右眼にかかり、神経に炎症が起きたと考えるのが自然である。
それならば投薬で治る。
とすると、どのようにアンドレに声をかけるべきか…。
二度目の診察に来たことが不自然でなく、また右眼について尋ねても彼が警戒せずに返答する方法。
しばし考えてから、ラソンヌ医師は、ようやく扉をノックした。
中から「はい、どうぞ」と声がした。
「やあ、アンドレ」
医師はわざと陽気に挨拶した。
自分が来たことを知らせるためだ。
「ラソンヌ先生、どうなさったのですか?」
驚きを隠せない様子ではあるが、アンドレはきちんとラソンヌの名を呼んだ。
見えているのか、あるいは声で聞き分けているのか。
ここからが正念場だ。
「実は先程忘れ物をしてね。取りに来たんだ」
「そうなんですか?」
「気づかなかったかね?」
とぼけてみる。
「何を忘れたんですか?」
アンドレはさぐりを入れるように聞いてきた。
「これだよ」
医師は、何も持たない手をアンドレの部屋の小机の上にやり、いかにも何かを掴んでいる振りをした。
一世一代の芝居である。
「な…んですか…」
アンドレが目をこらしている。
「なに、消毒液だよ」
「あっ、そうだったんですか…。気づかなかった…」
当たり前である。
はなから忘れていない。
小机の上には花瓶がひとつあるだけだ。
だが、アンドレはラソンヌが何かを手に持ち、往診鞄に入れていると思っている。
だから、それに話を合わせようとしている。
いじらしい、と医師は思う。
けなげだとも思う。
「悪かったね。戻ってからクリスに怒られて、取りに戻れと…。なかなか厳しい助手でな」
クリスをダシにラソンヌは作り話を語って聞かせる。
いかにもありそうで、アンドレはすっかり信じている。
「さもありなんですね」
「ああ、有能なんだがね。ところで、最近、眼の方はどうだね?」
クリスをフォローしてから、唐突に話を振ってみる。
「え?」
アンドレがギクリとしたのが伝わってくる。
それを無視してあえて続けた。
「まれにだが、片方の視力を失うと、残った目も見えなくなることがある」
「え…?」
アンドレが声にならない声を出す。
「ひとつに負担がかかり、疲れやすくなるのだ。若いので大丈夫かとも思うが、もしなにか異常を感じたらすぐに言いなさい」
「は…はい…」
「見えにくいとか、かすむとか、ないかね?」
「大丈夫です」
言い切るのが切ない。
「そうか、それならいいが…。けがもしたことだし、この機会に身体だけでなく眼の方も休ませると良い」
「ありがとうございます」
「では、邪魔をしたな。また次の診察は明後日だ。大事にするように」
「はい、色々と本当にありがとうございました」
心なしかアンドレの顔色が変わったようにラソンヌは感じた。
つまりは図星だったのだ。
軍隊で働いているのだから、まったく見えないわけではないのだろう。
もしそうなら危険が多すぎる。
書類も見るだろうし、銃も撃てば、剣の訓練もある。
警備ならば、見えていなければ意味がない。
だいたい団体行動自体が無理だ。
ラソンヌ医師は廊下を歩きながら思案し続けた。
そして再び将軍の部屋に伺候した。
将軍夫妻はそろってラソンヌの帰りを待ったいたようで、すぐに中に通された。
「とうであった?」
開口一番将軍が聞いてきた。
「まことに閣下のご明察どおりでございます」
「やはりそうか」
なぜか満足そうである。
「はい、間違いございません」
将軍は力強くうなずいた。
「おまえは今まで診察していて気づかなかったのか」
「面目次第もございません」
「さらに言うならば、オスカルはなぜ気づかんのだ!」
そこはラソンヌに聞かれても返答できることではない。
「おそらく、片眼にかかる負担により視神経が衰弱し炎症をおこし始めているのだと思われます。とりあえずわたくしはこれから家に戻り、医学書を読み直して、対応を考えようと思っております。いかがでしょうか」
「ぜひにもお願いします」
それまで黙っていた夫人が口を開いた。
「お薬が必要なら使って下さい。高価なものでもかまいません」
声に真剣さが感じられる。
「あなた、よろしゅうございますよね?」
将軍は事後承諾を求められ、夫人に答える代わりに、ラソンヌに命じた。
「そういうことだ。治療法がわかったらすぐに報告に来い。いいか、できるだけ早くだ」
「承知致しました」
ラソンヌは屋敷を下がり、ベルサイユからパリへの、本日二度目の帰途についた。