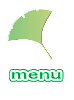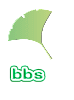若いだけのことはあるね、と晩の食事を届けに来たオルガが嬉しそうに言う。
「けがをしてること自体が情けない話なんだよ!」と心配で様子を見に来ておきながら毒づくマロンも、顔はほころんでいた。
だが、肝心のアンドレの顔色は冴えない。
マロンの言うとおり、オスカルの護衛の身が負傷したことを恥じてのことかと、オルガもマロンも受け止めている。
が、実は違う。
二人が部屋を出ていった後も、アンドレは食事に手を着けずにいた。
ラソンヌ医師に言われたことがずっと気になっているのだ。
片眼を失うと、まれに、反対の眼も視力を失うことがある…。
無情の宣告だった。
最近の自分の視力は相当おぼつかない。
見えている時ももちろんあり、不自由を感じないでいられることもあるにはあるが、日に日にその時間が短くなり、反対にかすむ時間が長くなっている。
目覚めても周囲が暗く、まだ宵かと思って時計を見ると、すでに朝だということもある。
今日もそうだった。
診察を終えた医師が帰り、午後から少しうとうとした。
そして目覚めると、目を開けているのにもかかわらず、あたりがかすんでいた。
起き上がって周囲を見回した。
窓、壁、家具…全体が暗くてぼんやりとしている。
続いてオルガが開け放したままにしてくれている扉に顔を向けた。
ふと、人影が見えたように感じた。
だがその瞬間に視界が真っ暗になり、何も見えなくなった。
ここまで真っ暗になったのは初めてのことだ。
あわてて誰かいるのかと声を掛けたが、返事はなかった。
ようやく視界が戻った時には、誰もいなかった。
わずかでも、残り香や気配が感じられればと思ったが、それらは一切なかった。
思い違いだったのだろうか。
色々と不安になっているため、誰かがいるように感じただけだったのかもしれない。
きっとそうなのだろう。
そう思いたい。
だが、その後、ラソンヌ医師が忘れ物をしたと部屋に戻ってきたとき、自分にはその薬の瓶が見えなかった。
あのときもかすんでいたのは確かだ。
医師の姿形はぼんやりと見えていたが、手元まではわからなかった。
何か持っているようだったから、それが薬瓶だったのだろう。
だが、そんなものが机に置いてあることも気づかなかった。
つまりは見えていなかったということだ。
医師には適当に話を合わせたが、今後、もし頻繁にかすむことや、真っ暗になることが増えてくるのだとしたら…。
隠し通すことができるだろうか。
屋敷内で、あるいは衛兵隊で、見えるようにふるまうことができるだろうか。
もうすでに衛兵隊ではアランが感づいている。
見えてないとは思っていないだろうが、普通に見えているわけではないことを、敏感なアランは察している。
だから、先日のパリ行きの時も、止めてくれたのだ。
パリはおまえのそんな眼で乗り込めるような状態ではない、と。
それを、オスカルの側にいたいからだろうとからかって、一笑に付した。
その結果がこれだ。
オスカルも自分も負傷した。
聞けば、オスカルはフェルゼン伯爵に救出されたということだ。
よりにもよってフェルゼン伯爵とは…。
もしこの眼のことを他言すれば殺す、とまでアランを脅した我が身が情けなくてたまらなかった。
怪我が完治し軍隊に復帰できたとして、果たして勤まるのか。
オスカルを守っていけるのか。
みじめだった。
この上なくみじめだった。
悶々とした思いが脳裏を駆け巡り、用意してもらった食事はどんどんと冷めていく。
頭に手をやりホーッと長い息を吐き、ようやくそれでも食べなければとスプーンを取った時、廊下からカツカツという靴音が聞こえてきた。
オスカルだ。
こちらに向かっている。
アンドレはスプーンを置くと、両頬を両手で叩き、「しっかりしろ、なにがあっても隠し通せ」と自分に命じた。
「アンドレ、ラソンヌ先生の診察はどうだった?」
ただいまの挨拶もなくつかつかと部屋に入ってくると、オスカルは寝台横の椅子にどっかりと腰を下ろした。
「随分良くなっているとのことだ。明後日また来るとおっしゃっていた」
まさか右眼のことを問われたということは言えなかった。
「そうか」
手袋をはずしながらオスカルはうなずき、目の前にアンドレの食事が置かれたままになっていることに気づいた。
「なんだ、食べてないのか?」
視力が心配で食べる気にならなかったとは言えない。
「ああ、おまえがまだ仕事中なのに、先に食べるのは気が引けた」
決して嘘ではない。
いつも、オスカルが戻るのを確認してから食べるようにしている。
ただ、今日は遅い時間に会議があるため、オスカルは自邸で夕食は取らないことになっていた。
つまり、すでにオスカルは宮殿で夕餉を済ませており、会議を終えて帰宅するなり、アンドレの部屋をのぞいているのだ。
「そんなことを気にしていたのか?」
オスカルが驚いている。
「しっかり食べねば治らんぞ。今後は届けられたらすぐに食べろ。わたしにかまうな」
おそらくオスカルならそう言うだろうとわかっていた。
「ああ、わかった。メルシー。ところで隊のほうはどうだ?今日は困ったことはなかったか?」
アンドレはさりげなく話題を変えた。
「おおありだ」
オスカルの答えにアンドレは吹き出した。
「そうか。それは大変だったな」
「ああ。聞きたいか?」
「長くなりそうだから、とりあえず着替えてこい。俺もその間にこれを片付けておく」
「よし、わかった。すぐに戻る。待ってろ」
オスカルは再び軍靴を響かせてアンドレの部屋を出ていった。
みじめだった自分の気持ちが、嘘のように和んでいる。
オスカルとのこんなに短い会話でも、自分の気分が高揚するのがわかる。
もしこれが不要だと、迷惑だと思われたら…。
いや、今それを考えるのはやめよう。
とにかく、オスカルが戻るまでに食事を済ませることが優先だ。
アンドレは短く食前の祈りを捧げるとスプーンを手に取った。
同じ頃、ラソンヌ医師は自邸で膨大な医学書が並ぶ書棚の前に立っていた。
一冊取っては、目次を確認し、パラパラとめくり、また元に戻す。
そしてときどき、頁を開いたまま、しばらく読んで、そこにしおりをはさむと本を脇の机に置いた。
そうやって数冊の書物が積み上げられた。
顔つきが怖いくらいに真剣だ。
ただならぬ様子に気づいたクリスが近づいてきた。
簡単に事情を説明すると、すぐに反対側の書棚の前に立ち、叔父と同じ行動を取り始めた。
二人が取り出した書物は10冊。
それを手分けして読み始めた。
医師は机の前の椅子に座り、クリスは応接椅子に腰掛けている。
たまにどちらともなく声をかけ、確認したあと、クリスが羽根ペンで1枚の紙に何やら書き付けていく。
アンドレには明後日もう一度診察すると言ってある。
おそらくその時には日常生活に戻せると告知してやれるだろう。
屋敷内で2~3日様子を見て、それから軍隊にも復帰の許可を出してやれる。
当初はその予定だった。
だが、怪我は完治しても、あの眼では軍隊に戻ることはできない。
眼を治すためにどんなものが必要で、どれほどの時間がかかるのか、医師は答を得るため、医学書と格闘していた。
夜はしんしんと更けていく。
「クリス、続きは明日にしよう。おまえはとりあえず、明日朝一番で、ここに書き出した薬を取り寄せる手配をしておくれ」
叔父に言われたクリスは本にしおりをはさみ、パタンと閉じた。
「少し目処がついてきましたわね」
「ああ。まだ間に合う。完全に光を失う前に気づいて良かった」