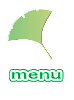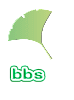「まだ間に合うということか?」
将軍は満足げである。
ラソンヌは慈悲深い主人だと感心しつつ返答した。
「はい、およそ1月、わたしどものところで治療を受ければほぼまちがいなく改善すると存じます」
「まあ、よかったこと。では先生、早速そのようにアンドレに伝えてやってくださいな」
夫人が涼やかな声音で依頼し、もちろんですと答えようとしたとき、将軍が口を挟んできた。
「いや、おまえが言う必要は無い。わしが直接アンドレに伝えてやる」
「え?」
夫人と医師が同時に声を上げた。
「あいつのことだ。たとえおまえに言われても、ひと月も休暇をとるなど絶対に承諾するまい」
医師は深く感銘を受けた。
その通りだ。
アンドレがあの見えにくい状態で、誰にも秘して日常生活や軍隊を続けてきたのはなんのためか。
主人であるオスカルに見破られることなくふるまってきたその真意を考えれば、将軍の言うことはまことにもっともであった。
「わしが命令するしかなかろう」
ラソンヌは感極まった。
「アンドレは、この上ない幸せ者でございますな…。このようなご配慮をいただけるとは…」
瞳を潤ませながらラソンヌは将軍に答え、続いて夫人に目を向けた。
そして少なからず違和感を覚えた。
それは、夫人に違和感を覚えた、というより、夫人が将軍に違和感を感じているように見えた、という方が正しいかもしれない。
夫人は、少し小首をかしげる仕草をしたのである。
通常の夫人ならば、このように温情あふれる措置を将軍がとったなら、ラソンヌ同様に感激し、すぐさま同意の発言をするはずだ。
ところが夫人は、何も言わない。
しばし沈黙していたのである。
それは、夫人を昔から知る医師にとってみれば、ちょっとあり得ない不思議な反応だった。
「奥さま…?」
医師は、つい夫人への違和感を口にしてしまった。
すると、夫人は即座に元の夫人に戻り、笑顔で言った。
「ええ、さようでございますね。もちろん、アンドレは先生からおっしゃって頂いても言うことを聞かないでしょう。だんなさまから言って頂くほかございませんわね」
将軍は大きくうなずき、ラソンヌに命じた。
「よいか。おまえは怪我の完治のみアンドレに伝えよ。そうすれば、あれは喜んで床上げし、出仕の仕度にかかるであろう。それからわしがあれに眼を治せと命令する」
「かしこまりました。すべて仰せの通りにいたします」
ラソンヌは、礼儀正しく挨拶を述べ、部屋を辞した。
その後ろ姿を見送って、満足そうな将軍の顔を、夫人はしげしげとながめた。
見かけによらず情に厚い人だいうことは了解済みだ。
だが、この態度は違う。
ただの温情だけではない。
妙に嬉しげなのだ。
それも、してやったり、という嬉しさに満ちている。
これはきっと何かたくらんでいるときの顔だ。
「よろしゅうございましたね」
あえて、水を向けてみた。
次に打つ手を披露したくてたまらないはずだからだ。
「うむ。何よりだった。ところで、この件は、オスカルには内密にする。そう心得ておくように」
「え?」
さすがに夫人は驚いた。
「アンドレの眼のことをですか?」
「そうだ。見えておらんことも、それから治療に行かせることも、あいつには知らせん」
「まあ!」
「元々気づいておらんのだから一向に問題はあるまい」
「それはそうですが…。でもそれならアンドレの治療中はどう説明するのです?ひと月、先生の元に行くことになっておりますよ」
「わしの命令で出張に行かせたことにする」
「?!」
夫人は返す言葉を失った。
「あいつはな、偉そうに指揮官ぶっておるが、実のところ自分の足元すら見えてはおらん。ちょっと心を配ればアンドレの眼のことなど気づかんわけはないのだ」
それはそのとおりだ。
至極まっとうな正論である。
「ならば、そのアンドレが不在となって、はじめておのれの無能さに気づくだろう」
手厳しい言葉だ。
夫人がため息をつきつつ同意しようとしたその時、将軍が小さい声でぶつくさとつぶやいた。
「親に向かって散々言いたいことを言いおって…。あの舞踏会にどれほど散財したことか…」
幸か不幸か、この小声が夫人の耳には聞き取れた。
それか…!
夫人はすべてを理解した。
これが企みの全貌だ。
あの婚約者公募舞踏会。
しっちゃかめっちゃかに衛兵隊員が騒ぎ、飲み、かっくらい、ために、絶望的なまでにひどいものとなり果てた。
お堅いジャルジェ将軍が、いかに美貌とはいえ、三十路を越えた現役武官である娘の婚約者を募って大々的に開催したはよいが、主役は男装で登場し、しかも次々に淑女たちと踊り、求婚しようとした男性は全員袖にされた。
前代未聞の舞踏会。
将軍の面目は丸つぶれ。
しばらくの間、ベルサイユはこの舞踏会の話で持ちきりとなり、将軍を見かけた人は、みなそろって、含み笑いをこらえきれない有り様で、さすがの将軍も宮廷への参内をしばらく控えた。
きっと将軍のはらわたは煮えくりかえり、いつの日か復讐をと考えていたのだろう。
そこへ、馬車襲撃事件とアンドレの失明発覚だ。
すべてオスカルの不手際だ。
ここで反撃せずしていつするか。
将軍がそう考えたのは間違いない。
そしてオスカルにとって一番の弱点はどこか。
それはここしばらくのオスカルの様子を見ていれば明らかだった。
間違いなくアンドレ・グランディエである。
オスカルは、手足のようにアンドレを使ってきた。
それは幼い頃からの習慣で、身体に染みついてしまっていて、おそらく本人はまったく自覚してこなかった。
アンドレの補佐がない、ということが、どれほどの痛手であるか、今頃になってようやくわかりつつあるようではあるが、もしその彼が突然姿を消せばどんな反応を見せるか。
どうやら将軍は父親としての情愛よりも、つぶされた対面と誇りへの復讐心の方が勝っているようだ。
なんという子供っぽさ…。
夫人はあきれ果てた。
だが…、と夫人は考えた。
たとえ将軍の動機がなんであれ、アンドレの眼は治るのだ。
主人の命令となれば、アンドレは誰にも何も遠慮もすることはない。
休暇も大手を振って取れる。
しかもオスカルは罪悪感にさいなまれずに済む。
良いことずくめだ。
反対する理由はない。
ただ、罪悪感にさいなまれない代償として、オスカルが相当辛い思いをするのも目に見えていた。
そしてそれは将軍が思うような、単に手足をもがれただけ、というにとどまらず、心の半分が失われたような痛みではないだろうか。
母として女として、そういう予感がするからこそ、夫人は躊躇したのである。
オスカルとアンドレはあまりにも近く魂を寄せ合ってきた。
そのことに気づきさえもしないほど近く…。
もしかすると、この将軍のささやかな復讐が、新たな気づきをオスカルに与えることになるのではないか。
そうなったとしたら、どうするのだろう。
オスカルは?
アンドレは?
そして将軍は?
いや、それよりも自分はどうするのか。
夫人は思いを巡らせ続ける。
そして心を決めた。
全力で娘を守る。
「あなた」
夫人は優しい声で夫を呼んだ。
「本当に、いつもながら素晴らしいご対応でございますね。アンドレの驚く顔が楽しみでございます。どうかわたくしも同席させてくださいませね」
将軍は妻の絶賛に満面の笑みでうなずいた。
こうして、馬車襲撃のさいに負った傷が癒えたあと、アンドレは将軍に呼び出されることとなるのである。
この時の彼は、まだ闇の中にいて、これから光がさしてくるとは思ってもいない。
これは光さす前の話である。
「はじまり」に続く