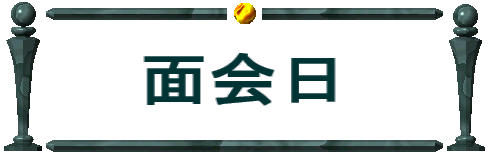いた。
たまの面会日に対する天の配慮だな、とアンドレは、司令官室の窓辺から歓声のあがる庭
を見下ろしながら、目を細めた。
オスカルとともに出勤する自分と違い、衛兵隊の隊士は兵舎住まいだから、家族と会える
面会日を待ちこがれている。
いつものことだが、やつらも人の子だな、と再認識したアンドレは、庭の隅に遠慮がちに
たたずむ黒髪の若い女の姿を見つけて思わず声を出した。
「ディアンヌ!」
書類に向かっていたオスカルが顔を上げた。
「来ているのか、ディアンヌが…?」
そう言って椅子から立ち上がり、アンドレの隣へ来て、窓の外を見下ろした。
確かにディアンヌだった。
一人ぽつんと立っている彼女を、一班の連中が目ざとく見つけ、皆、駆け寄って行った。
遠目にも、そこだけ花が咲いたように明るい笑顔の彼女が見て取れた。
フランソワがあわてて兵舎に飛び込んでいった。
アランを呼びに行ったのだろう。
「ディアンヌが来ることをアランは知らなかったのだな」
オスカルはアンドレに振り返りながら言った。
「そのようだな。来ると知っていたら、あいつのことだから、何か用事を作って門のあた
りをウロウロしていたはずだ」
「まったく、わかりやすいヤツだな」
オスカルはクスクスと笑った。
「ああ、だが、本人は絶対バレていないと信じているから、そこは尊重してやらんとな」
と言いながら、アンドレは、オスカル以上に笑っている。
アランを笑いながら、けれど、本当は面会に来られるほど立ち直ったディアンヌの姿が、
こういう微笑みを誘ってくれているのだと、二人とも知っていた。
呼びに来てくれたフランソワをはるか後方に置き去りにして、アランがディアンヌのとこ
ろへ駆けてきた。
息を整えながら、ディアンヌの肩をたたき、同僚には見せたことのないような優しい顔で、
何か話している。
ああ、幸せな光景だ、とオスカルとアンドレは思った。
もし、ディアンヌの許婚者が裏切らず、無事に結婚式を挙げていたら、きっとこれとは違
う幸福が、アランとディアンヌのそれぞれにあったのだろう。
だが、神はその幸福ではなく、絶望からの復活という厳しい試練を乗り越えたものにのみ
与えられる幸福を、二人に授けられたのだ。
「おや、こちらを見ているぞ」
オスカルが一班の連中の視線を察した。
「ジャンが指さしてるな。何か用かな?」
アンドレも不思議な面持ちで返した。
「ダグー大佐に書類を届けるついでに、様子を見てこよう」
アンドレは、オスカルが書き終えたばかりの書類を手に、司令官室をあとにした。
その後ろ姿を見送って、もう一度オスカルは庭を見下ろした。
賑やかで明るい家族や友人の語らいの場に目を細め、それから椅子にかけ直し、仕事の
続きを始めた。
衛兵隊員の勤務評定である。
今日中に終えてやらないと、支払いが滞って、兵士全員から総スカンを食らってしまう。
近衛隊からの異動直後の空気を思い出し、暴動など起きたらたまらんぞ、とばかり、真剣
に書類に向かった。
![]()
「アンドレ!」という言葉がとりわけ大きかったから聞こえたのか、あるいは、その言葉
に特に自分の耳が敏感だから聞こえたのか、とにかく、その声に吸い寄せられるように、
オスカルは再び席を立ち、窓辺に来た。
ディアンヌを囲む輪が少しくずれて、そこにアンドレが入っていた。
アランに寄り添っていたディアンヌがすっとアンドレに近づき、丁寧に頭を下げた。
くやしそうなアランの様子が面白いな、と、余裕を持って見ることができた。
白山羊亭のナタリーや、ロザリーにまで嫉妬していた自分が今では微笑ましい。
シャトレ家を訪ねた日など、一晩がかりでアンドレを問いつめたものだ。
もちろん疑いはアンドレに完全に否定された上、二人が抱き合っていた本当の理由もつい
に知ることはできなかった。
けれど幸か不幸か、長いつきあいの賜物で、彼が嘘を付いていないことだけは確信できた
から、追求はあきらめざるを得なかった。
彼が誤解を解くためにそのような心理的な方法だけではなく、物理的手段も駆使してきた
ことはいうまでもない。
が、それは司令官室で想起すべきことがらではないので、オスカルはあえて封印している。
ただ、嫉妬心とは別のところで、ささやかな懸念が心中に芽生えた。
アンドレではなく、ディアンヌについてである。
彼女が絶望のどん底からはい上がりつつあることは疑いない。
そして、そのきっかけが、自分たちのパリ訪問であったことも、うぬぼれるわけではなく
事実である。
窓から飛び降りようとしたディアンヌにアンドレがかけた言葉は、間違いなく希望の灯火
となり、再び生きる勇気を与えたといえる。
確か、クリスが言っていた。
仕事で紛らすのが一番よ…と。
その言葉が妙に実感されたのは、自分にも経験があったからだ。
フェルゼンへの失恋は、仕事によって閉じこめられたから。
近衛隊から衛兵隊に移り、慣れぬ職場で忙殺されて、次第に忘れていった。
だが、それだけだっただろうか?
あの失恋から立ち直るきっかけは、いや、あの失恋を忘れてしまうきっかけは、そうだ。
仕事ではない。
フェルゼンと別れてきた夜、突如自身の肉体に刻印されたアンドレの唇…。
思いも寄らぬ展開が、混乱を巻き起こし、失恋に浸る暇を与えてくれなかった。
つまり、新しい恋のはじまり。
それこそが失恋を忘却のかなたに追いやる最良にして最速の手段だったのだ。
だとしたら、ディアンヌのあの明るい笑顔は、単に仕事への没頭ゆえ、と考えるよりは、
彼女の心に婚約者を忘れさせる誰かが住み始めたから、と考える方が近いのではないか…。
と、そこまで考えて、オスカルは首を振った。
私とでこそ釣り合うが、ディアンヌから見たらアンドレは充分におじさんである。
そういう対象になるはずはない。
馬鹿なことを考えず、それこそ仕事に集中しなくては…、とオスカルは再び勤務評定にと
りかかった。