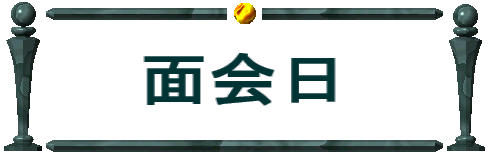書類に集中しているオスカルの耳に廊下を歩いてくる二つの足音が聞こえた。
ダグー大佐かな?と思いながら、そういえばこの間もアンドレとこんな会話をしたことが
思い出された。
あのときは、アンドレが
「いや、あの足音はちがう。あれは…、あれはアランだ」
と言い、事実そうだった。
アランが用を終え、退出するや、
「アンドレ、おまえ…、随分耳が良くなったな」
と声をかけた。
それから、アンドレのドキッとした顔を見て、しまった、と思ったが遅かった。
アンドレの耳がなぜよくなったのか。
それは失われた視力を残された五感を使って補おうとしたからに他ならない。
耳が良くなったのではなく、耳を鍛えて良くしたのだ。
そんなことにも気づかなかったなんて…、という思いが顔に露骨に出ていたのだろう。
アンドレは気の毒なほどうろたえ、
「たまたまだよ。たまたま当たっただけだ。ほら、アランの歩き方は特徴があるから」
と必死で訴えた。
自分に負担をかけまいとするその気持ちが痛いほど伝わり、騙されることにした。
「確かに、アランの歩き方は特徴的だな。いつも臨戦態勢の歩行法だ」
と、笑って話を合わせた。
今、聞こえる足音のひとつは間違いなく、その臨戦態勢のものだった。
ほどなく扉がノックされた。
「隊長、アランです。よろしいですか?」
という声がした。
予想したとおりだったのに、なぜアランが?と少し驚いたが
「入れ」
と答えた。
扉が開き、アランがディアンヌを伴って現れた。
さらに驚いた。
「仕事中にすいません。こいつが隊長にひとこと御礼をって言うもんで…」
アランに隠れるように立っていたディアンヌが恥ずかしそうに前に歩み出て、深々と頭
を下げた。
窓からの光を背に立つオスカルの髪がキラキラと反射して、慣れているはずのアラン
でもディアンヌがいなければぽかんと口を開けてしまいそうだった。
「よく来られましたね。先生のところは忙しいでしょう」
と声をかけられて、
「あ、はい。でも、とてもよくして頂いてますので…」
と、口ごもりながら返すデイアンヌの様子が兄の目からもいじらしい。
「あの、本当にいろいろとありがとうございました。なんといって良いか、わたし…、わ
たし、とても…、とても感謝しています」
ようやく意を決したように、ディアンヌは一気に言葉を続けた。
その様子をにこやかにながめ、
「礼には及ばない。わたしはなにもしていない。あなたを先生のところに紹介したのは
アンドレだ」
とオスカルは答えた。
「え、ええ。さっきお会いできたのであの方にも御礼を申し上げました。そしたら、今の
オスカルさまと同じようにおっしゃって、直接顔を見せて上げなさいって…」
ああ、それでここに来たのか…、とオスカルは納得した。
「そうでしたか。仕事はつらくありませんか?初めてのことでしょう、家を出て働くのは…
?」
ディアンヌは貧しい暮らしをしているとはいえ、貴族の娘である。
どういう経緯で没落したか、詳しくは聞いていないが、宮中に奉公するならともかく、労
働をして、給金をもらう、ということにはソワソン家として抵抗があったのではないか、
と案じていた。
その意味をすぐに察したディアンヌは
「お気遣い下さってありがとうございます。でも、わたし、本当はずっと働きに出たかった
んです。こんなことをオスカルさまの前で申し上げるべきではないのかも知れませんが、
兄のお給料だけでは、なかなか苦しくて…」
おいおい、とアランがあわてて止めようとするのをオスカルは手を振って制し、続きを促
した。
「でも、母が貴族の対面にこだわって、ずっと許してくれなくて…。今、自分で働いて、そ
の代価を頂くのがとても嬉しいのです」
そう言い切る顔に無理はなく、心底、仕事を誇りに思っていることが伝わった。
「そうですか。それは何よりだった。アラン、安心しただろう」
と、アランに顔を向けると、
「こいつが元気になるんだったら、どんな手段でもかまやしません。たとえ、アンドレの肝
いりでも…」
と、くやしさを隠さないまでも、義理は義理として捉えているのがアランらしい。
「では、それこそ、直接伝えたらどうだ?」
と、オスカルはニヤリと笑いながらちょうど用を済ませて戻ってきたアンドレを指さして
言った。
アランはギョッとして振り返り、それからいかにも始末の悪い顔で、
「チェッ!間の悪いヤツだぜ」
と吐き捨てた。
扉を開けるなり、アランのしかめっ面に出くわしたアンドレが、要領を得ない顔で室内の
三人を見つめながら、オスカルの執務机に近寄り、書類を置いた。
「メルシー。これでこっちは片づいたな」
と、オスカルがアンドレに声をかけた。
「ああ、あとは、勤務評定だけだな」
と、答ながら、アンドレはアランの方を見てこれまたニヤリと笑った。
「ケッ!俺はまじめに仕事してるぞ。最高の評価のはずだ」
と、アンドレに詰め寄ろうとするアランの袖をディアンヌが引いた。
「お兄様、もう失礼しましょう。お忙しいところ、お邪魔して申し訳ありませんでした」
と、言いながら、ディアンヌは並んで立つオスカルとアンドレにしばらく見とれていた。
ああ、やっぱり、二人並んでいるのが一番美しいわ…。
一人ずつよりずっといい。
いつまでも見つめていたい…。
金と黒の髪、頭ひとつ違う背丈、短い言葉の中に信頼があって外にあふれている。
世の中にはこんなにきれいな組み合わせもあるのね…。
見ているだけで幸せな気持ちになれる。
恍惚の表情で二人を見つめるディアンヌの袖を、今度はアランが引いた。
「おい、帰るぞ」
と言われて、ディアンヌはハッと我に返った。
「あっ…。すみません。あんまり美しい光景なので…」
と言ってしまってから、
「まあ、わたしったら変なことを口走ってしまって…。申し訳ありません」
と、あわてて頭を下げた。
「いや、かまわないが、なにか美しい光景がこの殺風景な部屋にありましたか?」
とオスカルに尋ねられ、ディアンヌは思い切って
「あの、えっと…。お気を悪くなさらないでくださいませね。お二人が並んでらっしゃるのが、
本当に美しくて…」
と言った。
さすがにアランが強引にディアンヌの腕を引っ張って
「失礼しましたっ!!」
と、部屋から連れ出した。
扉の外で、馬鹿野郎、と怒鳴るアランの声が響いた。
臨戦態勢の足音が遠ざかっていった。
![]()
残された二人は顔を見合わせて、それからクスクスと笑い出した。
「何がおかしいんだ?」
とオスカルが聞いた。
「おまえこそ何がそんなにおかしいんだ?」
と、アンドレも聞いた。
「わたしはてっきりディアンヌはおまえに気があるのかと思っていた…」
と、オスカルはまだ笑いながら答えた。
「俺もディアンヌはおまえに恋していると思っていた。ロザリーのように…」
アンドレも笑って答えた。
「まさか、わたしたちセットだったとは…な。フフフ…」
「ああ、意外だった」
「だが、とても愉快だ」
「まったくだ」
と、オスカルに相づちをうちながら、アンドレは、どうもそれを察していて最高に面白くない顔
をしていたアランのほうが、さらに愉快だ、と意地悪く思っていた。
アラン、おまえ、まだまだ青いな…、と。
「さあ、良い気分のまま、仕事にかかろう。今回の評定は甘くなりそうだぞ」
と、オスカルは机の前に座り、再び仕事にとりかかった。
「では、甘い評定に似合いの甘いショコラでも入れるか」
アンドレの言葉にオスカルは大きくうなずいた。
終わり