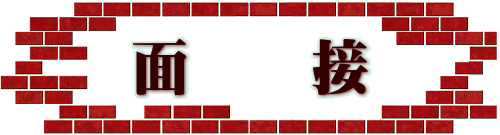
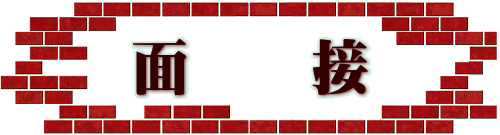

面接という言葉には全然似合わない場所で、アンドレのそれは実施された。
ジャルジェ邸のオスカルの私室である。
しかもテーブルの上にはボルドーの赤ワイン。
いったいどんな質問が投げかけられるのか、アンドレは戦々恐々の面もちでオスカルの向かいの椅子に腰掛けている。
「知っているようで知らないことも案外あるものだ」
オスカルが口を開いた。
当たり前だ。
別個の人間だ。
だがアンドレはそうは答えない。
「たとえばどんな?」
「ばあや以外の家族について…」
アンドレは虚をつかれた。
そんなことを聞かれるとは思っていなかった。
「それは、つまり両親のこと?」
「ああ、そうだ」
そういえばそうだったかもしれない。
屋敷に来て、オスカルに会って、色々質問された記憶はあるが、故郷のこと、生家のこと、家族のことを聞かれた覚えはないように思う。
好きな食べ物、好きな遊び、嫌いな仕事など、アンドレ個人に関することは散々聞かれたが…。
「あまり聞かれなかったから、言っていなかったな」
「あの頃は、聞いてはいけないと思っていたのだ」
意外な言葉だった。
「どうして?」
「なんとなく…。そう、母上がそんな雰囲気を醸し出しておられた」
「奥さまが…」
「初めておまえのことを母上からお聞きしたときだったと思うが、ばあやの孫がうちに来る。その子はばあやしか身寄りがいない。だからここに来たときに寂しい思いをさせないように、と言われたのだ」
アンドレは言葉を失った。
「そりはつまり、よけいなことを聞いて悲しいことを思い出させるな、という意味にわたしはとった」
オスカルはグラスを取り、口を付けた。
「だからあえて何も聞かなかったと?」
「まあ、そういうことだ」
アンドレもグラスを取った。
そして一気に飲み干した。
甘い香りがのどから鼻へと抜けていく。
グラスを持ったままフーッと大きく息を吐いた。
そんな気遣いをしてくれていたとは知らなかった。
単に興味がないのだと思っていた。
実際の所、伯爵家の御曹司として育てられたオスカルが、使用人である乳母の孫に関心を持つなど考えられないことであったから、何も聞かれないことを不思議にも思っていなかった。
名前を聞かれたのが、思えば唯一の質問だった気がする。
-きみ、名前は?-
出会いの言葉が脳裏をよぎる。
-アンドレ、アンドレ・グランディエ…-
名乗ったとたんに剣を渡された。
そして思い出す。
-ああ きみか、今度僕の遊び相手に…-
名乗った名前にすぐに反応したのは元からその名を知っていたということに今さらながら気づく。
「ひょっとしておれの名前は前もって聞いていた?」
「当然だ。ばあやに聞いておいた」
-ばあや、今度来る子の名前は?-
-アンドレ…でございます。アンドレ・グランディエと申しますんです。どうかよろしくお願いします-
当時かわされたであろう会話と光景が目に浮かぶようだ。
自分が引き取られてくる前に興味をもっていてくれたことが単純に嬉しい。
「あの頃は名前さえ知っていれば充分だと思っていたのだ。あとは実際に会えばわかることだからな」
そうかもしれない。
余計な情報は知らないほうが良い。
祖母に聞かされた「それはそれはお美しいお嬢さま」という知識はなんの役にも立たないどころか、事前情報と現実との落差に対する衝撃の度合いを増しただけだった。
自分もオスカル・フランソワという名前と年齢だけ知らされていた方が幸せだったろう。
性別だって知らない方が良かった。
そう思うとクスリと笑いが漏れた。
するとグラスの向こうでオスカルも笑う。
「事実、わたしのおかげで寂しい思いをすることはなかっただろう?」
それは、そのとおりだった。
日夜、慣れない剣のけいこで疲れ果て、寝台に入れば、即、眠りに落ちた。
母恋しさはあったが、泣くだけの体力が残っていなかったし、思い出して恋しがる時間も与えてもらえなかった。
あれは思いやりだったのか。
「おまえは嫌がっていたが、剣の筋は悪くなかった。鍛えればなかなかのものになると思った。日々上達していくのは楽しい。そうすれば寂しくない」
オスカルの、オスカルなりの理路整然とした説明には、いつもながら驚かされる。
自分こそ、知っているようで知らないことがあるのだと、アンドレは気づく。
オスカルが、出会う前から自分を気遣ってくれていた。
少々乱暴な手法ではあるが、配慮してくれていた。
まったく知らないことだった。
「そんなに驚くことか?」
オスカルはめずらしくアンドレのグラスにワインを注いだ。
それから自分のグラスに注ぐ。
「いや、その…」
口ごもるしかなくて、アンドレはふたたびグラスをカラにする。
「おお、今日はなかなかよくつきあってくれるではないか」
オスカルが満面の笑みを浮かべ、自分のグラスを空けると、そのままアンドレに向かって突き出した。
苦笑しながらアンドレはオスカルのグラスにワインを注いだ。
「どんな人だった?」
あの時に聞けなかったことをオスカルは聞いた。
「父は大きな人だった。よく肩車してくれた。おれはそれが好きだった。遠くまで見えるのが嬉しかった」
取り留めもない話だ。
だがオスカルはニコニコと聞いている。
「母もスラリとした人で…とても料理がうまかった」
そこでオスカルの突っ込みが入った。
「ちょっとまて!。ばあやの娘だろう?」
「うそではない。子どもだったから少し大きく見えたかも知れないが、細身の人だったと記憶している」
うーん、と言ったきり、オスカルは黙り込んだ。
「ばあやのご亭主が細身だったのか?」
「会ったことがないから知らん」
「肖像画とかもないのか?」
貴族じゃあるまいし、あるわけがない。
大きく首を横にふってやった。
「今度ばあやに聞いてみよう」
オスカルに聞かれたのなら、おばあちゃんも答えるかもしれない。
アンドレはまたもやクスリと笑った。
「大きな父上とスラリとした母上ということか。ばあやを見ていると疑わしいが、おまえを見ているとそうかもしれんという気がする」
オスカルは無理矢理納得しようとしている。
その様子がなんとも可笑しい。
ワインが心地よく回り出した。
聞かれもしないことがつい口をつく。
「姿はぼやけていくが、声は不思議と覚えている。親父の声、おふくろの声。目を閉じると聞こえる気がする」
「どんな?」
「親父はわりと太い声だった。何の仕事をしていたんだろうな。覚えてないんだが、帰ったよという声が大きくて、どこにいてもすぐにわかった。おふくろの声はちょっとかすれた感じでアルトだったな」
残された片眼を閉じる。
耳底に残る懐かしい声に集中する。
アンドレ、と呼ぶ声。
父の声、母の声。
「アンドレ」
耳元でオスカルの声がした。
驚いて目を開けると、すぐ隣に来ている。
「面接は終わりだ」
「もう?」
「ああ。ものたりないか?」
「いや、そういう意味ではないが…。で?おれはジャルジェ家に採用ですか?」
オスカルがフッと笑った。
「それはないと言っていただろう。今さらクビにはできまい」
だとしたらいったいなんのための面接だったのか。
「腑に落ちない顔だな」
「いまひとつ目的がわからない」
「深い意味はないのだ」
自分でも面接したかった意味はよくわかっていなかった。
強いて言えば、ただ知りたかっただけだ。
アンドレがどんな家庭で生まれ育ったのか。
どんな両親が彼を育んだのか。
だが、聞いているうちにどうでも良いような気がしてきた。
アンドレは、自分の知っているアンドレだけでいい。
それで充分だ。
だから面接は終わりだ。
結局、この後、衛兵隊は超多忙となり、面接は無期限延期となった。
アランとフランソワが、自分たちだけが面接されたことに表向き最大限の不満をこぼしながら、どこか嬉しそうであり、そしてまた他の兵士たちが、ホッとしている反面、なんとなく残念そうでもあるのがアンドレには愉快だった。
オスカルが、アンドレとの面接で、わざわざ面接せずとも、日々接していく中で見えてくる姿こそが肝心だと認識したことも無期限延期の大きな要因だったが、それは誰も知らないことである。
※ このお話も第1部の「パリ巡回」前後に入るものです
HOME MENU BACK NEXT BBS 「パリ巡回」