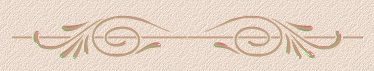
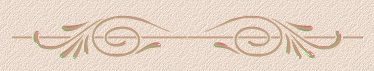
見 果 て ぬ 夢
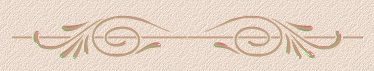
およそらしからぬことではあったが、王妃直々の要望、かつまた、病床の
王太子のたっての希望ということで、オスカルは、子連れでムードンに伺候した。
ノエルの休暇前に一度お目見えして以来の謁見であり、多忙とはいえ、いかに久しく尊顔を拝していなかったかを、その幼く上品ながら目に見えて痩せ衰えた王子の姿に思い知らされ、オスカルは、涙をこらえるのに相当の努力を要した。
豪華な寝台に痛みをこらえて横たわるルイ・ジョゼフ王子は、しかし、オスカルの背後にいつになくおとなしく控えているル・ルーを目にすると、満面の笑みを浮かべた。
長らく子どもと会うことがなかった王子が、オスカルの姪がベルサイユに来ていることを侍女の噂で聞きつけ、ぜひにも会いたいとの仰せだと、宮殿から使者が来たのは三日間の休暇があけてまもなくのことだった。
大急ぎでローランシー家と連絡を取り、さまざまにこのお転婆娘に礼儀作法を教え込み、とりあえず急ごしらえの令嬢に仕立て上げたのだが、オスカルとしては、王子の病状とともに、何をやらかすか全く見当の付かない姪のことにも不安が押さえきれなかった。
「オスカル、無理を言ってごめんなさい」
けなげな王子の言葉を聞くと、どんな希望でも叶えて差し上げたいとの思いに、オスカルは
「いいえ、とんでもございません。殿下のお召しとあれば、姪の一匹や二匹すぐにも連れて参上いたします」
と笑顔で答えた。
ちょっとその言い方はあんまりではないの?と、傍らでル・ルーがオスカルの袖を引っ張った。
「なんだ?ル・ルー?」
オスカルが小声で聞いた。
「それじゃ、まるでわたしが犬か猿みたいじゃないの?」
「アッハッハ…!」
王子が大きな笑い声をあげた。
「オスカル、こんなかわいい女の子に、一匹二匹はひどいなあ」
「あら、かわいいだなんて…」
ル・ルーが無邪気に笑った。
「殿下、わたくしの姪とはいえ、そのようなお気遣いは無用ですぞ。これは本当に人よりは猿に近いのです」
「オスカルお姉ちゃま!!」
「ねえ、君、名前は何というの?」
王子が嬉しそうに尋ねた。
「ル・ルーです。ル・ルー・ド・ラ・ローランシー」
「名前もかわいいね」
「そうでしょう?わたしも気に入っているんです!」
「こら、ル・ルー。馴れ馴れしい口を聞いてはいかん!」
オスカルが叱責するのを王子は笑いながら制した。
「ねえ、オスカル。ぼくはル・ルーと二人で話をしたい。だから、少し黙っていてもらえない?」
納得しがたいものを抱えつつ、仕方なくオスカルは、寝台から離れ、入れ替わるようにル・ルーが王子の枕元に近づいた。
すると王子は、オスカルに侍女たちが控えている方を指さした。
オスカルは仕方なく、さらに寝台を離れ、侍女たちの席まで下がった。
王子は、ル・ルーに、あらためて良く来てくれたね、と礼を述べた。
「ベルサイユにいるときは、おかあさまのお友達が子どもを連れてお見舞いにきてくれたのだけれど、ムードンに来てからは、誰も来ないんだ」
寂しそうな切ない表情だった。。
様態が悪化したためのムードン行きだったのだから、体力を消耗する面会を控えるよう周囲が取りはからうのは当然だったが、肉体的なこととは別の要因が、王子の健康を一層損ねていることにまでは、なかなか大人は気づかない。
「そうなの?こことベルサイユはそんなに離れてはいないのにね。わたしでよければ毎日でも来ます。あっ、あそこの怖〜い人が連れてきてくれれば、ですけど…」
ル・ルーはいかにも恐ろしげなものを見る目でオスカルの方を見た。
猿扱いされた腹いせに人を化け物扱いしているな、とオスカルはにらみ返したが、王子がクスクスと笑っているのを見て、その愛らしさに目を細めた。
「オスカルは怖いの?」
王子がニコニコとして尋ねた。
「そりゃ、もちろん!だってたくさんの部下を毎日怒鳴り散らしてるんですもの。わたしのようなかよわい女の子から見れば、それはそれは恐ろしいものですわ」
ル・ルーがツンとすまし顔で答えた。
「ぼくにはとても優しいんだけど…」
「それは王子さまですもの」
「そうかなあ。オスカルはぼくが王子でなくても、優しいと思うよ」
ル・ルーは大きく首を振った。
「王子さま、それはあんまりにも人を見る目がなさ過ぎます」
「え…?そう…かな…」
「そうです!あの人は軍人ですもの。上の命令には絶対服従。そして下のものには…。ああ、恐ろしい。わたし、きっと今日おうちに帰ったら、どうしてあんなことを王子さまに申し上げたんだっておしりをぶたれちゃうんだわ」
ル・ルーは大げさに身震いして見せた。
王子は目をまん丸くして、
「おしりを?」
と聞いた。
「ええ、そうよ。うちのお母さまはあの人のお姉さまなんだから、おしりくらい平気でぶつの」
「それって痛い?」
「そりゃあ、もう、痛いのなんのって…。真っ赤に腫れちゃうんだから!」
「なんてかわいそうに!わかった。ぼくがオスカルに頼んであげよう」
「本当ですか?」
「うん、約束するよ」
「王子さまの命令なら絶対ね。やったあ!!」
ル・ルーは万歳をした。
「ありがとう、王子さま」
「こうして来てくれた御礼だよ」
「わたし、何度だって来るわ。もしオスカルお姉ちゃまがつれてきてくれなくても、ひとりでだって来るわ」
「本当に?」
「もちろん。だって王子さまと話していると楽しいんですもの!」
王子は、ル・ルーの言葉に本当に嬉しそうに笑った。
離れて控えていたオスカルと侍医や侍女たちは、その笑顔に胸をつかれた。
日々お世話している侍女など、涙ぐんでしまい、そうっと部屋を出て行った。
自分の存在が、いつもいつも父や母や姉弟の負担になっていることを、どんなに心苦しく思っていたか。
その存在が喜びで、楽しいのだと、なんのてらいもなく言い切る少女がどんなに自分を喜ばせたか。
幼い王子は、もとより理屈ではなく、全身でそれを感じ取ったのだろう。
「本当にぼくといると楽しい?」
「ええ、とっても!ねえ、王子さま、もう少しお具合がよくなったら、今度はお庭に一緒に出ましょうよ」
王子の詳しい病状など知らぬル・ルーは、こともなげに言い放った。
王子は一瞬、遠くを見つめ、それからうなずいた。
「うん、そうしよう。今度はトリヤノンのお庭を案内してあげるよ。お花も鳥も魚もいるんだ」
「すご〜い!じゃあ、わたしはうちの裏の森を案内してあげる。ちょっと遠いけど、とっても素敵なところなのよ」
「わかった。きっと行くよ」
二人の子どもの会話は、黙って控える大人たちに、心地よい波のように届いた。
それは大きな笑い声だったり、小さなヒソヒソ話だったり、驚嘆のため息だったり、という風に耳をくすぐり、王子の日頃の苦痛を一瞬遠い空の彼方に連れ去った。
やがて、侍医が、この幸せなひとときに終わりが来たことを告げた。
王子はル・ルーに、あちらでお菓子をもらうように言うと、オスカルを呼び寄せた。
そして彼女の耳元で小さな声でささやいた。
「ねえ、オスカル。前にぼくが言ったこと、悪いけど忘れてくれない?」
「…?何のことでしょう?」
「ぼくが大人になるまで待ってと言ったこと…」
オスカルは思わずのけぞった。
「やっぱり、歳が違いすぎる。考えてみれば。オスカルってお母さまと同い年なんでしょう?ぼくはル・ルーを王妃にしたいんだ」
「殿下!」
「ル・ルーはあなたの血をひいている。きっと大きくなったらあなたのようなきれいな人になる。ぼくは絶対に元気になって、ル・ルーに求婚するんだ!」
「殿下、それは、あまりにも人を見る目がなさすぎますぞ。蓼食う虫も好き好きですが、あれだけはフランス国民のためにもおやめになったほうがよろしいかと…」
「オスカル。やっばり似ている。ル・ルーも同じことを言ったよ。ぼくがあなたを優しい人だと言ったら、人を見る目がなさすぎるって…。アッハッハ!」
「…!」
なんということだ、と憤慨しつつ、だが、オスカルはあの猿のためにでも元気で生きたいと思ってくださるのであれば、こんなにありがたいことはないと思った。
そして、チロリと菓子ほほおばるル・ルーに目をやり、
「殿下の思し召しとあれば、姪の一匹や二匹、いつでも献上いたします」
と胸を張り、大見得を切った。
帰路の馬車で、さすがに疲れて、ル・ルーはアンドレの膝に頭を乗せて熟睡していた。
「心臓に毛が生えているようなル・ルーでも、王太子殿下の前では緊張したと見える」
アンドレが、そっとル・ルーの顔にかかる髪をかきあげた。
「ああ。お話しているときは、そんな素振りも見せなかったが…。食い過ぎたのかもしれん」
「何か頂いたのか?」
「珍しいお菓子など、殿下が欲しいだけ食べて良いとおっしゃったものだから、ちょっとみっともないほと゜…な」
「ほう…!殿下はよほと゜ル・ルーがお気に召したと見える」
「お気に召しすぎだ。将来王妃にしたい、とまで言われた」
「えっ…!」
さすがにアンドレも絶句した。
「わたしは王妃になりそこなったわけだ」
「オ…スカル?」
「前回の謁見のあとに話しただろう?大きくなるまで待ってと言われたこと…」
「あ、ああ…、聞いた」
「あの話はなかったことにしてほしいとのお言葉だ」
一瞬の沈黙ののち、アンドレは爆笑した。
「アッハッハ…!」
「笑うな!」
「ああ、すまん。だが、殿下も随分だな。で、なんと申し上げたんだ?」
「人を見る目がない、と、一応は申し上げたが、だが、もし殿下がこいつのために生きたいと思ってくださるなら、こんな嬉しいことはないからな。喜んで献上いたします、とお答えした」
しんみりとしたオスカルの声に、アンドレは、優しくうなずいた。
「そのとおりだ。人は、どんな絶望の淵にいても、夢を見ることはできる。たとえどんなに見果てぬ夢でも…」
「もし、殿下の夢が叶うのなら、私は一生、ル・ルーの僕になってもよい」
オスカルは、目尻にたまった熱いしずくをそっとぬぐい、天を仰いだ。
「よし、わかった。そのときは俺は、ル・ルーの僕の僕になろう」
アンドレは膝の上の、生意気この上ない、けれど天性の明るさをはなつ少女の髪をそっと撫でた。
窓の外を見ると、遠くに浮かぶ雲が、いつになくせわしく東へ流れ行くのが見えた。
時よ、疾く過ぎゆくな
かの人の見果てぬ夢をかなえてのちにこそ
思うさま 流れゆけ…
二人は口には出さず、けれどもただ一つのことを同時に祈った。
終わり
![]()
![]()
![]()
![]()